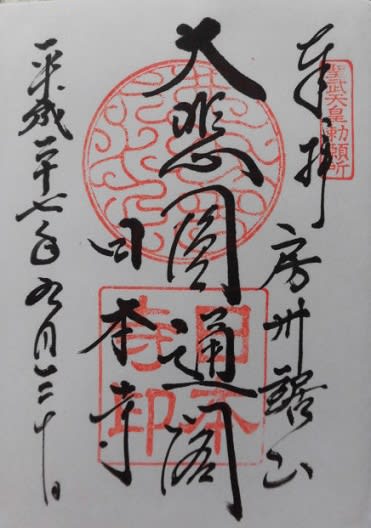先月報告しましたが、東京都では都民にぶ厚い「東京防災」という冊子を配布しております。
その冊子に関連して、都下各消防署で「東京防災セミナー」が催されています。10月14日までですが。何所でその情報を入手したのか覚えていないのです。
わが市の消防署のサイトに行きますと、各出張所でもセミナーが開催されているとあります。最寄駅に近い出張所に問合せしますと、『あなたの自宅からですともっと近い出張所がありますよ』と言うではありませんか。自宅近くの街道の一本裏側に出張所があったのです。自宅から15分くらいでした。
毎週、日月火水の4日で平日は19時から1時間です。
私のいつもの癖で、18時40分頃には着いておりました。受付の女性の対応の様子から、あまり受講者がいないのではと言う感じでした。
若い担当官とその上司の方が出てこられ、二階の会議室に案内されました。挨拶される二人の様子から参加者が全くない日もあったようで、私は歓迎されていたようです。
雑談の流れから、マンツーマンの講習が始まりました。まず驚いたのが防災のDVDを映したのが、14インチの全く古いブラウン管テレビだったのです。出張所近くのスーパーに行けば、2万円出せば安い液晶TVが買えるのにと思ってしまいました。色々予算削減が厳しいのでしょう。
さて講義内容ですが、
①「防災ブック」について
②今すぐできる防災対策について
③家具類の転倒、落下、移動防止について
④その他
でした。
①は読んで頂くということで、DVDは②から始まりました。内容は取り立てて目新しいことはなく、どこかで一度は聞いたということです。
若い担当官いわく『阪神大震災を知らない若い職員にこのセミナーを担当させることになったのです』と説明を始めました。
実は私の知人で、神戸市中央区でもろに震災を体験し生き残り、被災者の真っただ中にいたものがおり、彼から生々しい実はを聞いております。
担当官に幾つか実話を話してあげました。
19時に年配の御夫婦が受講に見えられました。すでにセミナーが始まっているのに驚いて、『19時からではなかったのですか』と文句を言っておられました。彼は自治会の役員をされているようで、その後の消火器の説明とか、消火器の新機種とか消防署に対する簡易消火器の啓もうに関して要望を出しておりました。以前も言いましたが、私の住んでいる地区は町内会が大きく地区ごとの防災訓練など熱心です。
消火栓に直結するスタンドパイプと言う消火器をご存知ですか。こんな消火器も町内会で訓練しているほどです。
セミナーの最後はいつもの、三角巾による応急処置の実演でした。
この日の一番の収穫は、以前お話しした、購入したばかりの防災ヘルメットの正しいかぶり方の確認です。会場にヘルメットを持参しました。担当官とその上司に事情を説明して教えを乞うたのです。
最近の常総市のニュース映像で、消防官、警察官、自衛隊員、国土省の係員の皆さんのヘルメットのかぶり方を注目しておりました。
一番気になったのは、アゴのバンドです。喉仏の付近にバンドがあるので、とても違和感があるのです。
でも担当官たちはそんなこともないということです。結局その日の結論は、「慣れでしょうか。緩めるとヘルメットが外れてしまいますから、ある程度はしっかりと」。何ということでしょう。まったく当たり前の結論でした。
セミナーのお土産は、防災一口メモの印刷されたクリヤーファイルや、そのほかリーフレットでした。
1時間くらいのセミナーではこのくらいの内容でしょうか。
その冊子に関連して、都下各消防署で「東京防災セミナー」が催されています。10月14日までですが。何所でその情報を入手したのか覚えていないのです。
わが市の消防署のサイトに行きますと、各出張所でもセミナーが開催されているとあります。最寄駅に近い出張所に問合せしますと、『あなたの自宅からですともっと近い出張所がありますよ』と言うではありませんか。自宅近くの街道の一本裏側に出張所があったのです。自宅から15分くらいでした。
毎週、日月火水の4日で平日は19時から1時間です。
私のいつもの癖で、18時40分頃には着いておりました。受付の女性の対応の様子から、あまり受講者がいないのではと言う感じでした。
若い担当官とその上司の方が出てこられ、二階の会議室に案内されました。挨拶される二人の様子から参加者が全くない日もあったようで、私は歓迎されていたようです。
雑談の流れから、マンツーマンの講習が始まりました。まず驚いたのが防災のDVDを映したのが、14インチの全く古いブラウン管テレビだったのです。出張所近くのスーパーに行けば、2万円出せば安い液晶TVが買えるのにと思ってしまいました。色々予算削減が厳しいのでしょう。
さて講義内容ですが、
①「防災ブック」について
②今すぐできる防災対策について
③家具類の転倒、落下、移動防止について
④その他
でした。
①は読んで頂くということで、DVDは②から始まりました。内容は取り立てて目新しいことはなく、どこかで一度は聞いたということです。
若い担当官いわく『阪神大震災を知らない若い職員にこのセミナーを担当させることになったのです』と説明を始めました。
実は私の知人で、神戸市中央区でもろに震災を体験し生き残り、被災者の真っただ中にいたものがおり、彼から生々しい実はを聞いております。
担当官に幾つか実話を話してあげました。
19時に年配の御夫婦が受講に見えられました。すでにセミナーが始まっているのに驚いて、『19時からではなかったのですか』と文句を言っておられました。彼は自治会の役員をされているようで、その後の消火器の説明とか、消火器の新機種とか消防署に対する簡易消火器の啓もうに関して要望を出しておりました。以前も言いましたが、私の住んでいる地区は町内会が大きく地区ごとの防災訓練など熱心です。
消火栓に直結するスタンドパイプと言う消火器をご存知ですか。こんな消火器も町内会で訓練しているほどです。
セミナーの最後はいつもの、三角巾による応急処置の実演でした。
この日の一番の収穫は、以前お話しした、購入したばかりの防災ヘルメットの正しいかぶり方の確認です。会場にヘルメットを持参しました。担当官とその上司に事情を説明して教えを乞うたのです。
最近の常総市のニュース映像で、消防官、警察官、自衛隊員、国土省の係員の皆さんのヘルメットのかぶり方を注目しておりました。
一番気になったのは、アゴのバンドです。喉仏の付近にバンドがあるので、とても違和感があるのです。
でも担当官たちはそんなこともないということです。結局その日の結論は、「慣れでしょうか。緩めるとヘルメットが外れてしまいますから、ある程度はしっかりと」。何ということでしょう。まったく当たり前の結論でした。
セミナーのお土産は、防災一口メモの印刷されたクリヤーファイルや、そのほかリーフレットでした。
1時間くらいのセミナーではこのくらいの内容でしょうか。