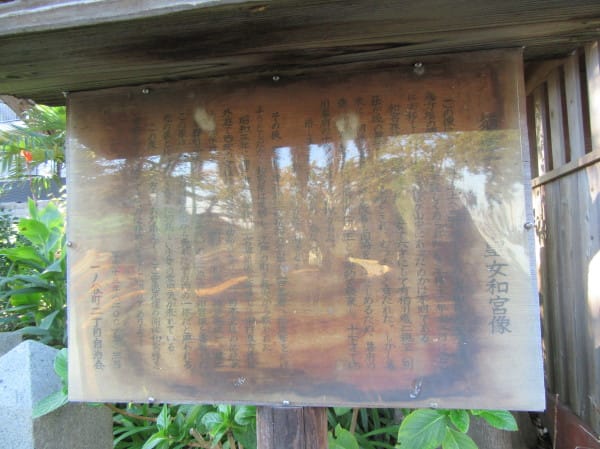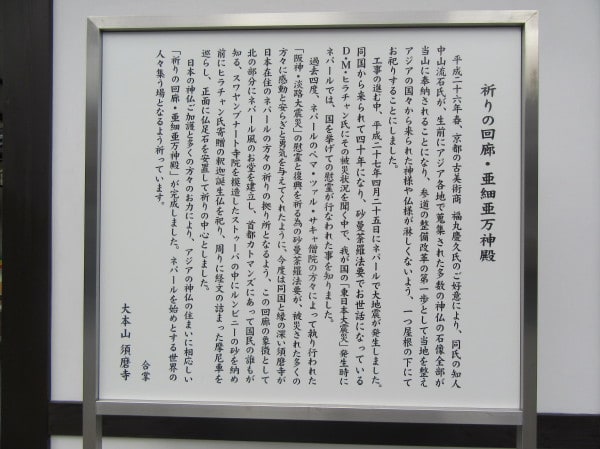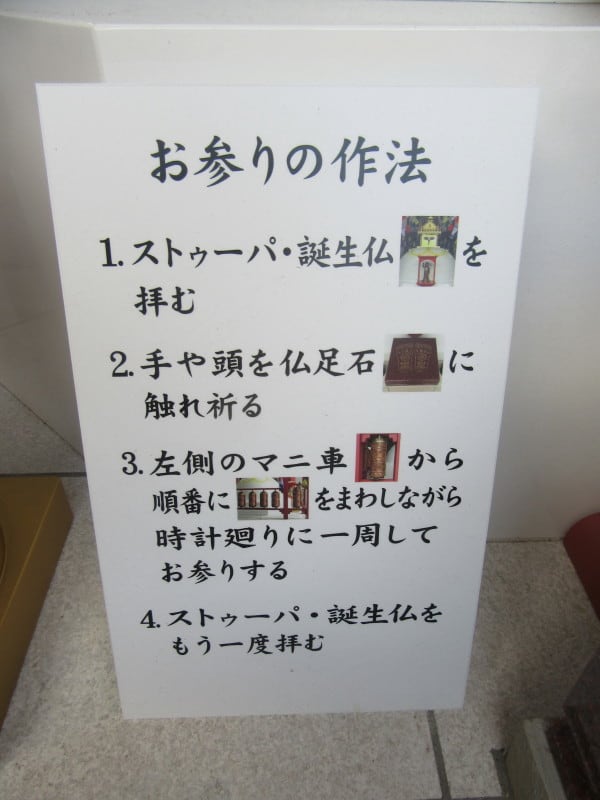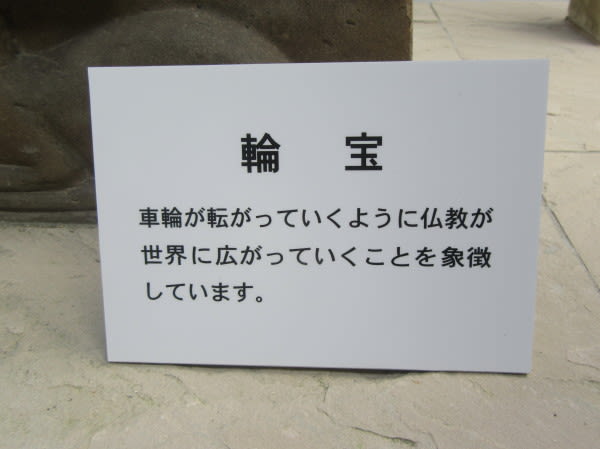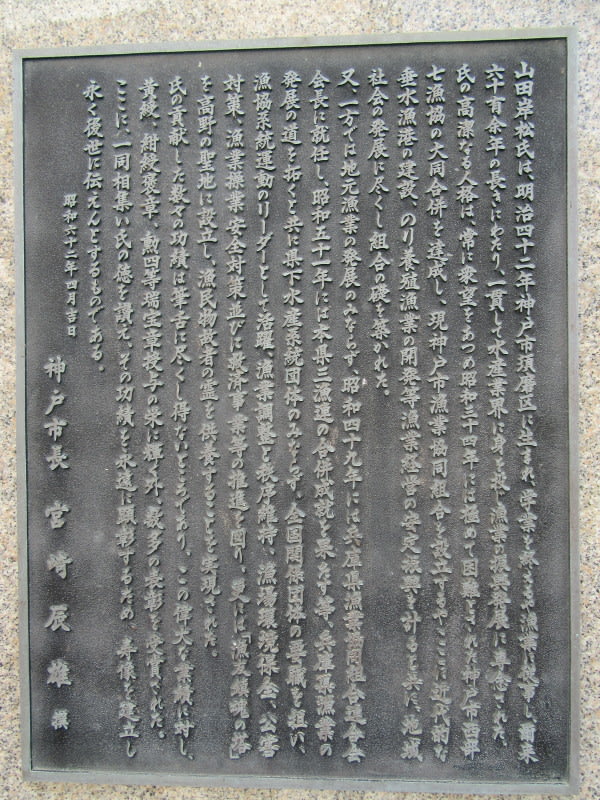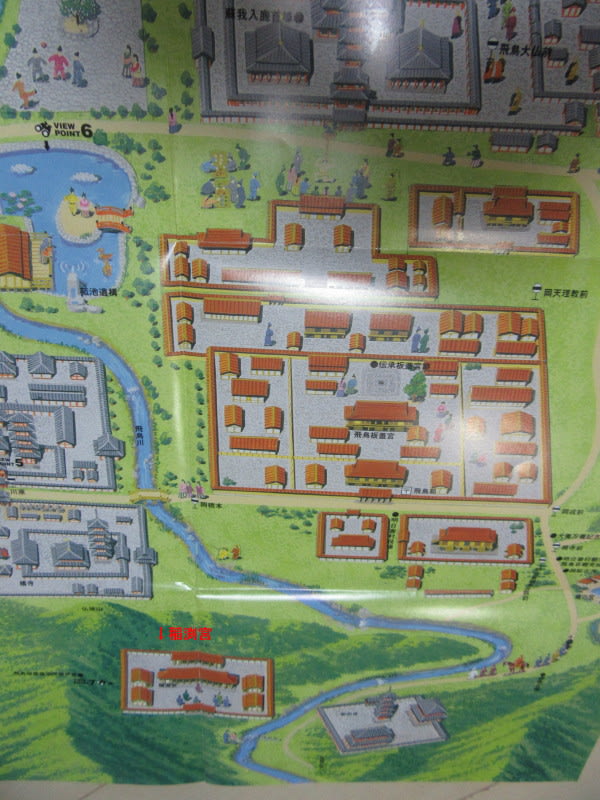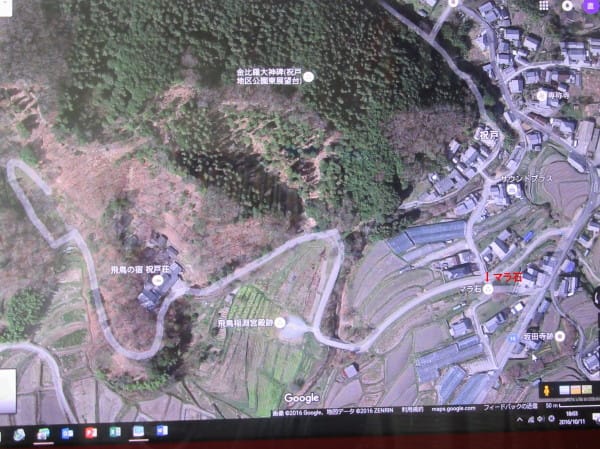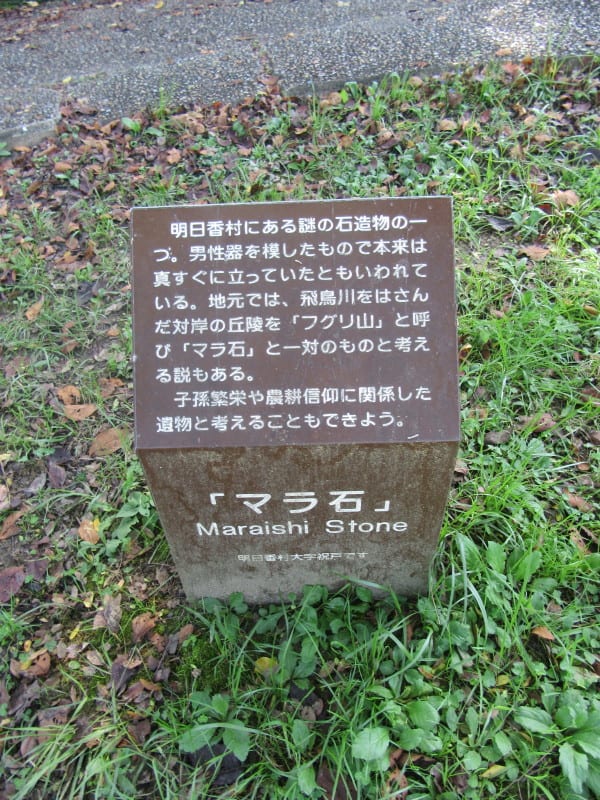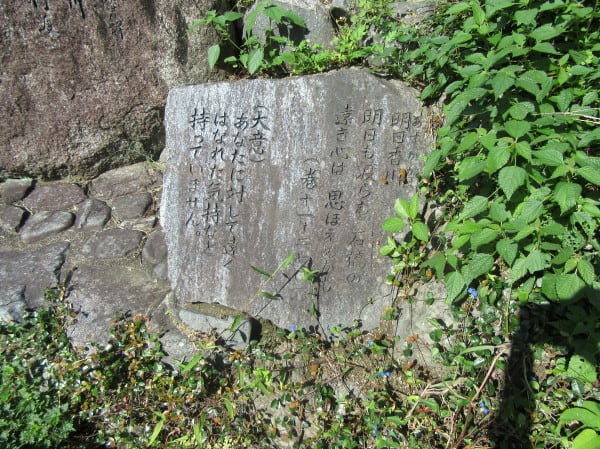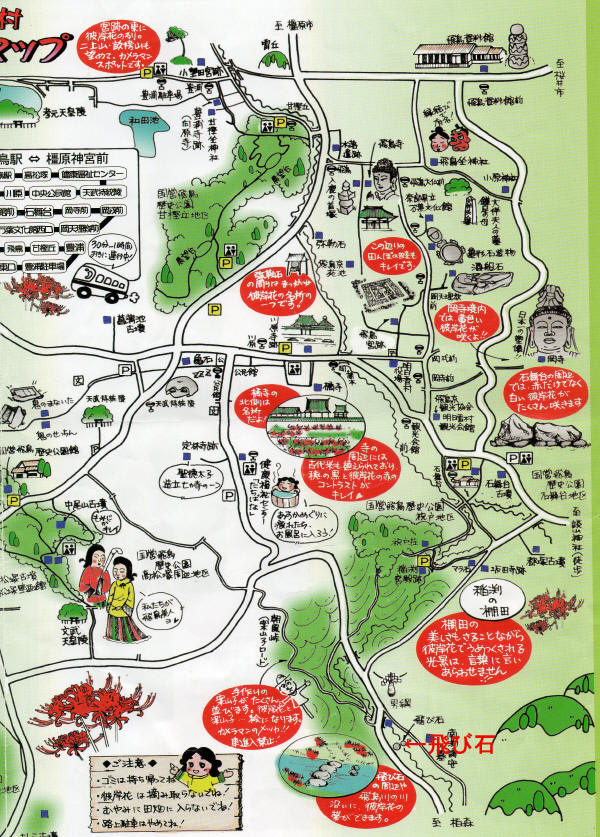神戸市交通局は、大正6年(1917)に神戸市電と電気事業を開始して以来、
平成29年(2017)8月1日に100周年を迎える予定です。
下の写真は神戸市営交通100周年を告知するポスターです。
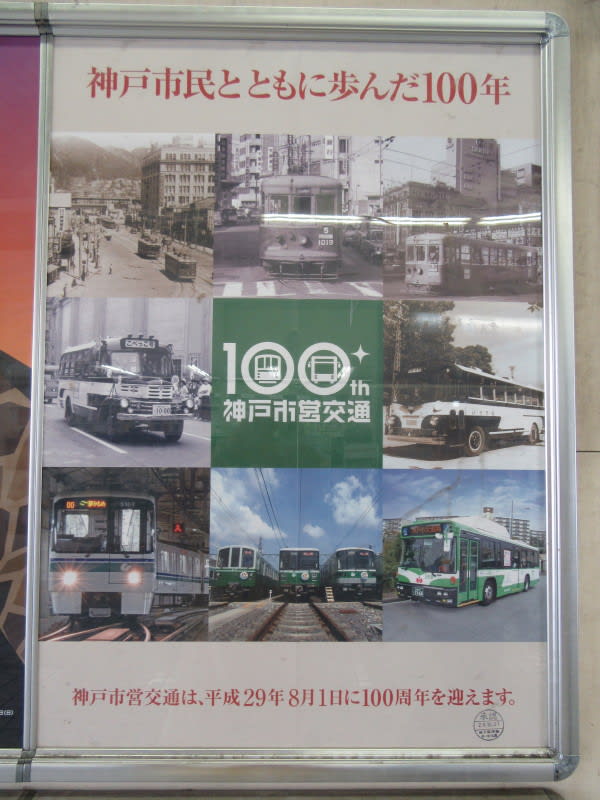
100周年の記念行事としては下記のようなイベントが実施されました。
(1)平成28年5月10日 神戸市営交通100周年記念ロゴマークが決定

上の写真は決まった神戸市営交通100周年記念ロゴマーク
東京都大田区在住のグラフィックデザイナー中村千秋さんの作品
298点の応募作品から選ばれました
(2)平成28年7月19日 市営交通100周年プレイベント
「北区山田町重要文化財めぐり」
(3)西神・山手線新長田駅~海岸線新長田駅連絡通路でなつかしの写真展
平成28年8月1日~8月31日
(4)市営地下鉄「新型車両デザイン総選挙」10月17日~10月23日
これからも色々とイベントが開催されると思います
神戸市営交通の歴史
http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2016/05/20160510701101.html
上記神戸市サイトより引用
1917(大正6)年8月1日 「神戸市電気局」を創設(※)市営として発電、
配電及び市街地路面電車事業を開始
1930(昭和5)年9月16日 市営バス事業を開始
1942(昭和17)年5月19日電気局を「交通局」と改称
1971(昭和46)年3月13日市電路線(路面電車事業) 全線廃止
1977(昭和52)年3月13日地下鉄西神線(名谷~新長田) 営業開始
1987(昭和62)年3月18日地下鉄西神・山手線 全線開通
2001(平成13年)7月7日地下鉄海岸線 営業開始
2017(平成29年)8月1日神戸市営交通100周年
※民営で行われていた発電、配電及び市街地路面電車事業を神戸市が引き継ぐ
平成29年(2017)8月1日に100周年を迎える予定です。
下の写真は神戸市営交通100周年を告知するポスターです。
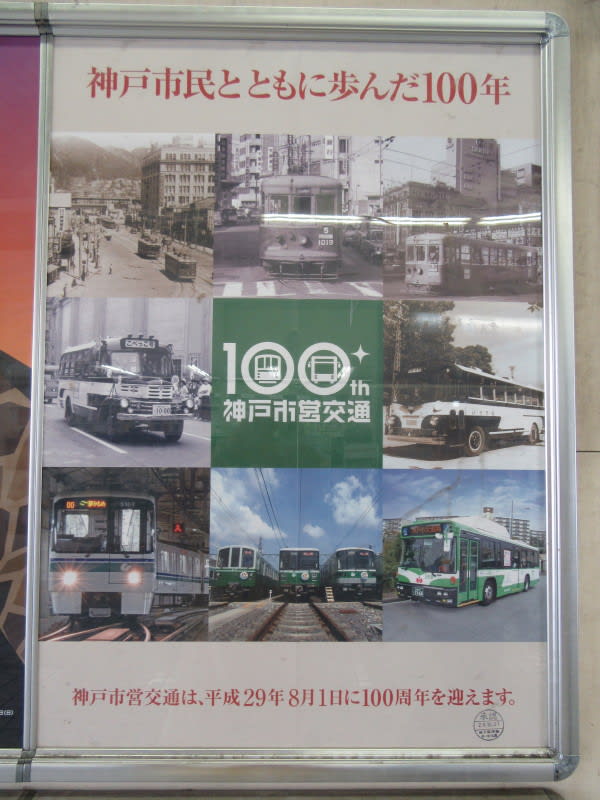
100周年の記念行事としては下記のようなイベントが実施されました。
(1)平成28年5月10日 神戸市営交通100周年記念ロゴマークが決定

上の写真は決まった神戸市営交通100周年記念ロゴマーク
東京都大田区在住のグラフィックデザイナー中村千秋さんの作品
298点の応募作品から選ばれました
(2)平成28年7月19日 市営交通100周年プレイベント
「北区山田町重要文化財めぐり」
(3)西神・山手線新長田駅~海岸線新長田駅連絡通路でなつかしの写真展
平成28年8月1日~8月31日
(4)市営地下鉄「新型車両デザイン総選挙」10月17日~10月23日
これからも色々とイベントが開催されると思います
神戸市営交通の歴史
http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2016/05/20160510701101.html
上記神戸市サイトより引用
1917(大正6)年8月1日 「神戸市電気局」を創設(※)市営として発電、
配電及び市街地路面電車事業を開始
1930(昭和5)年9月16日 市営バス事業を開始
1942(昭和17)年5月19日電気局を「交通局」と改称
1971(昭和46)年3月13日市電路線(路面電車事業) 全線廃止
1977(昭和52)年3月13日地下鉄西神線(名谷~新長田) 営業開始
1987(昭和62)年3月18日地下鉄西神・山手線 全線開通
2001(平成13年)7月7日地下鉄海岸線 営業開始
2017(平成29年)8月1日神戸市営交通100周年
※民営で行われていた発電、配電及び市街地路面電車事業を神戸市が引き継ぐ