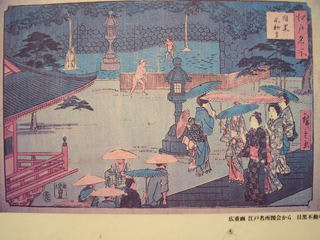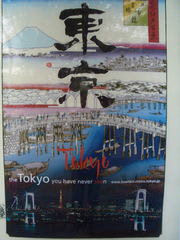写真は京都宇治とろろ家のとろろ料理
伏見大手筋店で京阪の伏見桃山駅からすぐ。
住所:
〒612-8081
京都府京都市伏見区新町5-510 オクダビル2F
味もgood
京都宇治とろろ家のHPはこちら

京都伏見は豊臣秀吉の伏見桃山城の城下町
としてまた30石船の伏見港として、酒どころ
として400年前には非常に栄えた街です。
30石船は伏見港と大坂を結ぶ過書船(幕府公認の船)
定員は28名であった。
(但し、上の写真は10石船)
30石船の他に伏見船15石、淀船(淀20石)、
高瀬船などがあった。
川辺の柳も情緒を増長している。
30石船の運航コースで三栖閘門資料館も見所。
この閘門は淀川からの逆流を防いでいる。
観光コースとしては酒蔵の見学、竜馬の寺田屋
長建寺、西岸寺、源空寺、大黒寺、宝福寺などが
あります。
運行時間、運航日などは伏見観光協会のHPへ

栗橋関所は利根川河川敷に設置され、敷地約120坪
建坪約16坪の小規模なものでした。
関所には4名の番士が任命され幕末の番士は足立、島田、
富田、加藤の四家でした。
番士の勤務は毎日朝6時から夕方6時まで2人1組で
5日間交代でした。手当ては20俵。
上の写真は足立家で現在も番士の子孫が住まわれている。
その敷地は約1,400平方メートル。
この足立家には膨大な関所日記が残されているそうです。
関所番士屋敷は寛永元年(1624)に栗橋関所の番士の
住まいとして江戸幕府が設置しました。

上の写真は栗橋関所跡の碑です。
栗橋関所は元和7年(1621)以降河川敷の現在地に
設けられました。元和7年(1621)以前は
日光街道は五霞町元栗橋にあり関所も別の場所に
あったが利根川の水害でつけかえられた。

上の写真は「放浪着」「浮雲」などで有名な尾道出身の
作家林芙美子が昭和16年(1941)から昭和26年(1951)
の約10年住んでいたところです。
西武新宿線の中井駅が最寄り駅です。
昭和14年に土地を購入した頃は1000坪だったそうですが
現在は約500坪で記念館となり東京都が管理しています。
緑が多く落ち着くところです。

上の写真は客間です。
詳細情報はこちら

法明寺
住所:豊島区南池袋3丁目18
雑司が谷の法明寺は弘仁元年(810)真言宗で開山。
威光寺として開創されました。
その後、正和元年(1312)日蓮宗に改宗し、
威光山法明寺と寺号が改められました。
雑司が谷の鬼子母神も法明寺の一部になっています。
境内の墓:
小幡景憲:関が原、大坂冬の陣など徳川方で功があった
軍学者
豊島氏:豊島氏は平安朝の末期より鎌倉、室町時代にかけ
武蔵の地一帯に勢力をもっていた。
文明10年(1478)太田道灌に攻め落とされた。
その生き残りの一族で徳川に仕えた八丈島の代官
になった豊島忠次を中心にその一族の墓である。
橘家円喬:明治時代に活躍した落語家
楠公息女:別名「姫塚」
桜の季節には桜トンネルとなり有名