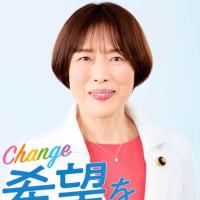*この論文は東京新聞2019年6月14日夕刊に掲載されたものです。電子版を俟ちましたが7月13日現在発見できず新聞紙を視写させていただきます。(櫻井智志)
(写真:週刊エコノミストから、池内 了氏)
序
悪名高い治安維持法は、第二次世界大戦が終わるまで、度重なる「改正」と拡大解釈によって取り締まる対象がどんどん拡大され、罰則も厳しくなって国民は物言えぬ状況に追い込まれた。国民の権利を制限し侵害する可能性がある悪法は、いったん成立してしまうと、権力はさまざまな理屈をつけて「改正」し、国民を支配する範囲を拡大するのが常である。
Ⅰ:権力者の都合
第二次安倍内閣になって以降、特定秘密保護法、安全保障関連法、組織的犯罪処罰法(いわゆる共謀罪法)など政治に絡むさまざまな法が作られたり改正されたりし、最近では「働き方改革」と称して労働基準法や労働安全衛生法など労働関連法が「改正」され、高度プロフェッショナル制度が新設された。
これら多数の法は、国会を通過してひとたび法律として施行されると、人々は「悪法も法」として従わざるを得なくなる。最初は露骨な悪法化は控えられるのだが、人々がその法に慣れて抵抗しづらくなると「改正」の動きが出てくる。権力を持つ者にとって都合が良いように変えられていくのだ。最近「改正」があった二例を検証してみよう。
Ⅱ:盗聴しやすく
一つは、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」(いわゆる盗聴法)で、オウム真理教事件を契機に一九九九年に成立した。犯罪の組織化や複雑化に対応するためとしてする、捜査に通信(電話やメールなど)の傍受(盗聴)をすることを可能としたのである。通信の秘密や自由を侵害する危険性があることから、最初は四つの犯罪類型に限られ、裁判官の傍受令状と通信事業管理者の立ち会いが義務であり、通信当事者には事後的な通知をすることとした。
ところが、相次ぐ「改正」で、窃盗や詐欺などさらに九つの犯罪も傍受可能と適用範囲が拡大し、事業者の立ち会いが不必要となり、事業者の施設で行っていた傍受を専用機器を備えた各警察本部で行えるようにした。どんどん警察の独断による盗聴が可能になり、秘密のうちに思想や行動調査のための監視を行う体制を整えるようになっている。現に労働団体の会合を盗撮するという警察の問題行動が暴かれたことがあった。
もう一つはドローン規制法の「改正」である。二〇一六年に成立したドローン規制法では、国会・首相官邸・皇居・原子力施設上空のドローンの飛行が禁止されたのだが、六月中に施行予定の今回の「改正」では、防衛関係施設として自衛隊および米軍施設を加え、施設・敷地の上空だけでなく周囲三百メートルの区域の上空までもが原則禁止になる。米軍についてはさらに基地の敷地外の提供水域や空域も含まれる。この影響を大きく受けるのが沖縄で、たとえば辺野古埋め立て現場は米軍キャンプ・シュワブと提供水域に囲まれているためドローンが飛ばせず、赤土で汚染された海域など工事の進捗状況が撮影できなくなる可能性が高い。
Ⅲ:基地の監視は
今後心配されるのはドローン禁止を口実にして基地周辺の監視が厳しくなって、基地内外の実情把握が困難になり、基地が治外法権となってしまう危険性があることだ。やはり戦前に基地が見える丘で写生していただけなのに、スパイと決めつけられて罰せられた事例があったことが思い出される。
初めは、あまり影響がないと思っていても、悪法は必ず「改正」され、国民の権利が蹂躙(じゅうりん)されていく道をたどる。国民の権利を制限する可能性のある悪法は、最初から一切拒否する姿勢を貫かねばならない。
(いけうち・さとる=総合研究大学院大学名誉教授)
(写真:週刊エコノミストから、池内 了氏)
序
悪名高い治安維持法は、第二次世界大戦が終わるまで、度重なる「改正」と拡大解釈によって取り締まる対象がどんどん拡大され、罰則も厳しくなって国民は物言えぬ状況に追い込まれた。国民の権利を制限し侵害する可能性がある悪法は、いったん成立してしまうと、権力はさまざまな理屈をつけて「改正」し、国民を支配する範囲を拡大するのが常である。
Ⅰ:権力者の都合
第二次安倍内閣になって以降、特定秘密保護法、安全保障関連法、組織的犯罪処罰法(いわゆる共謀罪法)など政治に絡むさまざまな法が作られたり改正されたりし、最近では「働き方改革」と称して労働基準法や労働安全衛生法など労働関連法が「改正」され、高度プロフェッショナル制度が新設された。
これら多数の法は、国会を通過してひとたび法律として施行されると、人々は「悪法も法」として従わざるを得なくなる。最初は露骨な悪法化は控えられるのだが、人々がその法に慣れて抵抗しづらくなると「改正」の動きが出てくる。権力を持つ者にとって都合が良いように変えられていくのだ。最近「改正」があった二例を検証してみよう。
Ⅱ:盗聴しやすく
一つは、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」(いわゆる盗聴法)で、オウム真理教事件を契機に一九九九年に成立した。犯罪の組織化や複雑化に対応するためとしてする、捜査に通信(電話やメールなど)の傍受(盗聴)をすることを可能としたのである。通信の秘密や自由を侵害する危険性があることから、最初は四つの犯罪類型に限られ、裁判官の傍受令状と通信事業管理者の立ち会いが義務であり、通信当事者には事後的な通知をすることとした。
ところが、相次ぐ「改正」で、窃盗や詐欺などさらに九つの犯罪も傍受可能と適用範囲が拡大し、事業者の立ち会いが不必要となり、事業者の施設で行っていた傍受を専用機器を備えた各警察本部で行えるようにした。どんどん警察の独断による盗聴が可能になり、秘密のうちに思想や行動調査のための監視を行う体制を整えるようになっている。現に労働団体の会合を盗撮するという警察の問題行動が暴かれたことがあった。
もう一つはドローン規制法の「改正」である。二〇一六年に成立したドローン規制法では、国会・首相官邸・皇居・原子力施設上空のドローンの飛行が禁止されたのだが、六月中に施行予定の今回の「改正」では、防衛関係施設として自衛隊および米軍施設を加え、施設・敷地の上空だけでなく周囲三百メートルの区域の上空までもが原則禁止になる。米軍についてはさらに基地の敷地外の提供水域や空域も含まれる。この影響を大きく受けるのが沖縄で、たとえば辺野古埋め立て現場は米軍キャンプ・シュワブと提供水域に囲まれているためドローンが飛ばせず、赤土で汚染された海域など工事の進捗状況が撮影できなくなる可能性が高い。
Ⅲ:基地の監視は
今後心配されるのはドローン禁止を口実にして基地周辺の監視が厳しくなって、基地内外の実情把握が困難になり、基地が治外法権となってしまう危険性があることだ。やはり戦前に基地が見える丘で写生していただけなのに、スパイと決めつけられて罰せられた事例があったことが思い出される。
初めは、あまり影響がないと思っていても、悪法は必ず「改正」され、国民の権利が蹂躙(じゅうりん)されていく道をたどる。国民の権利を制限する可能性のある悪法は、最初から一切拒否する姿勢を貫かねばならない。
(いけうち・さとる=総合研究大学院大学名誉教授)