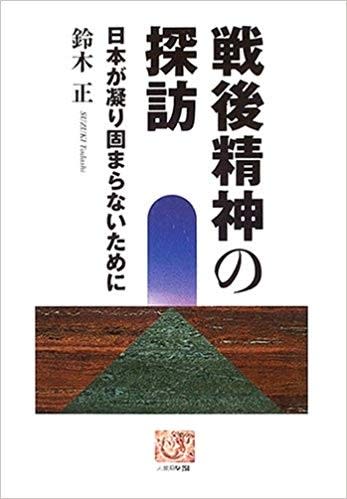
思想史家鈴木正の労作である。『書評拾集 日本近現代思想の諸相』『月日拾集 日本近現代思想の群像』につぐ戦後日本における思想史の探究である。
誠実な実践家であった鈴木は、肺結核に罹患してやむなき静養につとめる。唯物論研究会と思想の科学研究会の研究会に所属して、今までに思想家論に力点を置き、社会思想史の研鑽に努めてきた。
私が氏の存在に着目したのは、「岩田義道論」や、古在由重とご本人との対談など数回に及ぶ労作を掲載した季刊『現代と思想』においてである。この季刊雑誌は、一九七〇年から十年間にわたって青木書店から、江口十四一編集長のもとに刊行され続けた思想哲学雑誌である。統一戦線の思想的基盤を形成することをめざして編集された。一九七〇年代の革新運動の知的思想的母胎のひとつとよんでも大げさではない。そこで鈴木正の言論に感銘を受けて、以降氏の著作を店頭などで見つめると必ずといっていいくらいに購読したり図書館で借りたりして読み続けてきた。
本書は二〇〇五年三月が初版である。副題として「日本が凝り固まらないために」と記されている。歴史、人物、思想の三章から成立している。そのいずれも独創的な着眼点から思想を見つめ、堅苦しくない語り口の文体で、新鮮な思想史学を読者に提供している。中でも私には、第二章の「人物」編が強く印象に残った。
第二章で取り上げられている人物は、のべ二十人。「思想の科学研究会」における最良の方法論を駆使して、著名な思想家に偏らず、草の根の無名な人々に着目している。我が国の民衆史において継承するに値する真価を腑分けしてる。読み進むにつれてひきこまれてゆく。
梅本克己、芝田進午、古在由重、尾崎秀實、小林トミ、中江兆民研究者、安藤昌益研究者、白鳥邦夫、栗木安延、石堂清倫、家永三郎、藤田省三、土方和雄、江口圭一、高畠通敏などの広範で多岐にわたる人物についての叙述は、鈴木正ならではのものである。
中には、日本共産党の側にいるひと、日本共産党から追われたひとなどひとつの視点から見たら、相反するように見える人物選択には、鈴木の政治と思想に対する生き方と着眼点の見事さをうかがい知ることができる。誰でもなんでもよしとする、というのではない。同時代にどのように生きていたかの人間的な姿のありようを見極めて、多面的な人間像として把握するとともに、その矛盾や実態についてしっかりと見極めている。
古在由重は、核廃絶問題に取り組み、原水禁と原水協との統一行動における大衆運動の実践をめぐり、日本共産党と対立した結果、除籍された。芝田進午は、胆管がんでご逝去されて偲ぶ会の席上、友人代表として挨拶に立った上田耕一郎から永年党員と賞賛された。日本共産党からすれば、一方は好ましい存在として、他方は党の方針と異なる行動をとった存在として、両者は百八十度異なる価値付けをされるかも知れない。
だが、芝田は古在由重を戸坂潤とともに、戦前に独創的な世界レベルの唯物論哲学を築き上げた実践的唯物論者として尊敬していた。
鈴木正は、古在由重が戦時中に日本共産党員がすべて獄中につながれ、党が壊滅した後で、京浜地域の工場労働者たちの秘密学習会のチューターとして、実質的な党活動を行ったことを紹介している。同時に、中国共産党が日本からの侵略下で、激しい弾圧に対して「偽装転向」として転向上申書を書いて獄中から出て、即刻反戦活動を行ったことを述べている。その偽装転向は、中国共産党の政治的高等戦略として、中央指導部からだされた極秘方針として広く浸透していった。古在由重は、二度転向の上申書を提出している。ところが獄から出て、古在は即刻コミンテルンのスパイとして逮捕されていた尾崎秀實を釈放するために、弁護士を探すことに奔走し、弁護士を探し出すことに成功した。結果は、尾崎秀實は釈放されることはあたわずに、日本人共産主義者として唯一死刑に処された。鈴木正は、古在の実質的な抵抗としての反戦党活動の意義を、戦時下の中国共産党の戦略と照らし合わせて意義を讃えている。
また芝田進午についても、「私にとって芝田さんはフェアで寛容な人だった。」という書き出しで始まり、「小宮山量平氏(元理論社会長)がいう左翼に多い”分裂体質”とはちがった芝田さんのありし日の面影を偲びながら、つくづくもっと生きて活躍してほしかったと思う。」と結んでいる。小宮山量平は、つい最近2012年4月13日に95才の長寿ながら老衰でご逝去された。鈴木正は、本書では直接論じてはいないけれど、小宮山量平の「統一体質」という思想の気風で共通するものをお互いに感じている。鈴木と渡辺雅男と二人で小宮山から聴き取る対談集を『戦後精神の行くえ』(こぶし書房刊)として出版している。小宮山量平については、いずれ機会を改めてその比類なき文化形成の労作ぶりについて検証したい。
梅本克己は主体的唯物論として、石堂清倫は構造改革派として、藤田省三も政治思想的問題でそれぞれ日本共産党からは除名や除籍されている。鈴木正は、この三者をレッテル貼りで済ますようなことはしない。とくに石堂清倫は、グラムシを日本に紹介した先駆者である。いわゆる運動戦に対置して陣地戦をグラムシは提起して、先進的資本主義国での革命の論理を提起した石堂の卓越さを、惜しむことなく讃える。そして、石堂清倫と同郷で先輩の中野重治をも視野に入れて論じている。藤田省三についても、丸山眞男の政治学を継承した政治思想史の碩学として、藤田の学問的人間的豊かさを描き出している。
戦後直後に「主体性論争」の一方となる梅本克己についても、「戦後活躍した哲学者の中でも最も好きな一人である」と述べて、懐かしく梅本の、大衆につながる日常感覚の確かさと民族・日本人への深い関心の二点を特筆している。主体性論については、先に挙げた小宮山量平が、戦後直後に理論社から『季刊理論』を出版して、初期の黒田貫一をいちはやく逸材として発掘して、表現の場を与えている。黒田は、日本共産党と袂をわかち、革命的共産主義者同盟を組織して、革共同が分裂してからはいわゆる革マル派の理論的指導者として注目された。小宮山は日本共産党とも革共同とも無縁であったが、党派にとらわれず、納得したり共鳴したりする点では広く胸襟を開いて対話を行っている。その思想的体質は、小宮山量平と鈴木正とに著しく共通する点で、後の世代が継承するべき大切な事柄と考える。
鈴木をしてこのように戦後史における知識人を、近現代思想史上に位置づけて的確に把握させている基盤や原動力はなになのか?そのことが第一章の「歴史」、第三章の「思想」を読むと、はっきりとわかる。鈴木は、名も無き民衆の生活知と賢い理性とを大切にしている。そのことが、歴史上の無名な民衆や歴史の奥底で眠る重要な存在を発掘している。
「アテルイを知っていますか」という第一章の節では、桓武天皇の命を承けて東北地域「制圧」のために派遣された坂上田村麻呂によって滅ぼされた側の蝦夷の大将アテルイについて言い及んでいる。この節を読むと、歴史をどう見るかということを単眼でなく、複眼で見ることの鈴木の視座が明晰に伝わってくる。この見識も、2000年に京都清水寺の境内の墓碑の発見から始まっている。何気ない事物を虚心坦懐に見つめ、そこから思想史学を構築してきた鈴木の学問的方法論に、氏が青年の頃から学んできた思想の科学研究会での新たな学問的アプローチが体現されている。限られた紙数では語り尽くせない氏の、戦後史に題材をとった豊かな学問的発掘が本書には展開されている。
副題の「日本が凝り固まらないために」が同時に副題とされている第一章中の「敗走の訓練と散沙の民」という文章が象徴的である。森毅が、朝日新聞の対談記事で、
「昔の軍事教練で、敗走の訓練を覚えてます。隊列を組むな、バラバラで逃げろといわれた。・・・・・固まって逃げたら一斉にやられる。今、経済は『第二の敗戦』といわれてるでしょ。そんな時、みんな一緒のことやってたら、終わりです。」と述べていることに思いを寄せる。鈴木は、こうも述べている。
「メールをすぐ送るとか、ワープロで打った習作か草稿程度の文章を他人(ひと)に見せるとか、近ごろははき出すことが多すぎてどうも念慮が足りない。どうせ大した調査研究でないから、あとで盗作や剽窃といった心配も一向にないらしい。じっと息を懲らさないと表現は彫琢できないのに。携帯電話も同じで、ゆっくりする時間を奪う。ある友人は、恋人の間ではケイタイは監視機能を果たす凶器だ、とくさしていた」。
この節には、じっくりと考え、思想を熟成するような営みを軽んじて、電脳「文化」によって文化がculture「耕される」ものではなく、多機能映像機器の駆使としてしか扱われていない文明論的危機の表明が提起されている。さらに、孫文が中国の民衆を「散沙の民」と称したことと絡めての重要な指摘がなされている。こちらは直接これから読書なされるかたのために省略する。
本書に収められた鈴木正の論文は、名古屋哲学研究会の機関誌『哲学と現代』や労働運動の機関誌『人民の力』に執筆した論文が多い。名古屋をはじめとする中京文化圏は、名古屋大学哲学科の古在由重、真下信一や日本福祉大学の嶋田豊、福田静夫など有数の哲学者の足跡がある。法学の長谷川正安、社会学の本田喜代治、政治学の田口富久治などの学者の名が思い浮かぶ。唯物論研究協会に結集する哲学者の中にいる鈴木は、同時に鶴見俊輔や久野収などの思想の科学研究会でも今も研究を続けていらっしゃる。二つのフィールドが鈴木の学問をいっそう広く深いものとしている。
叙述の方法としては、鈴木は、歴史や人物に依拠しながら、思想について思想家を通じて論じている。何回か読む内にはっとした。叙述は読者が読みやすいような語り口となっ
ている。しかし、研究の方法としては、かなり構造的な範疇と歴史性とを踏まえて研究を進められていらっしゃる。そのことは、第一章の歴史編を読み、論じられている内容に注意すると見えてくる。その点を明確にしたいと考えたが、評者の力に余る作業なので中途で挫折した。いくつか事例をあげることで代えたい。
たとえば、「日中友好に尽くした人々」は、副題として「政治家、学者、芸能人から無名な一市民に至るまで」と書かれている。日中友好という歴史的事業がどのような担われ方をしたか、その主体と運動に着眼した構想をを示す典型と思う。また、「老人よ 哲学に戻れ」や「『愛』『反戦』の背後にあるもの それは人間」「孤高を嫌う現代人」などのタイトルに、主題と着眼点、思想史学の方法などが明晰に示されている。
最後にひとつ。第一章「歴史」の中の『「愛」「反戦」の背後にあるもの それは人間』の節である。著者は、最後をこう結んでいる。
「愛の神エロスと人間男女間の好色的(エロティック)な愛の境界線を引き離してはいけない。それが平和を愛する人間の知恵である。」と。
真面目である人、潔癖な正義感のもち主が、通俗のなかの光るものまで卑属とさげすみ、汚れると感じて、根っからそういうものをバカにして目も向けないとしたら、それは独善となってさまざまな多くの人と協力して戦争反対の実をとることはできない、鈴木はそう主張する。その主張には私は賛成する。たとえば休刊となった月刊『噂の真相』の健闘がある。編集者・作家の岡留安則は、いまは沖縄に住んでジャーナリスト活動をしている。その岡留が送り出した『噂の真相』は、一方ではスキャンダルやエロティックな記事も共存していた。スキャンダル記事は、当時の自民党政治家など権力者を撃った。本多勝一氏とは裁判にいたるなどさいごは犬猿の仲となったが、同じ週刊金曜日の佐高信などからはそのすぐれた報道感覚を評価されてきた。岡留の場合には、鈴木の主張が的確にあてはまり私にも理解できる。しかし、その根拠のひとつとしてヌードモデルとしてメッセージ入りの写真集などを発売しているインリン・オブ・ショイトイの事例があげられているる。週刊現代のグラビアの写真のそばに、彼女自らによって添えられたメッセージがある。
「愛 国家を捨て、個人のために生きよう。暴力を捨て、理性の為に生きよう。人間なら生存の為に出来るはずだ。」「非戦 平和を願うことは、ボケでも、理想主義でもない。平和は対話努力で築くものであり、武力・軍事同盟で生まれる事はあり得ない。」
正直私には、迷いがある。若い女性のインリン・オブ・ショイトイについては知っているが、著者の所論と彼女の芸能活動とは接続するものなのか。現在東京新聞の夕刊で、瀬戸内寂聴が『この道』と題する長編のルポルタージュを執筆している。そこでは大杉栄と伊藤野枝のやりとりをはじめ、性愛の奔放な実際と人間史を描き出している。エロスは人間の解放と分かちがたい。けれど、たとえば沖縄返還に関する密約を暴き出した毎日新聞の西山記者は、外務省の女性事務官との間を「情を通じて」いう偏見におもねる謀略で失墜させられて、長年経ってアメリカ機密外交文書が公開されるまで辛酸を舐める苦闘に陥った。そのことは山崎豊子の小説『運命の人』とそのTBSテレビドラマ化で広く知られている。戦前の非合法化の日本共産党の党員とハウスキーパーの女性たちとの関係は、戦後に厳しく世間で冷たい目にさらされた。鈴木正の展開の八割には、納得しながらも、生命の再生産過程に位置する恋愛や婚姻、性行為や出産など広義の「性」は、鈴木の結論とどのように構造化されるものか、私には読み下せない残り二割の課題として残された。 (農山漁村文化協会人間選書 2005年 定価1950円)
誠実な実践家であった鈴木は、肺結核に罹患してやむなき静養につとめる。唯物論研究会と思想の科学研究会の研究会に所属して、今までに思想家論に力点を置き、社会思想史の研鑽に努めてきた。
私が氏の存在に着目したのは、「岩田義道論」や、古在由重とご本人との対談など数回に及ぶ労作を掲載した季刊『現代と思想』においてである。この季刊雑誌は、一九七〇年から十年間にわたって青木書店から、江口十四一編集長のもとに刊行され続けた思想哲学雑誌である。統一戦線の思想的基盤を形成することをめざして編集された。一九七〇年代の革新運動の知的思想的母胎のひとつとよんでも大げさではない。そこで鈴木正の言論に感銘を受けて、以降氏の著作を店頭などで見つめると必ずといっていいくらいに購読したり図書館で借りたりして読み続けてきた。
本書は二〇〇五年三月が初版である。副題として「日本が凝り固まらないために」と記されている。歴史、人物、思想の三章から成立している。そのいずれも独創的な着眼点から思想を見つめ、堅苦しくない語り口の文体で、新鮮な思想史学を読者に提供している。中でも私には、第二章の「人物」編が強く印象に残った。
第二章で取り上げられている人物は、のべ二十人。「思想の科学研究会」における最良の方法論を駆使して、著名な思想家に偏らず、草の根の無名な人々に着目している。我が国の民衆史において継承するに値する真価を腑分けしてる。読み進むにつれてひきこまれてゆく。
梅本克己、芝田進午、古在由重、尾崎秀實、小林トミ、中江兆民研究者、安藤昌益研究者、白鳥邦夫、栗木安延、石堂清倫、家永三郎、藤田省三、土方和雄、江口圭一、高畠通敏などの広範で多岐にわたる人物についての叙述は、鈴木正ならではのものである。
中には、日本共産党の側にいるひと、日本共産党から追われたひとなどひとつの視点から見たら、相反するように見える人物選択には、鈴木の政治と思想に対する生き方と着眼点の見事さをうかがい知ることができる。誰でもなんでもよしとする、というのではない。同時代にどのように生きていたかの人間的な姿のありようを見極めて、多面的な人間像として把握するとともに、その矛盾や実態についてしっかりと見極めている。
古在由重は、核廃絶問題に取り組み、原水禁と原水協との統一行動における大衆運動の実践をめぐり、日本共産党と対立した結果、除籍された。芝田進午は、胆管がんでご逝去されて偲ぶ会の席上、友人代表として挨拶に立った上田耕一郎から永年党員と賞賛された。日本共産党からすれば、一方は好ましい存在として、他方は党の方針と異なる行動をとった存在として、両者は百八十度異なる価値付けをされるかも知れない。
だが、芝田は古在由重を戸坂潤とともに、戦前に独創的な世界レベルの唯物論哲学を築き上げた実践的唯物論者として尊敬していた。
鈴木正は、古在由重が戦時中に日本共産党員がすべて獄中につながれ、党が壊滅した後で、京浜地域の工場労働者たちの秘密学習会のチューターとして、実質的な党活動を行ったことを紹介している。同時に、中国共産党が日本からの侵略下で、激しい弾圧に対して「偽装転向」として転向上申書を書いて獄中から出て、即刻反戦活動を行ったことを述べている。その偽装転向は、中国共産党の政治的高等戦略として、中央指導部からだされた極秘方針として広く浸透していった。古在由重は、二度転向の上申書を提出している。ところが獄から出て、古在は即刻コミンテルンのスパイとして逮捕されていた尾崎秀實を釈放するために、弁護士を探すことに奔走し、弁護士を探し出すことに成功した。結果は、尾崎秀實は釈放されることはあたわずに、日本人共産主義者として唯一死刑に処された。鈴木正は、古在の実質的な抵抗としての反戦党活動の意義を、戦時下の中国共産党の戦略と照らし合わせて意義を讃えている。
また芝田進午についても、「私にとって芝田さんはフェアで寛容な人だった。」という書き出しで始まり、「小宮山量平氏(元理論社会長)がいう左翼に多い”分裂体質”とはちがった芝田さんのありし日の面影を偲びながら、つくづくもっと生きて活躍してほしかったと思う。」と結んでいる。小宮山量平は、つい最近2012年4月13日に95才の長寿ながら老衰でご逝去された。鈴木正は、本書では直接論じてはいないけれど、小宮山量平の「統一体質」という思想の気風で共通するものをお互いに感じている。鈴木と渡辺雅男と二人で小宮山から聴き取る対談集を『戦後精神の行くえ』(こぶし書房刊)として出版している。小宮山量平については、いずれ機会を改めてその比類なき文化形成の労作ぶりについて検証したい。
梅本克己は主体的唯物論として、石堂清倫は構造改革派として、藤田省三も政治思想的問題でそれぞれ日本共産党からは除名や除籍されている。鈴木正は、この三者をレッテル貼りで済ますようなことはしない。とくに石堂清倫は、グラムシを日本に紹介した先駆者である。いわゆる運動戦に対置して陣地戦をグラムシは提起して、先進的資本主義国での革命の論理を提起した石堂の卓越さを、惜しむことなく讃える。そして、石堂清倫と同郷で先輩の中野重治をも視野に入れて論じている。藤田省三についても、丸山眞男の政治学を継承した政治思想史の碩学として、藤田の学問的人間的豊かさを描き出している。
戦後直後に「主体性論争」の一方となる梅本克己についても、「戦後活躍した哲学者の中でも最も好きな一人である」と述べて、懐かしく梅本の、大衆につながる日常感覚の確かさと民族・日本人への深い関心の二点を特筆している。主体性論については、先に挙げた小宮山量平が、戦後直後に理論社から『季刊理論』を出版して、初期の黒田貫一をいちはやく逸材として発掘して、表現の場を与えている。黒田は、日本共産党と袂をわかち、革命的共産主義者同盟を組織して、革共同が分裂してからはいわゆる革マル派の理論的指導者として注目された。小宮山は日本共産党とも革共同とも無縁であったが、党派にとらわれず、納得したり共鳴したりする点では広く胸襟を開いて対話を行っている。その思想的体質は、小宮山量平と鈴木正とに著しく共通する点で、後の世代が継承するべき大切な事柄と考える。
鈴木をしてこのように戦後史における知識人を、近現代思想史上に位置づけて的確に把握させている基盤や原動力はなになのか?そのことが第一章の「歴史」、第三章の「思想」を読むと、はっきりとわかる。鈴木は、名も無き民衆の生活知と賢い理性とを大切にしている。そのことが、歴史上の無名な民衆や歴史の奥底で眠る重要な存在を発掘している。
「アテルイを知っていますか」という第一章の節では、桓武天皇の命を承けて東北地域「制圧」のために派遣された坂上田村麻呂によって滅ぼされた側の蝦夷の大将アテルイについて言い及んでいる。この節を読むと、歴史をどう見るかということを単眼でなく、複眼で見ることの鈴木の視座が明晰に伝わってくる。この見識も、2000年に京都清水寺の境内の墓碑の発見から始まっている。何気ない事物を虚心坦懐に見つめ、そこから思想史学を構築してきた鈴木の学問的方法論に、氏が青年の頃から学んできた思想の科学研究会での新たな学問的アプローチが体現されている。限られた紙数では語り尽くせない氏の、戦後史に題材をとった豊かな学問的発掘が本書には展開されている。
副題の「日本が凝り固まらないために」が同時に副題とされている第一章中の「敗走の訓練と散沙の民」という文章が象徴的である。森毅が、朝日新聞の対談記事で、
「昔の軍事教練で、敗走の訓練を覚えてます。隊列を組むな、バラバラで逃げろといわれた。・・・・・固まって逃げたら一斉にやられる。今、経済は『第二の敗戦』といわれてるでしょ。そんな時、みんな一緒のことやってたら、終わりです。」と述べていることに思いを寄せる。鈴木は、こうも述べている。
「メールをすぐ送るとか、ワープロで打った習作か草稿程度の文章を他人(ひと)に見せるとか、近ごろははき出すことが多すぎてどうも念慮が足りない。どうせ大した調査研究でないから、あとで盗作や剽窃といった心配も一向にないらしい。じっと息を懲らさないと表現は彫琢できないのに。携帯電話も同じで、ゆっくりする時間を奪う。ある友人は、恋人の間ではケイタイは監視機能を果たす凶器だ、とくさしていた」。
この節には、じっくりと考え、思想を熟成するような営みを軽んじて、電脳「文化」によって文化がculture「耕される」ものではなく、多機能映像機器の駆使としてしか扱われていない文明論的危機の表明が提起されている。さらに、孫文が中国の民衆を「散沙の民」と称したことと絡めての重要な指摘がなされている。こちらは直接これから読書なされるかたのために省略する。
本書に収められた鈴木正の論文は、名古屋哲学研究会の機関誌『哲学と現代』や労働運動の機関誌『人民の力』に執筆した論文が多い。名古屋をはじめとする中京文化圏は、名古屋大学哲学科の古在由重、真下信一や日本福祉大学の嶋田豊、福田静夫など有数の哲学者の足跡がある。法学の長谷川正安、社会学の本田喜代治、政治学の田口富久治などの学者の名が思い浮かぶ。唯物論研究協会に結集する哲学者の中にいる鈴木は、同時に鶴見俊輔や久野収などの思想の科学研究会でも今も研究を続けていらっしゃる。二つのフィールドが鈴木の学問をいっそう広く深いものとしている。
叙述の方法としては、鈴木は、歴史や人物に依拠しながら、思想について思想家を通じて論じている。何回か読む内にはっとした。叙述は読者が読みやすいような語り口となっ
ている。しかし、研究の方法としては、かなり構造的な範疇と歴史性とを踏まえて研究を進められていらっしゃる。そのことは、第一章の歴史編を読み、論じられている内容に注意すると見えてくる。その点を明確にしたいと考えたが、評者の力に余る作業なので中途で挫折した。いくつか事例をあげることで代えたい。
たとえば、「日中友好に尽くした人々」は、副題として「政治家、学者、芸能人から無名な一市民に至るまで」と書かれている。日中友好という歴史的事業がどのような担われ方をしたか、その主体と運動に着眼した構想をを示す典型と思う。また、「老人よ 哲学に戻れ」や「『愛』『反戦』の背後にあるもの それは人間」「孤高を嫌う現代人」などのタイトルに、主題と着眼点、思想史学の方法などが明晰に示されている。
最後にひとつ。第一章「歴史」の中の『「愛」「反戦」の背後にあるもの それは人間』の節である。著者は、最後をこう結んでいる。
「愛の神エロスと人間男女間の好色的(エロティック)な愛の境界線を引き離してはいけない。それが平和を愛する人間の知恵である。」と。
真面目である人、潔癖な正義感のもち主が、通俗のなかの光るものまで卑属とさげすみ、汚れると感じて、根っからそういうものをバカにして目も向けないとしたら、それは独善となってさまざまな多くの人と協力して戦争反対の実をとることはできない、鈴木はそう主張する。その主張には私は賛成する。たとえば休刊となった月刊『噂の真相』の健闘がある。編集者・作家の岡留安則は、いまは沖縄に住んでジャーナリスト活動をしている。その岡留が送り出した『噂の真相』は、一方ではスキャンダルやエロティックな記事も共存していた。スキャンダル記事は、当時の自民党政治家など権力者を撃った。本多勝一氏とは裁判にいたるなどさいごは犬猿の仲となったが、同じ週刊金曜日の佐高信などからはそのすぐれた報道感覚を評価されてきた。岡留の場合には、鈴木の主張が的確にあてはまり私にも理解できる。しかし、その根拠のひとつとしてヌードモデルとしてメッセージ入りの写真集などを発売しているインリン・オブ・ショイトイの事例があげられているる。週刊現代のグラビアの写真のそばに、彼女自らによって添えられたメッセージがある。
「愛 国家を捨て、個人のために生きよう。暴力を捨て、理性の為に生きよう。人間なら生存の為に出来るはずだ。」「非戦 平和を願うことは、ボケでも、理想主義でもない。平和は対話努力で築くものであり、武力・軍事同盟で生まれる事はあり得ない。」
正直私には、迷いがある。若い女性のインリン・オブ・ショイトイについては知っているが、著者の所論と彼女の芸能活動とは接続するものなのか。現在東京新聞の夕刊で、瀬戸内寂聴が『この道』と題する長編のルポルタージュを執筆している。そこでは大杉栄と伊藤野枝のやりとりをはじめ、性愛の奔放な実際と人間史を描き出している。エロスは人間の解放と分かちがたい。けれど、たとえば沖縄返還に関する密約を暴き出した毎日新聞の西山記者は、外務省の女性事務官との間を「情を通じて」いう偏見におもねる謀略で失墜させられて、長年経ってアメリカ機密外交文書が公開されるまで辛酸を舐める苦闘に陥った。そのことは山崎豊子の小説『運命の人』とそのTBSテレビドラマ化で広く知られている。戦前の非合法化の日本共産党の党員とハウスキーパーの女性たちとの関係は、戦後に厳しく世間で冷たい目にさらされた。鈴木正の展開の八割には、納得しながらも、生命の再生産過程に位置する恋愛や婚姻、性行為や出産など広義の「性」は、鈴木の結論とどのように構造化されるものか、私には読み下せない残り二割の課題として残された。 (農山漁村文化協会人間選書 2005年 定価1950円)



















