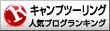8月20日。土曜日。狭い県道で長野県佐久市を往復するツーリングにでかけた。クネクネの峠道をはしってみたいとおもったのだ。群馬県南牧村の道の駅、オアシスなんもく、で休憩する。

今回は朝から晩までハードにはしる予定なので相棒はセローだ。

道の駅の先には景勝地の蝉の渓谷があった。峡谷だ。

庚申塔もたっている。田口峠にいたるこの県道は、昔から長野と群馬をつなぐ大事な街道だったのだろう。

群馬の最終集落の観能につくと、県道108号線は通行止めとある。元よりこちらにゆくつもりはなかったが、林道大上線が長野県側とつながっているようだ。土砂崩れが復旧したら走ってみたいものである。

県道94号線をゆく。狭い舗装林道で砂がういている。

路面もあれていた。

峠が群馬と長野の県境なのかとおもっていたらそうではなかった。県境から峠まで距離がある。その間の山奥にポツン、ポツンと民家があるのにおどろく。そしてこの山奥でチェアリング(気にいった場所で椅子にすわってすごす)をしている人がふたりいた。私は気がみじかいからこんなことはできないな。

ヘアピンカーブが連続する最終部分をぬけて田口峠に到着した。ここに来たのははじめてである。この道は難路で、北をはしる国道254号線をゆくよりも倍の時間がかかったとおもう。

峠の標柱のさきにトンネルがあり、

そのさきにピークがあった。ここで雨がふりだした。予報では晴れのはずだし、空は明るいのでカッパをつけずに佐久にくだった。

中込駅ちかくの三河屋食堂にやってきた。佐久名物の鯉をたべにきたのである。

12時すぎについたが満席で20分まって席に案内された。たのんだのは洗いと甘煮の定食2500円である。

鯉の洗い。淡白で繊細。ほんのりと甘い後味。わさびしょう油がよくて、酢味噌は香りが独特で口にあわなかった。

鯉の甘煮。煮付けである。鯉を筒切り(輪切り)にした部分と腹の剥き身(あばらの部分・骨付き)、内臓がもられている。他の魚で見ないY字形の小骨がおおいが、脂がのっていてトロトロ。金目鯛よりもやわらかいとかんじた。

はやの開きの唐揚げ。これは天然物なのだろう。野趣がほんのりとにおった。養殖の鯉はそんなことはまったくなかった。

本場の鯉はちがう。また来たいとおもった。

三河屋のむかいは鯉屋さんである。臼田鯉店。

店をでると雨がつよくなっていた。ただ空は明るいから、中込駅を見にいったり、

商店街をあるいたりするが、雨降りはやまない。いつまでも待っていられないから、カッパのズボンとブーツカバーだけをつけて走りだすことにする。このときはそのうちに降雨はやむだろうとおもっていたのだ。

弱い雨の中をやってきたのは八千穂の奥村土牛記念美術館である。

奥村土牛は明治にうまれて平成になくなった日本画家だ。戦時中にこの地に疎開していたのが縁で美術館がつくられたとのこと。

私が入館しようとすると、都内ナンバーのスクーターの男性と入れちがいとなった。

奥村土牛の作風はシンプルなものだった。少ない線で絵はかかれている。人物や風景よりも静物がよかった。ほかに見学者はいなくて、私がでようとするとまた年配の男がやってきた。入館料は500円。

美術館をでると雨はさらにつよくなっているので、カッパをフル装備して、ザックにもザックカバーをかけた。これから帰りのクネクネ道のはじまりである。

山小屋のような小海駅のまえをとおり、県道124号線で県境にむかう。長野県側はカーブはすくない。やがてぶどう峠に到着した。

峠には見覚えがある。前にきたことがあった。

峠からの風景はかすんでいた。ぶどう峠は長いあいだ通行止めだったようだ。それが最近通行できるようになったようで、タイミングがよかった。

群馬県側の下りは雨の上にガスもでて、しかも暗くなって視界がわるい。なんだか魔物がでてきそうな雰囲気だ。

望んだとおりの急坂、急カーブの連続を慎重にくだってゆく。浜平温泉しおじの湯までくだると、以前はなかった御巣鷹の尾根の案内がある。以前はちかづくことも、口にすることもはばかられた航空機の事故現場だが、時がすぎて案内板も必要になったのだろう。

雨の山道をひたすら下る。神流湖がみえるパーキングで休憩した。

天気予報は完全にはずれだ。半日雨の中をはしることになった。雨中走行したのはひさしぶりである。最近は天気をみてでかけているし、トランポ・ツーリングがおおいので、雨にあたることがなかったのだ。

帰宅してから確認すると、ブーツカバーとザックカバーが水漏れをおこしていた。ひさしぶりに雨にうたれてみると、交換しなければならない道具もわかるというわけだ。しかし雨天走行はきらいである。燃費は52、1K/Lと驚異的な数字をマークした。