 昨日の夕刊(2014/05/20「京ものがたりの」)に漱石と磯田多佳との交流についての記事が載っていた。
昨日の夕刊(2014/05/20「京ものがたりの」)に漱石と磯田多佳との交流についての記事が載っていた。昔、心斎橋近くの古書店で買った「磯田多佳女のこと」・谷崎潤一郎著を思い出した。
急いで書棚をひっくり返すと出てきたのが下の写真の本である。
 読み返してみると、まず、名文であることに感動した。
読み返してみると、まず、名文であることに感動した。磯田多佳女への哀惜の念が、失われた祇園の風景と二重写しになって語られる。
疎開のために打ち壊された祇園の茶屋「大友(だいとも)」。
多佳女の自分だけの三畳の居間。白川の音が心地よい眠りに誘う。まさに、枕の下を水の流るる感じ。
谷崎の名文により川の音は蘇り、一人の女性の姿が浮かび上がってくる。
漱石と磯田多佳についても書かれている。「春の川を隔てゝ男女哉 漱石」の句もある。
最初にこの句を読んだ時、
 区切りが分からなかった。
区切りが分からなかった。「春の川を/隔てゝ男/女哉」
分かってみると良い句である。
「流れた「約束」すれ違う男女」の新聞のフレーズも適切だ。
 だが、「を」は必要なのだろうか。
だが、「を」は必要なのだろうか。「を」によって、6,7,5になって、5,7,5の定型から外れている。
「を」を外してみる。
「春の川/隔てゝ男/女哉」
平凡な写生句になった。
定型を外すことによって、詩的な世界から小説的な世界にたった一文字で変貌している。
 俳句は怖い。
俳句は怖い。 「春の川を/隔てゝ男/女哉」の方がはるかに上だと分かった。
「春の川を/隔てゝ男/女哉」の方がはるかに上だと分かった。












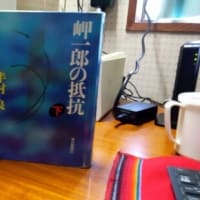







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます