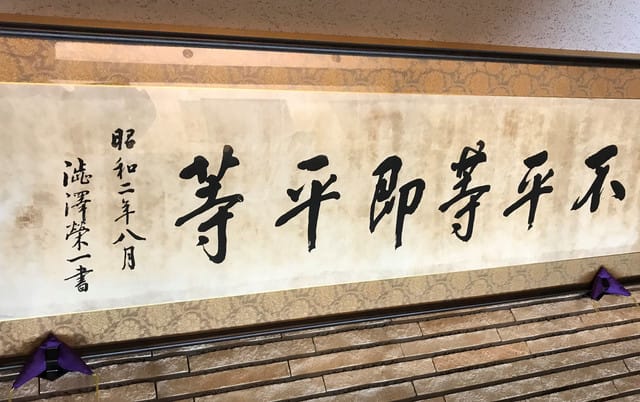2018年9月9日(日)
茗荷谷へ移動して月例のゼミ、修論主体だが博士課程からも学部卒研からも出席があり、毎度楽しい一日である。タボル山上のペトロさんではないが、座って聞いてて眠くなるといけないので、できるだけ立つようにしている。痩せる効果もありはしないかと期待するが、そううまくはいかないようで。
午前中ある院生に助言する中で、不意に「現実性と合理性」に関するヘーゲルの言葉が口をついて出てきた。正確にはマルクス・エンゲルスによる引用の方である。読んだのは40年近く前、以来思い出す機会もほとんどなかったはずだから、こんなことがあるのかと自分でも驚いた。それを誘導したのは院生の知的な資質で、あたかも彼女の磁石が当方の記憶の小鉄片を吸い出したかのようである。
帰宅後に確認:
「一例をとろう。「現実的なものはすべて合理的であり、合理的なものはすべて現実的である」というヘーゲルの有名な命題(へ―ゲル『法の哲学』)ほど、物のわからぬ政府の感謝と、それにおとらず物のわからぬ自由主義者の怒りをまねいた哲学的命題はなかった。」
これ、これ。面白いので長めに転記しておこう。
「これこそまさにすべて現存するものの聖化であり、専制主義、警察国家、専断的裁判、検閲の哲学的祝福ではなかったか。ヴィルヘルム三世(プロイセン国王、1770-1840)もそうとっていたし、その臣下たちもそうとっていた。しかしヘーゲルにおいては、現存するものはすべてただそれだけの理由で現実的でもあるとはけっしてかぎらないのである。現実性という属性は、かれによれば、同時に必然的でもあるものにのみ属するのであって、「現実性は、それが展開されると、必然的であることがわかる」とヘーゲルは言っている。したがってヘーゲルによれば、政府のどんな措置でも - ヘーゲル自身は「或る税制」の例をあげているが - 無条件に現実的であるということはけっしてない。しかし必然的なものは、けっきょくまた合理的でもあることが立証されるのである。したがってヘーゲルのあの命題は、当時のプロシャ国家に適用すると、次のようになるだけである。すなわち、この国家が合理的であり、理性にかなっているのは、そけが必然的であるかぎりにおいてである。それにもかかわらずもしそれがわれわれに悪く思われ、しかもそれが悪いにもかかわらず存在し続けるならば、政府の悪さは、それに対応する臣民たちの悪さのうちにしの当然の理由と説明を見いだすのである。つまり、当時のプロイセン人は、かれらにふさわしい政府をもっていたのである。」
ダメだ、面白すぎて全体を引用することになりかねない。優秀な院生のためにもう一ヶ所だけ、抜き書きして終わりにしよう。それにしても古びないものである。
「すべて人間の頭脳のなかで合理的であるものは、どんなにそれが現存する見かけだけの現実性と矛盾しようと、現実的なものになるように定められているのである。」「現実的なものはすべて合理的であるという命題は、ヘーゲル的思考方法のあらゆる規則にしたがって、すべて現存するものは滅亡に価するという他の命題に変わるのである。」
F. エンゲルス『フォイエルバッハ論』(松村一人訳、岩波文庫)P.14-16
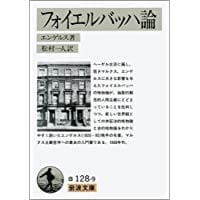
***
ところで大坂なおみ、凄いなぁ!
僕はテニスはやらないし、わからないので、にわかファンの典型たるものだが、とにかくびっくり、感動した。プレーの力強さとキレの良さに加え、あの異様な雰囲気とブーイングの嵐 - アメリカのテニスファンも大したことないね - の中で少しも乱れない自制の力。試合前後のいじらしいセリーナ・ファンぶりと、試合中の冷静果断、どちらも本物で虚飾がない。カウンセリングの成立条件にいう genuineness(自己一致)とはこういうものではないか。攻撃的・挑発的に時代を切り開いたセリーナの後を受け、朗らかで融和的な未来を築いてほしい。
もうひとつ、国とか民族とかをめぐる日本人の固定観念を、彼女が大いに揺さぶってくれるよう期待する。これは合理的であり、したがって現実的な期待のはずである。

Ω