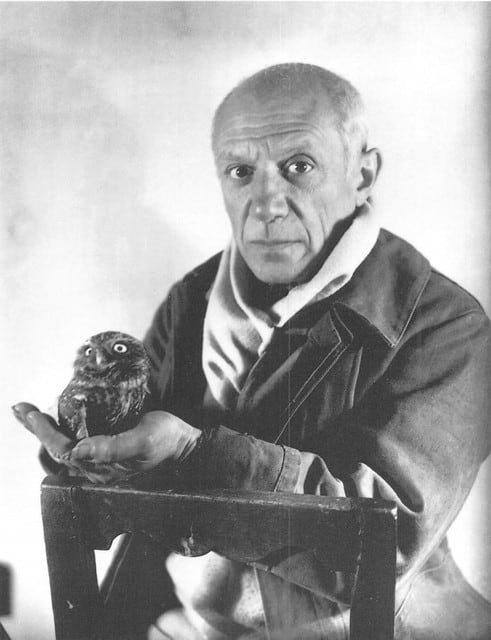2018年9月10日(月)
・・・この日に書いてあったのが、ほったらかしになっていた。
20代の頃、中国系マレーシア人の留学生女子に真顔で聞かれたことがあるというのが、話の発端である。
「丸石という姓は、丸い石ということでわかりますけど、石丸ってどういう意味ですか?」
答えに窮した。日本人からは出ない質問で、当時は未熟でもあった。今なら考えがある。確信はないけれど。
「丸」は円・球を意味するほか、別の用法もあるのは周知の通り。本丸とか真田丸とかは城郭の中の比較的独立した建造物、船の名に使われるのもこの「独立した建造物」から来ているのではないか。
「牛若丸」といった名前、とりわけ幼少児の呼び名に用いられたのは、丸々とした子どもへの愛しみ親しみに由来するらしい。そこから刀剣や楽器の持ち主が、愛用の逸品に「丸」の名を冠するようになった。船名の「丸」もこちらではないかとの説がある。
さてそうなると「石丸」は、
① 木造主体の日本の建築物の中で、特に石造りの一画を呼んだもの
② そのような建物に住んだりその建築運営に関わったりした人または職種
といったところだろうか。
船名ではあり得ない、沈んでしまう。愛称の「丸」の方は「石」一字との組み合わせでは無理がありそうだ。
***
石丸姓は愛媛県とりわけ中予に多いが、佐賀にもクラスターが存在する。桜美林時代に他学部に別の石丸先生が着任してからは、郵便物がしょっちゅう誤配された。フルネームも所属も違うのに、姓が珍しいので「ああ、あいつか」と決め込むらしい。いい加減なものだ。
ある時会って話したところ、この人は佐賀の方の石丸で、先祖は鍋島藩に仕えた武家とのこと。刃物を研ぐのを趣味にしておられ、その関係で松山周辺には親しみがあるという。そう言われて初めて砥部という地名の由来を知った。砥部焼の白磁を生む土壌は、良質の砥石の原料でもある。往古にその特産と技量をもって朝廷に仕えた部曲がこの地に存在したのだ。
そもそも砥部焼の起こりは、大洲藩・九代藩主の加藤泰候(かとう・やすとき 1760-87)侯が藩の財政を立て直すため、砥石くずを使った磁器づくりを命じたことに起源を発するとされる。加藤氏は秀吉麾下の猛将・加藤光泰を祖とするが、その子貞泰が関ヶ原で東軍に属して美濃の本領を安堵され、1617年に大洲へ移封された。何しろ砥石が先、焼き物が後である。
それにしても伊豫の石丸はどこに由来するものか。砥石の石とは関係なかろう。いつか知りたいと思っていたら、数年前のクリスマスだか誕生日だかに、家人が面白い本をプレゼントしてくれた。『えひめ名字の秘密』というのである。
著者の調査によれば、石丸姓は愛媛県内での順位が69位、全国では691位*とのことだから、やはり有意に多いのだ。
* 名字由来 net (https://myoji-yurai.net/prefectureRanking.htm)による
とはいえ愛媛県内でもさほどメジャーなものではなく、170ページ余りの本にたった二箇所出てくるだけである。
***
① 『朝倉の歴史』によると、石丸氏は、大内義弘の子・吉国を祖としています。大内氏が滅亡したのち、石丸甚左衛門吉富は、朝倉村(今治市)に帰農しました。のちに矢矧(やはぎ)神社の宮司となっています。(P.95)
② 明暦4(1658)年につくられた『明暦松山支配帳』から、この時期の百石取り以上の藩士を列記してみましょう。(中略)二百石の・・・石丸見棟・・・(後略)(P.158)
***
この二つの記述がどうつながるかは、よく分からない。大内氏が梟雄・陶晴賢に事実上滅ぼされたのは天文20(1551)年で、明暦支配帳までほぼ一世紀の空白がある。①と②の両系統間につながりのある証拠はないが、無関係なら今度は「石丸見棟」という侍(読み方が分からない!)のルーツを別に探さないといけない。
家の伝説では石丸姓を名乗って僕が14代目という。仮に一代30年とすれば開祖は西暦1500年代半ばの生まれ、20年とすれば1600年代の後半になる。石丸甚左衛門吉富に直接つながる可能性もなくはないが、ちょっときわどいかな。
あとはお寺の過去帳か。臨済宗善応寺、曾祖父が縁を切っちゃってるので、ちょっと敷居が高いのである。

Ω