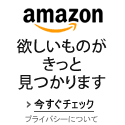色々と考える・・・何が正しいのか?すべてに正解は無いのは判っているが、
どうしたら間違った選択にならないのか?・・・何でも良いから手掛かりが欲しくなり
先に進みたい・・・と張り出したりする・・・そんな事が多々あった。
そう言うと今回だってこうして張った事を考えると、変わり無いじゃん・・・と思う人も
いるだろうが、大きく違うのはだるまである事。確かにここまで下絵をきちんと描き込んだ作品はあるが、それは人がモチ-フだったりした・・・しかし今回はだるま。
生きているものと生きていないものは全く違うのである。肌を生き生きと・・・見せたい
と思ったりするのが、立体に見えるように・・・となる。
両者ともタイルを切る行為は一緒だが、色の選択が大きく違って来る。
眉毛を1色で良いだるまとそうで無い人とでは、悩み具合いは大きく違って来る。
そんな事も踏まえて、下絵の追加だったり、描き込み方にこだわったのは、作り始めれば
決まった色をどんな形で表現するか?になり、考え事が大きく減る事に繋がって行くから
・・・・。そんな事からも、今日も下地を作ってのスタ-トだったが、悩んだ末に
こうなった・・・これが全景。

一体何処を抜くか?本来なら、文字部分も一緒に抜く事も考えたりする。
ただ確かに抜ければお洒落感は増す気はするが、抜くように描いて無いから、
間違いなく物理的に無理がある場所がある。ではそれを描き直す必要があるか?となる。
そもそも道具はバランスを見て配置してあり、その後の文字に付いては後出しとなり、
当然隙間に入った事になり、窮屈感は文字の方になる。ならば描き直して道具の上を
文字が通過すれば良い事になるが、そうなると道具が下になる。
百聞は一見にしかずと言うのなら、やはり文字よりも絵を見せた方がより判り易いかな
・・・とも思ったし、隠してしまうと大工の7つ道具の表現が曖昧になると困る。
何しろ絵なら成立するだろうが、モザイクって言うのは点々の繰り返し。
場合に寄ってはそう見えなくなるかも知れない。安全確保は備えあれば憂いなし。
だから道具が前になる。しかし今度は文字を下にしてしまうと読めなくなる恐れがある。
だから道具に近い余白に入れる事は正しいと思われる。
そしてこのバランスで保たれるだるまは鳥が木に止まっているようにも見えるし、
中心にいる・・・道具の・・・・つまり大工さんって言うのは単なる職人。
中心って言うのが、職人の中心となると、棟梁と名が変わる。
単なる仕事をするのは大工、仕事を取り、あらゆる職方の世話を焼き、家を丸々
請け負う人は棟梁。別物になる。この人は親子2代の棟梁。だから職方とのバランスも
必要となる。これが家族の中心と考えても良い。家族の干支もだるまには入っているから
・・・・いずれにせよ、そんな事を考えた末に出た答えはこの下地になった・・・・
ここに後悔や心残りが無ければ、黙々とタイルを切る形のみを考えれば、
大きな間違いは起こらないはず・・・そう思える所まで来た。
そんなこんなの張り出し。
どうしたら間違った選択にならないのか?・・・何でも良いから手掛かりが欲しくなり
先に進みたい・・・と張り出したりする・・・そんな事が多々あった。
そう言うと今回だってこうして張った事を考えると、変わり無いじゃん・・・と思う人も
いるだろうが、大きく違うのはだるまである事。確かにここまで下絵をきちんと描き込んだ作品はあるが、それは人がモチ-フだったりした・・・しかし今回はだるま。
生きているものと生きていないものは全く違うのである。肌を生き生きと・・・見せたい
と思ったりするのが、立体に見えるように・・・となる。
両者ともタイルを切る行為は一緒だが、色の選択が大きく違って来る。
眉毛を1色で良いだるまとそうで無い人とでは、悩み具合いは大きく違って来る。
そんな事も踏まえて、下絵の追加だったり、描き込み方にこだわったのは、作り始めれば
決まった色をどんな形で表現するか?になり、考え事が大きく減る事に繋がって行くから
・・・・。そんな事からも、今日も下地を作ってのスタ-トだったが、悩んだ末に
こうなった・・・これが全景。

一体何処を抜くか?本来なら、文字部分も一緒に抜く事も考えたりする。
ただ確かに抜ければお洒落感は増す気はするが、抜くように描いて無いから、
間違いなく物理的に無理がある場所がある。ではそれを描き直す必要があるか?となる。
そもそも道具はバランスを見て配置してあり、その後の文字に付いては後出しとなり、
当然隙間に入った事になり、窮屈感は文字の方になる。ならば描き直して道具の上を
文字が通過すれば良い事になるが、そうなると道具が下になる。
百聞は一見にしかずと言うのなら、やはり文字よりも絵を見せた方がより判り易いかな
・・・とも思ったし、隠してしまうと大工の7つ道具の表現が曖昧になると困る。
何しろ絵なら成立するだろうが、モザイクって言うのは点々の繰り返し。
場合に寄ってはそう見えなくなるかも知れない。安全確保は備えあれば憂いなし。
だから道具が前になる。しかし今度は文字を下にしてしまうと読めなくなる恐れがある。
だから道具に近い余白に入れる事は正しいと思われる。
そしてこのバランスで保たれるだるまは鳥が木に止まっているようにも見えるし、
中心にいる・・・道具の・・・・つまり大工さんって言うのは単なる職人。
中心って言うのが、職人の中心となると、棟梁と名が変わる。
単なる仕事をするのは大工、仕事を取り、あらゆる職方の世話を焼き、家を丸々
請け負う人は棟梁。別物になる。この人は親子2代の棟梁。だから職方とのバランスも
必要となる。これが家族の中心と考えても良い。家族の干支もだるまには入っているから
・・・・いずれにせよ、そんな事を考えた末に出た答えはこの下地になった・・・・
ここに後悔や心残りが無ければ、黙々とタイルを切る形のみを考えれば、
大きな間違いは起こらないはず・・・そう思える所まで来た。
そんなこんなの張り出し。