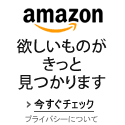今日は朝オイル交換からスタート。午後からさくら教室。そんな中、1時間位、昨日の下絵を切らせて貰ったのね。それをさくらに動画に撮って貰って、様子を見たかったのね。一体どの位の時間が掛かって、どれだけ疲れるか?正直、描き写した段階で、思ったよりも大変で結構時間が掛かった。当然それを切るのだから、もっと
時間は掛かる・・・それをやる前の想像の中でヤキモキするよりも、大体この位・・・の目安があれば検討が付き、今後の展開を予測する事も出来る。

その結果がこれ。恐らく1回で1時間程度を2回やらないとならず、結構気持ちが削られるのね・・・長さが90cmもあるのに、5mmのベニアをこんな複雑に抜くって言うのは、失敗すると折れる訳で・・・どの位、慎重に何処から切るのか?みたいな事を考えながらやらないとならず、けれどそれを1枚やっただけでは、上手く行けば、
簡単だと判断したり、失敗すれば手慣れていないだけかも知れないのに、必要以上にダメージを受ける。人の気持ちとはそんな単純なもので、最初に成功をすると痛みも知らずの成功は、失敗した時の立て直し方や用心する場所など、何の何処が成功に至ったか?の検証が出来ず、かと言って、1枚目で失敗をすれば、その
難しさが何枚も続くのか?・・・と果てしなさを覚える。しかしその失敗の是正の参考にもなる訳で。しかしそう思えてもそのダメージと引き換えな訳で。いずれにしても、そう言う事無しで、ただ切るって進められる人はそれで良いが、その人は自分が出来ても、何故成功したのか?を説明する事は出来ない。こんな人が職人に多い
のね。つまり技術は盗むもので教わるものじゃ無いからって言う理屈。でも確かに一理あるのね。つまり痛みを伴わない技術は、一定の成果は得られるが、それは教科書通りの工程を何事も無く進んだ場合の結果であって、いつもの環境や状況では無く、イレギュラーな事が起こった場合の対処は海千山千の現場をこなした
ものにしか中々難しい事で、ありとあらゆるハードルを逃げ切った事で得たものは、お母さんがハンカチ、テイッシュは持った?ほらテレビに集中しないで、こぼすからとか、歯磨いた?とか、宿題やったの?・・みたいに、そいつがきっとやっていないだろうな?を先読みされている訳で。それを習慣漬けされると、出来るようになり、
あたかも自分一人で出来るようになった気分で、判っているよ的な発言になったりするも、亡くなったからの有難みなんてものに繋がったりもして、それも全て伝承的なもので、反復練習だったりする。けれど言われていなくても、反面教師として出来ない人の失敗を見て、あぁにはならない・・・って勉強するのは盗む行為。
それも逆も真なりで、それを出来る能力があれば、出来たりもする。しかしその欠点は、必ず教わったものの中に失敗があり、反面教師の中にもわずかながらの成功がある。それを見極める眼は常に必要な訳で。道具1つ取っても時代が変われば、それに対応出来るか?出来ないか?で能率効率は上がる。しかし、それが
無くても、出来た時代はあった訳で。みんながみんなそうしている中、1人だけ昔のやり方みたいな行為はあまのじゃく的になるが、それはある意味、個性とも言える紙一重な行為な訳で。常に新しいモノを作ろうと先端に向かう考え方がある中、山下達郎さんは5.60年代の歌に詳しかったりすると、それも初めて知れば、
新曲だ・・・のように唱える訳で。それを今風に、自分風にアレンジをすると、それが新しいモノに見えたりする成功例だったりする。話はそれたが、常に何をしても教える事が出来るように・・・と人に教える前提でモノを考える癖があるのね。つまりもう一人の自分が俺の中にいて、こうしてイレギュラーな切る行為はいつも
手慣れた事とは違う訳で。つまり初心者では無いが、挑もうって言うような人の例だな・・・と。さてどっから切る?切り抜けば切り抜くほど、安定感は無くなり、折れる可能性は高まる。本来安定感と言うのなら、スタイロフォームって断熱材を引けば平らで切りやすいが、それを買ってまで捨てる前提の予算は無い・・・。
当然、厳しさは増す。つまり工夫だけで乗り越える練習かぁ・・・になる。慌てるな、良く考えろ、大丈夫か?先に進む事ばかりで何も考えないと、折れるぞ・・・何処が危ない?離れて見て見ろ・・・全部みんなに教えて来た事を自分に当てはめるだけ・・・しかし難易度が上がればそれだけでは乗り切れないし・・・。それが器。
1時間でこれだけ出来たんだから、1日で終わるじゃん・・・こんな楽観的な考えは過信。思った以上に疲れた訳で・・。つまりまだまだ先が長いのに、そんなに身を削っては、長く続かなくなる。言い方は悪いが騙し騙し進まないと。無理せず余力を残してグレードを保つ量や時間はここまで・・・とし、その余力でモザイク。
不得意得意の分量をほどほどにして、継続する。休まずに・・・って感じね。それで難関を突破すれば、得意な分野に進めるが、無理して疲れを残したり、グレードを下げると、モザイクでカバーしたり、時間を取り戻そうとグレードを下げては本末転倒な訳で。これもそれも全てそうならないように・・・教える為の体験。
そうね、つまり俺が切っているのに、もう一人の自分が見ていて、どうなんだ?って自問自答している感じなのね・・・いつもいつも。そう言う状況の人は今どんな気持ちで、どんな事に悩む?って。・・・いちいち手を止めてでも。そんな風に教えるって行為の練習をしている・・・って前提でさくらの小物作品を説明すると・・・
大作の下絵が描けていないんで、昔から持っていた下地を見つけたらしく、それをやるって決めたらしいのね。紐から見て小指の第二関節弱の大きさ。バックはビーズが付けたいとなると、土留めじゃ無いが、縁取りでせき止める事が必要だろう。では縁取り。アトリエにあるタイルでは9mmが最小でも、こんな小さくては
切らないと張れない。ではこの縁取りの黄金比は?となった時、この画像が適切に見えたとしたら?1cmの9分の1なのね。しかし、外側に切り口を見せる訳には行かないのね。危ないから。それを踏まえて、普通9分の1は、短冊に3列に切ってそれを3等分にする。その繰り返しを3回やると、成功すれば9パーツになる。
゜
しかし真ん中は両方切り口なるから、触るであろう端っこの縁取りには使えない。だから中の1列を捨てる覚悟の3等分のイメージ。ただ厳密に言えば真ん中の1粒だけ使えないだけなんだけれどね。まぁ先に進むと、そもそもこれを3個作ろうとしていたのね。けれど、恐らくやりそうな事は、サンプル的に1個仕上げようと、
する可能性があるのね・・・1個ずつみたいに。これが上手く行かない状況を作るのね。そもそも3個作るみたいなのは、大作と違って流れ作業なものなのね。つまり能率効率。こんな9分の1みたいなパーツ、ピッタリ切り終われると思う?恐らく余ったりするのね。それなのに次の工程に進むって。きっと無くすのね。
だから同じ工程は続けてやる。ここでせ若干ひねくれていたり、中々のツワモノは、さっきの下地続けてやらなかったじゃん・・・って突っ込んで来るのね。そうだね、確かに。でもね、あれは難易度高いって言ったよね。つまり身を削るから無理しない為だったのね。でもこの場合、余りが出ているパーツの放置になるのね。
ではまだ信用出来ない人へ。もし仮に1つずつ進んでいたとしよう。どうなるか?まだ乾いていない張り終わった縁取りの次に桜の花びらを張るのね。中心に合わせようとしたくなるのね。けれど、既存のパーツじゃないから、同じ大きさじゃないのね。つまり何と無く中心に合わせるしか無いのね。あっちこっち触るね。
その時に桜にばかり気を取られると、縁取りを触るのね。当然張ったばかり・・・動かすよね。直すよね。ズレるよね。深みにはまってさぁ大変。ドジョウが出て来てこんにちは・・・って事になりそうでしょ?つまり失敗する方向に向かうと思うのね。それをそっとして置いて、次々と縁取りをやっていると、最初のが乾いて来る。
その時に桜の花びらを張って、また張ってと3つやって、また戻る。すると今度はボンドのベタベタ感が落ち着く。そこでカッターでいらないボンドをそぎ落として・・・もう少し放置。帰り際に木工用のボンドを垂らして、ビーズを押し込む。それをスポンジで拭けば今日はおしまい。もう触らない。そして明日以降に目地。
こうした流れ作業で無駄な時間を使わない。これが1点モノじゃない作り方。けれど、目地をしていないから次回以降に持ち越しにはなるんだけれど。
時間は掛かる・・・それをやる前の想像の中でヤキモキするよりも、大体この位・・・の目安があれば検討が付き、今後の展開を予測する事も出来る。

その結果がこれ。恐らく1回で1時間程度を2回やらないとならず、結構気持ちが削られるのね・・・長さが90cmもあるのに、5mmのベニアをこんな複雑に抜くって言うのは、失敗すると折れる訳で・・・どの位、慎重に何処から切るのか?みたいな事を考えながらやらないとならず、けれどそれを1枚やっただけでは、上手く行けば、
簡単だと判断したり、失敗すれば手慣れていないだけかも知れないのに、必要以上にダメージを受ける。人の気持ちとはそんな単純なもので、最初に成功をすると痛みも知らずの成功は、失敗した時の立て直し方や用心する場所など、何の何処が成功に至ったか?の検証が出来ず、かと言って、1枚目で失敗をすれば、その
難しさが何枚も続くのか?・・・と果てしなさを覚える。しかしその失敗の是正の参考にもなる訳で。しかしそう思えてもそのダメージと引き換えな訳で。いずれにしても、そう言う事無しで、ただ切るって進められる人はそれで良いが、その人は自分が出来ても、何故成功したのか?を説明する事は出来ない。こんな人が職人に多い
のね。つまり技術は盗むもので教わるものじゃ無いからって言う理屈。でも確かに一理あるのね。つまり痛みを伴わない技術は、一定の成果は得られるが、それは教科書通りの工程を何事も無く進んだ場合の結果であって、いつもの環境や状況では無く、イレギュラーな事が起こった場合の対処は海千山千の現場をこなした
ものにしか中々難しい事で、ありとあらゆるハードルを逃げ切った事で得たものは、お母さんがハンカチ、テイッシュは持った?ほらテレビに集中しないで、こぼすからとか、歯磨いた?とか、宿題やったの?・・みたいに、そいつがきっとやっていないだろうな?を先読みされている訳で。それを習慣漬けされると、出来るようになり、
あたかも自分一人で出来るようになった気分で、判っているよ的な発言になったりするも、亡くなったからの有難みなんてものに繋がったりもして、それも全て伝承的なもので、反復練習だったりする。けれど言われていなくても、反面教師として出来ない人の失敗を見て、あぁにはならない・・・って勉強するのは盗む行為。
それも逆も真なりで、それを出来る能力があれば、出来たりもする。しかしその欠点は、必ず教わったものの中に失敗があり、反面教師の中にもわずかながらの成功がある。それを見極める眼は常に必要な訳で。道具1つ取っても時代が変われば、それに対応出来るか?出来ないか?で能率効率は上がる。しかし、それが
無くても、出来た時代はあった訳で。みんながみんなそうしている中、1人だけ昔のやり方みたいな行為はあまのじゃく的になるが、それはある意味、個性とも言える紙一重な行為な訳で。常に新しいモノを作ろうと先端に向かう考え方がある中、山下達郎さんは5.60年代の歌に詳しかったりすると、それも初めて知れば、
新曲だ・・・のように唱える訳で。それを今風に、自分風にアレンジをすると、それが新しいモノに見えたりする成功例だったりする。話はそれたが、常に何をしても教える事が出来るように・・・と人に教える前提でモノを考える癖があるのね。つまりもう一人の自分が俺の中にいて、こうしてイレギュラーな切る行為はいつも
手慣れた事とは違う訳で。つまり初心者では無いが、挑もうって言うような人の例だな・・・と。さてどっから切る?切り抜けば切り抜くほど、安定感は無くなり、折れる可能性は高まる。本来安定感と言うのなら、スタイロフォームって断熱材を引けば平らで切りやすいが、それを買ってまで捨てる前提の予算は無い・・・。
当然、厳しさは増す。つまり工夫だけで乗り越える練習かぁ・・・になる。慌てるな、良く考えろ、大丈夫か?先に進む事ばかりで何も考えないと、折れるぞ・・・何処が危ない?離れて見て見ろ・・・全部みんなに教えて来た事を自分に当てはめるだけ・・・しかし難易度が上がればそれだけでは乗り切れないし・・・。それが器。
1時間でこれだけ出来たんだから、1日で終わるじゃん・・・こんな楽観的な考えは過信。思った以上に疲れた訳で・・。つまりまだまだ先が長いのに、そんなに身を削っては、長く続かなくなる。言い方は悪いが騙し騙し進まないと。無理せず余力を残してグレードを保つ量や時間はここまで・・・とし、その余力でモザイク。
不得意得意の分量をほどほどにして、継続する。休まずに・・・って感じね。それで難関を突破すれば、得意な分野に進めるが、無理して疲れを残したり、グレードを下げると、モザイクでカバーしたり、時間を取り戻そうとグレードを下げては本末転倒な訳で。これもそれも全てそうならないように・・・教える為の体験。
そうね、つまり俺が切っているのに、もう一人の自分が見ていて、どうなんだ?って自問自答している感じなのね・・・いつもいつも。そう言う状況の人は今どんな気持ちで、どんな事に悩む?って。・・・いちいち手を止めてでも。そんな風に教えるって行為の練習をしている・・・って前提でさくらの小物作品を説明すると・・・
大作の下絵が描けていないんで、昔から持っていた下地を見つけたらしく、それをやるって決めたらしいのね。紐から見て小指の第二関節弱の大きさ。バックはビーズが付けたいとなると、土留めじゃ無いが、縁取りでせき止める事が必要だろう。では縁取り。アトリエにあるタイルでは9mmが最小でも、こんな小さくては
切らないと張れない。ではこの縁取りの黄金比は?となった時、この画像が適切に見えたとしたら?1cmの9分の1なのね。しかし、外側に切り口を見せる訳には行かないのね。危ないから。それを踏まえて、普通9分の1は、短冊に3列に切ってそれを3等分にする。その繰り返しを3回やると、成功すれば9パーツになる。
゜
しかし真ん中は両方切り口なるから、触るであろう端っこの縁取りには使えない。だから中の1列を捨てる覚悟の3等分のイメージ。ただ厳密に言えば真ん中の1粒だけ使えないだけなんだけれどね。まぁ先に進むと、そもそもこれを3個作ろうとしていたのね。けれど、恐らくやりそうな事は、サンプル的に1個仕上げようと、
する可能性があるのね・・・1個ずつみたいに。これが上手く行かない状況を作るのね。そもそも3個作るみたいなのは、大作と違って流れ作業なものなのね。つまり能率効率。こんな9分の1みたいなパーツ、ピッタリ切り終われると思う?恐らく余ったりするのね。それなのに次の工程に進むって。きっと無くすのね。
だから同じ工程は続けてやる。ここでせ若干ひねくれていたり、中々のツワモノは、さっきの下地続けてやらなかったじゃん・・・って突っ込んで来るのね。そうだね、確かに。でもね、あれは難易度高いって言ったよね。つまり身を削るから無理しない為だったのね。でもこの場合、余りが出ているパーツの放置になるのね。
ではまだ信用出来ない人へ。もし仮に1つずつ進んでいたとしよう。どうなるか?まだ乾いていない張り終わった縁取りの次に桜の花びらを張るのね。中心に合わせようとしたくなるのね。けれど、既存のパーツじゃないから、同じ大きさじゃないのね。つまり何と無く中心に合わせるしか無いのね。あっちこっち触るね。
その時に桜にばかり気を取られると、縁取りを触るのね。当然張ったばかり・・・動かすよね。直すよね。ズレるよね。深みにはまってさぁ大変。ドジョウが出て来てこんにちは・・・って事になりそうでしょ?つまり失敗する方向に向かうと思うのね。それをそっとして置いて、次々と縁取りをやっていると、最初のが乾いて来る。
その時に桜の花びらを張って、また張ってと3つやって、また戻る。すると今度はボンドのベタベタ感が落ち着く。そこでカッターでいらないボンドをそぎ落として・・・もう少し放置。帰り際に木工用のボンドを垂らして、ビーズを押し込む。それをスポンジで拭けば今日はおしまい。もう触らない。そして明日以降に目地。
こうした流れ作業で無駄な時間を使わない。これが1点モノじゃない作り方。けれど、目地をしていないから次回以降に持ち越しにはなるんだけれど。