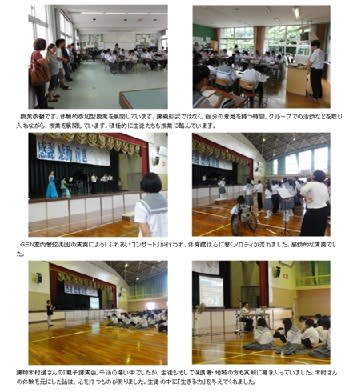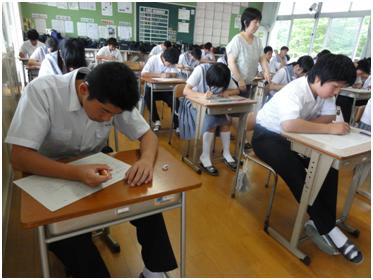山あいの半分過ごした20代
山あいの半分過ごした20代心のアルバム開いて見てる

うなぎ・・・思い出のPARTⅡです。西谷のよっくんのお父さんやあっこちゃんのお父さんはうなぎどりの名人です。もちろんいろんな技を知っています。何度かうなぎどりに連れて行ってもらいました。
縦1メートル半、横10メートルくらいの網の端を2~3人ずつで持って海の中を引きずって回ります。網の真ん中にうなぎが入るようになっています。不思議な網です。腰くらいの深さの水の中を歩き回ります。水の抵抗があることと、網を引きずるので、足が疲れます。
この網の経験をした人はあまりいないかも。一回10分くらいひきずったら、網の中には、獲物がどっさどっさ。うなぎがにょろにょろ。うなぎは、とれるときで一回10~20ひきはいます。
(ちなみに生き物としてウナギを数える場合は「ひき」。食材として扱う場合は「本」もしくは「尾」だそうです。

調理して蒲焼になったら、形状によって「串」「枚」もしくは「尾」になるそうです。)そのほかにも、エイ、クルマエビ、いろんな魚・・・
引くうちにだんだんとパワーが消えていきます。しかし、うなぎの獲得のためには、そのくらいは我慢?
潮が満ちてきて、歩けなくなるまでは、10回程度は網を引けます。

ある時、潮が満ちてきてもしっかりとうなぎがとれていたので、そっちに集中していると、足が海の底に着かなくなりアップアップしていました。ちょっとびっくり。
この漁法の時期は、6月ごろでした。なんと100匹近くのうなぎをとって帰っていました。衝撃的な感動でした。もちろん、5~6人で行くので、ひとり頭の持って帰る数は、その割った分ですが、ぞれでも20匹近くはしっかりとゲットしていました。
今でもよっくんたちのお父さんたちは行っているのでしょうか。つれあいや父、母がさばくだけでも大変でしたが、しばらくは、豪華なうなぎ丼が続きました。

西谷では海から山までいろんな経験をさせてもらいました。
今は、学校の中でも企業戦略、競争原理などが持ち込まれています。教育語の中にも実績評価・戦略・数値目標・達成指標・PDCAなど今までにはない言葉が次から次へと出てきます。当然必要なものですが、人と人との結びつき、関わり合いがあってのことだと思います。

「せんせいになったのは、子どもが好きだから。」という先生がほとんどだと思うのですから。






























 この暑さ暑いと言うなその言葉
この暑さ暑いと言うなその言葉