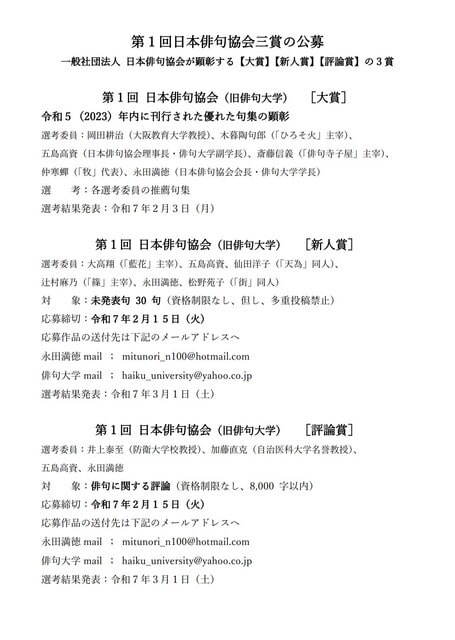俳句大学国際俳句学部よりお知らせ!
Facebook「華文俳句社」
〜【俳句界】2025年2月号〜
◆2024年『俳句界』2月号が発行されました。
◆華文圏に俳句の本質かつ型である「切れ」と「取り合わせ」を取り入れた二行俳句を提唱して行きます。
◆2020年1月からは月刊『俳句界』に「華文俳句」の秀句を連載しています。
◆どうぞご理解とご支援をお願いします。
俳句大學國際俳句學部的通知!
~Facebook 「華文俳句社」Kabun Haiku 2025.2
◆2024年『俳句界』2月號已出版。
◆於華文圏提倡包含俳句的基礎「一個切」和「兩項對照組合」的二行俳句。
◆請各位多多支持指教。
華文俳句「俳句界」2月号(2025年)
永田満徳選評・洪郁芬選訳
※
穿過房門的擤鼻涕聲
寒流
●
黃士洲
〔永田満徳評論〕
「寒波」是指自大陸南下的寒氣團如波浪般襲來的現象。在臺灣,每逢仲冬到晚冬期間,大陸寒氣團會多次經過,帶來明顯的降溫。「擤鼻涕」的現象不僅限於感冒,還可能由感染症或過敏等原因引起。而當「擤鼻涕聲」從門外傳來時,那種情景不禁讓人聯想到嚴寒的「寒波」來襲,令人心生共鳴。
ドア抜けて鼻をかむ音寒波来る
●
黃士洲
〔永田満徳評〕
「寒波」とは大陸から南下してもたらされる寒気団が波のように押し寄せてくること。台湾は仲冬から晩冬にかけて、大陸からの寒気団が何度も通過する。「鼻をかむ」現象は風邪ばかりではなく、感染症やアレルギーなどでも起こる。「鼻をかむ音」がドアの向うで聞こえるさまはいかにも厳しく冷え込む「寒波」の襲来を思わせて、共感できる。
※
腳踏車叮鈴的晨喚
冬陽
●
昭麗
〔永田満徳評論〕
「冬日」是同時具有「冬日一天」與「冬日陽光」雙重意義的季語。在這裡,它指的是冬季的陽光或日照。冬天的陽光雖然微弱而顯得不甚可靠,但從雲隙間灑落的寒冷光輝,往往能喚起人們的親切感與懷舊情懷。「腳踏車叮鈴的晨喚」描繪的可能是冬日清晨的景象。在冷冽的空氣中,聲音顯得格外清晰,這句俳句準確捕捉了冬日早晨的那種鮮明而獨特的氛圍。
冬の日や自転車ベルの響く朝
●
昭麗
〔永田満徳評〕
「冬の日」は冬の一日と冬の太陽の両方の意味で使われる季語です。ここでは、冬の太陽や日射を指す。冬の日差しは弱々しく頼りなげであるが、雲間からの寒気の中の輝かしい日差しなどには親しみや懐かしさを覚える。「自転車ベルの響く朝」とは早朝の情景であろうか。空気が冷えて、音がより鮮明に聞こえる冬の朝の雰囲気をよく捉えている。
※
呼嘯而過的一列火車
枯野
●
揚晨
〔永田満徳評論〕
「枯野」指的是草木枯萎後的原野。這樣的枯野形態各異,有的廣闊無邊,有的則位於山間的狹窄地帶,或者沿著海岸延伸的枯野。雖然是一片枯黃,但在夕陽照耀下閃閃發光,依然讓人感受到一絲華麗的氣息。在這片枯萎的原野中,飛馳而過的「一列火車」,描繪出一幅動靜交織的畫面。這首俳句雖然傳遞出荒涼之感,卻也清晰展現了枯野廣闊而鮮明的景致。
一両の汽車駆け抜くる枯野かな
●
揚晨
〔永田満徳評〕
「枯野」とは草木が枯れ果てた野原のこと。広く果てしないような枯野もあれば、山間の狭い枯野や海に沿って延びる枯野などさまざまである。枯れ一色とはいえ、夕日を浴びて輝くさまは華やぎを感じさせる。枯れてしまった野原のなかを疾駆する「一両の汽車」。荒涼としているものの、広がりのある枯野の景色がくっきりと見える句である。