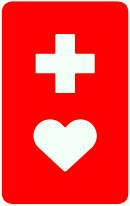○中川委員 それでは、よろしくお願いします。
持続可能な畜産という観点から質問させていただきたいというふうに思います。
化学肥料や配合飼料の価格高騰が続いていて、9月定例会、また11月定例会でもその観点で質問をさせていただきました。最近の価格動向については、資料で御説明があったとおり、化学肥料の関係で言えば1.5倍、それから畜産の配合飼料などがやはり同じように1.5倍で、高止まりで推移しているという報告でありました。この間、国・県が様々支援事業をしているわけですけれども、一つは、化学肥料に関係して、農家から申請して、そして支援をするということになってきていますけれども、この申請状況がどうなっているか、一つ教えてください。
それから、配合飼料の関係です。これは高止まりした場合は、前回もお聞きしましたけれども、補助事業じゃない、保険のほうがなかなか反映されないということにつながってきていて、県としても国に対して繰り返し制度の変更などについて要請をするという答弁がありました。この点についても今どんな状況なのかということ、それから最後に、最後というか、状況の話ですが、これも前回質問いたしましたけれども、生乳の学乳への価格転嫁をすべきだ、直ちにできない場合は農政部が教育委員会と相談して支援をすべきだというお話をして、農政部長は教育委員会と相談をしてという答弁がありました。現段階でそのお話がどうなったのか、そしてまた来期についてどんな状況なのか、その3点をまずお聞かせください。
○小林農業技術課長 私のほうから、化学肥料の関係の申請状況についてお伝えをいたします。
今回、長野県につきましては、秋肥と春肥を一本化して申請を受け付けるという形になっておりまして、一本の価格上昇率というのが3月3日に国から示されました。これが1.4倍という数字が使われるという形になりまして、示されておりますので、この示したものを受けて4月1日から受付を開始するという形で、あした臨時総会を開いて正式決定をして、皆さんにお知らせをする予定でございます。
対象となる肥料は、昨年の6月から今年の5月までに購入した肥料という形になりますので、この春肥が一番影響が大きいと思っておりますので、その肥料に対して助成を出していくという形になってまいります。
○吉田園芸畜産課長 私からは、配合飼料の国の要請の状況のお尋ねでございます。
議会の答弁にもありましたが、国に対しては、配合飼料が、補塡の算出方法が、直近1年間の逆算で算出されているということがございまして、この直近1年間が高くなってしまうと、その前の2年、3年前のものと比べても高止まりで補塡金額の格差が少なくなるという、そういった算出方法をぜひ見直してほしいということを、昨年度春と秋2回、さらに今年になって2月10日に緊急要請をさせていただきました。その中で、国の担当者のほうのお話を踏まえますと、あの配合飼料の補塡制度自体が、国も当然基金を造成するんですけれども、飼料メーカー、餌のメーカーも基金造成をしていただいているという実情がありまして、今そこのところがやっぱり難点になっているそうでございます。
ついては、算出方法を直ちに見直すというのには時間がかかる、そういったことで、今回、高止まりはちょっとしているんですけれども、それを補うために緊急補塡という形で、R5年の1月から3月、それから4月以降について、緊急補塡についても前向きに検討していくという答えをいただいているところでございます。
○村山農産物マーケティング室長 私のほうからは、学校給食への牛乳の価格改定の状況ということでお答えをさせていただきたいと思います。
11月の委員会のときにも若干仕組みを御説明させていただいたところでございますけれども、現在、県内の学校給食を供給する事業者からの学校への供給価格につきましては、毎年国の要綱等に基づいてマーケティング室のほうで入札をしまして、価格を設定しているところでございます。令和4年については、11月に乳業メーカーが、いわゆる資材等生産コストの上昇を勘案して値上げをしたところでございまして、また、さらに令和5年の4月以降もさらなる厳しい状況ということで、生乳の価格を値上げしたことが決定したところでございます。
農政部としては、4月以降の供給価格の状況を勘案して、さらに生乳価格だけではなくて、学校給食への配達とか、そういったところも燃料費とか値上がりしてきますので、そういったものを全て勘案をさせていただいて、本年1月末に例年より3週間ほど前倒しして、令和5年産の学乳の価格を入札をさせていただいたところでございますけれども、その結果としましては、牛乳1本200ミリリットル当たり、平均価格で令和4年に比較して約5円の値上げとさせていただいたところでございます。
11月のときのすみません、ちょっと私の答弁もなかなか言葉足らずのところもございましたけれども、いわゆる農家への生乳価格というのは、いわゆる生乳メーカーが値上げということでもう決定して、その分は農家に反映されていたところでございまして、私どもの入札の部分はいわゆる学校給食の供給事業者から学校へのというところの価格になりますので、若干11月から3月までのところは、供給する事業者が少しちょっと負担が増えていたということで御理解をいただければと思います。よろしくお願いします。
いずれにしましても、教育委員会と常に連携をさせていただきまして、市町村に対しては、秋のうちからこういった状況があるということで、市町村に対してはあらゆる機会を通じて値上げの方向でいくということはずっとアナウンスをさせていただいてきたところでございまして、生乳の値上がりの部分については、今お話ししたとおり、学校給食の経費にも反映をしていくという状況でございます。よろしくお願いします。
○中川委員 ありがとうございました。
一つ配合飼料の関係ですが、緊急補塡をしていくという方向性が出されているということなんですが、県としても、この間、プラス6,000円で支援をしてきていますので、引き続き、県としての支援も検討してほしいという要望をしておきたいというふうに思います。
それから、学乳のほうは、もちろん販売価格に転嫁をしないと学乳自体がもたないということはありますから、それは必要なことなんですが、一方で、消費者としての立場もあるものですから、ぜひ教育委員会とも相談していただいて、そこら辺のやはり配慮というのが必要かなと思いますので、これはここで言うことではないんですが、そういう心配もあるなということは申し上げておきたいというふうに思います。
それで、2月22日に日本経済新聞社が主催しまして、日経のアニマルウェルフェア・シンポジウム2023というのが開催されました。これに松本家畜保健衛生所、宮澤所長も参加をしていまして、化学肥料や配合飼料が高騰する中で、国のみどりの食料戦略システムもあるわけですけれども、長野県も環境に優しい農業や有機農業の取組を拡大しようとしています。畜産においても、国産粗飼料の生産拡大への支援も、今回も提案がされているところです。
今、畜産農家だけではなくて、消費者も含めて、新型コロナ以降、様々な不安というのが広がっているなと思うんですね。今回の問題でいえば、輸入飼料に強く依存する畜産が将来も本当に大丈夫なんだろうかだとか、家畜が利用できる食品工業残渣などが焼却処分されてもったいないよねだとか、あるいは、家畜の餌に入れられているんですが、抗菌性物質の利用によって人に対する堆積が出現するんじゃないかという心配もあったり、医薬品などの開発がいつまで病原体の進化に追いついていけるのか、家畜の介入によって遺伝的多様性が失われて多くの家畜に感受性を持つ病原体が発現しないのかというような、様々な不安があります。これらの不安というのは、実は今に始まったわけではなくて、2001年にBSE、牛海綿状脳症が国内で発生をして、そのときに長野県は全国に先駆けてトレーサビリティーを導入したり、それから継続してBSEの検査、これもずっとやってきたという体制を取ってきた県です。
これらの経験から、2007年2月に、長野県松本家畜保健衛生所が、家畜にも人にも優しい信州コンフォート畜産認定基準というのを発表していることを知りました。この発表文の冒頭の挨拶の中に、以下のように問題意識が述べられています。農業や化学肥料に依存しない、人にも環境にも優しい有機農産物、放し飼いにより伸び伸びと快適に飼養されている鶏の産んだ卵、そんな農畜産物が消費者の心をつかみ始めている、一方、アメリカ産トウモロコシへの全面的依存畜産はいつまで存続できるのだろうか、輸入穀物による家畜飼養は世界の環境問題に負の影響をもたらすのではないか、こういった懸念がありますと書かれていて、先ほど申し上げましたような現在の新型コロナの中で感じている不安をこの当時からも指摘されています。
これにより、資源循環型畜産と家畜福祉、いわゆるアニマルウェルフェアの基準が定められたんですね、当時。加えて、抗菌性物質の基準も当初はつくることを考えていたようですが、2016年の薬剤耐性アクションプラン以前のことでもあり、適正に使用すれば生産性が向上し、人の健康被害も生じないということで、日本は世界的にも厳しい基準で国が承認をしているということから、この基準づくりは断念した経過があるのだそうです。
そこで、2007年に取り組まれた家畜にも人にも優しい信州コンフォート畜産認定基準の中で、食品残渣を飼料原料としている県内飼料製造届出業者が当時8社あったんですね。これが今どうなっているのかということについて、御存じでしたら教えてください。
○青沼家畜防疫対策室長 コンフォート事業についてのお尋ねでございます。
平成18年に松本家畜保健衛生所が現地提案事業として取り組んだものでございます。対象を松本家畜保健所管内に限りまして、対象の基準を決めて畜産物や生産者を、これは認定といいますか、そういう取組をしているかどうかというのを確認するといった取組でございました。この基準の作成には、当時、アニマルウェルフェア等々先端の知見を持っております日本大学や東北大学の先生も参加していただきまして、先ほど委員が御指摘のとおり、資源循環、それからアニマルウェルフェア、この2本を柱に検討が行われたところです。最終的には平成19年2月に基準の公表を行ったところでございます。
当時の資料によりますと、食品残渣を飼料原料としている県内の飼料製造届出業者の記載がございますが、これにつきましては、食品残渣を収集いたしまして飼料として製造している事業者、これは5社ございました。豆腐会社のように直接飼料を供給している会社が3社ございまして、この方たちがそれぞれのうどんやそばですとかお菓子、そういったものの余ったものについて、収集、製造して販売をしてきたところでございます。現在、このうち3社の方は事業を撤退いたしまして、5社の方が事業を継続しているといった状況でございます。
○中川委員 その3社、撤退した方たちの理由、ちょっと分かりますか。
○青沼家畜防疫対策室長 誠にすみません、理由については、こちらのほうでは把握はしていない状況です。
○中川委員 資源循環型畜産の推進ということを考えたときに、食品残渣を飼料とすることのほか、家畜のふん尿と食品残渣をメタンガス発酵させてエネルギー源や液肥とする方法などが考えられます。これには先ほど小林委員からも関連した質問があったところですが、食品残渣を飼料とする場合に、やはり安定した供給ができるのかという課題があります。また、堆肥についても、これも先ほど小林技術課長からも答弁がありましたけれども、その安全性についての懸念が残るということが指摘されています。ただ、国のみどりの食料システム戦略などを考えると、環境に優しい農業を展開する地域づくりという観点から、オーガニックビレッジの中で展開するということは望ましい姿じゃないかなというふうに私は思いますので、その点、いかがでしょうか。
○小林農業技術課長 先ほども申し上げたオーガニックビレッジの中で展開するのが望ましいんじゃないかという御質問かと思います。
有機農業を生産から流通、そして消費、販売まで結びつけていくのは、地域が一体となって一貫とした取組、これを行うのを、市町村が行っていただくんですが、オーガニックビレッジという形で支援をしておるわけでございますけれども、そのうちの生産の部分、堆肥や何かをやはり地域の畜産農家や地域の食品加工会社から出た資源、これを地域の中で耕畜連携で使う、これがやはり一番望ましい姿だなと考えております。それはコスト面、そして環境面から見ても、耕畜連携を地域の中で図ること、これは非常にいいことだと思っております。
ですので、大きな考え方とすれば、委員御指摘の方向で進めたいわけでございますが、現在、オーガニックビレッジという形で有機という形で進めるには、そういった堆肥まではまだ活用できていないというのが状況でございます。今後、地域の畜産農家やそういうものがあれば、そういったものの取組も含めて検討していくことが大切かと考えておるところでございます。
○中川委員 今そういう話がありましたけれども、例えば、オーガニックビレッジに手を挙げている松川町では堆肥を使っているということもありますので、ぜひそんな点を含めて検討を、前に進めていただきたいというふうに思います。
長野県畜産試験場で、持続可能な畜産の研究の中で、柿の皮の粉末が牛の消化管内のメタンガスの発生を抑制すると、こういう研究結果が、11月でしたか、9月でしたか、発表がありました。これは信州大学の上野准教授の実験室内の研究で、柿の皮サイレージに含まれているタンニンなどのポリフェノールがメタンガスの発生を抑制するということは分かっていたわけですけれども、実際に牛で柿の皮を給与し、利用したというところが注目点だというふうに思うんですね。柿の皮の粉末を作るということは、何か聞くところによると、特許申請するくらいの技術なんだそうです。県農政部としては、持続可能な畜産業ということについて今後どのように推進していくのか、お聞きします。
○吉田園芸畜産課長 持続可能な畜産業に関するお問合せでございますが、畜産業は、今委員御指摘のとおり、牛のげっぷですとか、いわゆる家畜の肺、ふん尿から出るNO2ですとか、温暖化を進めてしまう温室効果ガスも排出しているという、環境的にちょっとマイナスの面を持っている産業でございます。ところが一方、人間にとって食料を供給する、たんぱく質を供給するという意味においては、大変重要な産業というふうに捉えております。
そういったことから、長野県としてはこの畜産業を持続、継続可能な産業にしていくためには、このマイナス面とプラス面、この両方のバランスを取りながら進めていくべきであるというふうに考えてございます。ただ、その際には、やはり畜産農家に過度な負担を強いない状況でこのマイナス面も補っていくような、そういう技術開発が待たれているところでございます。例えば、今の柿の皮のように、牛のげっぷから出るメタンガスを少なくする技術については、国の研究施設においてもメタンガスを抑制するような餌ですとか、あと、メタンガスを出す量を低くするような牛の品種を改良していくですとか、そういった技術の今イノベーションが開発されていますので、長野県の畜産農家にとってあまり負担がないような感じで取り入れられるような技術開発であれば、そこに導入を進めていこうというふうに思います。
それから、プラス面の部分では、畜産から出る家畜ふん尿というのは、まさに土づくりに大変有用な部分でございますので、長野県の高原野菜ですとか果樹ですとかお米に関しても、土づくりは欠かせないものというふうに考えてございます。今現在、この家畜ふん尿を使いやすくする、ペレット堆肥というふうに加工をするんですけれども、そういった先進的なことも、県内の1か所でJAが取り組んでいることもございます。それから、長野県はキノコの産業が大変全国1位でございます。キノコから出る廃培地も、例えば、エコフィードではないんですが、家畜の餌にできるような、そういった開発の技術もなされているということでございますので、こういったマイナス面とプラス面のそれぞれの技術開発、イノベーションの部分が進んできて、それを導入することによって持続可能な畜産、バランスを取った畜産業を目指していきたいなというふうに考えているところでございます。
○中川委員 一つだけ申し上げておきたいことは、前回も申し上げましたけれども、今本当に畜産業が苦しい状況の中にある。国が様々大規模な投資をして酪農に投資をしたけれども、しかし増え過ぎたので、今度は廃用牛を殺すために13万円の補助金を出すというようなちぐはぐな政策が、私から見れば、そして、酪農をやっている皆さんからしても、一体何なんだというようなことが行われているので、これはとても持続可能な畜産業を目指しているとは言い難いことがあるので、そんな点もぜひ心してやっていかないと、本当にここのところの新聞でも、酪農家の、少し読むと、新聞でいうと、酪農家、減る生乳需要、飼料価格高騰の二重苦、それから、離農加速、酪農戸数6.5%減、そういった記事がずっと続いているわけですよね。なので、ここはしっかり県農政部として取り組んでいただきたいというふうに思います。
新型コロナの蔓延によって、人、動物、自然の健康を一体的に考えるワンヘルスという考え方が今改めて注目をされています。最近の新聞を読んでいても、鳥インフルが哺乳類にも次々感染をしている、こういう記事も実際出ています。昨年2月の国連の環境総会で、アニマルウェルフェア環境持続的発展の関連に関する決議が採択されていまして、この決議の中で、アニマルウェルフェアが環境問題に対処し、ワンヘルスへのアプローチを推進し、SDGsを達成し得ることを認める、動物の健康と福祉、持続的発展、環境問題は人間の健康と幸福につながっていることを認める、これらの連携をワンヘルスや総合的発想を通して追及することへの要請を認める、アニマルウェルフェアを支える科学的蓄積があることを認めるという決議がされています。
ヨーロッパでは、アニマルウェルフェアに配慮した畜産でなければ流通しないという状況にまでなってきていますし、アメリカでも、州法ですけれども、鶏のケージフリーや繁殖豚の生涯ストール飼育の禁止が打ち出されてきているところです。東京オリンピックの際には、アスリートの皆さんから日本の選手村でアニマルウェルフェアの観点のケージ飼いの卵は出さないでほしいという要望があったり、母豚を妊娠期間中に担当飼育する個別のおりである妊娠ストールの肉は出さないでほしいという要望があったり、野菜はオーガニックにしてほしいといった要望があって、それに対する配慮が東京オリンピックではされたというふうに聞いています。
新型コロナ後のインバウンドを考えたときに、外国の観光客の皆さんが求めるものはこうした傾向から明確だというふうに思うので、アニマルウェルフェアに対応した畜産の推進ということがこれまで以上に強く求められてきていると思います。動物の健康を優先した飼育は、動物にポジティブな気持ちを抱かせ、それが免疫力を高め、死亡や疾病を低減し、生産効率を高め、環境にも貢献し、貧困や飢餓からの解放、気候風土に合った品種への重視につながっていくと思われます。ですので、2007年につくられた信州コンフォート畜産認定基準の中で目指された基準は、今で言うアニマルウェルフェアの基準として適用できるものだというふうに思うんです。信州コンフォート畜産認定基準を生かした認証制度をつくって、長野県畜産の付加価値を上げて、まさに稼ぐ農業を目指したらどうかと思いますが、いかがでしょうか。
○青沼家畜防疫対策室長 稼ぐ農業の実現に向けた取組ということで御質問いただきました。
コンフォート事業につきましては、先ほど申しましたとおり、アニマルウェルフェア、それから資源循環、こういったことがしっかり盛り込まれている基準でございます。このうちアニマルウェルフェアにつきましては、その項目の幾つかが県内の全家畜農家が取り組んでおります飼養衛生管理基準に盛り込まれておりますし、また、県独自に牛の農場を認定する信州あんしん農産物制度、これにアニマルウェルフェアばかりではなく、JGAPなどの考え方も盛り込みながら、一歩進んだ取組をしているといった状況でございます。
県といたしましては、この既存制度をしっかり充実させなければいけないという考えでございまして、現在、国におきましては、今まで国というのは畜産技術協会が定めましたアニマルウェルフェアの指針がございますが、この普及に努めていたんですが、ようやく今後、国際獣疫事務局、OIEといいますけれども、そこが示す水準を踏まえまして、国のほうで指針を示すといった作業が行われております。
県といたしましては、農場HACCP、畜産GAP、これらの手法に加えて、アニマルウェルフェアも広く農家に周知いたしまして、畜産農家の皆様それぞれが販売する先の実需者ですとか消費者の皆様の要望に応えられるように、研修会や農場での実践指導など、こういったものに取組を進めてまいりたいと考えておりますし、また、アニマルウェルフェアを盛り込んだ牛以外の畜種についても基準づくりを進めてまいりたいと考えております。
○中川委員 そういったことがやはり持続可能な長野県の畜産につながっていくんだという、やはり将来を見ながらつくっていく必要があるというふうに思います。私は2021年、おととしの9月定例会で、新型コロナウイルスや2009年のパンデミックインフルエンザウイルスが人から家畜やペット、動物園の動物に感染した事例も知られていることから、家畜、野生鳥獣への対策とともに、健康福祉部としても新型コロナを含め、新興感染症対策としてワンヘルスの立場から獣医師との連携を強化しておく必要があるのではないかと、これは健康福祉部長に質問をさせてもらって、部長からは、人、動物、環境の衛生に携わる方たちが連携して取り組むワンヘルスという考え方が世界的に広がってきていると、国においても医学や獣医学といった分野間の連携を推進しているところで、県としても、今後発生し得る新興感染症の予防探知、治療などに効果的に取り組めるよう、国の取組なども踏まえながら、獣医師や関係機関との連携について研究していきたいというふうに答弁があったところです。
つきましては、農政部が主導して健康福祉部に働きかけて、県庁内にワンヘルス推進に向けた検討会を立ち上げたらどうかと思うんです。実は、これは福岡県では既に条例がつくられていますし、四国でもどこかの県でこの条例がつくられてきているところです。ワンヘルスのアジアの協会の事務局が日本の福岡に今度新たに設置されるということもありまして、ぜひ長野県としてもこの新型コロナを振り返りながら、やはり鳥から獣、そして人間、こう変異をしながら拡大をしてきているのがこのウイルスの状況ですので、人獣共通の感染症ということになっていますので、このワンヘルスの体制をつくっていくということが今後起こり得る新興感染症への対応、対策ということになるというふうに思いますので、ぜひ長野県としても先進的に取り組んでいっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○青沼家畜防疫対策室長 ワンヘルスについてでございます。
全ての感染症につきましては、その約半数近くが、委員御指摘のとおり、人から動物、動物から人といった人獣共通の感染症と言われています。農政部といたしましても、人、それから動物、あと環境、この衛生に携わる方たちが連携して取り組むワンヘルスというのは非常に重要という考えは持ってございます。
農政部としましては、令和5年度には新たにワンヘルス・アプローチによる薬剤耐性菌対策といたしまして、薬剤耐性菌を獲得しやすい大腸菌につきまして、公共牧場で採材検査を実施しまして、まずは野生動物と家畜との間でワンヘルス上のリスクに関するデータの収集といたしまして、これについて実態を把握する中で、健康福祉部のほうにも情報提供をしながら対策を進めていきたいと考えてございます。
現在も、農政部関係で申しますと、豚熱や鳥インフルエンザ、こういったものにつきましては、健康福祉部や林務部と連携いたしまして、情報は当然共有いたしますし、実際の防疫に際しては、現場のほうにつきましても健康福祉部のほうで参加していただきまして、連携した取組を行っているというところでございます。
今後、先ほど委員もおっしゃいましたとおり、健康というのを守るのが大事ですので、健康福祉部や林務や環境部と連携、それから情報共有するのはもちろんなんですが、必要に応じまして議論の場というものは設けていかなきゃいけないというふうに考えてございます。
○中川委員 今回、小林農政部長も退職されるということなんですが、現場にいる松本家畜保健衛生所長の宮澤さんや、畜産試験場長の神田さんも今回退職されるわけですが、私、現場をずっとこの4年間歩く中で、みんな新型コロナの中でもう本当に苦労しながらやってきたなと思うんです。たまたまなんですが、松本の家畜保健衛生所に行ったら、この前も話したかもしれませんけれども、東京都から譲り受けた防護服だとかマスクだとかゴーグルだとかというのが大量にあって、新型コロナでこんなにみんなが困って足りないと言っているときなんだから、これは健康福祉部に融通したらどうなんだということを提案して、結果的に国の予算がついているものについては国に聞かないと分からないというふうに言うので、国会議員を通じて聞いて、それも融通していいよという判断になって、約1万5,000個だったですか、家畜保健衛生所にあった防護服だとかマスクだとかを健康福祉部に融通したということがありました。
私、こうやって現場の中で頑張っている皆さんが今日までやっぱり積み上げてきたことを、ぜひ今後の県農政部の中で生かしてほしいなというふうに思うので、そんな点、現場を大切にしてほしいということを私のほうから要望して、ちょっと部長に一言いただければと思いますが、いかがですか。
○小林農政部長 委員のほうから御指摘いただいたとおり、ワンヘルス、そしてまたアニマルウェルフェアというような取組、まさに長野県の畜産試験場長、または松本の家畜保健衛生所長でございますけれども、それぞれ日本を代表する取組というような形の中で、自らも学びながら、長野県の現場においてそういった取組を展開してきているところでございます。私としても、そういった部分については評価をしておりまして、そういった取組は県としても進めていくべきところは進めていきますしというふうには考えているところでございます。
そういう中で、今マスクのお話もありましたけれども、例えば、農政部だけという話ではなくて、健康福祉部や林務部とも、先ほど青沼室長のほうから回答がございましたけれども、長野県庁としてどういった取組をしていくんだという視点の中で、これからもどういった取組をしていくかということについては考えていきたいなというふうに思っております。
さらに、ワンヘルス、そしてアニマルウェルフェアというような取組の中で、遡ればコンフォート畜産、まさに地元の地域の中で発想して、それをその地域の中で進めていた取組だというふうに理解しておりますので、現場の声も十分に聞きながら、県としてそういった声を生かせる予算や施策に反映していくというようなことも考えながら、長野県農政部の施策を進めてまいりたいと考えておりますので、引き続き、委員の皆様方にも御理解、御協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○中川委員 ありがとうございました。
ちょっと時間があるので、あと一、二点お願いします。
一つは、鳥獣被害の防護柵についてです。これは松本の東山で松枯れによって枯れた松が鹿柵を倒して、倒しちゃうものですからまた鹿が入ってくるということがあって、現場に農村支援センターと、それから林務課に来てもらってやったんですが、らちがなかなか明かないんですよ。鹿柵のほうは農政部の予算で、それで直すための費用は松本市が費用を出して、そのうち多分8割だったかな、特別交付税で措置がされているという話だったんです。どっちがどっちだという話になるとなかなかこれは進まない話で、もちろんこの後の林務部でも私これは同じ質問をするつもりでいますけれども、農政部としても林務部としっかり連携してこの対策をしっかり取ってもらいたいと思いますが、いかがですか。
○小林農業技術課長 鳥獣の防護柵の設置につきましては、農政部が主体となって、国の交付金を使って整備を進めておるところでございます。令和2年度までに県内約2,000キロを超える整備が、2,084キロですか、国庫事業を使って整備しておるわけでございます。これらの維持管理につきましては、中山間の直接支払のお金を自分たちで地域の皆さんがためて、維持に使ったり、今委員御指摘のようなお金を使って整備をしておるわけでございます。大雨とか大雪とかやむを得ない気象災害とか、そういったものに対する壊れてしまったとか、そういう修繕につきましては、再度国庫補助事業が対象となりますが、松枯れによります倒木、そういったものは、松枯れのほうの管理がきちっとしておれば本来は防護柵は被害を受けなかったという点もございまして、現段階では補助対象にはなってございません。
そういった面もありますが、委員御指摘のとおり、双方が連絡を取って貴重な電気柵、整備したわけでございますから、それを長寿命化していく必要はあると思いますので、今後国に対しても、県としてこういった施設はやはり一つの基盤整備の事業の一環だというような位置づけの中で、長寿命化について補助対象となるよう、国へは要望してまいりたいと思いますし、林務部とも十分に連携を取る中で、維持管理等に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
○中川委員 鹿柵が枯れた松が落ちてきて人家に入るのを防いでいるという、ちょっと大変な状況があるものですから、ぜひよろしくお願いします。
最後に一つだけ、すみません。長野県有機農業研究会が、ゲノム編集作物を受け取らないでほしいという要望書を県から全77自治体と77の教育委員会に出しました。回答がありまして、77教育委員会のうち72の教育委員会、それから、77自治体のうち69の自治体から回答がありまして、受け取らないとしたのが29自治体、32教育委員会、その他39自治体、39教育委員会、受け取るとしたのはゼロという、そういうのが長野県有機農業研究会のホームページに掲載されていました。
この間、前にも一度言いましたけれども、まだ安心・安全だということが確立されていない中で言えば、県の遺伝子組み換え作物のガイドライン、この中にやはりゲノム編集のものも入れ込むべきだというふうに私は前に質問をして、答弁は、国の動向を見てという答弁だったんですが、状況に変化はありますか。
○小林農業技術課長 前回お答えしたとおり、国の状況等も踏まえる中で、状況に変化はございませんでして、国の方針が変わらない限り、現段階では県のほうでは前回と同じ回答になります。
○中川委員 現実に自治体、教育委員会、そして県民の中にも不安があるということをしっかり踏まえた対応をしていただきたいということを要請して、終わります。