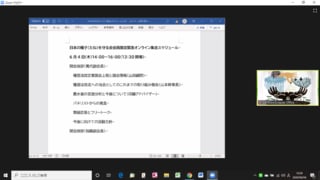長野県農政部との意見交換会
1、冒頭あいさつ(中川)
日頃、長野県農政の発展と県民のいのちと暮らしを守るためご尽力をいただいていますことに敬意を表します。
近年、日本の農業をめぐる情勢が大きく変わろうとしています。大きくはTPP11や日欧EPAの発効により、農業もグローバリズムの中にあります。長野県農業もその影響を受けざるを得ません。
2018年主要穀物種子法が廃止され、これまで日本の食料を守ってきた公共品種の育成を裏付ける法律が無くなりました。しかし、長野県は、これまでのコメ・ムギ・ダイズにソバや伝統野菜を加えて、種子を守る条例をつくりました。国の農業競争力強化支援法で、公共品種の知見を民間事業者に提供することとなっていますが、長野県は「県民益にならない提供は行わない」と明言しています。
第201通常国会に提案された種苗法の改正案では、これまで「登録品種は自家増殖ができる」から、「自家増殖するためには許諾が必要」と変わります。長野県においては、許諾料の設定など農家の負担増にならない取組を切望します。
現在、気候変動の危機とともに、新型コロナウイルスによる人類への危機が叫ばれています。食糧自給率が4割を切る日本で、海外から食料や種子が入ってこない恐れさえあると言われていますが、今こそ、日本の農業を元気にするチャンスと受け止める必要があるのではないでしょうか。
食料自給率をあげていくこと、地産地消を拡大していくこと、持続可能な開発目標(SDGs)への農業分野での貢献、環境にやさしいエシカル消費の推進、有機農業の拡大などの政策を展開していくためにも多様な種子を守る仕組みが必要だと考えます。
気候非常事態宣言を行った長野県として、より環境への負荷を低減できる有機農業の推進拡大に取り組むことは、県内農産物のブランド化の推進にもつながります。また、農福連携や未来を担う子どもたちに、持続可能な環境や社会を残すために、「作り手の思いに触れること」、「自然や環境に優しい社会づくり」など、食育を通じて子どもたちに「生きる力」を育むことが長野県農政にも求められていると思います。
有機農業を拡大するためには、指導する人を育成することは大変重要なことです。これまで様々な取り組みを行ってきている長野県有機農業研究会の皆さんや有機農業や自然農業の研究機関とも力をあわせて担い手の拡大に取り組みましょう。
同時に、有機農産物の消費を拡大することが必要です。長野県営業局では都内の有名料理店のシェフに有機野菜の畑を見てもらっています。県内でも、レストランや料理店で有機農産物を使った料理を提供している店が増えてきています。今後、「学校給食有機の日」の取組や、有機農産物だけでつくるACE弁当など、消費者需要の喚起も力をあわせていきましょう。
「有機はオシャレ」「有機はもうかる」を合言葉に、私たちは県農政部と力を合わせていきたいと考えています。
以上の点を踏まえ、「種苗法の改正について」「有機農業の推進について」意見交換をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
■参加団体・参加者
NAGANO農と食の会
子どもの食・農を守る会伊那谷
松川町
ずくだせ農場
いのちをつなぐ里山の会
上田農と食の会
OBUSE食と農の未来会議
社会福祉法人くりのみ園
北アルプスいのちと食の会
長野県有機農業研究会
食とみどり水を守る県民会議