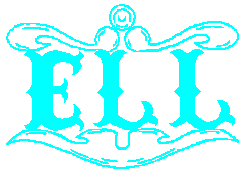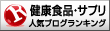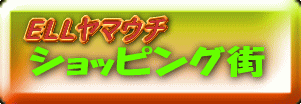日々のパソコン案内板
【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)
【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】
【PDFの簡単セキュリティ】
【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】
【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】
【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】
【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】
【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】
【手書きで書くように分数表記する方法】
【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】
【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】
【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】
年の瀬も押し詰まっているのに・・・
未だに、年末の掃除をやる気がわいてきません・・・と云うか、
仕事上で・・・断片的に・・・あっ!これをやっておかなくては・・・などと
雑用をやっていると、一日が過ぎてしまっています。
昨夜は、「クリスマスイブや!」・・・と、急きょ想い出し、
妻の妹から「クリスマスに飲んでね」と頂いていたスパークリングワインを頂きました。
結局、何をしなくてもクリスマスが来て・・・正月が来るわけですよね
年々、惰性で生きてるような感じも・・・無きにしも非ずです・・・
新年が来たら、心を引き締めて神社へ初詣でも行ってきますか・・・
ところで、お参りする時のしきたりって、ちゃんとご存知の方いらっしゃるでしょうか?!
・・・何となく・・・手を洗い・・・何となくお辞儀をし・・・何となく拍手し・・・って
こんな方が殆どじゃないんでしょうか。勿論、私もそうなのですが・・・
基本だけは、抑えておく方がいいかも・・・ですね。
今朝は、初詣の正しい作法を紹介した記事を転載してみようと思います。
~以下、12月25日読売新聞朝刊より抜粋~

マナー

京都大名誉教授(宗教学)で秩父神社(埼玉県秩父市)宮司の薗田稔さんは、「お正月は各家庭に年神様をお迎えする大切な行事。神棚のお神札を新しくして、玄関に門松を立て、しめ飾りをして家族一緒にお正月を祝います。
細かな作法は、神社や地域によっても異なるが、基本の手順は次の通りだ。
鳥居をくぐる前に軽く一礼する。境内に手水舎があれば手や口を清める。
手水舎では、先ずひしゃくを右手に取り、水をくんで左手を静かに清める。ひしゃくを左手に持ち替え、同様に右手を清める。再度、右手でひしゃくをとって水をくみ、左手に水を受けて口をすすぐ。ひしゃくを直接、口に運ぶのは禁物だ。口をすすぎ終えたら、もう一度、左手を水で清めて、最後にひしゃくを伏せる形で元に戻す。白いハンカチで、ぬれた手や口を拭く。
前年のお守りやお神札、破魔矢などは「納札所 」に収めると神社で「焚 き上げてくれる。
本殿に向かう際はなるべく左側を歩く。中央は「神様の通り道」とされ、混雑時以外は歩かないほうがよい。
本殿に鈴があれば、参拝の際にこれを鳴らす。お「賽銭 は神様へのお供えなので、静かに賽銭箱に入れる。
参拝は「二拝二拍手一拝」が一般的。背中を平らにし、90度腰を傾けて2回礼をし、大きく2回拍手、さらに1回深く礼をする。出雲大社など、参拝の作法が異なる神社もある。
新年のお神札やお守り、おみくじを受けるのは参拝が終わってから。参道を戻る際は左側を歩き、鳥居を出る前に改めて本殿に向き、軽く一礼をしてから帰る。
身だしなみに厳格な決まりはないが、清潔さを心がける。菩提 寺を訪れることもある。現代礼法研究所代表の岩下宣子さんは「ご先祖様に一年の無事と感謝の気持ちを伝えるためにも、正月は是非、菩提寺にも行ってください」と話す。
先ず、門前で会釈してから入る。手水舎があれば、神社と同じ作法で清める。本堂に向かう際は中央を避けて。
本堂では、本尊に向かい、手を賽銭箱に近づけ、そっと賽銭を入れる。両手を静かに合わせ、合掌したまま深くお辞儀をする。参拝が終わったら、さらに軽く一礼する。
岩下さんは、本尊を参拝した後、続けて墓参りをするよう勧める。彼岸などと同様、花を供え、供え物をささげる。年末に墓掃除ができなかった場合は、墓を清め、落ち葉やゴミを拾う。墓参りが終わったら、供え物を引き取って帰る。
未だに、年末の掃除をやる気がわいてきません・・・と云うか、
仕事上で・・・断片的に・・・あっ!これをやっておかなくては・・・などと
雑用をやっていると、一日が過ぎてしまっています。
昨夜は、「クリスマスイブや!」・・・と、急きょ想い出し、
妻の妹から「クリスマスに飲んでね」と頂いていたスパークリングワインを頂きました。
結局、何をしなくてもクリスマスが来て・・・正月が来るわけですよね
年々、惰性で生きてるような感じも・・・無きにしも非ずです・・・
新年が来たら、心を引き締めて神社へ初詣でも行ってきますか・・・
ところで、お参りする時のしきたりって、ちゃんとご存知の方いらっしゃるでしょうか?!
・・・何となく・・・手を洗い・・・何となくお辞儀をし・・・何となく拍手し・・・って
こんな方が殆どじゃないんでしょうか。勿論、私もそうなのですが・・・
基本だけは、抑えておく方がいいかも・・・ですね。
今朝は、初詣の正しい作法を紹介した記事を転載してみようと思います。
~以下、12月25日読売新聞朝刊より抜粋~
年始には初詣を予定している人も多いだろう。新年の無病息災を祈願するにあたっては、正しい作法を守りたい。

マナー


!
- ■ 初詣のポイント
- まず地域の守り神である「氏神様」にお参りする
- なるべく1月7日の「松の内」まで、遅くとも1月15日の「小正月」までには済ませる
- 古いお守りなどは、神社で受けたものは神社、お寺で受けたものはお寺に納める
- 家族そろってお参りするとよい
(薗田さんの話を基に作成)
手水舎あれば手・口清める
? 初詣
神社への初詣は、先ずは自宅や実家近くにある『氏神様』をお参りしましょう」と話す。細かな作法は、神社や地域によっても異なるが、基本の手順は次の通りだ。
鳥居をくぐる前に軽く一礼する。境内に手水舎があれば手や口を清める。
手水舎では、先ずひしゃくを右手に取り、水をくんで左手を静かに清める。ひしゃくを左手に持ち替え、同様に右手を清める。再度、右手でひしゃくをとって水をくみ、左手に水を受けて口をすすぐ。ひしゃくを直接、口に運ぶのは禁物だ。口をすすぎ終えたら、もう一度、左手を水で清めて、最後にひしゃくを伏せる形で元に戻す。白いハンカチで、ぬれた手や口を拭く。
前年のお守りやお神札、破魔矢などは「
本殿に向かう際はなるべく左側を歩く。中央は「神様の通り道」とされ、混雑時以外は歩かないほうがよい。
本殿に鈴があれば、参拝の際にこれを鳴らす。お「
参拝は「二拝二拍手一拝」が一般的。背中を平らにし、90度腰を傾けて2回礼をし、大きく2回拍手、さらに1回深く礼をする。出雲大社など、参拝の作法が異なる神社もある。
新年のお神札やお守り、おみくじを受けるのは参拝が終わってから。参道を戻る際は左側を歩き、鳥居を出る前に改めて本殿に向き、軽く一礼をしてから帰る。
身だしなみに厳格な決まりはないが、清潔さを心がける。
◇
先祖の眠る先ず、門前で会釈してから入る。手水舎があれば、神社と同じ作法で清める。本堂に向かう際は中央を避けて。
本堂では、本尊に向かい、手を賽銭箱に近づけ、そっと賽銭を入れる。両手を静かに合わせ、合掌したまま深くお辞儀をする。参拝が終わったら、さらに軽く一礼する。
岩下さんは、本尊を参拝した後、続けて墓参りをするよう勧める。彼岸などと同様、花を供え、供え物をささげる。年末に墓掃除ができなかった場合は、墓を清め、落ち葉やゴミを拾う。墓参りが終わったら、供え物を引き取って帰る。