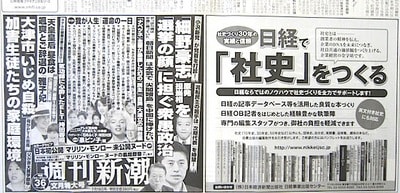■群馬県と業者が結託し、違法の限りを尽して群馬県安中市大谷地区に設置したサイボウ環境一般廃棄物(イッパイ)最終処分場は、平成19年4月に稼働を始めてから今年の3月末で、5年が経過します。この間に、当初から安中市、平成19年9月20日から館林市、平成22年4月1日から沼田市外二箇村清掃施設組合(沼田市、川場村、昭和村)、平成23年12月22日から甘楽町、そして平成24年3月1日から渋川地区広域市町村圏振興整備組合(渋川市、伊香保町、小野上村、赤城村、北橘村、吉岡町、榛東村)から、約2万7000トンの焼却灰、飛灰(ばいじん)、不燃残渣等が搬入されました。現在でも、毎月約1400トン、容積にして約1165㎥のゴミが運び込まれています。

↑サイボウ処分場の看板。↑
当会では、昨年7月末から8月初めと、昨年12月末にそれぞれ20トントラック数十台分の得たいの知れない残土と称する物質が、サイボウ処分場に持ち込まれたのを契機に、サイボウ処分場に持ち込まれる廃棄物について、安中市に情報開示を請求しました。その結果、判明した事項について報告します。
■もともとサイボウ処分場は、平成2年ごろ、地元の元市議会議長で不動産屋をしていた御仁(故人)が、安定五品目のサンパイ場を作ろうと画策したのが発端です。その計画は、地元の反対にあって平成5年に頓挫しましたが、それと入れ替わるようにして、埼玉県大宮市の株式会社サイボウ(埼玉防災の略称がそのまま社名になった)が関心を示しました。サイボウは自治体相手の防災用品を扱っているうちに、廃棄物処分場のニーズの高いことを知り、当時の同社社長の結城文夫(現在は息子の結城剛が社長)が、地元の元市議会議長らの誘いに乗り、進出してきたのでした。一方、群馬県では、東毛地方に自前の処分場を持たない自治体が多く存在していたため、民営の一般廃棄物処分場としては群馬県で3番目となるサイボウの処分場にやがて注目し始めました。
一方、地元安中市では、中島博範・前安中市長が平成7年11月の出直し市長に出馬した際、サイボウ社長の結城文夫が3千万円を持って、支援に駆けつけました。その甲斐あってか、その後、サイボウ処分場の計画は、地元住民の必死の反対運動にもかかわらず、行政支援のもとで、着々と進められたのでした。
■そして、平成11年8月30日にサイボウ処分場設置許可が群馬県から出されました。ところが、これと前後して、いろいろな問題が明らかになったのでした。とりわけ、進入道路の境界確定手続書類が偽造されていることが判明し、平成11年5月に地元住民が警察に告発しましたが、平成12年3月31日に、なぜかサイボウ社長の結城文夫ではなく、測量会社の社長だけが起訴され、平成12年5月12日の初公判で結審し、有罪判決が下されましたが、執行猶予付きだったので、サイボウは無傷のうえ、有罪の測量会社社長も平常どおり営業を継続したのでした。
この他にも、さまざまな問題が浮上し、地元住民はそれらを事件として提訴しましたが、全て住民側の敗訴となりました。裁判所は行政とグルになって、サイボウ処分場の建設に向けて側面からサポートしたのでした。
そうした経緯を辿って平成19年4月から稼働を始めたサイボウ処分場ですので、開業後もいろいろな問題が出てくることを当会を始め地元住民らは懸念しているのです。
■今では、誰一人認めようとしませんが、もともと安中市はサイボウ処分場に安中市のゴミは入れないと言ってきました。一方、ゴミ処分場施設の許可権限を持つ群馬県は上記のように東毛地区の一般ゴミの処分場が不足している為、サイボウ処分場の設置に積極的でした。
平成19年4月にサイボウ子会社のサイボウ環境が、処分場の稼働をスタートさせた時、安中市の市長は、前年の平成18年(2006年)4月の合併市長選で、中島博範・前市長を破った岡田義弘でした。岡田市長は、前市長の発言内容を遵守するつもりは皆無だったのでしょう。安中市は、平成10年に碓氷川クリーンセンターの焼却設備を完成させた当時は、松井田地区にあった処分場に焼却ゴミを捨てていましたが、まもなく満杯になり、平成13年からは、草津町にある㈱ウィズウェイストジャパンのイッパイ処分場に捨てるようになりました。
■ちなみに、同社の前身は山一カレット㈱といい、昭和63年3月に、群馬県新治村に県下最初の民営のイッパイ処分場を完成させました。その後平成4年4月に同社は本社を戸田市から大宮市に移転し、同年5月に山一カレットから㈱ウィズウェイストジャパンに社名を変更し、同年7月に、今度は草津町に草津ウェイストパークと称するイッパイ処分場を完成させました。
同社はその後も、平成6年2月に青森市で東北産業廃棄物㈱を発足させてサンパイ最終処分場をオープン、平成7年10月には霞ヶ浦町にイッパイ中間処理施設を完成、翌8年2月には千葉県東金市にサンパイ中間処理施設を完成、翌3月には福島県小野町にイッパイ処分場を完成、平成13年8月には草津ウェイストパークの増設工事を完了しました。さらに、平成16年12月には青森県三戸町にサンパイ処分場を完成させ、平成22年1月には新草津ウェイストパーク(埋立地面積41,866㎡、埋立容積85万㎥)を稼働開始させており、ガラス屑のリサイクルメーカーだった同社は、今や廃棄物処理が主要な業務となり、日本を代表する廃棄物処理業者のひとつです。
■さて、安中市によれば、平成13年から平成18年までは毎年3月に、入札でその年度の焼却ゴミの処分委託先業者を選定して、上記のウィズウェイストジャパン社の草津町のイッパイ処分場に焼却灰等を搬入していました。しかし、平成18年4月に岡田義弘市長が当選すると、平成19年3月に入札でサイボウ環境を選定し、平成19年4月の稼動に合せて、安中市の一般ゴミ焼却灰等を捨て始めたのでした。安中市環境推進課と碓氷川クリーンセンターによれば、以降、入札は行われておらず、毎年随意契約で、サイボウの大谷処分場に焼却灰、飛灰(ばいじん)、不燃残渣を捨てており、ずっと一律1トンあたり税抜きで1万7500円(運賃込み)でサイボウ環境に最終処分を委託しているそうです。
安中市の場合、一般ゴミが入らない水曜日のほか、火曜日と金曜日に、いずれも午前10時過ぎにサイボウ環境の所有する20トントラック2台がやってきて、あおりの付いた荷台に11トン程度の一般ゴミを積み込んでいます。
■安中市が、それまでの方針を変更して、イの一番にサイボウ処分場に一般ゴミを入れ始めましたが、半年後の平成19年9月20日に安中市長・岡田義弘、館林市長・安樂岡一雄、サイボウ環境社長・結城剛との間で「三者間公害防止協定書」が締結されました。この協定書は、沼田市、甘楽町、渋川市とも同じ内容です。




館林市では、現在、館林市苗木町字北近藤2494番地1にイッパイ最終処分場(不燃物・焼却残渣用、埋立面積11,370㎡、埋立容量8万㎥)があり、平成5年5月20日から使用してきました。平成27年度に次期処分場が完成するまで、8年間、現処分場の残余容量を確保しておきたいということで、平成28年3月31日まで延長使用できるように、焼却灰を安中市のサイボウ処分場に持ち込みたいというのが、委託理由でした。
館林市長から毎年、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物処理委託理由書」によると、次の変遷を辿っています。
●平成19年9月14日付/
理由:次期処分場の完成予定年度である平成27年度まで、現処分場の残余容量を確保したいため。
<現処分場の概要(平成18年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成20年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量17,930㎥、残余率22.4%。
年間埋立量:約3,400㎥、内訳;不燃物411t(換算容量330㎥)、焼却残渣3,923t(換算容量3,077㎥)。
最終覆土量5,000㎥、残余年数約3.8年(平成22年度まで)。
●平成20年4月25日付/
理由:次期廃棄物処理施設の計画を現在進めておるところですが、現一般廃棄物最終処分場の残余容量が厳しくなる中、容量確保のため。
<現処分場の概要(平成19年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成24年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量17,582㎥、残余率21.9%。
年間埋立量:約3,277㎥、内訳;不燃物369t(換算容量296㎥)、焼却残渣3,801t(換算容量2,981㎥)。
最終覆土量5,000㎥、残余年数約3.8年。
●平成21年7月1日付/
理由:次期廃棄物処理施設の計画を現在進めておるところですが、現一般廃棄物最終処分場の残余容量が厳しくなる中、容量確保のため。
<現処分場の概要(平成20年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成24年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量17,103㎥、残余率21.3%。
年間埋立量:約3,175㎥、内訳;不燃物311t(換算容量250㎥)、焼却残渣3,730t(換算容量2,925㎥)
最終覆土量5,700㎥、残余年数約3.5年。
●平成22年7月9日付/
理由:次期廃棄物処理施設の計画を現在進めておるところですが、現一般廃棄物最終処分場の残余容量が厳しくなる中、容量確保のため。
<現処分場の概要(平成21年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成24年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量13,709㎥、残余率17.0%。
年間埋立量:約3,197㎥、内訳;不燃物330t(換算容量265㎥)、焼却残渣3,739t(換算容量2,932㎥)
最終覆土量5,700㎥、残余年数約2年。
●平成23年7月13日付/
理由:次期廃棄物処理施設の計画を現在進めておるところですが、現一般廃棄物最終処分場の残余容量が厳しくなる中、容量確保のため。
<現処分場の概要(平成21年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成24年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量16,330㎥、残余率20%。
年間埋立量:約3,180㎥、内訳;不燃物313t(換算容量251㎥)、焼却残渣3,735t(換算容量2,929㎥)
最終覆土量5,700㎥、残余年数約2.5年。
館林市長から毎年、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物の処理の委託について(通知)」によると、次の変遷を辿っています。
◆平成19年9月4日付/処分期間:平成19年9月20日~平成20年3月31日、焼却灰3,532t(2,770㎥)
◆平成20年4月25日付/処分期間:平成20年5月1日~平成21年3月31日、焼却灰3,218t(2,523㎥)
◆平成21年7月1日付/処分期間:平成21年7月1日~平成22年3月31日、焼却灰3,070t(2,407㎥)
◆平成22年7月9日付/処分期間:平成22年7月15日~平成23年3月31日、焼却灰4,000t(3,137㎥)
◆平成23年7月13日付/処分期間:平成23年7月19日~平成24年2月29日、焼却灰3,350t(2,627㎥)
このように、館林市から安中市に搬入される一般ゴミの流れを見るといくつか不思議なことに気づきます。それらを列挙してみました。
(1)館林市からの一般廃棄物(焼却灰)の搬出場所は館林市苗木町2492番地1(館林市一般廃棄物最終処分場)となっている。一方、館林市は、現処分場の処理対象物は不燃物・焼却残渣としか書いていない。
(2)上記の館林市から安中市あての「一般廃棄物の処理の委託について(通知)」、いわゆる「事前通知」によると、毎年年度始めの4月から7月まで、処分期間の休止が行われており、この期間は、館林市のイッパイは一旦、処分場にストックされているものと見られる。
(3)現処分場の残余容量と残余年数は、毎年の年間埋立量(不燃物や焼却残渣)が3,100~3,400tあるのに、5年前の約3.8年から1年ちょっとしか減っていない。
(4)館林市は、平成28年3月31日まで現処分場を延命させる予定だが、そのために、一旦現処分場に捨ててあった焼却灰以外の不燃ゴミ(不燃物・焼却残渣)も、焼却灰とまぜこぜにして、安中市に持ち込んでいる可能性がある。つまり、サイボウ処分場は、館林市の現処分場の分身といえるのではないか。
【ひらく会情報部・この項つづく】
※参考資料
【館林市とのH19協定起案】
起案用紙
年度 平成19年度
文書種類 契約
文書番号 第11351号
保存年限 永年
受付年月日 平成19年9月14日
保存期限
起案年月日 平成19年9月14日
廃棄年度
決裁年月日 平成19年4月20日
分類番号 大5 中4 小0 簿冊番号3 分冊番号2
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称 契約書(永)
完結年月日 平成20年5月31日
分冊名称 契約書
施行区分 重要
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 市民部環境課廃棄物対策係 職名 課長補佐 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田 部長・秋山 課長・小泉 係長・真下 係・渡辺 公印・岡田9/20
関係部課合議
課内供覧 環境衛生係長・内?
宛先
差出人 群馬県館林市城町1番1号 館林市
件名 三者間公害防止協定の締結について(館林市)
上記のことについて、次のように協定を締結してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、サイボウ環境(株)結城剛及び館林市長安楽岡一雄から安中市大谷地内にあるサイボウ環境(株)の設置する一般廃棄物最終処分場における一般廃棄物の処分に際し、市民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害の対応について、三者協定を締結したい旨の依頼がありましたので別添協定書により協定を締結したいがよろしいか伺います。
【館林市とのH19三者間公害防止協定書】
三者間公害防止協定書
安中市(以下「甲」という。)と館林市(以下「乙」という。)及びサイボウ環境株式会社(以下「丙」という。)は、丙が群馬県安中市大谷字西谷津1893番地7他15筆に設置した一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の搬入並び処分に際し、関係住民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害を未然に防止するため並びに万が一公害が発生した場合の対応について、次のとおり協定を締結する。
(法令等の遵守)
第1条 乙及び丙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準、公害関係諸法令、群馬県の生活環境を保全する条例並びに本協定書の各項を厳守するものとする。
(搬入する廃棄物)
第2条 処理施設に搬入するものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める一般廃棄物のうち、群馬県内の市町村及び一部事務組合が収集及び処分した一般廃棄物(焼却灰、不燃残渣)に限定し、その他は一切搬入しないものとする。
2 一般廃棄物を搬入するにあたっては、甲、乙及び丙との間で本協定書を締結した後でなければ搬入してはならないものとする。
(事前協議及び報告)
第3条 乙及び丙は、甲が一般廃棄物についての協議が必要と認めた場合、これに応じなければならない。
2 乙は毎年度末までに、次年度に関する一般廃棄物処理計画に基づき、処分場で処理される予定の一般廃棄物の量を丙に報告し、丙はこれをまとめて甲に報告するものとする。
3 丙は、当該年度の搬入に係る一般廃棄物の種類及び量並びに処理量の実績を翌年度4月末日までに甲に報告するものとする。
(一般廃棄物の受け入れ基準)
第4条 丙が処分場に受け入れるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)に規定された一般廃棄物のうち、一般廃棄物の処理施設から搬出された焼却残灰(熱しゃく減量10%以下)及び不燃残渣に限定し、その他のものは一切搬入しないものとする。
2 甲及び丙は、廃棄物の受け入れにあたっては、乙に廃棄物の分析結果の報告を求め、法に基づく基準及び前項に定める規定に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(一般廃棄物管理票の使用)
第5条 乙は、丙に対し、処理・処分を委託する一般廃棄物の種類、数量その他必要事項を記載した一般廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、丙は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容と搬入された廃棄物を確認しなければならない。
2 甲は、必要に応じ、乙及び丙に一般廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求めることができるものとする。
(搬入する一般廃棄物の確認)
第6条 丙は、搬入する一般廃棄物の確認を受け入れ時において行うものとする。丙はその確認により不適合とした場合は、一般廃棄物の受け入れを行わないものとし、乙に対してその旨を通知するものとする。
(各種検査等の報告)
第7条 乙及び丙は、甲が行う必要な調査、検査及び各種測定等について協力し、それに係わる資料の要求があった場合は、これに応じるものとする。
2 丙は、処理施設に関する各種の検査が行なわれた時は、その結果を甲に報告しなければならない。
(被害補償)
第8条 丙は、埋め立てた一般廃棄物に起因して地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合は、速やかに加害原因の除去、原状回復その他適正な措置を講じるとともに、その状況・対策について甲に報告し、乙と連帯してその損害を賠償するものとする。
2 乙及び丙は、公害の事故等について公害の拡大又は再発を防止するため、甲が操業の一時停止を含む必要な措置を要請したときは、甲の指示に従うものとする。
3 丙は搬入に際し、甲又は第三者に被害を及ぼしたときは、直ちにその加害要因を除去するとともに、甲又は第三者に被害を補償しなければならない。
(一般廃棄物の搬入方法、時間帯)
第9条 甲及び丙による平成10年6月5日締結の協定書に基づき搬入車両は丙の車両とする。
2 搬入時間は8時30分から正午までとする。
3 協定書に変更があった場合は、甲、乙及び丙の協議により決めるものとする。
(立入調査等)
第10条 甲は、この協定の履行状況を確認するため、丙の処理施設に甲の指定する職員の立入調査を実施し、必要な報告を求めることができるものとし、乙及び丙はこのことに応じると共に協力するものとする。
(この協定書の失効)
第11条 本協定書に定める各条項については、処分場を閉鎖(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上に基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第17号で規定された「閉鎖」をいう)した日を持って効力を失うものとする。
(協議)
第12条 本協定書に定めのない事項または疑義については、甲、乙及び丙が協議の上決定する。
この協定を証するため、本書三通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自一通を保有する。
平成19年9月20日
(甲) 群馬県安中市安中一丁目23番13号
安中市代表者安中市長 岡 田 義 弘 印
(乙) 群馬県館林市城町1番1号
館林市代表者館林市長 安樂岡 一 雄 印
(丙) 群馬県安中市大谷1900番地1
サイボウ環境株式会社
代表取締役 結 城 剛 印
【館林市から安中市長へのH19一般廃棄物処理委託理由書】
5・3・1
平成19年9月14日
安中市長 岡田義弘様
館林市長 安樂岡一雄
一般廃棄物処理委託理由書
一般廃棄物(焼却灰)の処理について、下記の理由により貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ委託したいと存じますので、事情をお酌み取りのうえご理解を賜りたくお願い申し上げます。
記
1.理由
次期処分場の完成予定年度である平成27年度まで、現処分場の残余容量を確保したいため。
2.現処分場の概要(平成18年度末現在)
(1)施設名称 館林市一般廃棄物最終処分場
(2)設置場所 館林市苗木町宇北近藤24 9 4番地1
(3)処理対象物 不燃物・焼却残涜
(4)埋立面積 11,370㎡
(5)埋立容量 80,000㎥
(6)埋立期間 平成5年5月20日から平成20年3月31日まで
※平成28年3月31日まで延長予定
(7)残余容量 17,930㎥ 残余率22.4%
(8)年間埋立量 約3,400㎥/年
不燃物 411t/年(換算容量 330㎥/年)
焼却残涜 3,923t/年(換算容量 3,077㎥/年)
(9)最終覆土量 5,000㎥
(10)残余年数 約3.8年(平成22年度まで)
環境水道部資源対策課(館林市清掃センター)
担当:施設管理係 乙部
TEL:0276-72-4576 FAX:0276-72-4566
EML:seiso⑥city.tatebayashi.gunma.jp
※収受印:安中市19.9.14環境推進課収受

↑サイボウ処分場の看板。↑
当会では、昨年7月末から8月初めと、昨年12月末にそれぞれ20トントラック数十台分の得たいの知れない残土と称する物質が、サイボウ処分場に持ち込まれたのを契機に、サイボウ処分場に持ち込まれる廃棄物について、安中市に情報開示を請求しました。その結果、判明した事項について報告します。
■もともとサイボウ処分場は、平成2年ごろ、地元の元市議会議長で不動産屋をしていた御仁(故人)が、安定五品目のサンパイ場を作ろうと画策したのが発端です。その計画は、地元の反対にあって平成5年に頓挫しましたが、それと入れ替わるようにして、埼玉県大宮市の株式会社サイボウ(埼玉防災の略称がそのまま社名になった)が関心を示しました。サイボウは自治体相手の防災用品を扱っているうちに、廃棄物処分場のニーズの高いことを知り、当時の同社社長の結城文夫(現在は息子の結城剛が社長)が、地元の元市議会議長らの誘いに乗り、進出してきたのでした。一方、群馬県では、東毛地方に自前の処分場を持たない自治体が多く存在していたため、民営の一般廃棄物処分場としては群馬県で3番目となるサイボウの処分場にやがて注目し始めました。
一方、地元安中市では、中島博範・前安中市長が平成7年11月の出直し市長に出馬した際、サイボウ社長の結城文夫が3千万円を持って、支援に駆けつけました。その甲斐あってか、その後、サイボウ処分場の計画は、地元住民の必死の反対運動にもかかわらず、行政支援のもとで、着々と進められたのでした。
■そして、平成11年8月30日にサイボウ処分場設置許可が群馬県から出されました。ところが、これと前後して、いろいろな問題が明らかになったのでした。とりわけ、進入道路の境界確定手続書類が偽造されていることが判明し、平成11年5月に地元住民が警察に告発しましたが、平成12年3月31日に、なぜかサイボウ社長の結城文夫ではなく、測量会社の社長だけが起訴され、平成12年5月12日の初公判で結審し、有罪判決が下されましたが、執行猶予付きだったので、サイボウは無傷のうえ、有罪の測量会社社長も平常どおり営業を継続したのでした。
この他にも、さまざまな問題が浮上し、地元住民はそれらを事件として提訴しましたが、全て住民側の敗訴となりました。裁判所は行政とグルになって、サイボウ処分場の建設に向けて側面からサポートしたのでした。
そうした経緯を辿って平成19年4月から稼働を始めたサイボウ処分場ですので、開業後もいろいろな問題が出てくることを当会を始め地元住民らは懸念しているのです。
■今では、誰一人認めようとしませんが、もともと安中市はサイボウ処分場に安中市のゴミは入れないと言ってきました。一方、ゴミ処分場施設の許可権限を持つ群馬県は上記のように東毛地区の一般ゴミの処分場が不足している為、サイボウ処分場の設置に積極的でした。
平成19年4月にサイボウ子会社のサイボウ環境が、処分場の稼働をスタートさせた時、安中市の市長は、前年の平成18年(2006年)4月の合併市長選で、中島博範・前市長を破った岡田義弘でした。岡田市長は、前市長の発言内容を遵守するつもりは皆無だったのでしょう。安中市は、平成10年に碓氷川クリーンセンターの焼却設備を完成させた当時は、松井田地区にあった処分場に焼却ゴミを捨てていましたが、まもなく満杯になり、平成13年からは、草津町にある㈱ウィズウェイストジャパンのイッパイ処分場に捨てるようになりました。
■ちなみに、同社の前身は山一カレット㈱といい、昭和63年3月に、群馬県新治村に県下最初の民営のイッパイ処分場を完成させました。その後平成4年4月に同社は本社を戸田市から大宮市に移転し、同年5月に山一カレットから㈱ウィズウェイストジャパンに社名を変更し、同年7月に、今度は草津町に草津ウェイストパークと称するイッパイ処分場を完成させました。
同社はその後も、平成6年2月に青森市で東北産業廃棄物㈱を発足させてサンパイ最終処分場をオープン、平成7年10月には霞ヶ浦町にイッパイ中間処理施設を完成、翌8年2月には千葉県東金市にサンパイ中間処理施設を完成、翌3月には福島県小野町にイッパイ処分場を完成、平成13年8月には草津ウェイストパークの増設工事を完了しました。さらに、平成16年12月には青森県三戸町にサンパイ処分場を完成させ、平成22年1月には新草津ウェイストパーク(埋立地面積41,866㎡、埋立容積85万㎥)を稼働開始させており、ガラス屑のリサイクルメーカーだった同社は、今や廃棄物処理が主要な業務となり、日本を代表する廃棄物処理業者のひとつです。
■さて、安中市によれば、平成13年から平成18年までは毎年3月に、入札でその年度の焼却ゴミの処分委託先業者を選定して、上記のウィズウェイストジャパン社の草津町のイッパイ処分場に焼却灰等を搬入していました。しかし、平成18年4月に岡田義弘市長が当選すると、平成19年3月に入札でサイボウ環境を選定し、平成19年4月の稼動に合せて、安中市の一般ゴミ焼却灰等を捨て始めたのでした。安中市環境推進課と碓氷川クリーンセンターによれば、以降、入札は行われておらず、毎年随意契約で、サイボウの大谷処分場に焼却灰、飛灰(ばいじん)、不燃残渣を捨てており、ずっと一律1トンあたり税抜きで1万7500円(運賃込み)でサイボウ環境に最終処分を委託しているそうです。
安中市の場合、一般ゴミが入らない水曜日のほか、火曜日と金曜日に、いずれも午前10時過ぎにサイボウ環境の所有する20トントラック2台がやってきて、あおりの付いた荷台に11トン程度の一般ゴミを積み込んでいます。
■安中市が、それまでの方針を変更して、イの一番にサイボウ処分場に一般ゴミを入れ始めましたが、半年後の平成19年9月20日に安中市長・岡田義弘、館林市長・安樂岡一雄、サイボウ環境社長・結城剛との間で「三者間公害防止協定書」が締結されました。この協定書は、沼田市、甘楽町、渋川市とも同じ内容です。




館林市では、現在、館林市苗木町字北近藤2494番地1にイッパイ最終処分場(不燃物・焼却残渣用、埋立面積11,370㎡、埋立容量8万㎥)があり、平成5年5月20日から使用してきました。平成27年度に次期処分場が完成するまで、8年間、現処分場の残余容量を確保しておきたいということで、平成28年3月31日まで延長使用できるように、焼却灰を安中市のサイボウ処分場に持ち込みたいというのが、委託理由でした。
館林市長から毎年、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物処理委託理由書」によると、次の変遷を辿っています。
●平成19年9月14日付/
理由:次期処分場の完成予定年度である平成27年度まで、現処分場の残余容量を確保したいため。
<現処分場の概要(平成18年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成20年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量17,930㎥、残余率22.4%。
年間埋立量:約3,400㎥、内訳;不燃物411t(換算容量330㎥)、焼却残渣3,923t(換算容量3,077㎥)。
最終覆土量5,000㎥、残余年数約3.8年(平成22年度まで)。
●平成20年4月25日付/
理由:次期廃棄物処理施設の計画を現在進めておるところですが、現一般廃棄物最終処分場の残余容量が厳しくなる中、容量確保のため。
<現処分場の概要(平成19年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成24年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量17,582㎥、残余率21.9%。
年間埋立量:約3,277㎥、内訳;不燃物369t(換算容量296㎥)、焼却残渣3,801t(換算容量2,981㎥)。
最終覆土量5,000㎥、残余年数約3.8年。
●平成21年7月1日付/
理由:次期廃棄物処理施設の計画を現在進めておるところですが、現一般廃棄物最終処分場の残余容量が厳しくなる中、容量確保のため。
<現処分場の概要(平成20年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成24年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量17,103㎥、残余率21.3%。
年間埋立量:約3,175㎥、内訳;不燃物311t(換算容量250㎥)、焼却残渣3,730t(換算容量2,925㎥)
最終覆土量5,700㎥、残余年数約3.5年。
●平成22年7月9日付/
理由:次期廃棄物処理施設の計画を現在進めておるところですが、現一般廃棄物最終処分場の残余容量が厳しくなる中、容量確保のため。
<現処分場の概要(平成21年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成24年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量13,709㎥、残余率17.0%。
年間埋立量:約3,197㎥、内訳;不燃物330t(換算容量265㎥)、焼却残渣3,739t(換算容量2,932㎥)
最終覆土量5,700㎥、残余年数約2年。
●平成23年7月13日付/
理由:次期廃棄物処理施設の計画を現在進めておるところですが、現一般廃棄物最終処分場の残余容量が厳しくなる中、容量確保のため。
<現処分場の概要(平成21年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成24年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量16,330㎥、残余率20%。
年間埋立量:約3,180㎥、内訳;不燃物313t(換算容量251㎥)、焼却残渣3,735t(換算容量2,929㎥)
最終覆土量5,700㎥、残余年数約2.5年。
館林市長から毎年、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物の処理の委託について(通知)」によると、次の変遷を辿っています。
◆平成19年9月4日付/処分期間:平成19年9月20日~平成20年3月31日、焼却灰3,532t(2,770㎥)
◆平成20年4月25日付/処分期間:平成20年5月1日~平成21年3月31日、焼却灰3,218t(2,523㎥)
◆平成21年7月1日付/処分期間:平成21年7月1日~平成22年3月31日、焼却灰3,070t(2,407㎥)
◆平成22年7月9日付/処分期間:平成22年7月15日~平成23年3月31日、焼却灰4,000t(3,137㎥)
◆平成23年7月13日付/処分期間:平成23年7月19日~平成24年2月29日、焼却灰3,350t(2,627㎥)
このように、館林市から安中市に搬入される一般ゴミの流れを見るといくつか不思議なことに気づきます。それらを列挙してみました。
(1)館林市からの一般廃棄物(焼却灰)の搬出場所は館林市苗木町2492番地1(館林市一般廃棄物最終処分場)となっている。一方、館林市は、現処分場の処理対象物は不燃物・焼却残渣としか書いていない。
(2)上記の館林市から安中市あての「一般廃棄物の処理の委託について(通知)」、いわゆる「事前通知」によると、毎年年度始めの4月から7月まで、処分期間の休止が行われており、この期間は、館林市のイッパイは一旦、処分場にストックされているものと見られる。
(3)現処分場の残余容量と残余年数は、毎年の年間埋立量(不燃物や焼却残渣)が3,100~3,400tあるのに、5年前の約3.8年から1年ちょっとしか減っていない。
(4)館林市は、平成28年3月31日まで現処分場を延命させる予定だが、そのために、一旦現処分場に捨ててあった焼却灰以外の不燃ゴミ(不燃物・焼却残渣)も、焼却灰とまぜこぜにして、安中市に持ち込んでいる可能性がある。つまり、サイボウ処分場は、館林市の現処分場の分身といえるのではないか。
【ひらく会情報部・この項つづく】
※参考資料
【館林市とのH19協定起案】
起案用紙
年度 平成19年度
文書種類 契約
文書番号 第11351号
保存年限 永年
受付年月日 平成19年9月14日
保存期限
起案年月日 平成19年9月14日
廃棄年度
決裁年月日 平成19年4月20日
分類番号 大5 中4 小0 簿冊番号3 分冊番号2
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称 契約書(永)
完結年月日 平成20年5月31日
分冊名称 契約書
施行区分 重要
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 市民部環境課廃棄物対策係 職名 課長補佐 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田 部長・秋山 課長・小泉 係長・真下 係・渡辺 公印・岡田9/20
関係部課合議
課内供覧 環境衛生係長・内?
宛先
差出人 群馬県館林市城町1番1号 館林市
件名 三者間公害防止協定の締結について(館林市)
上記のことについて、次のように協定を締結してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、サイボウ環境(株)結城剛及び館林市長安楽岡一雄から安中市大谷地内にあるサイボウ環境(株)の設置する一般廃棄物最終処分場における一般廃棄物の処分に際し、市民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害の対応について、三者協定を締結したい旨の依頼がありましたので別添協定書により協定を締結したいがよろしいか伺います。
【館林市とのH19三者間公害防止協定書】
三者間公害防止協定書
安中市(以下「甲」という。)と館林市(以下「乙」という。)及びサイボウ環境株式会社(以下「丙」という。)は、丙が群馬県安中市大谷字西谷津1893番地7他15筆に設置した一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の搬入並び処分に際し、関係住民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害を未然に防止するため並びに万が一公害が発生した場合の対応について、次のとおり協定を締結する。
(法令等の遵守)
第1条 乙及び丙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準、公害関係諸法令、群馬県の生活環境を保全する条例並びに本協定書の各項を厳守するものとする。
(搬入する廃棄物)
第2条 処理施設に搬入するものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める一般廃棄物のうち、群馬県内の市町村及び一部事務組合が収集及び処分した一般廃棄物(焼却灰、不燃残渣)に限定し、その他は一切搬入しないものとする。
2 一般廃棄物を搬入するにあたっては、甲、乙及び丙との間で本協定書を締結した後でなければ搬入してはならないものとする。
(事前協議及び報告)
第3条 乙及び丙は、甲が一般廃棄物についての協議が必要と認めた場合、これに応じなければならない。
2 乙は毎年度末までに、次年度に関する一般廃棄物処理計画に基づき、処分場で処理される予定の一般廃棄物の量を丙に報告し、丙はこれをまとめて甲に報告するものとする。
3 丙は、当該年度の搬入に係る一般廃棄物の種類及び量並びに処理量の実績を翌年度4月末日までに甲に報告するものとする。
(一般廃棄物の受け入れ基準)
第4条 丙が処分場に受け入れるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)に規定された一般廃棄物のうち、一般廃棄物の処理施設から搬出された焼却残灰(熱しゃく減量10%以下)及び不燃残渣に限定し、その他のものは一切搬入しないものとする。
2 甲及び丙は、廃棄物の受け入れにあたっては、乙に廃棄物の分析結果の報告を求め、法に基づく基準及び前項に定める規定に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(一般廃棄物管理票の使用)
第5条 乙は、丙に対し、処理・処分を委託する一般廃棄物の種類、数量その他必要事項を記載した一般廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、丙は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容と搬入された廃棄物を確認しなければならない。
2 甲は、必要に応じ、乙及び丙に一般廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求めることができるものとする。
(搬入する一般廃棄物の確認)
第6条 丙は、搬入する一般廃棄物の確認を受け入れ時において行うものとする。丙はその確認により不適合とした場合は、一般廃棄物の受け入れを行わないものとし、乙に対してその旨を通知するものとする。
(各種検査等の報告)
第7条 乙及び丙は、甲が行う必要な調査、検査及び各種測定等について協力し、それに係わる資料の要求があった場合は、これに応じるものとする。
2 丙は、処理施設に関する各種の検査が行なわれた時は、その結果を甲に報告しなければならない。
(被害補償)
第8条 丙は、埋め立てた一般廃棄物に起因して地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合は、速やかに加害原因の除去、原状回復その他適正な措置を講じるとともに、その状況・対策について甲に報告し、乙と連帯してその損害を賠償するものとする。
2 乙及び丙は、公害の事故等について公害の拡大又は再発を防止するため、甲が操業の一時停止を含む必要な措置を要請したときは、甲の指示に従うものとする。
3 丙は搬入に際し、甲又は第三者に被害を及ぼしたときは、直ちにその加害要因を除去するとともに、甲又は第三者に被害を補償しなければならない。
(一般廃棄物の搬入方法、時間帯)
第9条 甲及び丙による平成10年6月5日締結の協定書に基づき搬入車両は丙の車両とする。
2 搬入時間は8時30分から正午までとする。
3 協定書に変更があった場合は、甲、乙及び丙の協議により決めるものとする。
(立入調査等)
第10条 甲は、この協定の履行状況を確認するため、丙の処理施設に甲の指定する職員の立入調査を実施し、必要な報告を求めることができるものとし、乙及び丙はこのことに応じると共に協力するものとする。
(この協定書の失効)
第11条 本協定書に定める各条項については、処分場を閉鎖(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上に基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第17号で規定された「閉鎖」をいう)した日を持って効力を失うものとする。
(協議)
第12条 本協定書に定めのない事項または疑義については、甲、乙及び丙が協議の上決定する。
この協定を証するため、本書三通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自一通を保有する。
平成19年9月20日
(甲) 群馬県安中市安中一丁目23番13号
安中市代表者安中市長 岡 田 義 弘 印
(乙) 群馬県館林市城町1番1号
館林市代表者館林市長 安樂岡 一 雄 印
(丙) 群馬県安中市大谷1900番地1
サイボウ環境株式会社
代表取締役 結 城 剛 印
【館林市から安中市長へのH19一般廃棄物処理委託理由書】
5・3・1
平成19年9月14日
安中市長 岡田義弘様
館林市長 安樂岡一雄
一般廃棄物処理委託理由書
一般廃棄物(焼却灰)の処理について、下記の理由により貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ委託したいと存じますので、事情をお酌み取りのうえご理解を賜りたくお願い申し上げます。
記
1.理由
次期処分場の完成予定年度である平成27年度まで、現処分場の残余容量を確保したいため。
2.現処分場の概要(平成18年度末現在)
(1)施設名称 館林市一般廃棄物最終処分場
(2)設置場所 館林市苗木町宇北近藤24 9 4番地1
(3)処理対象物 不燃物・焼却残涜
(4)埋立面積 11,370㎡
(5)埋立容量 80,000㎥
(6)埋立期間 平成5年5月20日から平成20年3月31日まで
※平成28年3月31日まで延長予定
(7)残余容量 17,930㎥ 残余率22.4%
(8)年間埋立量 約3,400㎥/年
不燃物 411t/年(換算容量 330㎥/年)
焼却残涜 3,923t/年(換算容量 3,077㎥/年)
(9)最終覆土量 5,000㎥
(10)残余年数 約3.8年(平成22年度まで)
環境水道部資源対策課(館林市清掃センター)
担当:施設管理係 乙部
TEL:0276-72-4576 FAX:0276-72-4566
EML:seiso⑥city.tatebayashi.gunma.jp
※収受印:安中市19.9.14環境推進課収受