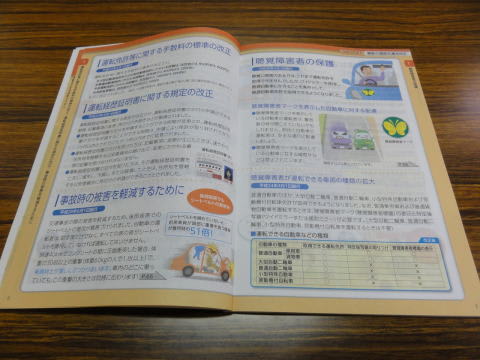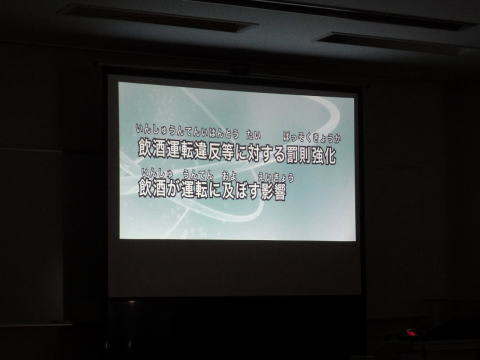旧長崎税関三池税関支署の内部の様子

明治41(1908)年4月1日に三池港が開港し、4月6日に開港場に指定された。
このときに、同時に開庁したのが、旧長崎税関三池税関支署です。
建物は木造平屋建、入母屋造に切妻造附き桟瓦葺一部銅板葺で、
3方の出入り口をもつ土間で関税の手続きが行われていた。
当時は本館および附属建物からなっていた。
三池炭鉱専用積み出し港である三池港に設置された当税関は、
企業側で設計・建築され、明治期の洋風建築としての風貌を残し、
三池港の歴史・港湾機能を考える上でも重要な施設である。
この税関は三池港開港と同時に使われ、
開港場として築かれた三池港の港湾機能(海外貿易)を示すものであり、
三池港繁栄の歴史の象徴であり、往時の三池港の景観の一部として不可欠な建物である。
現在も当時と同じ場所に残されており、当時の景観を現代に伝えている。
現在、旧長崎税関三池税関支署の南側には、
現在も専用鉄道敷きの木製の枕木と鉄のレールが埋没している。
これは当時周辺に立ち並んでいた倉庫群に引き込まれていた線路敷きの遺構である。
専用鉄道敷きが各坑口をつなぎながら三池港まで至り、物流網を形成したことがよく解かる。
当時、税関支署の周りには三池港務所の倉庫群や、貯炭場が広がっていた。