■ 市議会議員選挙の立候補者が私よりも若い ■
統一地方選挙の投票が有りました。浦安でも市議会議員選挙が行われ、沢山の立候補者のポスターが貼られていました。その顔ぶれを見てショックを受けた。「みんな、俺よりも若い・・・」
ほとんどの候補者が、「福祉の充実」とか「子育て支援」を公約に掲げています。これなら誰に投票しても同じでは無いか・・・そんな感想しか出て来ない顔ぶれ。
■ 行政の監視役としての議会 ■
議会制民主主義において議会は行政の監視役として機能します。
1)税金が正しく使われているか
2)配分は適切か
元々は、イギリスで資本家達が自分達が収めた税金の使い方が妥当かどうか、専制君主を監視する為に勝ち取ったシステムが議会制民主主義です。議員は納税者の代表として、税金の使い道を監視します。
■ 議員は住民の代表? ■
地方の議員は様々な理由があって立候補されます。
1) 業界の代表
2) 地域の代表
3) 地元の名士
4) 困った人の代表
5) 宗教団体の代表
主だった立候補の理由はこんな所でしょう。彼らは自分達を支援する人達の為に、予算を分捕るのが仕事。
■ ベットタウンでは納税者と受益者が異なるケースも ■
浦安の様なベットタウンでは、選挙と言われてもピンと来ない人がほとんどです。納税者の多くは東京の企業で働くサラリーマンや派遣社員ですが、地元との繋がりは希薄です。当然、立候補者は無縁な人達ばかりで、誰に投票すれば自分の利益になるのか分かりません。
立候補者は、「誰に投票したら良いか分からない票」を獲得する為に、とりあえず、不特定多数の人が反対しないであろう「子育て支援の充実」や「福祉の充実」を公約に掲げます。間違っても「自分の支持者の利益を守る」などとは選挙中には言いません。
■ 議員は暇な人の集まりになってしまった・・・ ■
議員は議会運営である程度の時間拘束を受けますから、サラリーマンを続けながら議員活動をする事は不可能です。当然、議員は「暇な人」が立候補する事になります。
例えば、市民活動に精を出す主婦だとか、定年後のサラリーマンだとか、商工会の顔役的な暇な商店主とか・・・。或いは、時間に余裕のある会社経営者などです。
本来、議会制民主主義は、「有権者よりも知見のある有識者」に判断を託す事で、有権者の利益と公共の利益のバランスを取る為のシステムです。当然、議員は一般的な有権者よりも優れた人が勤める事が前提です。
地方議会は意外にまともで、村の有力者が議員になりますから、ある程度「地域の総意」が実現します。一方、首都圏のベットタウンでは、議員は有象無象の集団となりがちですから、議員に政策判断の知識すら無い場合も多い。自分に関わる議案意外は、何となく議場の空気に流されて賛成、反対を決めている方も多いでしょう。
■ 落選したら無職・・・議員は職業になってしまった ■
最初は労働組合の代表として、業界団体の代表として立候補する方も多いかと思います。しかし、議員を何期か勤めているうちに「職業=議員」になってしまう人も多い。
そうなると「当選=職の獲得」となりますから、地元の集まりに足しげく通い顔を売り、地元の人からの陳情に耳を傾け、その実現に努める様になります。これ自体は悪くは無い事です。
ただ、その結果が、信号の無い交差点に信号を設置させた・・・程度の実績だったりします。そして、その信号が原因で渋滞が発生したりする。
■ ヨーロッパなどでは地方議会の議員は無報酬で、議会も夜間に開催されたりする ■
議会制民主主義の発祥の地の欧州では、地方議員は名誉職の一つで、議員報酬は極めて低い。さらには、昼間働いている市民が議員のなれる様に、議会が夜間開催されるケースも有ります。
そうしないと、ヨーロッパと言えども議会が「プロ市民」と「業界の代表」に占拠されてしまうからです。
尤も、ヨーロッパでも「プロ市民」は議会に浸透しています。ドイツの「緑の党」などが良い例え、かつてのドイツ赤軍の活動家達が、「環境保護団体」に姿を変えて生き延びています。
■ ネットの時代の議会制民主主義 ■
議会制民主主義の目的は二つです。
1) 物理的に有権者全てが議決に参加する事は不可能
2) 有識者の代表が議決件を持つ方が公共の福祉を達成し易い
ネットの時代に直接民主主義は技術的に達成可能です。「イイネ!」の感覚で議案に投票させる事は簡単でしょう。ただ、それが正しいかと言えば、「私利私欲の人気投票」に陥り、「究極のポピュリズム」が完成します。人々は税負担を嫌い、福祉の充実を求めます。
では、将来的にAIに公平性を担保させる事は可能でしょうか?「AI議員」や「AI議会」です。
長谷敏司のSF小説『BEATLESS』では、AI政治家の実験が作中で登場します。AIはネットから人々の要求を収集し、最適化の学習をする・・・。これも「究極のポピュリズム」に陥りそうですが、「最適化」の中で、むき出しの私欲は抑制されます。
実際にはAIに政治を委ねる事は人間には抵抗が有ります。SF小説の多くは、コンピューターやAIの支配する未来を、ターミネーターの様な「デストピア」として描く傾向が強い。これは、人間が「エゴ」むき出しの存在である事の自覚と、コンピュターやAIが合理性を追求するという理想おギャップが生み出す妄想です。エゴは合理的で無いと理解している。
■ 集団生存を目的とする「ミーム=社会的遺伝子」 ■
かつて一世を風靡した「利己的な遺伝子」という発想は、個体の進化は、個体を構成する遺伝子生存戦略に支配されるという思想です。優秀な遺伝子を後世に伝える為に、遺伝子レベルの競争が絶え間なく繰り返される。
一方、昨今は「社会的遺伝子=ミーム」という発想が注目を集めています。これは「個は集団の存続を優先させる」という発想にも通じています。「人が個人としては不合理な選択をするのは、集団利益を優先する為だ」・・・日本人には自然に理解できますが、個人主義の欧米では目新しく感じるのでしょう。
一見不合理に思える現代の議会制民主主義ですが、集団社会がこのシステムを生み出し、発展させて来たのならば、そこには何等かのメリットが在るのかも知れません。或いは、システムの劣化が集団淘汰の原因となるのか・・・・。
地方選挙のポスターの顔ぶれを見て、「この集団は負けてしまうかも知れない」という恐怖を感じたのは、私だけでは無いハズです。











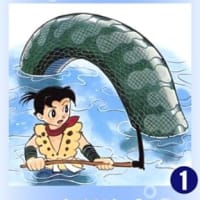
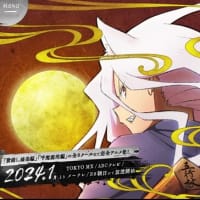







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます