
■ 資産買い入れを再開していたFRB ■
FRBの利下げ報道の影に隠れていまうが、実はFRBは2019年9月から資産買い入れを再開しています。上のグラフはFRBのバランスシート推移ですが、右端で跳ね上がっている事が分かります。
1年未満の短期の国債購入を行っている様ですが、これって「QE4(量的緩和)」じゃね?と思うのは私だけではありあません。
「それがアヒルのように見え、アヒルのように歩き、アヒルのように鳴くなら、それはアヒルだ。」と発言したのは経済評論家のピーター・シフですが、資産買い入れ再開を量的緩和では無いと言い張るパウエルFRB議長を皮肉った。
■ 資金供給量が増えればバブルは膨らむ ■
FRBの利下げ以降顕著な市場の上昇ですが、QE4の効果もそれなりに出ているはずです。焚火に燃料を追加すれば、炎は一層激しく燃え上がります。
トランプの要求に渋々対応するふりをしながらも、FRBはしっかりと市場に燃料をくべて、大統領選まで相場を上昇させる気満々です。
■ 様々な事件にに敏感に反応する市場 ■
FRBの緩和拡大で市場のファンダメンタルは上昇ですが、先日のイランと米国の緊張の高まりで大きく値を下げた様に、様々な出来事に過敏に反応しています。
現在は米中貿易協定の第一ラウンドが、どうにか丸く収まると見て、市場は相当強気になっていますが、直ぐに調整に入り、ダウが一気に3万ドルに達する事は無いでしょう。
ただ、大統領選まではトランプ政権は相場を上昇させたいので、あの手、この手を使うでしょう。FRBに強引に利下げも要求する。
■ 株式はリスクが少なく、債券はリスクが高い? ■
FRBの利下げによって債券の金利が下がってしまったので、債券市場の金利はリスクに見合わなくなっています。結果的にリスクに対して債権よりもマシな金利(利益)が確保できる株式市場に資金が流れ込み、株価を押し上げています。
日本と同様に、アメリカの株価は実体経済と乖離しています。特にIT系企業でその傾向は顕著ですが、アップルの業績が振るわなかったり、WeWorkのIPOが延期されるなど、昨年辺りから不安材料は増えています。
現在の株高は、緩和マネーの生み出した過剰流動性が行き場をを無くして、株式市場に流入しているだけかも知れません。
■ 市場との対話って・・・■
FRBは市場を焦らしたり、エサを与えたりが上手です。これを市場との対話と表現します。しかし、昨今の隠れQE4や利下げの経緯を見ると、ご主人様は市場で、FRBはその要求に屈服している様にも見えます。
結果的には相場は持ち直し、一時は凍り付いた債権市場にも再び活気が戻りつつあります。これを良しとするか、それともバブルの総仕上げと見るかは、個人の主観に任せるしかありません。
ただ、市場は今後、益々ピーキーな動きになるでしょうから、個人は振り落とされ無い様にしがみ付くか、或いは列車を降りるか判断すべき時期に来ていると思います。
・・・・正直な気持ちを言ってしまえば・・・市場って意外にタフだなと思う今日この頃。











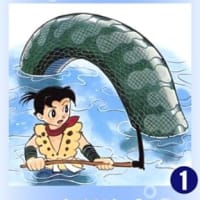
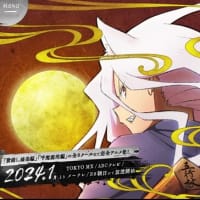







それに合わせてバフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイの資産の現金比率が過去最高になり、株安に備えていると言われています。
バフェット指数は米国1.6倍に対し日本は1.23倍(東証1部661兆円、2部8兆円、JQ10兆円、マザーズ6兆円、名目GDP 557兆円)で、割安です。
ここにも、2020年相場は「米国株より日本株」が見えます。
相場はキリスト教原理主義者のトランプの手のひらの上
2019年の相場は、年間を通じてトランプ大統領の発言に右往左往させられることになりました。
その1つがFRBへの利下げ圧力です。クリスマス・ショックを受けて、景気後退を避けるためにと、TwitterでFRBに利下げを迫る圧力をかけ続けました。これを受け、利下げに対する市場の期待感が高まり、年前半の上昇が起こります。
しかし、元はと言えば昨年までトランプ大統領自らが仕掛けた米中貿易戦争により中国経済が減速し、株価が急落したのです。大統領としては自らの手腕で株価を上げたように発言していますが、見れば見るほど自作自演、マッチポンプなのです。
市場が利下げを織り込むと、夏頃には再び勢いがなくなってきます。そこで大統領は米中貿易戦争の和解をちらつかせ、投資家の心をくすぐったのです。すると、秋頃から年末にかけて、株価は見事に上昇しました。
米国株は史上最高値を更新し続け、大統領はご満悦です。Twitterを使った「株価操作」に関して彼の右に出る人はいないように思えます。
なぜトランプ大統領がここまで株価にこだわるのかと言えば、2020年11月3日には2期目をかけた大統領選挙が行われるからです。米国では大多数の国民が何かしらの形で株式を持っていますから、株価の上げ下げは支持率に直結します。
これから大統領選挙にかけてトランプ大統領の思い通りになるとすれば、株価はもう下がりようがないという気さえします。
https://www.youtube.com/watch?v=4tkcoC0mgmU
前議長、パウエル現議長の金融政策の舵取りは極めてエ
レガントという感じがします。
幸か不幸か2015年からドルの水準をほぼ一定にキープで
きており、妙に崩れないままだらだら続く適温相場の正
体かもしれません。明確にわかるのは、原因がなんであ
れこれが動いたらやばそうということくらい。
米ドル指数
https://jp.investing.com/currencies/us-dollar-index-streaming-chart
長期のドルインデックスのチャートは米国株と同じ経過をしているだけですね:
S&P500 は 09 年安値(666)以来、サイクル第Ⅰ波の上昇局面にあるとみている。第Ⅰ波はプライマリー級の 5 波構成─(1)-(2)-(3)-(4)-(5)─となる。18 年 12 月 26 日安値(2346)以来プライマリー第(5)波が進行中。
NY ダウは 6 月 3 日安値(24680 ドル)以来、プライマリー第(5)波における第(iii)波の上昇トレンドが進行中である。
長期のドルインデックスのチャートも
プライマリー第(5)波における第(iii)波の上昇トレンドが進行中
米国選挙が終わったらプライマリー第(5)波も終了して長期下降トレンドに入るのですね。
高くなり過ぎった米株より日本株は魅力的ですが、海外勢が大量買いするのは、一度値が大きく落ちた後ですかね。それまではチョロチョロと吊り上げてはストンと落とし、日銀なGPIFが下値を支える展開が続くのでしょう。
ドル、株ともに大統領選がピークと見る投資家は多いでしょう。トランプが変な気を起こさない限り、この予測通りだと思いますが・・・何せトランプ・・・。
しかし、裏で誰が筋書を書いているのかは知りませんが、面白い役者に仕立て上げたものですね。大統領のTwitterって本当に本人が書いているのか疑問です。絶妙なタイミングで相場を手玉に取る。実はウォール街のメインフレームで稼働するAIだったりして・・・。
「税金は取りやすい所から取る」は鉄則ですが、選挙で消費税増税に国民が反対を示さない限り、消費税が増税され、法人税が減税される・・・。
消費税は消費の量に比例して自動的に課税されるので、ある意味「公平な税」ですが、低所得層の税負担が重くなるという「逆進性」も顕著です。
公平な税制は基本的に実現不可能ですが、少なくとも消費税を上げるのならば、「負の所得税」の様な逆進性を緩和する税制とセットであるべき。補助だとか、控除といった小手先の変更は恣意的であり、政治家の点稼ぎと使われる一方で継続性が無く、税収を不安定にする要因です。
「負の所得税」という形で年金制度や生活保護を一体化すれば行政コストは大幅に削減され、「口利き」などの利権を防ぐ事も出来ますが、これには公明党が反対しそうですね。「口利き」は彼らのビジネスになっていますから。
基本的には税制の全体のビジョンを語らず、増税や減税を政治の道具とする現在の国会の在り方に問題が有るのですが、財務省も政治家への影響力を維持する為に税制を利用している節があります。
FRBの金融政策は一見エレガントですが、ある意味においては対症療法的とも言えます。一種のフィードバック型のシーケンス制御とも言えますが、「空気を読む」センサーの性能が高い。
FRBに対する「市場の信頼」というのが何かいつも不思議に思うのですが、「期待に応えてくれる」「期待を裏切らない」という事が目下の所、信頼を支えている様に思えます。
「ちょっと市場に資金が足りないな・・・」と市場が感じた時、きちんと蛇口を開いてくれる信頼。
FRBは自体経済の様々な指数や失業率を金融政策の指標にしている「振り」をしていますが、実際には「市場の空気」により敏感に、そして先行して反応しています。そこまでのアナウンスも上手い。
一方、黒田日銀の政策発表はいつも唐突に見えますが、きっと裏での根回しは完璧なのでしょう。
いずれにしても主要通貨の為替の安定が現在の「ぬるま湯」相場を維持していますが、風呂の水が上から少し溢れる程度なら問題は在りませんが、底が抜けると浴び驚嘆の世界となります。過熱感の無い「ぬるま湯」ですが、リスクの総量が増えている・・・。
米国時間12月10日から11日までアメリカの中央銀行Fed(連邦準備制度)は金融政策決定会合であるFOMC会合を行い、政策金利を1.50%から1.75%の範囲に維持することを決定した。政策金利の維持は事前の市場予想と一致している。つまり市場の想定通りである。
パウエル議長の職務放棄
いつも通り発表された資料を見てゆくが、まず発表された声明文ではほとんど意味のあることを言っていない。「われわれは現在の政策スタンスが経済活動の持続的拡大や強い労働市場、そして2%のインフレ目標を支えるために適切だと考えている」とのことである。
会合に参加している委員による将来の政策金利の予想値を示したドットプロットでは13人が2020年内の政策金利の現状維持、4人が1回の利上げを予想している。
これまでのFedの動きをフォローしている投資家にとっては、こうしたメッセージが何の意味も持たないことは明らかだろう。Fedは今年3回の利下げを行ったが、彼らが言っているような労働市場やインフレ率がその根拠になったのではなく、単に金利先物市場における今後の金利の予想がそうなっていたからFedはそれに従ったのである。
パウエル議長は明らかに市場の予想に反して市場の逆鱗に触れることを恐れている。彼は表立っては認めていないが、2018年の世界同時株安の原因となったのがFedの金融引き締めだからである。
そしてパウエル議長はそれがトラウマになっているのである。
ということで、Fedの発表にまともに耳を傾けることにほとんど意味はない。逆に実質的に政策金利を決めている金融市場の今後の予想がどうなっているかと言えば、2020年中に政策金利に変更なしがメインシナリオ、1回の利下げが次点のシナリオということになっている。つまり、今回Fedが何もしなかったのも市場がそれで良いというお墨付きを与えていたからなのである。