■ 甲子園準優勝・おめでとう習志野高校 ■
私の実家の有る習志野市が誇る、市立習志野高校が春の選抜甲子園で準優勝を果たしました。
昭和42年と昭和50年に全国優勝を果たしている古豪です。夏の大会に8回、春の大会には今回を含め4回出場しています。
かつて野球王国と呼ばれた千葉県ですが、習志野高校や銚子商業といった名門公立校が甲子園に出場する機会は少なくなりました。練習環境の整った私立高校の台頭が目覚ましく、公立高校が良い選手を集めるのは難しい時代です。
■ 軍都・習志野が生んだスーパー市立高校 ■
習志野市は千葉県の北西部にある小さな市です。本来ならば平成の自治体合併で千葉市か船橋市に吸収されていてもおかしく無い規模(人口17万人)ですが、昔から両市との仲が悪く、合併のお誘いがありません。
習志野市は司馬遼太郎の『坂の上の雲』でおなじみの陸軍騎兵連隊が置かれていた軍都で、騎兵連隊はその後、鉄道連隊となって大陸での兵站を支えます。
かつての軍都の面影は、今ではJR津田沼駅前に有る千葉工業大学の赤レンガの正門の留めるのみですが、独特の教育理念は昭和40年代までは健在でした。要は「軍隊教育」です。
私が学んだ小学校は体育が盛んな事で全国的にも有名でした。年中、教育研究会が開催され、全国の先生方が見学に訪れていた。特に機械体操には力を入れていて、小学校4年生で運動神経の良い生徒は「バク転」が出来る。鉄棒で「大車輪」は危険なので禁止されていました。
教育方針は軍隊教練そのもので、チャイムが鳴ったら直立不動。少しでも動けば先生のビンタが飛びます。朝礼での「起立、気を付け、礼」のタイミングが揃わない時は、1年から6年まで、全校生徒が何十回とも無く、「起立、気を付け、礼」を繰り替えさせられました。
運動の出来ない子供にとっては「地獄」とも言える環境でしたが、厳しいのは「躾」だけで、実はとても自由闊達な校風でもありました。先生と生徒は仲良しでしたし、様々な事にチャレンジする学校でした。
一方で、隣の小学校は音楽がとても盛んでした。管弦楽部は全国一位の常連校。当然、その卒業生が入学する中学の管弦楽部も全国一位が当たり前で、中学生ながらウィーンへ演奏に行っていました。
そんな「尖がった教育」が行われた習志野市の市立高校が習志野高校です。昭和40年代が黄金時代ですが、サッカー、野球、ボクシング、そして吹奏楽部が全国制覇を成し遂げています。
今でこそ市立高校としては隣の市立船橋高校の方が有名になりましたが、これは習志野に対抗意識を燃やす船橋市が、ライバル心むき出しで「強化」した結果です。
ちなみに、今回の甲子園で監督を務めた小林監督は、習志野高校のピッチャーで甲子園に出場していますが、教員で最初に赴任したのは市立船橋高校。ここの野球部を3年で甲子園に導いた名監督です。
習志野高校の吹奏楽部も超有名で、全国大会の金賞の常連校。「金賞コレクター」の異名も持ちます。(昨年は銀賞)
今年の甲子園の決勝は、ブラスバンドファンには夢の共演でした。東邦のマーチングバンド部が海外遠征中だったので、その穴を大阪桐蔭の吹奏楽部が埋めていたのです。大阪桐蔭の吹奏楽部は日本管楽合奏コンテストで2度の全国一位を獲得している名門中の名門。決勝では、遠征から戻った東邦と大阪桐蔭の混成で、「美爆音」と呼ばれる習志野高校の吹奏楽部に対抗した。
・・・これ、多分、最初で最後の出来事でしょう。球場に居た吹奏楽ファンは至福の時を過ごされた事でしょう。
■ 本当はダーティーな「美爆音」 ■
大編成の大音量で他チームを圧倒する「美爆音」の吹奏楽部ですが、これ、意外にダーティーなんです。ラッパの口をピッチャーに向けて圧倒しろ・・・こんな指導を顧問の先生がやっているそうで・・・。
県大会の初戦などは、相手チームはこの「音」だけで浮足立ってしまいます。守備の連係なども音で乱れます。確か、地方大会では「自粛要請」があったとか・・・・。
尤も、そんな大音量なのに、キレッキレの演奏をするから全国にファンが多い訳で、曲の切り替えのスムースさも相当なものです。
「モンキーターン」や「レッツゴー習志野」など、この演奏を聴きたくて球場に足を運ぶファンも多い。
ネットから星稜戦の映像をお借りしました。
これがオリジナル曲の「レッツゴー習志野」です。
「モンキータン~アフリカンシンフォニー」
ラッパの口がピッチャーマウンドを向いていますね・・・。
良いんです。ブラスバンドの源流は戦争で戦士の士気を高め、敵を恐れさせるものですから。軍都、習志野では、これがスタンダードです!!
■ サイン盗みや、騒音クレーム ■
決して前評判の高く無かった習志野高校ですが、初戦に快勝した後は、格上の高校に対して苦戦続きます。先制点を奪われた後、得意の機動力を生かして、泥臭く足で走る野球で逆転します。ダブルスチールなども決めているのは、流石は名将の小林監督。
一方、2回戦では星稜高校の監督が「サインを盗んだ」と言って、試合後に控室に乗り込むという事件が発生します。2塁走者の挙動が不審だったと。試合中にクレームを付けていたのですが、審判は不正は無しと判断していました。
不正があったのか・・・これは定かではありません。(1999年のルール改定からサイン盗みは禁止されています)。
さらに、この試合の最中に「ブラスバンドの音がウルサイ」と甲子園の近隣住人からクレームが入ります。大会委員は、とりあえず楽器の編成を少なくして対応して欲しいと要請し、習志野高校も受け入れます。試合後に大会規約に音量の項目が無い事を確認した大会委員は、習志野高校に、これまで通りの応援で大丈夫と伝えたそうです。
習志野高校が準決勝に勝利したパワーの源は、「疑惑をプレーで払拭したい」という選手の強い思いが有ったのかも知れません。
■ 公立高校は優勝出来ない? ■
2007年以来の公立高校の優勝かと期待された決勝戦でしたが、結果は東邦の石川党首のワンマンショーとなってしまいました。投げては2塁を踏ませね完封。打っては2本塁打。6-0という一方的な試合結果。試合時間も90分程度と、決勝戦としては、ややつまらない内容となってしまいました。
甲子園で活躍した公立高校として金足農業高校が記憶に新しいと思います。3年生が10人した居ない学校で9人が野球部という環境ですが、超高校生級のピッチャー、吉田投手を擁し決勝に進出しました。しかし、連投の為、決勝戦は大差で敗れます。
「公立高校は甲子園で優勝出来ない」というのは、云わば常識となっています。私立の強豪校は全国から有力選手を集め、万全の練習環境と指導体制を整えます。投手も普通の公立高校のエース級を何人も抱えています。
勝ち進む毎に試合日程が厳しくなるトーナメント戦で、エースを温存出来るチームと、エースを連投させざるを得ないチーム・・・準決勝や決勝になると、その差は歴然です。
「打線は水物」と言われる様に。強打のチームでも打てない時には打てません。そうなると、頼るはやはり投手力となります。
勝負は時に運ですから、公立高校が優勝する事も有ります。しかし、その確率は10回の大会で1回が良い所では無いでしょうか・・・。
尤も、今大会に置いては、東邦の石川投手は準決勝でも完投するなど、これまで結構な投球数で、むしろ習志野の飯塚投手の方が温存されています。やはり、実力の差は大きかったと言う事でしょう。
■ 実は甲子園の実況を観るのって久しぶりなんです ■
知った様な事を沢山書いてしまいましたが、私、スポーツ中継ってほとんど観ません。オリンピックも観ません。箱根駅伝だけが楽しみです。
当然、野球中継なんてほとんど観ない(TV有りませんから)のですが、習志野高校が地方大会で勝ち進むと、応援しますし、時間が有れば球場に足を運びます。あの「美爆音」を「生」で聴きたくて。
私が小学生の時、習志野高校は夏の甲子園で優勝します。7点差を逆転したりと、当時の習志野高校は、とにかくミラクルなチームで、私達のヒーローでした。
野球王国千葉県でも、市立高校の台頭が目立ち、地区大会の決勝大会は市立同士の対決となる事が多くなりましたが、やはり習志野高校や銚子商業といった、かつての黄金時代を築いた学校が準々決勝に勝ち上ると、県内の高校野球ファンが千葉マリンスタジアムに殺到します。当然、球場チケットは早々に売り切れ、球場から入れなかったファンの長蛇の列が駅に向かってトボトボ歩く光景を目にする事が出来ます。
習志野高校には是非、夏の大会にも出場して欲しい。出来れば、県大会で「習志野 VS 銚子商業」なんて夢のカードが実現してほしい。
最後に、優勝した東邦高校の皆さん、おめでとうございます。完璧な試合でした。完敗です。











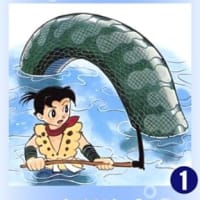
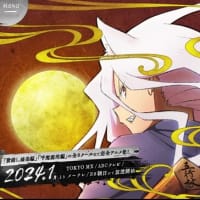







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます