内閣府の防災のページで面白い記事を見付けました。
<引用開始>
我々は子どものころから、台風がきたら何をしなくちゃいけないかというのは、分かっていたんです。この土地はまわりに比べて低いから、「雨が降ったら大変だな」という思いは、自然と体の中にしみついていました。
昔は、農業をしている家は、だいたいが食料の米や麦などを床下に置いていて、どこの家も台風がくるとなったら、そういうものを家の中に移動して、畳はぬれないように柱に立てかける、いわば「畳上げ」をしたものです。そういう準備に必要な角材や丈夫なヒモなどは、私の家にもありました。
けれども、10年ぐらい前に、ここに雨水ポンプ場という排水施設ができてからは、「もう水は上がらないよ」という雰囲気になっていたんです。ところが今回は、「未曾有 ※ の雨」だから、どうにもならなかったんですね。私も、水が出そうかなんて、いっさい気にしていませんでした。ちょっと油断があったのかなと反省しています。
※未曾有(みぞう)とは、昔から今までに、まだ一度もないこと。
<引用終わり>
赤字に大した意味は有りません・・・ただ、内閣府のページなので。。。グフフフって思っただけ。(私自身、誤字王ですから!!)
■ かつて浸水被害は日常的に起きていた ■
今から20年から30年前までは、少しの雨でも中小河川の多くが氾濫していました。東京では神田川や善福寺川は集中豪雨があると、直ぐに氾濫して、床下浸水や床上浸水のニュースが流れた。神田川近くの秋葉原の電気街では台風の前にはシャッターの前に土嚢を積む店舗も有りました(石丸電機とか)。神田川は高田馬場の周辺でも良く溢れていました。
身近な場所でも、大雨になると「水が出る」場所は沢山あった。旧川筋や、かつて沼だった地域は大雨に弱かった。私の通っていた中学も、かつて沼地だった畑の真ん中にあったので、中学1年の時に振った豪雨で冠水して下校出来なくなりました。
この様に、都心部、郊外、田舎に限らず、かつては大雨による浸水被害は日常茶飯事で、台風の時などは1000軒単位で床下、床上浸水などは普通に発生していました。
■ 治水事業で浸水被害は過去のものになった? ■
自治体もこれらの浸水被害に無策だった訳では無く、様々な対策を講じています。
1) 河川改修で川を流れやすくする
2) 護岸工事で護岸を崩れにくくする
3) 貯水池を整備して、短時間に大量の水が川に流れ込まない様にする
4) 排水機場を整備して、低地の排水性を向上させっる
地表をコンクリートで固められた東京では、神田川や善福寺川に多くの雨水が短時間に流れ込んで氾濫を繰り返していました。そこで、東京都は地下に巨大な貯水池を作り、川に流れ込む雨水を調整できるようにしました。
下の写真は善福寺川の地下調整池ですが、公園などの地下に巨大な空間が作られています。この様な地下調整池は宅地化が進んだ地域の学校のグランドの地下などにも有ります。

■ ゼロメートル地帯などでは排水機場が整備された ■
東京では江東区などの下町も洪水被害の多い地域でした。この一帯は地盤沈下によって海面よりも土地が下がっているので、大雨で川に放水出来なくなるのです。排水機場が整備される事によって、ポンプで強制的に低地の雨水を川に放流できる様になり、この地域での浸水被害も過去の話となります。
■ 佐倉一体は洪水地帯だった ■
今回の豪雨で浸水被害のあった千葉県の佐倉市一帯は洪水との戦いの歴史でした。
平安時代までは「内海」だった印旛沼周辺は、渡良瀬川(現利根川)の堆積物で海と隔てられ「印旛沼」となりますが、雨が降ると周辺の雨水は全て沼に流れ込んで来ます。今回氾濫を起こした鹿島川も印旛沼に流入する河川です。
一方、明治時代までは沼から海に流出する河川は有りませんでした。逆に、幕府による利根川東遷によって増水した利根川の水が印旛沼に流入する様になり、印旛沼は調整池になってしまいす。(江戸時代に安食に水門が建設されます)
大雨が降ると印旛沼の周辺の低地の干拓地では農家が水に浸かった。農家も慣れっこだったので、天井裏に小舟を常設していて洪水に備えていまいした。
江戸時代に印旛沼の水を東京湾に流す河川を作る工事が何度か試みられますが、難工事を極め完成には至りませんでした。明治時代になってやっと「花見川(新川)」が東京湾に開通し、大雨の水を印旛沼から排水出来る様になりました。
印旛沼周辺の干拓地には多くの排水機場と、沼をグルリと囲んで排水用の水路が整備され、最近では洪水は過去の話になりました。しかし、私が高校生に成る頃までは、鹿島川は大雨で度々浸水被害を起こす川でした。しかし、それもここ20年程は記憶に有りません。
■ 限界を超える雨が降ると、「水が出る」地域から浸水する ■
過去の話の様になった「浸水被害」ですが、台風19号や、21号の様な記録的な豪雨に見舞われると、貯水池や排水機場の能力が限界に達して浸水被害が発生します。
二子玉川では土手の整備されていない場所(明治時代に川岸に料亭が立ち並び、堤防工事に反対した為、土手が住宅地の背部にあるので、この地域は正確には「河川敷」)で浸水が発生しましたが、地元では水害で有名な地帯だった。
この様に、かつて「水が出る」とされる地域では、治水設備の限界を超える雨が降れば、当然浸水被害が発生します。
実は私の家の前の市道も、以前、台風の大雨で冠水した事が在ります。この様な場所では、マンションの立体駐車場の地下部分は、排水が出来なくなるので、車が水没する恐れが有り、注意が必要です。さらに、マンションの地下に受電設備やポンプ設備が有る場合も、これらが浸水被害を受ける可能性が有ります。
■ 急激な都市化によって新しく起こる災害 ■
タワーマンションが林立する武蔵小杉でも浸水被害が発生していますが、急激な都市化が引き起こした災害と言えます。
武蔵小杉の浸水は多摩川の水が下水を逆流した「逆流氾濫」です。河川の周辺は「後背湿地」で、昔は大雨が降ると川から溢れた水が一体を覆った地域です。ですから増水した川の水位よりも土地が低い。こんな場所は全国の低地の平野部はほとんどです。ですから、河川が増水した時は、河川への下水の流入ゲートを閉じて逆流を防ぎ、ポンプによって排水をします。
ただ、明らかに増水による逆流が懸念される地域以外は、ポンプの排水施設を備えていない場所も多い。川崎市では多摩川河口近くの川崎区や、幸区、そして武蔵小杉の有る中原区の一部もポンプ排水のエリアでしたが、土地が若干高い武蔵小杉には下水道にポンプ排水設備が無かった様です。

一方で急激な都市化で下水道への生活排水や汚水の流入量は増え、雨水も地中にしみ込む事無く排水溝に集まって来ます。武蔵小杉の駅から南側の地域では、古い下水設備を使用していて、下水と雨水を同じ下水管で流す「合流式」。下水道の多摩川へのゲートを安易に閉鎖すると大雨によって下水が溢れる「内水氾濫」が発生する可能性が高い。そこで、ゲートの閉鎖を躊躇った結果、急激な多摩川の増水によって、多摩川の水が下水を伝わって逆流したと見られています。
ただ、ゲートを閉じた所で、大雨による雨水は行き場を無くして、結局は下水は溢れたと思われます。武蔵小杉一体はかつて沼だったと言われ、周囲より低くなっているので、ゲート閉鎖で逃げ場を失った下水は、やはりこの一帯で「内水氾濫」を起こたハズです。
以前は田圃を埋め立てたり、ゆるい丘陵地帯を急激に宅地開発するなど、未計画な都市化によって保水力が失われ、それらの地域の低地で浸水被害が多発しました。現在では調整池が整備され、ポンプ設備なども作られて、これらの地域の浸水被害は随分少なくなりましたが、やはり予想を超える降雨量には注意が必要です。
■ 災害に強くなって、災害を忘れた日本人 ■
台風15号で房総の被災地で高齢者達が口々に語っていたのは「油断していたよ」という言葉です。房総地域は台風の通り道ですが、近年、大きな台風は房総半島を避ける様な進路が多かった。
今回の千葉県の豪雨被害でも、「やっぱ水が出る所に住むべきじゃないね」と、昔なら当たり前だった事が改めて意識されたと人々が言い合っていました。
高校時代の教師の話では、四国では台風を前に、窓に板を打ち付けたり、天戸の裏に竹の棒を通す準備をしたと言います。
冒頭の内閣府の記事ではありませんが、水の出る地域では「畳み上げ」は台風の風物詩さったでしょう。
しかし、現在は二重サッシの実家のマンションでは、台風19号の強い南風の音も、ほとんど気付かなかったと母が語っていました。(1重サッシの我が家では、いつ窓が割れるかと寝る事が出来ませんでしたが・・・)
この様に、治水設備が整い、住宅の性能が上る事で、私達は「災害」を意識しなくなりました。畳上げが出来るのは畳の上に物が無いからで、現在の老人の住宅は家具や物に溢れていますから、いざ畳を上げように上げる事が出来ません。
昔は、座敷には物は置かず、板敷きに納戸(なんど)に功利などの少量の衣類や道具が収納されていました。この様な生活をしていれば「畳み上げ」も「功利の移動」も簡単に行えます。板敷きならば、浸水しても水が引いたら雑巾掛けでキレイになります。
今回の様な記録的な豪雨は、そう何度も起きる事では無いので、それに備える事にどれ程の意味があるのか、経済的には微妙ではありますが、イザという時の心構えは、日頃から怠らない様にしたいものです。少なくとも、避難指示が出た時に、防災グッズと貴重品だけは、直ぐに持ち出せる準備は必要なのかも知れません。











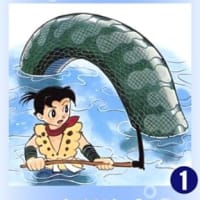
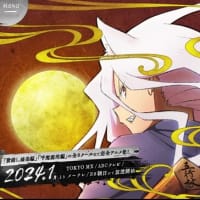







東京では大した被害が起きないで、千葉や福島で大災害が何度も続けて起きるというのは
上級国民が沢山住む東京で災害が起きると困るから、防災に金をかける
下級国民しか住んでいない千葉や福島はどうなってもかまわないから防災に金を出さない
という事なのですね。
日本人が上級国民と下級国民とにはっきり階級分化したのが根本的な原因ですね。
[2019.10.28放送]週刊クライテリオン 藤井聡のあるがままラジオ(KBS京都ラジオ) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=-X-9-fmHoRU
今週のテーマは『台風19号災害、それは予算削減が導いた人災である』です。
まあ、日本の地方が壊滅したらマンサントが農地をタダ同然で買い占めて、中国人移民を時給100円で農作業させれば、日本農業復活ですね。
もう日本以外では遺伝子組み換え農産物は作れなくなっているので、日本農業の一人勝ちですね:
韓国のスーパーでもオーガニックコーナーができ、オルゴク小学校(清州市・500人)では、有機・無償で学校給食を提供している。パンやサンドイッチは輸入小麦に頼らざるを得ないのではないかと思ったが、パンやパスタは一切使わず、うどんは全部国産の小麦粉だという。日本の大手3社の小麦粉を調べてみると、グリホサートがたくさん含まれている。もっとも入っているのが日清製粉の「全粒粉強力粉」だ。オルゴク小学校はアレルギーの子どもが七人しかいなかった。
韓国の農水省の課長に全国の状況を聞くと、ほぼ小・中学校は有機・無償でやっており、高校はもう少しかかるということだった。保育園・幼稚園でも始め、何年か後には妊婦にも有機の物を食べさせたいと思っているという話だった。
韓国も台湾も、食の安全に対する取り組みを始めている。日本は農薬や食品添加物の基準でいうと台湾の400倍も緩い。小麦粉のグリホサート残留農薬基準は中国の150倍緩い。そして世界各国がグリホサート、ラウンドアップを規制しようとしているなかで、こともあろうに日本だけがグリホサートの残留農薬基準を、物によっては400倍にまで緩めた。そば粉やナタネなどは75倍、100倍、テンサイは75倍だ。今、世界で一番農薬の残留基準が緩いのが日本だ。
ロシアも2016年に遺伝子組み換え農産物はつくらせない、輸入させないという法律を上院下院で通した。中国も2017年から同じように輸入も国内栽培も禁止している。いずれも国を挙げて有機栽培に力を入れている。アメリカも、じつは遺伝子組み換え農産物は2016年から頭打ちで、今オーガニックの生産がなんと年に10%の割合で伸びている。
上級下級はともかくとして、首都機能を持ち金融センターの一つである東京が防災上優先されるのは当然ですよね。
中小河川の氾濫の問題は管理が自治体なので財政力の差が影響しますし、費用対効果としても高い訳では無いので後回しにされやすい。
問題は大河川の堤防の決壊で、土を積み上げただけの堤防は越水が起きると堤防の外側が落水によって削られて決壊に繋がる。ここを補強する方が、緊急放流で洪水被害を拡大するダム建造よりも防災効果が高いのですが....堤防は長いので難しい問題です。
スーパー堤防計画は用地買収の問題から頓挫していますが、完璧で無くても今よりマシな堤防はスーパー堤防の予算が有れば、もっと安価に構築可能です。
ここら辺が土木行政の不思議な所ですが、定期的に台風で被災して工事が発生する事で地元の土建業者は生き延びているとも言え....政治的な問題なのかも知れません。
因みに政界では台風は票に繋がらないと言われているみたいです。毎年襲って来て、ニュース性に乏しいので政治的な得点に繋がり難いらしい。嘘か本当かはわかりませんが。
食品に関しては所得格差が如実に反映されますよね。アメリカでは20年以上前からオーガニックスーパーが有り、そこの商品は高かった。一方で一般のスーパーは安いけど、牛乳も食パンも酷い味がした。
日本も二極化で健康や長寿はお金で買う時代になりました。
遺伝子組み換えにはヒステリックな日本人も残留農薬には無頓着です。単位面積当たりの農薬使用量は日本と韓国が他国えお群を抜いて高い。これは消費者が綺麗な野菜しか買わない為です。
遺伝子組み換え時代には大した問題は無く、耐除草剤性が高まる事で使用量が増えるグリサポートなどの残留農薬に問題が有ります。日本のホームセンターに行けば大きなボトル入りで売られており、農家が畑の畦道などにジャンジャン撒いています。流石に畑に撒くと遺伝子組み換えでない作物も一緒に枯れてしまうので撒きませんが。
こうしてグリサポートが乱用されると耐性を持ったスーパー雑草が生まれる悪循環が繰り返されます。最近はグリサポートと枯葉剤に耐性持つ遺伝子組み換えさくもつの特許がデュポンから提出されていたと記憶しています。
まあ、長生きしても年金が貰えないかも知れない私たちは、安い食品を食べて早死にするのも人生の選択肢の一つなのかも知れません。
誤) グリサポート
正) グリホサート
「もう堤防には頼れない。 国頼みの防災から転換を」(日本経済新聞 久保田啓介編集委員)
首都を含む多くの都県に「特別警報」が発令され、身近な河川が氾濫する事態を「自分の身に起きうること」と予期していた市民は、どれほどいただろうか。近年、頻発する災害は行政が主導してきた防災対策の限界を示し、市民や企業に発想の転換を迫っている。
2011年の東日本大震災は津波で多数の死傷者を出し、防潮堤などハードに頼る対策の限界を見せつけた。これを教訓に国や自治体は、注意報や警報を迅速に出して住民の命を守る「ソフト防災」を強めた。しかし18年の西日本豪雨でその限界も露呈した。気象庁は「命を守る行動を」と呼び掛けたが、逃げ遅れる住民が多かった。
堤防の増強が議論になるだろうが、公共工事の安易な積み増しは慎むべきだ。台風の強大化や豪雨の頻発は地球温暖化との関連が疑われ、堤防をかさ上げしても水害を防げる保証はない。人口減少が続くなか、費用対効果の面でも疑問が多い。
健康保険と年金は廃止
生活保護費減額
医療費・教育費補助廃止
防災費用減額
をしないと国家破綻するんですね。
時給100円で働く中国人移民からは所得税は取れないから消費税も30%まで増額するしかないですね
中国人移民はチャイナタウンに住んで日本語ではなく中国語を使うので、義務教育も小学校までにしないといけないでしょう。
安倍先生も移民対策は色々考えているみたいですね:
『安倍首相 病院再編と過剰なベッド数の削減など指示
高齢化を踏まえた将来の医療体制をめぐり、安倍総理大臣は、経済財政諮問会議で、持続可能な地域医療体制を構築するため、都道府県ごとに策定された構想に基づいて、病院の再編とともに、過剰なベッド数の削減などを進めるよう関係閣僚に指示しました。
総理大臣官邸で開かれた、28日の経済財政諮問会議は社会保障制度改革が議題となり、民間議員は、都道府県ごとに作成され、2025年までに目指すべき医療体制の将来像を示した「地域医療構想」について、「実現に向けた進捗が十分ではない」と指摘しました。
そのうえで、厚生労働省が公立 公的病院の再編、統合をめぐり、診療実績が特に少ないなどの全国400余りの病院名を公表したことを踏まえ、「病院や過剰なベッドの再編は、公立公的病院を手始めに、官民ともに着実に進めるべきだ」などと提言しました。
“独立”する富裕層 - NHK クローズアップ現代 2014年4月22日(火)放送
100万ドル以上の資産を持つアメリカの富裕層。
その富裕層が今、自治体の在り方を変えようとしています。
富裕層は税金が貧困層のためばかりに使われていると反発。
みずからが住む地区を周囲と切り離し、新たな自治体を作る動きを強めています。
富裕層が作る自治体 衝撃の運営手法とは
富裕層の動きを後押ししているのが、同じジョージア州で大きな成功を収めた市の存在です。
州の北部にある人口9万4,000人のサンディ・スプリングス市です。
市民の平均年収は1,000万円近く。
医師や弁護士、会社経営者などが多く住む高級住宅地です。
住民グループ代表 オリバー・ポーターさん
「政府による所得の再分配には反対です。
人のお金を盗む行為だと思います。」
ジョージア州で50年ぶりに新たな市として誕生した、サンディ・スプリングス。
州の法律によってさまざまな財源が与えられました。
市民が支払う固定資産税の15%。
売上税の一部。
そして酒税や事業の登録料など、市の去年(2013年)の収入は、日本円にしておよそ90億円。
州で1、2を争う豊かな自治体が誕生したのです。
さらに富裕層は、市の運営にビジネスのノウハウを取り入れました。
警察と消防を除く、すべての業務を民間に委託。
同じ規模の市なら数百人は必要な職員の数を9人に抑え、徹底的なコストカットを進めました。
市民課や税務課。
道路や公園などを造る建設課。
さらに、市の裁判所の業務まで民間に委託しました。
裁判長は必要なときだけ時給100ドルで短期雇用します。
この結果、当初年間5,500万ドルと試算された市の運営費を、半分以下に抑えることに成功したのです。
下級国民を甘やかしたらかえって彼らの為にならない。
佐藤 いったいこの世の中に「理想の税」というのは存在しているのか、あるいはこうすればより「理想に近い税のあり方」になるはずだというのがあるのなら、最終的にはその辺までさらにお聞きしたいなと思っているんですけど。
竹中 私は人頭税というのが理想の税だと思うんですね。
佐藤 人頭税?
竹中 そうです。佐藤さんにも、私にも、皆同じ金額をかけるんです。国民一人ひとりの頭数にかけるわけですから、これほど簡単なものはないですね。(後略)
佐藤 国っていうのは正当化されたヤクザと言ってもいいんじゃないですか。
竹中 おっしゃる通りです。税金というのは結局ヤクザのみかじめ料みたいなものです。国は強制的にお金をとるのに大義名分や理屈を並べたてるけど、ヤクザはいちいちそんなことは言わない。みかじめ料と税金の差は、それくらいのものでしょう。
竹中 ・・・やはり多くの人は税による所得の「再分配効果」というのを期待するわけです。再分配効果というのは、たとえばこういうことです。佐藤さんはすごく所得が多いとする。こちらのAさんは所得が少ない。そうすると、Aさんは
佐藤さんからお金を分けてもらいたいわけです。佐藤さんが儲けたお金の一部を自分ももらいたいんですよ。もらいたいときに、政府を通してもらうんですよ。
佐藤 でも、それ、もらいたいって、ずるいじゃないですか。
竹中 ずるいですよ、すごく。『フェアプレーの経済学』という本にもはっきりと書かれているんです。著者はランズバーグという数学者なんですけど、すごくシンプルに見ていくと、今の税はおかしいと言うのです。彼はそれをこんなふうに表現しています。
子供たちが砂場で遊んでいるんです。ある子はオモチャをたくさんもっている。その子はお金持ちの家の子なんですよ。もう一人の子は家が貧しいからオモチャを一個しかもってないんです。しかし、だからといって、自分の子に向かって「○○ちゃん、あの子はオモチャたくさんもっているからとってきなさい・・・・・」などと言う親がいるかというわけです。
ところがそんなことが、国の中では税というかたちで実際に行われているという言い方をしているんですね。これは、みんなのやる気をなくさせる原因になります