
「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」 12巻 ガガガ文庫 より
■ ビルディングスロマーン(教養小説) ■
「ビルドゥングスロマーン」という言葉をご存じでしょうか?日本語では「教養小説」というロマンの欠片も感じられない小説ジャンルです。語源はドイツ語のBildungsromanで「自己形成小説」と訳される事もあります。
ドイツの市民社会の形成期にギリシャ哲学の影響を受けて人間形成(パイデイア)の概念が広がり、絶えず自己形成を意識した小説、例えばゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター』などが生まれます。
何だか、一時期流行した自己啓発セミナーのテキストの様ですが、一言でいえば「少年が様々な経験を経て立派な大人になりました。おしまい。」といったジャンルの小説です。
代表的な作品にヘッセの『デミアン』などがありますが、私は大学の一般教養の授業ではヘッセの『車輪の下』や、ジョイスの『若き芸術家の肖像』なども、広義のこのジャンルに含まれると教わった記憶が在ります。
でも、『車輪の下』の主人公は成長半ばにビール飲んで川に流されて死んでしまいますし、『若き芸術家の肖像』は「ウシモウモウは・・・」から始まって意味不明だし・・・「自己形成」とはかくも難しいものなのかと・・・そんな感想しか持ちえませんでした。
日本においては山本有三の『路傍の石』が『車輪の下』に近い作品かなと思いますが、なんとこの作品、主人公の成長半ばで「筆を折る」と、イキナリ打ち切りされちゃってる不人気アニメの様な作品です。
この様に私は「ビルドゥングスロマーン」的な小説にあまり良い印象を持っていませんが、それは私が50才を過ぎてもラノベやアニメを嗜好するという、成長や自己形成を否定した存在である事に起因しているに違いありません。
■ 「ビルドゥングスロマーン」はアニメやラノベの中に生きている ■
「ビルドゥングスロマーン」を単純に「少年少女が成長する物語」と解釈するならば、多くのアニメやラノベはこのジャンルに含まれます。
『機動戦士ガンダム』の主人公アムロ少年は、ブライト艦長に殴られ、ランバ・ラルに導かれ、ハモンさんやセイラさんにおだてられ、マチルダさんに発情・・いえ憧れて、立派なニュータイプになります。これは「自己形成」の物語です。
『ワンピース』も航海を通してルフィーが成長する物語です。彼は結構伸びてますよね・・ゴムだけに。
ロボットや超能力が存在しない普通の世界でも、『とらドラ』などは主人公の男女の成長を描く傑作です。(小説もアニメも)
この様に、読者や視聴者が少年少女に限定?されたジャンルの作品には、「ビルドゥングスロマーン」的なテーマを持った作品が今も量産されています。これをゲーテが知ったら喜ぶのか、悲しむのか・・・。
■ 「大人の存在する世界」でこそ子供達は成長する ■
ラノベやアニメの「ビルドゥングスロマーン」的な作品には、ある特徴が在ります。それは少年少女達を導く「大人」の存在がしっかりと描かれている事。
『とらドラ』は少し面白くて、大人は「駄目な存在」として描かれています。竜司の母親の泰子はキャバクラ勤めのシングルマザーで昼間は寝ています。家事全般もダメダメで高校生の竜司がかいがいしく母親の世話をしています。大河の父親に至っては「クズ」とも言える性格で、娘より愛人を優先する・・・。担任の先生も未婚三十路の頼りない教師。それでも、大人達は様々な問題を抱えながらも必死に子供を育て、その成長を見つめています。結局は竜司も大河も一度は家族の関係を断ち切りながらも、その絆によって救済され、しっかりと成長します。
一方、親や教師が出て来ない作品の主人公達は「永遠の学生生活」や「永遠の休日」の中に閉じ込められていて成長しない場合が多い。
『魔法少女☆まどかマギカ』は大人はほとんど出て来ません。彼女達は苦難のループの中の閉じ込められていますが、それは、苦悩する若者を導き救済する大人の不在によって起こる事象と捉える事も出来ます。まどかの導き出した答えも、子供の世界での究極の選択肢で、彼女は「成長」せずに「人間性を放棄」する事に解決を求めています。もし大人の助言が有れば自己犠牲とは別の答えが得られたかも知れない・・・。
だから、私はラノベやアニメの「良い作品」の条件に「良い大人の存在」を真っ先に挙げたい。
■ 「人間関係の成長」に主眼を置いた『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』 ■
<ここからネタバレ全開。要注意>
「少年少女の成長譚」として私が現在一番注目している作品は渡航の『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』です。(長いので以下『俺ガイル』とします)
高校生活初日に交通事故に遭い、2か月入院した比企谷 八幡(ひきがや はちまん)は高校2年にもなって「ボッチ」。彼は極端に自意識過剰な上に、ヒネクレタ性格の持ち主。さらに同年代の男子に比べ少し大人びた所があるので、周囲を上手く付き合う事が出来ません。
生物の授業のレポートで「熊は群れる事が無い。出来る事なら私は熊になりたい」と提出しては怒られ、職場見学先として「自宅を希望する、なぜなら俺は専業主夫を目出しているからだ」と言って怒られる・・・そんな高校二年生。
そんな彼が「更生」の為に強制的に入部させられたのが「奉仕部」という部活。生徒達のお悩み解決を活動内容とする部活です。奉仕部には先に一人の部員が居ます。雪ノ下 雪乃(ゆきのした ゆきの)は同じ学年の国際教養化の生徒ですが、頭脳明晰、容姿端麗・・・でも彼女も人とのコミュニケーションが上手く出来ません。だから奉仕部に入れられた。
ガランとした部室で二人きりにされた比企谷は、交わされたトゲトゲしい会話の中で、雪ノ下に自分と同質の物を感じ取ります。彼はつい「俺と・・・(友達にならないか)」と言いかけますが、「俺と・・」だけ言った所で「それは無理」と拒絶されます。後には彼の人間性を根本的に否定する罵詈雑言が続くのですが・・・実はこの「無理」には深い意味が隠されています。
そんあ奉仕部に最初の依頼を持ち込んだのは、比企谷のクラスメイトの由比ヶ浜 結衣(ゆいがはま ゆい)。彼女は上手なクッキーの焼き方を教えて欲しいと依頼する。何度教えても焦げ焦げの練炭みたいなクッキーしか出来ないダメっぷりですが、厳しく教える雪の下に彼女を羨望の眼差しを向けます。「人と合わせようとしないなんてスゴイ。私なんてこんな八方美人の性格だから・・」と。
実は由比ヶ浜がクッキーをあげたい相手は比企谷。クラスでもほとんど会話した事が無く、彼をヒッキーと呼ぶ彼女でしたが、比企谷が交通事故に遭ったのは由比ガ浜の飼い犬を助ける為だったのです。それ以来、比企谷は彼女にとって恩人であり、気になる存在。だから彼女は学校での彼の行動をそこはかとなく観察しており、彼が実は繊細で良い人だという事も密かに知っています。
比企谷に近づく意図を秘めながら、由比ガ浜も奉仕部に加わって、女性2人と男一人の不思議な部活動が始まります。
生徒達の取るに足らない依頼を引き受ける奉仕部ですが、比企谷の出すアイデアはどれも「酷い」。彼のやり方は卑怯で卑屈で・・・そして自己犠牲の上に成り立っています。今さら友達受けなんて必要としない彼は、自分が悪役を引き受ける事で事件を解決して行きます。
しかし、それに気付いた依頼主達は、一部は彼の熱烈なファンとなり、一部は消極的ながらも彼の存在を認める事になります。そして、そんなやり方しか出来ない比企谷を見守る奉仕部の二人は、ひそかに心を痛めるのです。
雪ノ下には秘密が在ります・・。高校初日に比企谷を轢いた車には雪ノ下が乗っていたのです。「俺と・・(友達になろう)」という誘いを即座に「無理」と切り捨てた理由は、彼の楽しい高校生活を奪ったという自責の念。
それでも、自分と同質の物を持ち、人間関係に諦めを抱きながらも強い羨望も持ち続ける比企谷にう雪ノ下は無自覚の内に惹かれて行きます。それを複雑な思いで由比ガ浜は見つめています。彼女は一見バカですが、人の心の機微に敏感で、本人も気付かない気持ちを察知する能力に長けている。そして本能的に何が正しいのかを見抜く事が出来る。
自分が何者で何を望むのか理解していない比企谷と雪ノ下、彼らが何を望み、自分が何を望むのか・・・そしてそれが両立しない事を理解する由比ガ浜。3人の簡潔は、様々な事件を通じて密接になり、お互いがお互いを大切にしながらも、そこから先に進む事に臆病な関係。
そう、『俺ガイル』の面白い所は、俺や私といった個人の成長より、俺たち、私たちの「人間関係の成長」に主眼を置いた点にあります。これに、家族やクラスメイトや生徒会会長が絡んで、様々な人間関係が生まれますが、作品全般を通して、これらの関係も変化し成長し続けます。
■ ラノベのフォーマットを利用した「ビルドゥングスロマーン」の傑作 ■
作者の渡航は就職活動に失敗するのではとの恐れからラノベを書き始めたと言いますから、この世界では遅咲きの作家と言えます。(中学生、高校生からデビューする作家も多い)
逆にデビュー当時から「大人の視点」を持った作者だとも言えます。比企谷は同年代の男子生徒よりも醒めて世間を見ています。これは社会人になる年頃の男子が昔の自分の「黒歴史」を思い返して作られたキャラクターと言えます。私はアニメの1話目を見た瞬間、高校時代の自分を発見して驚きました・・・。当時、私は周囲から浮いていましたから・・・。
『俺ガイル』は高校生活の様々な出来事を、ラノベならではの軽快でカラフルな調子で物語っていますが、その内容はかなり重たい。人と人の関係性や繋がりを、辛い所まで突き詰めて、一歩一歩苦悩の前進を続ける物語です。
ただ、この物語を普通の小説で発表しても、それは擦り切れたジャンルでしかありません。恩田陸の様な名手ならば、素晴らしい「小説」にする事も出来ますが、普通の書き手では難しい。そこで作者はラノベを偽装して、「普遍的な高校生の成長譚」を読者の中学生や高校生に届けようとしています。そしてそれは見事に成功し、多くの読者の共感を獲得して累計で700万部の売り上げを達成します。
一般の小説は4万部でヒット作と言われるので、ラノベが如何に出版社にとって「ドル箱」で、さらにラノベ作家が「稼ぎまきっている」かが分かります。
有能な書き手の多くが、桜庭一樹や有川浩の様に、ラノベ作家から一般作家に転向する中で、一部の作家は戦略的に「ラノベ作家であり続ける」選択をする時代なのです。西尾維新などが典型的な例でしょう。
ただ、ラノベ作家であり続ける事は意外に難しく、「大人になっても子供の心を失わない」というのは意外に難しい。ラノベ独特のキラキラした世界感や、ドキドキした高揚感は、心がすり減った大人では書けないのです。
その点、『俺ガイル』の比企谷君は、最初からネガティブ全開ですから、作者が就職して社畜として生きる今も、ブレる事無くネガティブを吐き出し続けます。
12巻で奉仕部の3人は前進する事を選択します。しかし、それは彼ら、彼女らにとって明るい未来を約束するものでは無い様です。何故なら、それは互いの関係性に結論を出すと言う事だから。
彼らを助けるが顧問の平塚先生ならば、敵として彼らの成長を促すのは雪ノ下の姉。12巻で姉は彼ら3人の関係を「共依存」と看過します。比企谷が雪ノ下を助けるのは「自己満足」の為なのだと。この一筋縄では行かない姉の存在も、「成長を促す大人」として見事に機能しています。
やなり「素晴らしい作品」には「良い大人」は不可欠なのです。
本日は50才を過ぎたオヤジが、ラノベを熱く語ってみました。
追記
人力さんは雪ノ下派か、由比ガ浜派か聞かれる前に答えます。私は川なんとかさん派・・・ウソ。いろはす、最高。
追記2
最近、『サクラダリセット』を読んでいるので、久しぶりにラノベらしいラノベを読みました。読み始めは「あれ、50才になるとラノベって結構キツイな」と思ったりしましたが、読み進めるうちにあれよあれよとページは進み、数時間で読み終わりました。「読みやすい仕掛けがイッパイ」というのも中高生に読ませる為の重要な要素です。だから売れる。











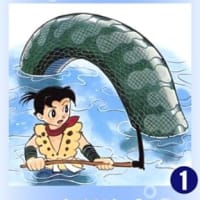
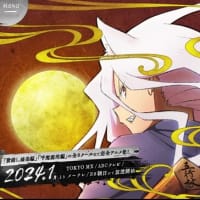







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます