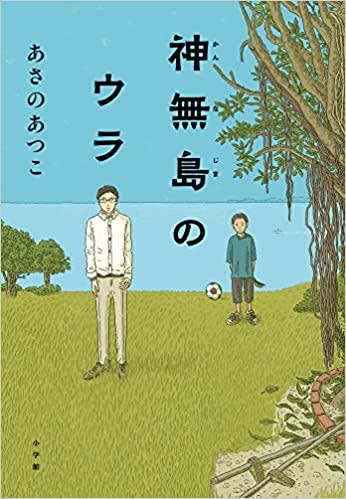
帯には令和の『二十四の瞳』なんて書いてあるから離島での教師と子どもたちとの触れ合いを描く「感動もの」かとたかを括って読み始めたが、これはそんな甘いものではなかった。ラストまで極度の緊張感が持続する。だから一瞬も気が抜けない。これは『バッテリー』を凌ぐあさのあつこの最高傑作ではないか。
20年振りに島に戻ってきた男が主人公だ。島の学校の臨時教師として。彼はこの島で生まれ12歳まで育った。父の死後、島を離れてからは一度も戻ってない。ここには忌まわしい思い出しかないようだ。だがその謎は最後まで明かされない。神無島は鹿児島港からフェリーで12時間。在籍生徒数12名のこの離島の小、中学校に赴任する。
こんなに集中して小説を読んだのは久しぶりのことだ。描かれることがまるで自分のことのように思えた。親との確執。子どもたちへの思い。ここに描かれるものすべてが人ごとではなかった。もちろん自分のことではない。ないけど、すべて心あたりのあることばかりで、身につまされる。描かれる生徒との関わりはあの頃の僕が体験したいくつもの事例、出来事と呼応する。自分の無力を実感したこと、愚かなまでもの自信満々な対応、若かった頃、疲れきっていた頃、時間は前後するが、そんなあらゆることが鮮明に蘇ってくる。だからこれは人ごとではないのだ。
まだ若い(30台になったばかり)主人公の深津が、ここで出会った子どもたちの過酷な現状。それをなぜか一歩引いて見守る視線の謎。彼は熱血教師なんかではない。単純ではない彼の思い。目の前の子どもたちと向き合いながら、徐々に核心に向かっていく展開。やがて神さまの問題になり、ラストはまさかの横溝正史かと思わせるような展開まである。しかも、それがこんなにもリアルで胸に迫る話なのには驚く。島の子どもたちを守るウラという神の存在がお話の前面に出てくる。でもこれはスピリチュアルな話ではない。ここには切なる祈りが描かれる。子供とともに親からの虐待と向き合う。本来なら守るべき肉親である大人たちから受ける痛み。追い詰められた子どもたちの最後の砦になるのは学校なのか。ひとりの無力な教師に何ができるのか。
先日読んだ『キッズ・アー・オールライト』に続いて、これもまた追い詰められた子どもたちと向き合う大人たちの物語だ。学校現場が抱える様々な問題を描くのではない。ただただ救いを求めるだけの子供たちの苦しむ姿を見つめる。手を差し伸べることはできるのか、と問いかける。

























