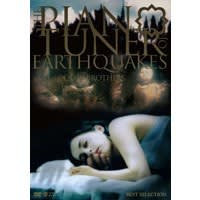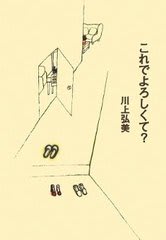この2本立はなんだかかなりお得感がある。25分と、40分なので1本の芝居を見るより短いくらいなのだが、満足度は高いのではないか。どちらも面白いのだが、これを2本並べた時、とても豪華な気分にさせられる。それぞれ方向性は異なる2作品を同時に見れて、しかも、満腹感を得られるなんて、贅沢だ。
『クーラー』のバカバカしさは、そのへんてこな身体表現と、無意味に繰り返されるセリフのやり取りのくだらなさの見 . . . 本文を読む
先週はたくさんのDVDを見た。それぞれ書きたいことがたくさんあるが、時間もないので、簡単にここに列記したい。
まず、ガルシア・マルケスの映画化である『コレラの時代の愛』。これはちょっとがっかりだった。2時間17分に及ぶ大作だが、この題材では仕方あるまい。これでもまだ短いくらいだ。きちんとディテールを描かなくては面白くはならない。ストーリーを描くだけでいっぱいいっぱいになっている。表層的なスト . . . 本文を読む
前回この作品を見たときは、もっとシンプルなセットだったような印象がある。今回はきちんと作り込んだのか、なんて思ったのだが、終演後アイホールの館長である山口さんと話していたら、そうでもないよ、前回もこんな感じ、って言われ、そうだったんだぁ、と思った。
作品の印象がシンプルだから美術もそうだと思いこんでいただけなのかも知れない。まぁ別にそんなことはどうでもいいような事なのだが、青年団のリアルな . . . 本文を読む
白いスーツにブルーのネクタイをしたブッダが悪の化身である新興宗教の教祖と戦うSFロマン。なんとその教祖のバックには悪魔がついていて彼を操っていたとは。トホホ。
あほらしくて見ていられないような映画だが、「幸福の科学」制作の作品だから大丈夫。これがもし普通に映画なら、信じられないことだ。とは言え、一応これでプロパガンダを目指しているのだとしたらそれはそれで凄いことだ。お子様ランチでももう少し歯 . . . 本文を読む
演劇についての演劇だ。演劇と世界ではなく、演劇×世界というスタンス。この世界は演劇を愛している。これは演劇というものへのオマージュではなく、演劇というシステムが世界を形作り、世界が演劇を必要とするということを描く。
いくつもの戯曲を引用していきながら、それがひとつのドラマを作るのではなく、演劇という世界を作りあげていくようになるのだ。舞台上で役者たちは役者という自分を演じている。この劇場の舞 . . . 本文を読む
森見ワールドはすべての作品がひとつにつながっている。しかもこの京都という世界で起こる出来事は、ほかの世界とは隔絶している。今回の短編連作でもそれは同じだ。『夜は短し歩けよ乙女』からこっちずっと同じ小説を読んでいる気がする。
この作品の中でも、ちゃんと各エピソードが、完全につながっている。祇園祭の宵山の日の幻想世界をコメディーと背中合わせで描いていくバカバカしいとしか言いようのない乙川による大 . . . 本文を読む
30年の歳月を経て振り返るあの夏の日々。少年時代の夢。とても感傷的で自己陶酔的なお芝居だ。それを真正直に描いてくれる。この直球勝負は見ていて気恥ずかしい。だけど、吉野さんは照れることなく、この単純な物語を思い切って見せる。それはそれで潔い。
実は見ていて何度も、話をもう少し整理したらいいのにと思った。改訂版として上演しているはずなのに、5年前の初演の時と変わらない恥ずかしさがここにはある。そ . . . 本文を読む
『死霊のはらわた』を初めて見たときの衝撃は生涯忘れることは出来ないだろう。あの1作で僕はホラー映画の虜になった。サム・ライミである。
スプラッターというおバカなジャンルを作ったのは彼だ。笑えるホラーなんていったい誰が考えたりしようか。ありえない。だが、そんなありえないことを彼は成し遂げてその後の歴史を作った。
僕の生涯ホラーベスト3は、中3の時の見た『エクソシスト』、高校の時見た『悪魔のい . . . 本文を読む
先週、富田林のスバルホールでコンクールの7作品を見てきた。もう今週の土日に府大会があり、結果は出たことだろうが、この地区の代表作品はどんな評価をえたのだろうか。気になる。
大阪南部の高校演劇部の芝居を見るのは初めてのことで、楽しみにしていたのだが、想像以上にレベルも高くて充実した1日を過ごすことが出来た。審査員として選考に携わった。審査に関わるのは3回目だが、今回は演劇関係者として呼ばれたの . . . 本文を読む
『ストリート・オブ・クロコダイル』を初めて見た時から、彼らの人形アニメの虜になった。なんだかよくわからないのだが、ビジュアルの美しさと耽美的なその世界に魅せられる。だからついつい新作が来る度に見てしまう。今回は2作目の実写作品。しかもテリー・ギリアムを製作総指揮に迎えてのブラザーズ・クエイの長編劇映画最新作だ。
今回もまたなんだかよくわからないまま、スクリーンに釘付けにされる。アニメのシーン . . . 本文を読む
肩の力が抜けたようなゆるゆる感がいい。こんなにも軽くて、さりげない小説を川上弘美さんが書くんだ、って感心した。そりゃ彼女の小説はあっさりしたものもなくはない。でもここまであたりさわりのないものって他にはないはずだ。だいたいいつもならもっと「なんか」がある。腹に一物もつような、そんなものが彼女の作品の特徴だ。もちろん、だからといって、これがつまらないというわけではない。それどころか、これがまた、な . . . 本文を読む
ケラリーノ・サンドロビッチの描く世界はいびつで、それをブラックユーモアと呼ぶには、いささか品がよろしくない。つまらない訳ではない。淡々とあきれたドラマを見せられただ呆然と見守ることとなる。だが、だんだん疲れてくる。あまりにくだらないから、どうでもよくなるのだ。出しっぱなしにしたエピソードを忘れた頃にもう一度引っ張り出してきて見せる。そう言えばそんな話もありました、って感じ。で、全体を一応きちんと . . . 本文を読む
ポン・ジュノ監督最新作。『グエムル』以来の長編だ。『殺人の追憶』の流れを組むミステリーだが、当然単純な話ではない。知的障害を持つ息子を可愛がり、彼だけのために生きる母親が主人公である。冒頭の母親のダンスのシーンが凄い。荒涼とした野原で彼女が体をくねらせて踊りだす。その姿を延々と捉える。一体何が始まるのか、と思わせる。
兵役から戻り5年振りの映画出演となるウォンビンが息子を演じる。彼の小鹿のよ . . . 本文を読む
今回の『黄昏れる砂の城』は初演よりずっといい。アイホールの広い空間で、よりダイナミックに増幅された4人のダンサーによるアクロバチックな演技が作品世界を押し広げることになったからだろう。この作品を初めてロクソドンタで見た時、これのどこが泉鏡花なのかわからなかった。今回は最初からそういう先入観を持たずに見れたのもよかった。前回は、これが『春昼後刻』を原作にしているという前情報が規制になり、素直に作品 . . . 本文を読む
取り壊しの決まった団地。もう既に住人の引っ越しはすべて完了し、ここには誰ももういない。ある夫婦がここに戻ってくる。忘れ物を取りに来た。2人はここを出ると同時に離婚する。だが、夫にはためらいが残る。別れたくはない。この自分たちが住んでいた部屋に、なぜか今、ひとりの青年が住んでいる。彼はかって子ども時代にこの部屋で暮らしていたらしい。幸福な少年時代の思い出がここには詰まっている。今では壊れてしまった . . . 本文を読む