2013年9月25日(水)
雨模様の午後、新所沢公民館で開催された山里探訪会の第8回講座に参加しました。

今日の演題は「大河紀行 荒川」、講師は紀行作家の伊佐 九三四郎(いさ くみしろう)
さんです。
伊佐さんのお名前は、ハイキングガイドなどの著者として以前から知っていましたが、
お話を聞くのは初めてです。
私も、カントリーウオークの仲間と、1994年から足かけ4年かけて荒川(隅田川)
河口から源流の真ノ沢まで歩いたことがあり、今日のテーマは大変興味深いものでした。

前半の1時間は、埼玉県の中央部を西から南東に貫いて東京湾に注ぐまでの地図を見な
がら、ポイントになる地の歴史や産業、宗教、氾濫への対応、歩いて感じたことなど、源
流から河口までの荒川にまつわる幅広い話をされました。
それらお話の中で、メモしたポイントの幾つかは以下のようなものです。
伊佐さんは昭和25年頃から奥多摩や奥秩父の山を歩かれ、いつかは源流から河口まで
歩きたいという考えておられたが、なかなか機会が得られなかった。
荒川というのは、その名の通り氾濫を起こしたりする荒れ川、暴れ川で、全国では青森
から沖縄まで36本もある。
過去の氾濫を知る場所としては、秩父の長瀞の持田氏宅と樋口に寛保2年(1742)
の大洪水の水位を示す印や「水」と刻まれた石があり、現在の水位よりかなり高いことが
分かる。
荒川上流の真ノ沢が荒川源流点になっているが、最初の1滴の落ちる甲武信ヶ岳
(2,475m)からは5㎞ほど下ったところ。国土交通省の荒川起点碑はさらに下流で、
ここから河口までは173㎞あり、国内の河川の長さでは15番目になる。
秩父湖の下流にある御岳山は、木曽の御岳山と関係が深く、木曽御岳の王滝口というの
は、秩父の大滝ゆかりの名。
鉢形城は3,000の軍勢で3万以上の敵と戦い、持ちこたえた。
川本付近の荒川には、以前かなりの数のコハクチョウが来ていたが、餌(え)づけを止
めたので近年は数が少なくなっている。
熊谷付近から、かつての荒川は利根川に注いでいたが、江戸の洪水を防ぐために入間川
の流れに付け変える西遷を行い、一方、東京湾に入っていた利根川は東遷して銚子に流す
ようにした。
鴻巣付近は川巾日本一として知られ、約2.5㎞あるが、ふだんの流れは細い。鴻巣市
ではこれにちなみ、川巾ウドンを売り出しているが、幅がありすぎて味は?。
川島町は川に囲まれているので大水被害が多かった。現在は輪中(わじゅう)とよぶ集
落を囲む高い堤防で守られている。また、ここでは「すったてうどん」よ呼ぶキュウリの
付いたもりうどんが知られていて、こちらの方がおいしい。
荒川に流入する入間川は、飯能の西川材で知られ、たびたび大火のあった江戸の復興に
欠かせない材木は、荒川を経て江戸に入った。
さらに下流の新河岸川も、江戸との舟運が栄えた。
戸田は、戦前中止された東京オリンピックが計画された際から、競艇場を造る計画があ
り、反対も多かったが、1964年の東京オリンピックの際に競艇場も造られ、それが現
在では、同種の国内ギャンブル施設の売り上げでは日本一だという。
東京の洪水対策として近年出来たのが彩湖。これらのお陰で荒川の氾濫が減り、氾濫に
よる肥沃な土が枯れたのと、帝都復興用にこの地の壁土が大量に採取されたために、田島
ヶ原のサクラソウは見る影もなくなった。
明治43年(1910)の大洪水を機に、東京を水禍から救うため、北区岩渕付近に本
流(現在の隅田川)の流れを分流する荒川放水路(現在は荒川という)を造ることになり、
当時でも大変な規模の住宅や学校などの移転、鉄道の付け替えなどを行った。
その工事を指揮したのは、パナマ運河の工事を経験した青山 士(あきら)で、岩渕に
残る赤い水門が当時のもの、青い水門はその後の新しい水門である。
青山 士は大変謙虚な人で、工事終了後、犠牲者の氏名を刻んだ慰霊碑を水門のそばに
自費で建立したが、自分の名はどこにも記してない。
荒川河口には東京ゲートブリッジが建設されたが、歩き終えた日はちょうど橋の開通日
で、橋に上がって歩いて来た長い道のりをふり返った。
まだほかにも、たくさんは話されましたが、メモした主なもののみ紹介しました。
休憩後の後半には、歩いた行程で撮った写真をまとめたスライドを上映しながら、それ
らの説明をされ、私も過去に歩いたときに見たり訪ねたりしたところが多く、大変興味深
く拝見しました。
蛇足ながら私たちが歩いたのは、1994年5月から1997年7月まで12回13日、
隅田川のかちどき橋から源流の真ノ沢と股の沢との分流点付近まででした。流域より迂回
したところもあり総歩行距離は232㎞、使用した2.5万分の1地形図は18面です。
会場の後方には、写真や荒川の立体パノラマ地図、伊佐さんの著書などが展示されてい
ましたが、撮り忘れたので、並んでいた著書の幾つかを以下に紹介します。
「大河紀行 荒川」白山書房、「武蔵野の散歩みち」山と渓谷社、「幻の人車鉄道」河
出書房新社、「東京江戸を歩く」実業之日本社、「奥多摩奥武蔵の山々」実業之日本社、
「モロッコの風」白山書房など。
ちなみに、荒川は埼玉県の中央部を流れ、長さ日本一の利根川は埼玉県北部から東部へ
と県境を流れていますが、埼玉県内にはほかにもたくさんの川があり、県の総面積に対す
る河川の占有面積は日本一となっています。
それらたくさんの川を丹念に歩かれたのが、今日の講座を開催した山里探訪会の代表、
飯野治(よりじ)さんで、飯野さんは、埼玉の川沿いの道75コースを紹介した「埼
玉の川を歩く」という図書を、昨年8月にさきたま出版会から出版されました。

まえがきで飯野さんは、「水辺では、街道や山道とも異なる自然の躍動や生命力に心癒
やされ、河川をたどりながら周囲の景観を楽しむと同時に、その土地ならではの歴史的事
物から過去の思いをはせると心躍るのである」と記されています。
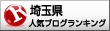 埼玉県 ブログランキングへ
埼玉県 ブログランキングへ

にほんブログ村
雨模様の午後、新所沢公民館で開催された山里探訪会の第8回講座に参加しました。

今日の演題は「大河紀行 荒川」、講師は紀行作家の伊佐 九三四郎(いさ くみしろう)
さんです。
伊佐さんのお名前は、ハイキングガイドなどの著者として以前から知っていましたが、
お話を聞くのは初めてです。
私も、カントリーウオークの仲間と、1994年から足かけ4年かけて荒川(隅田川)
河口から源流の真ノ沢まで歩いたことがあり、今日のテーマは大変興味深いものでした。

前半の1時間は、埼玉県の中央部を西から南東に貫いて東京湾に注ぐまでの地図を見な
がら、ポイントになる地の歴史や産業、宗教、氾濫への対応、歩いて感じたことなど、源
流から河口までの荒川にまつわる幅広い話をされました。
それらお話の中で、メモしたポイントの幾つかは以下のようなものです。
伊佐さんは昭和25年頃から奥多摩や奥秩父の山を歩かれ、いつかは源流から河口まで
歩きたいという考えておられたが、なかなか機会が得られなかった。
荒川というのは、その名の通り氾濫を起こしたりする荒れ川、暴れ川で、全国では青森
から沖縄まで36本もある。
過去の氾濫を知る場所としては、秩父の長瀞の持田氏宅と樋口に寛保2年(1742)
の大洪水の水位を示す印や「水」と刻まれた石があり、現在の水位よりかなり高いことが
分かる。
荒川上流の真ノ沢が荒川源流点になっているが、最初の1滴の落ちる甲武信ヶ岳
(2,475m)からは5㎞ほど下ったところ。国土交通省の荒川起点碑はさらに下流で、
ここから河口までは173㎞あり、国内の河川の長さでは15番目になる。
秩父湖の下流にある御岳山は、木曽の御岳山と関係が深く、木曽御岳の王滝口というの
は、秩父の大滝ゆかりの名。
鉢形城は3,000の軍勢で3万以上の敵と戦い、持ちこたえた。
川本付近の荒川には、以前かなりの数のコハクチョウが来ていたが、餌(え)づけを止
めたので近年は数が少なくなっている。
熊谷付近から、かつての荒川は利根川に注いでいたが、江戸の洪水を防ぐために入間川
の流れに付け変える西遷を行い、一方、東京湾に入っていた利根川は東遷して銚子に流す
ようにした。
鴻巣付近は川巾日本一として知られ、約2.5㎞あるが、ふだんの流れは細い。鴻巣市
ではこれにちなみ、川巾ウドンを売り出しているが、幅がありすぎて味は?。
川島町は川に囲まれているので大水被害が多かった。現在は輪中(わじゅう)とよぶ集
落を囲む高い堤防で守られている。また、ここでは「すったてうどん」よ呼ぶキュウリの
付いたもりうどんが知られていて、こちらの方がおいしい。
荒川に流入する入間川は、飯能の西川材で知られ、たびたび大火のあった江戸の復興に
欠かせない材木は、荒川を経て江戸に入った。
さらに下流の新河岸川も、江戸との舟運が栄えた。
戸田は、戦前中止された東京オリンピックが計画された際から、競艇場を造る計画があ
り、反対も多かったが、1964年の東京オリンピックの際に競艇場も造られ、それが現
在では、同種の国内ギャンブル施設の売り上げでは日本一だという。
東京の洪水対策として近年出来たのが彩湖。これらのお陰で荒川の氾濫が減り、氾濫に
よる肥沃な土が枯れたのと、帝都復興用にこの地の壁土が大量に採取されたために、田島
ヶ原のサクラソウは見る影もなくなった。
明治43年(1910)の大洪水を機に、東京を水禍から救うため、北区岩渕付近に本
流(現在の隅田川)の流れを分流する荒川放水路(現在は荒川という)を造ることになり、
当時でも大変な規模の住宅や学校などの移転、鉄道の付け替えなどを行った。
その工事を指揮したのは、パナマ運河の工事を経験した青山 士(あきら)で、岩渕に
残る赤い水門が当時のもの、青い水門はその後の新しい水門である。
青山 士は大変謙虚な人で、工事終了後、犠牲者の氏名を刻んだ慰霊碑を水門のそばに
自費で建立したが、自分の名はどこにも記してない。
荒川河口には東京ゲートブリッジが建設されたが、歩き終えた日はちょうど橋の開通日
で、橋に上がって歩いて来た長い道のりをふり返った。
まだほかにも、たくさんは話されましたが、メモした主なもののみ紹介しました。
休憩後の後半には、歩いた行程で撮った写真をまとめたスライドを上映しながら、それ
らの説明をされ、私も過去に歩いたときに見たり訪ねたりしたところが多く、大変興味深
く拝見しました。
蛇足ながら私たちが歩いたのは、1994年5月から1997年7月まで12回13日、
隅田川のかちどき橋から源流の真ノ沢と股の沢との分流点付近まででした。流域より迂回
したところもあり総歩行距離は232㎞、使用した2.5万分の1地形図は18面です。
会場の後方には、写真や荒川の立体パノラマ地図、伊佐さんの著書などが展示されてい
ましたが、撮り忘れたので、並んでいた著書の幾つかを以下に紹介します。
「大河紀行 荒川」白山書房、「武蔵野の散歩みち」山と渓谷社、「幻の人車鉄道」河
出書房新社、「東京江戸を歩く」実業之日本社、「奥多摩奥武蔵の山々」実業之日本社、
「モロッコの風」白山書房など。
ちなみに、荒川は埼玉県の中央部を流れ、長さ日本一の利根川は埼玉県北部から東部へ
と県境を流れていますが、埼玉県内にはほかにもたくさんの川があり、県の総面積に対す
る河川の占有面積は日本一となっています。
それらたくさんの川を丹念に歩かれたのが、今日の講座を開催した山里探訪会の代表、
飯野治(よりじ)さんで、飯野さんは、埼玉の川沿いの道75コースを紹介した「埼
玉の川を歩く」という図書を、昨年8月にさきたま出版会から出版されました。

まえがきで飯野さんは、「水辺では、街道や山道とも異なる自然の躍動や生命力に心癒
やされ、河川をたどりながら周囲の景観を楽しむと同時に、その土地ならではの歴史的事
物から過去の思いをはせると心躍るのである」と記されています。
にほんブログ村














