能登半島災害を謳う (2)
能登半島地震災害から7カ月が経とうとしている。
新聞やテレビなどのニュースの能登関連記事も最近では見られなくなってしまった。
パリオリンピックや大谷選手のニュースが毎日のように報道され、
復旧半ばの被災地の人々はままにならない生活環境の不便さを続けながら、
ときには、取り残されていく淋しさにくじけそうになる時がある。
人口流出は能登半島地域の震災以前からの課題だったが、
震災がそれに拍車をかけ、多くの業種が人手不足に苦しんでいる。
人口流出と経済復興の停滞する中で、地元の建設会社のK氏は
「復旧工事は10年以上続くだろう。全く先が見通せない」と将来の不安を述べる。
以下の歌は、能登地震から2~3カ月過ぎた頃の歌で、朝日歌壇、俳壇に掲載された歌である。
震災の記憶が時間の経過とともに薄れていく現在、
震災被害のなまなましい風景がよみがえってくる。
「はがやしい」朝市あつた焼け跡に両手を合はすひとりの女性 大熊佳世子
「はがやしい」とは、石川県金沢あたりの方言で、「思い通りにいかない心のありよう」を
表現する。ここでは「誰にもわかってもらえない悔しい思い」という意味を含んでいる。
標準語では表現することが難しい、その土地で培われた素晴らしい言葉。
被災5カ月を経てやっと6月4日に公費解体が始まった。
公費解体には、建物の所有権を持つ全員の同意が必要で、復旧の遅れの原因になっていた。
そこで、法務省は5月末、輪島朝市の264棟が建物としての価値がなくなったとして、
「減失登記」をして、建物の解体を進めやすいようにした。
しかし、崩壊建物の中に放置された物品の破壊や撤去には、物品の所有者の同意が必要になり、
その同意も得られたとして解体に着手した。
「はがしい」と輪島朝市の焼失した現場に立ち、両手を合わせる女性の姿が目に浮かぶ。
珠洲原発を造らせなかった闘いは正しかったといま胸を刺す 十亀弘史
珠洲原発は1975年に計画された。その計画は住民の反対運動と、
それを切り崩す電力会社との28年に及ぶ闘争になった。原発設置は珠洲の高屋地区だったが、
当初住民のほとんどが反対していた。
関電側の住民の切り崩し運動はえげつない懐柔策だった。
「原発視察名目の視察旅行」、「芸能人のコンサート」など、
いずれも無料の大盤振る舞いだったという。
数え上げたらきりのない寄付ゃ接待というカネの力に、
一人二人と反対派の住民が切り崩され、地域は分断されて行った。
説明会はいいことずくめの話で、住民の心を揺さぶり続けた28年間であったという。
激しい原発反対運動に電力会社は2003年12月計画凍結を発表し、計画は頓挫した。
今回の能登半島地震で、珠洲原発予定地の高屋地区の海岸線は数メートルも隆起した。
「もし、あの時珠洲原発が高屋地域に建設されていたら」と隆起した海岸線を眺めながら、
当時を振り返る。
臓物のはみ出すごとく家具吐きし家屋の呻くこゑする通り 北野みや子
慣れ親しんだ住まいが倒壊し、雨ざらしになっている思い出のある品々が散乱している。
色あせ、汚れ破壊された大切な品々が、倒壊現場の哀しさがこみ上げ、
家屋の呻き声が生き物の叫びのように聞こえてくる。臨場感に溢れた被災者の叫びだ。
無事だった船四隻で水揚げす甚大被害の蛸島漁港 瀧上裕幸
一体何隻の船が被害に遭ったのかニュースからはわからない。漁港岸壁には隆起や地割れがあり、
被害に遭わなかった船は片手にも足りない。漁師にとっては手足を奪われたような甚大な被災だ。
海に生きる漁師たちは、代々船を受け継ぎ家業として続ける人が多い。
東日本大震災で被害を受けた漁師の言葉を思い出す。
愛する者を津波に奪われ、船も無くなった。だが「俺は海を恨まない」。
代々海で暮らしを立ててきた漁師の意地が、
くじけそうになる自分を鼓舞するようにつぶやいた言葉が耳に残っている。
1月21日深夜定置網漁が再開された。自宅も事務所も漁港も損壊したが、
残った船を操業し、年末に仕掛けた定置網漁を再開した。水揚げは寒ブリ約600匹。
タイ、フクラギなど15トンを揚げた。(参考:北国新聞)
蛸島漁港=石川県輪島市にある漁港。
海が好き漁はやめぬと若者の見つめる先に隆起せし浜 阿久津利江
漁師の仕事は過酷な仕事だ。親から子へと家業として受け継ぐ人が多い。
海にどんな仕打ちを受けようと、海は母の懐のように優しい。
浜が隆起しようが、地割れしようが海への希望と感謝を忘れない。
その心意気が上の瀧上さん歌にも通じるものがある。
能登の地震(ナイ)海苔(のり)掻(か)く岩場隆起して 内田幸子
能登の岩のリは、長い海岸線を持つ能登半島の外浦が産地として知られている。
毎年12月から3月にかけて、自然が育てた海の幸である岩ノリ採りが行われる。
能登では収穫したばかりの収穫したばかりの岩ノリが海水を含み「ぼたぼた」した状態なので
「ぼたのり」ともいわれている。生産地であるだけに、多種多様あるようだが、
珠洲や輪島では、正月の雑煮に香ばしく焼いた岩ノリを入れた「ぼたのり雑煮」を食べるのが習わし
で、初春を彩る具材として用いられます。
磯の香りのする「ぼたのり雑煮」を食べてみたい能登の正月です。
過疎化が進む能登では、半島を離れ、金沢や都市圏で生活する人も多いが、
暮れから正月にかけて里帰りをし、家族が一堂に会して「郷土料理」を食べ、
正月を祝う習慣があります。その一家だんらんの日を地震と津波と火事が襲った。
「珠洲の塩使っています」とメモのあるバゲット一本トレーにのせる 平野野里子
能登の塩づくりは、能登の伝統産業です。昔ながらの製法で「能登塩」には人気があります。
地方への出店があり、震災地の店があれば必ず被災地の名産を購入する。
夏東日本大震災時には宮城県・女川市の出店などで少しばかりの援助をしていました。
「珠洲の塩」を使ってバゲットを作る。それを客が買っていく。小さな支援の輪が広がっていく。
(人生を謳う№120) (2024.07.28記)












 (随筆に添えられた絵)
(随筆に添えられた絵)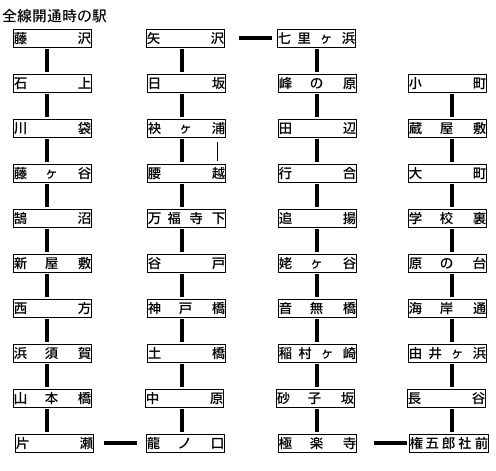 図で示したように
図で示したように

 (eiga.com)
(eiga.com) (写真はウエブ朝日新聞より引用)
(写真はウエブ朝日新聞より引用)







