
(つづき)
連節バスの「回送」を営業運転化する今回のダイヤ改正だが、
「原則、連節バスでの運行となります」とのことで、連節バスではない「特快」もやってくる可能性があることを示唆。
となると、同じバス停から出る、

福岡空港国際線行きの「特快」や、「特快162番」との停車停留所の違いを、“車両の違い”によって区別することが難しい場面も出てくるということか。

「151番」「152番」の種別の整理は、「特快」の使用が無駄に拡散するのを抑える意味合いもあったと言えるのかも。
一方、「特快300番」は、「BRT(連節バス)で運行します」という案内。
この案内を作った人は、“BRTとは車両のことだ”、という解釈をしているもよう。
でも、乗り場の案内表示などからみても、連節バスによる「中央ふ頭~天神~博多駅~中央ふ頭」の循環運行路線のことを指して「BRT」と言う、という方向性?が何となく形成されているようにも感じる。
車両のことは単に「連節バス」と呼び、「BRT」は連節バスによる都心部の循環路線のことを指す、という整理にしたほうが現状では妥当のような気も。
それが正しいのか?はまた別の話なのですが。
「都心BRT」と「郊外BRT」という呼び方を用いる、とか、連節バスによる路線には新たに別体系の行先番号を振り直す、とか、他にもいろいろやり方はありそうだが、そんなことは、この事業を始める前に考えないといけないことだと思われ、今回の「営業運転化」は、当初は特にそんな計画はなく、連節バス運行開始後に思いついたのでは??というのは想像。
言葉の使い方の整理、という意味では、「西鉄香椎駅前」と「西鉄香椎」という、わかったようなわからないような使い分けも、この機会に改めてもよかったのでは?
あと、「青果市場前」や「東部青果市場前」の改称は、しなくてよかったんですかね?
(つづく)










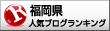





















































まあ、交通規制や大雪などで連節バスが運休することがあっても、この「特快」は通常の路線車で運行しますよということかもしれませんが。
151番、152番の全便快速化は確かに順当だと思いますが、予想以上に短命に終わりましたね。利用者としては時刻表も見やすくなって大歓迎ですが。しかし、天神北~ヤフオクドーム前間で停車バス停を選んだ時に伊崎が出てくるとは。それなら那の津口に止めた方がまだ需要あったんじゃ・・・
返信がたいへん遅くなって申し訳ないです。
>連節バスでない「特快」が来る可能性があるということは、連節バスでない「都心BRT」が拝める可能性があるということなんでしょうか?
連節バスではない「都心BRT」は、既に何度か運行されているようですね。
>天神北~ヤフオクドーム前間で停車バス停を選んだ時に伊崎が出てくるとは。それなら那の津口に止めた方がまだ需要あったんじゃ・・・
伊崎もそこそこ利用は多いですよね。
それにしても、西公園ランプ経由と百道ランプ経由の「中間」をどうしても残したいんですかね。
その「中間」を敢えて選んで乗っている利用者は、まだまだ多くはない気もしますが。