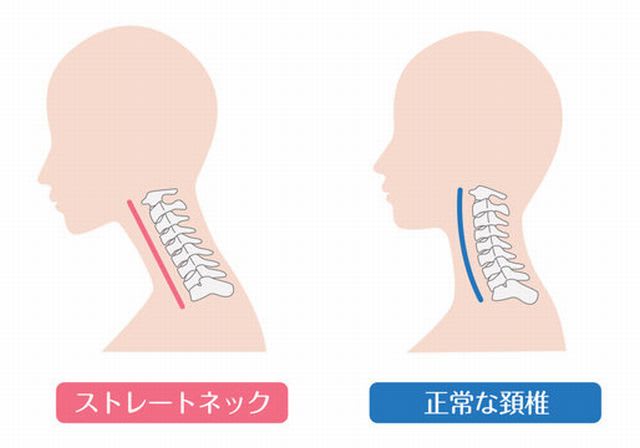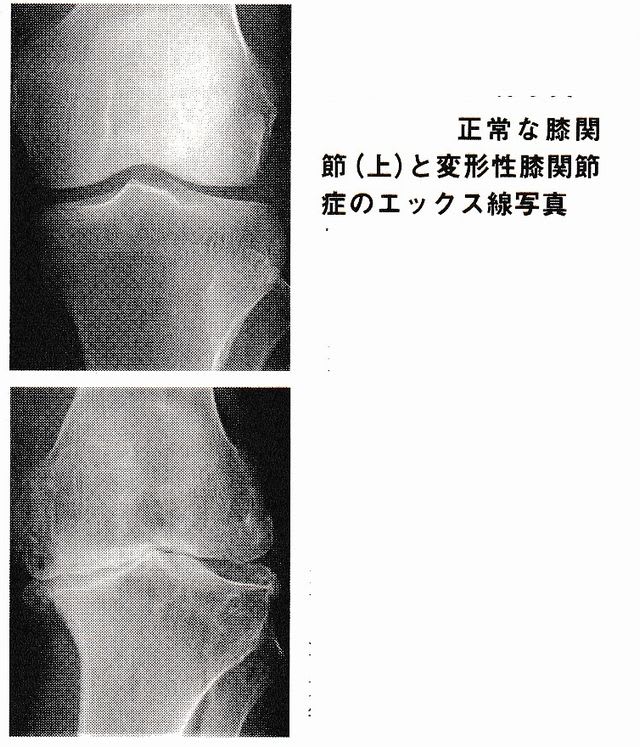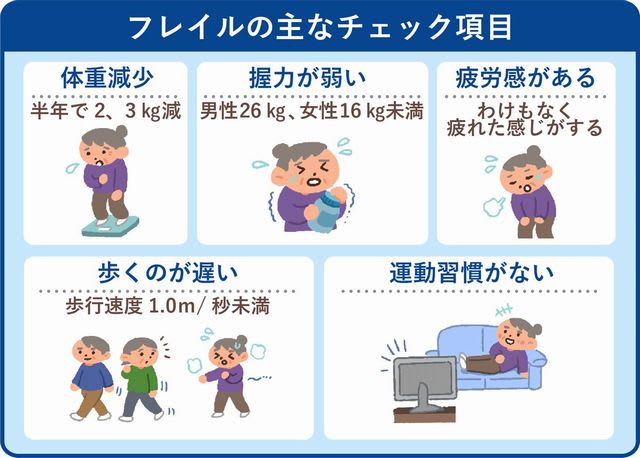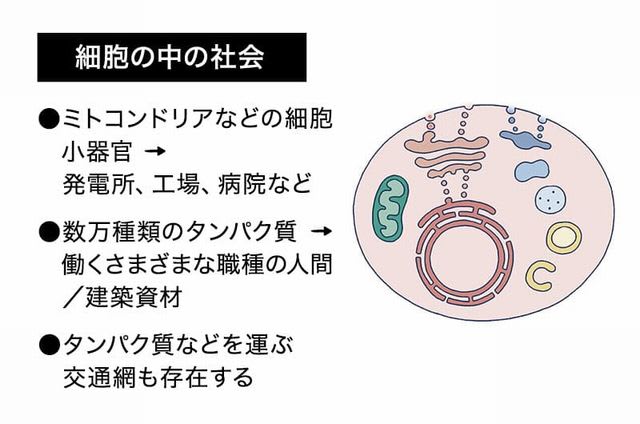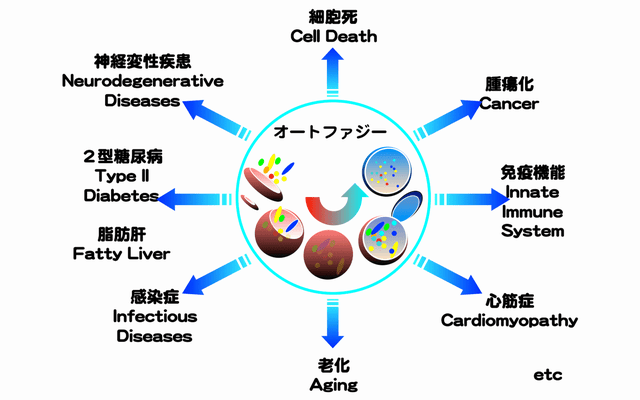🌸『死後の真実』
☆エリザベス・キューブラー・ロス博士の『死後の真実』
*世界的に有名な「死」の研究者
☆自身の臨床経験や数多くの臨死体験例をもとに
*死後の世界について深く探求した一冊
☆『死と医療』の本を読み興味持ち読みました
⛳はじめに
☆昨今、注目を浴びている「死」というものに
*博士ほど真剣に取り組んだ人はありません
*数千人もの人の死ぬ瞬間に立ち会ったという博士
*死ぬ過程には、あるパターンがあることを発見した
*死ぬ過程には、あるパターンがあることを発見した
☆博士の「死にゆく過程の五段階」説
*「死後のいのちは永遠である」と言っている
*「気づく」かどうか、「知る」かどうかの問題であるとも言っている
*「死後のいのちは永遠である」と言っている
*「気づく」かどうか、「知る」かどうかの問題であるとも言っている
*ようなことが1冊の本として発表されたことはありませんでした
*医学界にも衝撃を与える本なのです
☆博士は、自身が気づいた「死後の真実」
☆博士は、自身が気づいた「死後の真実」
*2万件以上ものデータで裏付けし、身近な実例で説明している
*人が人生で直面する苦しい体験(精神的、肉体的両面)
*すべが遅かれ早かれ、その人自身の役に立つ
*その言葉に、筆者にとって考えさせられました
⛳『死後の真実』の論点
☆死は終わりではない
*死は人生の終着点ではない
*新たな始まりであるという考え方を提示している
☆臨死体験
*数多くの臨死体験例を紹介している
*それらの共通点や意味を分析することで
*死後の世界の一端を垣間見せてくれる
☆魂の永遠性
*人には肉体を超えた魂が存在し
*それは永遠であるという考え方を支持している
☆愛とつながり
*死後も愛する人々とのつながりは続くというメッセージを伝える
☆死に対する恐れを手放してくれる
*死を恐れずに、穏やかに人生を送るためのヒントを与えてくれる
⛳『死後の真実』の本の魅力
☆具体的な体験談に基づきストーリーを進めている
*実際の臨死体験者の証言を多数紹介しており
*身近に死後の世界を感じることができる
☆科学的な視点で、読者に新たな視点を与えてくれる
*臨死体験を科学的に分析し、その可能性を探り
☆心の安らぎと希望を与えてくれる
*死に対する不安や恐怖を抱えている人々に
⛳『死後の真実』の本、読者に与える影響
☆死生観の変化
*死に対する考え方や、人生の意味を問い直すきっかけとなる
☆心の癒し
*失恋や死別など、心の傷を抱えている人々の癒しにつながるかも
☆生きる喜び
*死は必ず来るものだからこそ
*今を大切に生きようという気持ちになる
⛳『死後の真実』の本の留意点
☆『死後の真実』あくまでも一つの考え方である
*科学的な証明がされているわけではない
☆読者によって、受け止め方は様々
⛳まとめ
☆『死後の真実』は、死という普遍的なテーマを扱いながらも
*読者に希望と勇気を与えてくれる
☆死を深く考えたい方、心の癒しを求めている方、読んでみて下さい
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、『人はどう死ぬのか』
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、『人はどう死ぬのか』



『死後の真実』『死にゆく過程の五段階』『キューブラー・ロス』
(『死後の真実』記事、ネットより画像引用)