今回のはなしはレイアウトというよりも「特撮のミニチュア」寄りの話となりますがご容赦を。

今回の特撮博物館に出かける前に少し危惧していたこと。
撮影用のミニチュアを実際に見たらちゃちな感じを持ってしまうのではないかという点です。
実際に過去故郷などでやっていたイベントでは如何にもとって付けた様なビルと称する箱、住宅と称するダンボール細工みたいな家なんかを見ることが多かったので漠然とですが不安を感じていました。

ところが実際にセットの中に入ってみるとこれが全く気にならない、そればかりか映像以上の生々しさを感じるライブ感に驚かされたのです。
自分自身レイアウトなんかで街並みを構築したりしてはいても今のN(実はHOも)ではサイズが小さすぎて俯瞰で疑似風景を眺める楽しみはあっても(とはいえ、ディスプレイのフレームから中に入れないCGよりははるかにライブ感はあるのですが)風景の中に入り込む楽しみは十分とは言えないのではと思います。
ですが元々が人間の入る着ぐるみが暴れまわる事を前提に設計されている特撮スケールのミニチュアではそうした不満はほとんど感じませんでした。
むしろ映像の方が「手に触れられそうな」ライブ感がない分損をしている(実際映像ではちゃちに見えても実際のミニチュアが意外に大型モデルだったのに驚かされたのも今回の見学の収穫の一つでした)

そんな所から、特撮のミニチュアの今後の展開として映画・映像の表現技法としてばかりでなく、ミニチュア自体をライブ感あるショーとして使うのはどうかと思えてきています。
こうした実例としてドイツのミニチュアワンダーランドやオランダのマドローダム、日本でなら東武ワールドスクェアなどがそれに該当しますが、映画の特撮セットの場合これらと異なる特徴として「場面に応じて設定を変える」ことを頻繁に行う関係上セット自体の組み換えが容易に行える点があると思います。極端な話、昨日は石油コンビナートだったのが今日は東京駅、明日は下町の住宅街と切り替えることができる訳です。
ここにライブ的エンターテイメントとしてのミニチュアの生き残りの鍵があるのではないかと。
鉄道模型のレイアウトでもこれに近い事を(例えばショッピングモールにモジュールレイアウトを持ち込んでの運転会など)やっているケースがありますがおおむね観客の反応は好いようです。
ですがこれは「きしゃの模型が走っている」というだけでなく「それぞれに趣向を凝らした風景」との組み合わせがあって初めて好印象になっているのではないかと感じるのです。
これが車両展示だけ、ジオラマ展示だけだったとしたらあれだけの誘引力があったかどうか。
ミニチュア風景は決してそれ自体が主役にしゃしゃり出てくるという事は稀ですしそれをやったケースの殆どが「ショーケースの飾り物」の域から出られません。
ですがレイアウトや特撮のミニチュアならばそれに組み合わせるべき「動く主役(それが列車かクリーチャーかという違いはありますが)」があって初めて100パーセント魅力を発揮できる点で共通なものがあると考えます。
この点で最初からそれ自体のディスプレイを目的としているジオラマとは異なると思えます。
上記の場合で言うなら「セットに入り込んでいる人間(客)」がそれに相当します。一種のガリバー気分の疑似体験というのは(当のガリバー旅行記が300年前の登場という事を考えても)時代を超えたライブ的な魅力があるのではないかと思えるのです。
同じことはレイアウトについても言えます。
今回ミニチュアセットをうろつきながらふとそういう事を考えました(笑)
光山鉄道管理局
HPです。
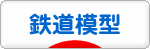
にほんブログ村

にほんブログ村
現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。

今回の特撮博物館に出かける前に少し危惧していたこと。
撮影用のミニチュアを実際に見たらちゃちな感じを持ってしまうのではないかという点です。
実際に過去故郷などでやっていたイベントでは如何にもとって付けた様なビルと称する箱、住宅と称するダンボール細工みたいな家なんかを見ることが多かったので漠然とですが不安を感じていました。

ところが実際にセットの中に入ってみるとこれが全く気にならない、そればかりか映像以上の生々しさを感じるライブ感に驚かされたのです。
自分自身レイアウトなんかで街並みを構築したりしてはいても今のN(実はHOも)ではサイズが小さすぎて俯瞰で疑似風景を眺める楽しみはあっても(とはいえ、ディスプレイのフレームから中に入れないCGよりははるかにライブ感はあるのですが)風景の中に入り込む楽しみは十分とは言えないのではと思います。
ですが元々が人間の入る着ぐるみが暴れまわる事を前提に設計されている特撮スケールのミニチュアではそうした不満はほとんど感じませんでした。
むしろ映像の方が「手に触れられそうな」ライブ感がない分損をしている(実際映像ではちゃちに見えても実際のミニチュアが意外に大型モデルだったのに驚かされたのも今回の見学の収穫の一つでした)

そんな所から、特撮のミニチュアの今後の展開として映画・映像の表現技法としてばかりでなく、ミニチュア自体をライブ感あるショーとして使うのはどうかと思えてきています。
こうした実例としてドイツのミニチュアワンダーランドやオランダのマドローダム、日本でなら東武ワールドスクェアなどがそれに該当しますが、映画の特撮セットの場合これらと異なる特徴として「場面に応じて設定を変える」ことを頻繁に行う関係上セット自体の組み換えが容易に行える点があると思います。極端な話、昨日は石油コンビナートだったのが今日は東京駅、明日は下町の住宅街と切り替えることができる訳です。
ここにライブ的エンターテイメントとしてのミニチュアの生き残りの鍵があるのではないかと。
鉄道模型のレイアウトでもこれに近い事を(例えばショッピングモールにモジュールレイアウトを持ち込んでの運転会など)やっているケースがありますがおおむね観客の反応は好いようです。
ですがこれは「きしゃの模型が走っている」というだけでなく「それぞれに趣向を凝らした風景」との組み合わせがあって初めて好印象になっているのではないかと感じるのです。
これが車両展示だけ、ジオラマ展示だけだったとしたらあれだけの誘引力があったかどうか。
ミニチュア風景は決してそれ自体が主役にしゃしゃり出てくるという事は稀ですしそれをやったケースの殆どが「ショーケースの飾り物」の域から出られません。
ですがレイアウトや特撮のミニチュアならばそれに組み合わせるべき「動く主役(それが列車かクリーチャーかという違いはありますが)」があって初めて100パーセント魅力を発揮できる点で共通なものがあると考えます。
この点で最初からそれ自体のディスプレイを目的としているジオラマとは異なると思えます。
上記の場合で言うなら「セットに入り込んでいる人間(客)」がそれに相当します。一種のガリバー気分の疑似体験というのは(当のガリバー旅行記が300年前の登場という事を考えても)時代を超えたライブ的な魅力があるのではないかと思えるのです。
同じことはレイアウトについても言えます。
今回ミニチュアセットをうろつきながらふとそういう事を考えました(笑)
光山鉄道管理局
HPです。
にほんブログ村
にほんブログ村
現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。









