レイアウトの駅、ホームのはなしから。

先日紹介した「鐵道模型レイアウトの製作」の「駅とホームの製作」の中に興味深い資料を見つけました。
山手線の主要駅を中心にして「ホームの幅と上屋の構造を図式化した表」です。
正直言ってこれまでこうした表を見るまで「実物の適切なホームの幅」というものがどれくらいなのか考えた事がありませんでした(恥)
これによると最も幅の狭い日暮里で6.3メートル、特急が停まる上野駅で9.4メートル、最も広い東京駅に至ってはホームの幅は12メートルを超えます。
これを単純にNスケールに当てはめるなら日暮里で4センチ強、上野や新橋で5~6センチ、東京駅では8センチ強となります。

一部を除いて市販品のホームに比べて桁外れのスケールです(笑)
とはいえ、個人所有のレイアウトではスペースの関係から幅を狭くしたホームでないと線路を増やせないという事情もあるのでやむを得ません。

ですが、博物館やイベントでのショーモデルとして、あるいは夢想の中での「大レイアウト」を検討するならこの数字を無視できないのも事実です。
なぜなら「ホームの幅の設定で駅のスケール感そのものが決定される要素が大きい」事が上の資料から示されているからです。
同時にホームの形態についても市販品では物足りない側面があります。
それは「カーブ」の存在です。
実景の駅の俯瞰や鳥瞰図をチェックすれば分かりますが市販品の様などこまでも真っ直ぐなホームがいくつも並んでいる光景と言うのは非常にまれです。
大抵の場合側線や退避線を含めた線路は周囲の地形や諸事情に合わせて微妙にカーブしている事が多く、それに付随するホームも例外ではありません。
言い換えれば「ホームほど周囲の地形やトラックプランに依存した形態となりやすい=カーブしやすい」駅施設は無いとも言えます。
それを実感させられるのが、数は少ないながら特撮映画のミニチュアに出てくるホームです。
「新幹線大爆破」の浜松駅や「妖星ゴラス」の有楽町駅(?)などは微妙にカーブした構造のホームがそこはかとないリアリティを感じさせてくれます。

同時にそれはホームと線路のコラボレーションと言う形で「魅力あふれる俯瞰」を構成する要素の重要なひとつとなり得ると思えます。
とはいえ、このメリットが生かせるのはある程度以上の規模の大レイアウトのみでしょう。
あるいは「駅だけの大規模なセクションかモジュール」でも言えるかもしれません。

結論として、もし大レイアウトを作れるなら(ランドマークたる)駅の本屋とホームだけはフルスクラッチに近い自作が望ましそうです。
そして「線路とそれに付随したホームは周囲の地形設定に準拠する形で可能な限り美しいカーブを描くことで大レイアウトらしいスケール感とリアリティを発揮するだろう」となりそうです。
とはいえ、これはあくまでも理想論です。決して「絶対にこうであるべき」という意味ではない事を最後に強調しておきます。
(模型の写真は本題とは関係ありません)
光山鉄道管理局
HPです。
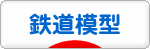
にほんブログ村

にほんブログ村
現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。

先日紹介した「鐵道模型レイアウトの製作」の「駅とホームの製作」の中に興味深い資料を見つけました。
山手線の主要駅を中心にして「ホームの幅と上屋の構造を図式化した表」です。
正直言ってこれまでこうした表を見るまで「実物の適切なホームの幅」というものがどれくらいなのか考えた事がありませんでした(恥)
これによると最も幅の狭い日暮里で6.3メートル、特急が停まる上野駅で9.4メートル、最も広い東京駅に至ってはホームの幅は12メートルを超えます。
これを単純にNスケールに当てはめるなら日暮里で4センチ強、上野や新橋で5~6センチ、東京駅では8センチ強となります。

一部を除いて市販品のホームに比べて桁外れのスケールです(笑)
とはいえ、個人所有のレイアウトではスペースの関係から幅を狭くしたホームでないと線路を増やせないという事情もあるのでやむを得ません。

ですが、博物館やイベントでのショーモデルとして、あるいは夢想の中での「大レイアウト」を検討するならこの数字を無視できないのも事実です。
なぜなら「ホームの幅の設定で駅のスケール感そのものが決定される要素が大きい」事が上の資料から示されているからです。
同時にホームの形態についても市販品では物足りない側面があります。
それは「カーブ」の存在です。
実景の駅の俯瞰や鳥瞰図をチェックすれば分かりますが市販品の様などこまでも真っ直ぐなホームがいくつも並んでいる光景と言うのは非常にまれです。
大抵の場合側線や退避線を含めた線路は周囲の地形や諸事情に合わせて微妙にカーブしている事が多く、それに付随するホームも例外ではありません。
言い換えれば「ホームほど周囲の地形やトラックプランに依存した形態となりやすい=カーブしやすい」駅施設は無いとも言えます。
それを実感させられるのが、数は少ないながら特撮映画のミニチュアに出てくるホームです。
「新幹線大爆破」の浜松駅や「妖星ゴラス」の有楽町駅(?)などは微妙にカーブした構造のホームがそこはかとないリアリティを感じさせてくれます。

同時にそれはホームと線路のコラボレーションと言う形で「魅力あふれる俯瞰」を構成する要素の重要なひとつとなり得ると思えます。
とはいえ、このメリットが生かせるのはある程度以上の規模の大レイアウトのみでしょう。
あるいは「駅だけの大規模なセクションかモジュール」でも言えるかもしれません。

結論として、もし大レイアウトを作れるなら(ランドマークたる)駅の本屋とホームだけはフルスクラッチに近い自作が望ましそうです。
そして「線路とそれに付随したホームは周囲の地形設定に準拠する形で可能な限り美しいカーブを描くことで大レイアウトらしいスケール感とリアリティを発揮するだろう」となりそうです。
とはいえ、これはあくまでも理想論です。決して「絶対にこうであるべき」という意味ではない事を最後に強調しておきます。
(模型の写真は本題とは関係ありません)
光山鉄道管理局
HPです。
にほんブログ村
にほんブログ村
現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。



















