
桜も咲きかけというこの季節、先日の知事の呼びかけもあってこの週末は外出自粛ムード一色。
どうかすると金曜日の段階で駆け込み上京している人達までいるとの事で緊迫感と「なにやらよくわからん」がないまぜになった変な心持です。
まあ、それを切り離してもこの週末は3月末としては冷え込みがきつく、どうかすると首都圏には大雪の可能性まであるとの事ですから肺炎騒ぎがなくとも外出には二の足を踏みそうです。
という訳で当面は休日と言えども自宅蟄居状態というのが当たり前になりそうですが、こういう時を使ってできるインドアな趣味として鉄道模型で手を使って少しでも気晴らしをしたいところです。

前にも書いたように私の場合性に合いそうなことと言えば工作か読書か運転という事になりますが、今回は主に作る方で。
雨天下でもできる自宅の工作というとキットメイクか自作がまず思いつきますが、ウィルスが怖くて家にいる人間がシンナーや塗料をバンバン使うプラ工作や半田の鉛、ヤニの影響を受ける金属工作というのもなんだかという気もします。
シンナー接着や塗装(もっともこれは悪天候下では基本禁じ手ですが)の影響を受けず、それでいて「工作したぞ、手を使っているぞ」という達成感のある工作は何か?
そこまで考えて思い出したのが10年ほど前からと気に入ったモデルをちょこちょこ買いだめていながら事実上積みプラ化していたさんけいの「みにちゅあーと」です。
ペーパー製なので基本カッターとピンセット、木工ボンドで足りますし色紙を組み合わせる独特な工法ゆえに素組みなら塗装の必要もありません(もっとも、モデルの性質上ウェザリングはやりたいことが多いですが)
「そうだこれだ」と思い出して押し入れの中から未組み立てのみにちゅあーとを発掘してみたらこれがまあ出るわ出るわ。

商店街が一つできるくらいのボリュームはたっぷりありそうです。
年に一つか二つしか買わなくともそれを10年も続ければそれなりに溜まるものです。
このシリーズはアイテムによる工作の難易度の幅が広く小さくても手間がかかる建物があり、どうかすると完成まで1週間くらい掛かるものもあるのでこうした蟄居中の工作には打ってつけの気がします。
という訳でさっそく平日の就寝前のひと時が積みキットの消化に費やされることになります。それぞれの進捗などは随時このブログでも紹介するつもりです。


















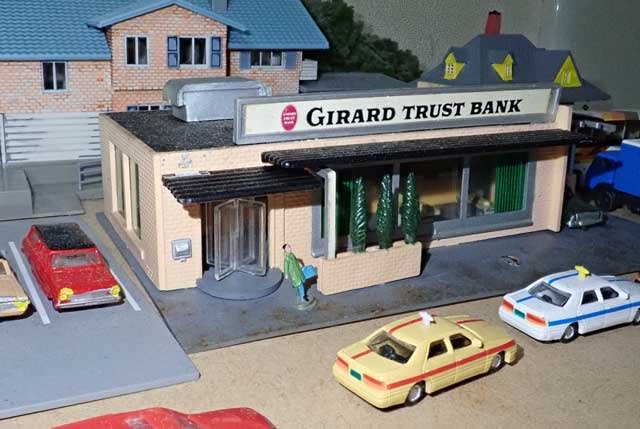








 久しぶりに実車のはなしから
久しぶりに実車のはなしから


