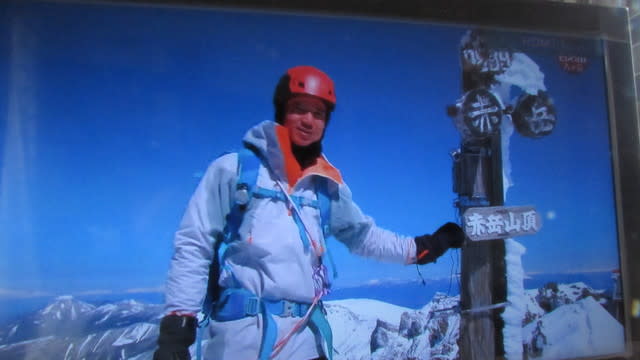全長約486mの日本最大の前方後円墳。周遊路が整備されており、一周するには1時間かかる。
世界遺産に仁徳天皇陵
工期15年8か月
作業員数延べ680万7000人
ピーク時1日当たり2000人
総工費796億円
大手ゼネコンの大林組が古代工法で試算
- 歴史的建造物(文化財含む)
- 古墳
-
大仙陵古墳
全長約486m/後円部径約249m/高さ約35.8m/前方部幅約307m/高さ約33.9mの日本最大規模の前方後円墳。『延喜式』は、この古墳を「百舌鳥耳原中陵」(もずのみみはらのなかのみささぎ)と命名し、現在は宮内庁が第16代仁徳天皇の陵墓に治定・管理している。墳丘は3段に築成され、左右のくびれ部に造出し(つくりだし)があり、三重の濠がめぐっているが、現在の外濠は明治時代に掘り直されたもの。明治5年(1872)、前方部で竪穴式石室に収めた長持形石棺が露出し、刀剣・甲冑・ガラス製の壺と皿などが出土した。また、アメリカのボストン美術館には、本古墳出土と伝えられる細線文獣帯鏡や単鳳環頭太刀などが所蔵されているほか、円墳周囲には、「陪塚」(ばいちょう)と呼ばれる、小型古墳10基以上も確認されている。約2.8kmの周遊路が整備されており、一周するには1時間かかる。
住所-
〒 590-0035 大阪府堺市堺区大仙町7-1アクセス
-
JR阪和線「百舌鳥駅」より徒歩10分
-
見学自由
仁徳天皇陵古墳と履中天皇陵古墳の間に位置し、芝生広場や日本庭園などもある緑豊(...)
古墳の概要
築造時期・被葬者
採集されている円筒埴輪や須恵器の特徴から5世紀前半から半ばに築造されたものと考えられている。前方部埋葬施設の副葬品は5世紀後期のものと考えられるが、前方部に存在する副次的な埋葬施設の年代として問題ないとされる。
治定について
『記紀』『延喜式』などの記述によれば、百舌鳥の地には仁徳天皇、反正天皇、履中天皇の3陵が築造されたことになっている。しかし、それぞれの3陵として現在宮内庁が治定している古墳は、考古学的には履中天皇陵(上石津ミサンザイ古墳)→仁徳天皇陵(大仙陵古墳)→反正天皇陵(田出井山古墳)の順で築造されたと想定されており、大きく矛盾が生じている。このことから、百舌鳥の巨大古墳の中で最も古く位置づけられる伝履中天皇陵を伝仁徳天皇陵にあてる見解もある。しかし、この場合は後述する『延喜式』の記述と大きく食い違うことになる。
規模
大仙陵古墳の規模について、堺市の公式サイトでは以下の数値を公表している。
- 古墳最大長:840メートル
- 古墳最大幅:654メートル
- 墳丘長:486メートル -> 525.1メートル
- 墳丘基底部の面積:103,410平方メートル -> 121,380平方メートル
- 後円部 - 3段築成
- 直径:249メートル -> 286.33メートル
- 高さ:35.8メートル -> 39.8メートル
- 前方部 - 3段築成
- 幅:307メートル -> 347メートル
- 長さ:237メートル -> 257メートル
- 高さ:33.9メートル -> 37.9メートル
墳丘長は、第2位とされる大阪府羽曳野市の誉田御廟山古墳(応神天皇陵)の425メートルを上回り、日本最大である。
-
-
ここでは「 -> 」の後に 2018年4月12日宮内庁の三次元測量調査による修正値を記載する。
-
宮内庁の調査は重要で考慮しておく必要がある。なお一重濠の下にはヘドロは水の2倍以上も堆積していて墳丘の裾はヘドロの中に食い込んでいて600m以上ある可能性もある。
-
体積は300万立方メートル以上と秦の始皇帝陵を超える体積の可能性もある。
-
墳丘本体の体積はコンピューター計算により164万立方メートルと、水面上の体積だけで誉田御廟山古墳の143万立方メートルを超えていることがわかった。