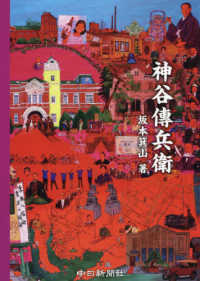© NASA
グリーンピースは、環境保護と平和を願う市民の立場で活動する国際環境NGOです。
問題意識を共有し、社会を共に変えるため、政府や企業から資金援助を受けずに独立したキャンペーン活動を展開しています。
本部(グリーンピース・インターナショナル、事務局長 ジェニファー・モーガン、バニー・マクダーミッド)はオランダのアムステルダムにあり、世界で300万の個人サポーターに支えられています。
世界55カ以上の国と地域で活動し、国内だけでは解決が難しい地球規模で起こる環境問題に、グローバルで連携して解決に挑戦することが私たちの強みです。
国連の総合協議資格
 「生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)」で海洋生態系の保護を訴えるグリーンピース・ジャパンのスタッフ
「生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)」で海洋生態系の保護を訴えるグリーンピース・ジャパンのスタッフまた、国連では国際的なNGOに与えられる最も高い地位の1つである「総合協議資格」が認められていて、総会を含むほとんどの会議にオブザーバーの資格で出席しています。
このようにグリーンピースは、国際的に認められたNGOですが、環境破壊をする企業や政府に正面切って「No」を突きつけるその姿勢から批判の対象となることも多く、特に目立たない事をよしとする日本においては誤解されることが多いのも事実です。
なお、グリーンピースは、シーシェパードとは関係のない別の団体です。
グリーンピースの誕生
グリーンピースの誕生から約45年。
1971年に、アメリカの地下核実験に反対し、「船で実験場の近くまで行って抗議しよう」と集まった人々が、環境を守る「グリーン」と反核・反戦・平和の「ピース」を結びつけ「グリーンピース」と名乗ったのが、私たちグリーンピースの名前の由来です。
 アフリカ・カメルーンの熱帯雨林にかかる虹。コンゴ盆地の自然林は生物多様性の宝庫で住民にも生活の糧を提供しているが、近年では大規模なパーム油農園開発の危機に瀕している。
アフリカ・カメルーンの熱帯雨林にかかる虹。コンゴ盆地の自然林は生物多様性の宝庫で住民にも生活の糧を提供しているが、近年では大規模なパーム油農園開発の危機に瀕している。この時、非暴力的な方法で環境破壊の現場に立会い、一般市民の目の届かないところで起こる環境破壊を多くの人に知らせて世論を動かし、ついには核実験を終了させることに成功したのが、グリーンピースの最初の功績です。
活動をともにしてきた船もいまでは3隻に増え、世界中を航行しています。
グリーンピースの活動において、企業や政府機関が対象となる場合があります。
これはその対象企業や団体そのものやそこで働く方々を批判するためではなく、地球環境保護のために協力を促すことを目的としています。
活動方針の「非暴力直接行動」とは?
 ©Masaya Noda/Greenpeace
©Masaya Noda/Greenpeace「グリーンピース」と聞くと、日本では多くの方が過激な団体と連想されますが、それは、活動で用いる「非暴力行動」が、誤解されているからかもしれません。
環境破壊を行っている当事者に、いくら理路整然と「環境破壊をやめてください」と伝えても、動いてもらえないことがほとんどです。
グリーンピースの活動のステップは
- 環境破壊の現場での調査
- 科学的な分析結果に基づいたレポートや代替案の作成
- 国連「総合協議資格」を利用して国際会議での働きかけ
- 政府・企業に対して問題点と代替案の提案
ですが、環境破壊の速度があまりに速く、政府や企業の対応が追い付いていない場合は、迅速に広く、人々に問題を伝えるため、 さまざまな行動(非暴力行動)を呼びかけます。
非暴力行動には、オンラインで署名を集めるものから、デモやパレード、さらには座り込みなど幅広い活動が含まれます。
※「INGO Accountability Charter (INGO説明責任憲章)」について
グリーンピースは、国際的な非政府組織(International Non-Governmental Organizations、以下 INGO)が組織運営において果たすべき責任を定めた「INGO Accountability Charter (INGO説明責任憲章)」を採択しています。
グリーンピース・ジャパンはこの憲章に則り下記のポリシーを定めて活動をしています。
- 「情報公開ポリシー」 (年次報告書等を通じて活動内容、ガバナンスストラクチャー、財務状況などを公開することを定めたもの)
- 「内部告発者保護ポリシー」 (組織内における不正などを告発した職員を保護することを定めたもの)
- 「汚職防止ポリシー」 (職員が職務を通じて金銭的な賄賂等を受けることを禁じるもの)
- 「多様性ポリシー」 (あらゆる人を人種、出身、年齢、ジェンダー、婚姻状況、性的指向、ジェンダーアイデンティティ、宗教、そして身体的特徴などに関係なく平等に扱うことを定めたもの)
グリーンピースの船について
 © Greenpeace / Gavin Newman
© Greenpeace / Gavin Newmanグリーンピースの最大の特徴の1つに、一般の人々が行けない所へ船で行き、目の届かないところで起こる環境破壊の現場に立ち会う活動があります。
その活動に欠かせないのが、3隻の船:虹の戦士号、アークティックサンライズ(北極の日の出)号、エスペランサ(希望)号です。
虹の戦士(Rainbow Warrior)号
北米先住民族の伝説「虹の戦士」からその名を取った、環境保護活動を支えてきた世界で最も有名な船です。
過去21年間に渡り、数多くの知られざる環境問題に光を当て、人々をつなぐ掛け橋としてグリーンピースと一緒に世界中を航海、活躍してきました。
2004年にはフランス映画「スパイバウンド」(モニカ・ベルッチ主演)でも題材にされ、話題になりました。
現在の虹の戦士号は、3代目(虹の戦士号Ⅲ世)です。
III世建造にあたりご寄付を頂いたみなさま、誠にありがとうございました。