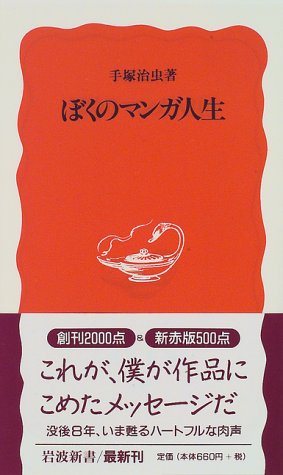ユニセフの子育て6つのヒント
【2020年4月10日 東京/ニューヨーク発】
新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックの影響は、世界各国の家庭にも及んでいます。
学校の休校、在宅勤務、人同士の物理的な距離をとること(physical distancing)--。
誰もが知りたいことがあるなかで、特に保護者の方々が必要としている情報は多いのではないのでしょうか。
ユニセフ(国連児童基金)は、Parenting for Lifelong Healthイニシアチブと共同で、COVID-19のもたらしたこれまでと違う日常を過ごすのに役立つ便利なヒントを発信しています。
* * *
子育て6つのヒント
目次
1対1の時間をつくろう
ポジティブでいよう
日常を整えよう
子どもが誤ったふるまいをしたら
ストレスとうまく付き合おう
新型コロナウイルスについて話そう
1.1対1の時間をつくろう
自宅の窓から近所の人による人形劇を鑑賞する生後7カ月のレオンちゃんと両親。(スペイン、2020年3月30日撮影)
© UNICEF/UNI316067/ López Tazón
自宅の窓から近所の人による人形劇を鑑賞する生後7カ月のレオンちゃんと両親。(スペイン、2020年3月30日撮影)
仕事は在宅、学校が休校、お金が心配…ストレスを感じて困惑するのは当然のことです。けれども、休校措置は、子どもとより良い関係を築くチャンスでもあります。お金がかからず、楽しく子どもと1対1で向き合える時間があります。愛され、安全で、大切に思われていると子どもたちが感じることのできる時間です。
子ども一人ひとりと過ごす時間を確保しましょう
ほんの20分、あるいはそれ以上――どれだけの時間を費やすかは、私たち次第です。毎日同じ時間に設定すると、子どもはその時間を楽しみにするでしょう。
子どもに何をしたいかたずねてみて
子どもは、自分で選ぶことで自信がつきます。人との物理的距離をとれない「何か」をしたいと子どもが望んでいる場合は、距離を取ることについて話をするチャンスです。
赤ちゃんとできることがあります
たとえば、
子どもの表情や声をまねする
歌を歌ったり、鍋やスプーンで音楽を奏でる
コップやブロックを積み重ねる
お話をしたり、本を読んだり、絵を見せる
小さな子どもはこんなことができます
本を読む、絵を見る
屋外でも家のすぐ近くでも、散歩に出てみましょう
音楽に合わせて踊ったり、歌を歌ったり
一緒に家事をする:掃除や料理をゲーム感覚で!
学校の課題を一緒にやる
10代の子どもとはこんな風に過ごしてみては
スポーツや音楽、芸能人、友達のこと…子どもが好きなものについて話す
屋外でも家のすぐ近くでも、散歩に出てみましょう
好きな音楽を聴きながら身体を動かす
テレビや携帯電話の電源を切り、子どもたちの話を聞き、目線を合わせて、まっすぐ向き合う。楽しんで!
2.ポジティブでいよう
全国放送のテレビ教室プログラムを見ながら、ヨガの練習をする5歳のマクシムくんとジャンくんの双子の兄弟。(北マケドニア、2020年3月25日撮影)
© UNICEF/UNI314054/Klincarov
全国放送のテレビ教室プログラムを見ながら、ヨガの練習をする5歳のマクシムくんとジャンくんの双子の兄弟。(北マケドニア、2020年3月25日撮影)
子どもの行動によって余裕がなくなっている時、ポジティブでいるのは難しいかもしれません。結局、「やめなさい!」と言ってしまうかもしれません。でも、前向きな内容を伝えて、正しい行動を褒めてあげれば、伝えたことを実行してもらいやすくなるでしょう。
してもらいたい行動を伝えましょう
子どもに何をすべきかを伝える際は前向きな言葉を使いましょう。例えば、「散らかさないで」ではなく、「服を片付けてきれいにして」といったように。
すべて、伝え方しだいです
子どもに向かって、強い口調で叱りつけたり大きな声で怒鳴ったりすることは、あなた自身にも子どもにも、よりストレスと怒りをもたらすだけです。名前を呼んで子どもの注意を引き、穏やかな声で話しましょう。
よくできたときには、褒めましょう
何かを上手くできたとき、褒めてあげましょう。態度には見せないかもしれませんが、子どもはきっと褒められたことをまたするでしょう。あなたが気にかけていることで、子どもも安心します。
本当にできること?
あなたが子どもに求めていることは、本当にできることでしょうか? 子どもにとって1日中家の中で静かにしているのは難しいですが、例えばあなたが電話で大事な話をしている15分間であれば、静かにすることはできますよね。
10代の子ども同士のつながりを維持する
特に10代の子どもにとっては、友達とコミュニケーションできることは大切です。SNSやその他の安全な距離を保てる方法で、つながりを維持できるようにしてあげましょう。これも一緒にできることです!
メニューに戻る
3.日常を整えよう
自宅で保育園の友達とテレビ電話をする4歳のマルゴットちゃん。(米国、2020年3月30日撮影)
© UNICEF/UNI316263/Bajornas
自宅で保育園の友達とテレビ電話をする4歳のマルゴットちゃん。(米国、2020年3月30日撮影)
COVID-19によって、仕事、家庭、学校生活といったこれまでの日常は奪われてしまいました。子どもやあなた自身にとっても大変なことです。こういう時には、新しい習慣をつくることが役立ちます。
柔軟に、でも一定の日課を設けましょう
決められた活動をする時間と自由時間との、両方を含めたスケジュールを立てることで、子どもたちは安心し、より良い行動をとれるようになるでしょう。学校の時間割のように、その日の計画を立ててみましょう。子どもたち自身で計画を立てると、より守りやすくなるでしょう。
毎日、運動する時間をつくりましょう。これはストレスが溜まっている人や、家にいてエネルギーがありあまっている子どもにとって有効です。また、子どもに、責任の持てる簡単な仕事を与えましょう。子どもたちができることにしてくださいね。そして、それをやり遂げたら褒めてあげるのを忘れずに!
安全な距離を保つことについて教えましょう
身の安全を守る方法について話してあげると、子どもは安心します。もし問題がない状況なら、子どもを外に連れ出してください。手紙を書いたり、絵を描いたりして、誰かと共有しても良いでしょう。
手洗いを、楽しく
手を洗うための20秒の歌を作ります。身振り手振りを加えましょう。「手洗いポイント」をあげるなど、日々の手洗いをほめましょう。顔をさわる回数の少なさを競うゲームをするのも良いでしょう。
あなたは子どもの行動のお手本です
あなた自身が安全な距離を保ち、衛生的な環境を保てるよう実践し、他の人、特に病気や弱い立場に置かれた人に思いやりをもって接すれば、子どもたちはあなたの行動を見習うでしょう。
1日の終わりに、その日について振り返る時間をもちましょう。子どもに、ポジティブなことや楽しいことをひとつ伝えましょう。今日あなたががんばったことを自分で褒めましょう。100点満点!
4. 誤ったふるまいをしたら
遠隔授業の合間に母親とサッカーを楽しむ8歳のルカくん。(米国、2020年3月17日撮影)
© UNICEF/UNI313393/McIlwaine
遠隔授業の合間に母親とサッカーを楽しむ8歳のルカくん。(米国、2020年3月17日撮影)
子どもはみな、良くない行動をしてしまうことがあります。疲れていたり、お腹がすいていたり、恐怖を抱えていたり、あるいは自立の過程では当然のことです。家にずっといたら、あなたを困らせることもあるでしょう。
方向転換をしてみましょう
誤ったふるまいになるべく早く気づき、子どもたちの注意を悪い行動から良い行動に向けさせます。
子どもたちが誤った行動をし始める前に止めましょう。子どもが落ち着かなくなったら、面白いものや楽しいもので気を紛らわせましょう。「さあ、お散歩に行こう!」といったように。
深呼吸しよう
カッとして怒鳴りたくなりましたか?そんな時は、10秒ストップ。ゆっくりと5回深呼吸します。その後、なるべく落ち着いて応じてください。
子どもと1対1の時間をもち、良い行動をほめ、そして一定の日課があれば、誤った行動は少なくなります。
5. ストレスとうまく付き合おう
オンライン授業の中でエクササイズに取り組む高校2年生のシャオユウさん。(中国、2020年2月18日撮影)
© UNICEF/UNI304638/Ma
オンライン授業の中でエクササイズに取り組む高校2年生のシャオユウさん。(中国、2020年2月18日撮影)
いまはとてもストレスの多い時期です。子どもを支えるためにも、自分のケアをしましょう。
あなたはひとりではありません
何百万人もの人々が私たちと同じ恐怖を抱えています。自分の気持ちを話すことができる人を見つけてください。その人たちの話に耳を傾けてください。あなたをパニックに陥らせるソーシャルメディアは避けましょう。
休息を取りましょう
私たちはみな、時には休息が必要です。あなたの子どもが眠っているとき、何か楽しいことをしたり、リラックスしたりしてください。あなたが好きな健康的な活動のリストを作りましょう。好きなことをしていいのです!
子どもの話に耳を傾けてください
子どもたちの話を聞いてください。子どもたちはあなたに、サポートと安心を求めています。子どもたちが自分の気持ちを話すときには、耳を傾けてください。彼ら気持ちを受け止め、安心させてあげましょう。
一息入れましょう
ストレスや心配を感じるときいつでもできる1分間のリラクゼーション方法をご紹介します。
ステップ 1: 準備
ゆったりと座り、足を床に降ろし、手は膝の上に置きます。
心地よい状態で、目を閉じます。
ステップ2:考え、気持ち、体に目を向ける
自分が今何を考えているのか、自問してみてください。
自分の考えがわかったら、それが否定的な考えか前向きな考えかを考えましょう。
いまどんな気持ちですか。それが幸せな気持ちかどうかを考えましょう。
体の状態を感じましょう。痛みや緊張はありますか。
ステップ3:自分の呼吸を意識する
吸ったり吐いたり、自分の呼吸を聞いてください。
お腹に手をあてて、息をするたびにおなかが上下するのを感じてみましょう。
「大丈夫。それが何であれ、私は大丈夫」と自分に語りかけてみてください。
その後、しばらくの間、まだ呼吸を聞いてください。
ステップ4:意識を戻す
あなたの全身が感じることに意識を向けましょう。
部屋の音を聞きましょう。
ステップ 5: 自分と向き合う
なにか違いを感じますか?
準備ができたら、目を開いてください。そして、子どもたちの話を聞いてください。
少しの間立ち止まることは、あなたが子どもに対してイライラしていたり、子どもが悪いことをしてしまったときにも有効です。落ち着くことができるでしょう。何度か深呼吸をしたり、足を付けて床の感覚を感じるだけでも違います。また、子どもと一緒に一息入れるのも良いでしょう。
6.新型コロナウイルスについて話そう
小学校で正しい手洗いの方法を学び、実践する女の子。(ヨルダン、2020年3月10日撮影)
© UNICEF/UNI313265/Matas
小学校で正しい手洗いの方法を学び、実践する女の子。(ヨルダン、2020年3月10日撮影)
どんどん話しましょう。子どもたちはすでにいろいろと耳にしています。沈黙したり秘密にすることは、子どもたちを守ることになりません。正直に、オープンに話しましょう。子どもたちがどのくらい理解できるのかに気を付けてください。あなたが子どもたちのことをいちばん良く知っているのです。
自由に話せる環境をつくりましょう
子どもたちに自由に話しをさせてください。子どもたちが自由に答えられる質問をして、彼らがすでにどれだけ知っているかを確認しましょう。
正直に答えましょう
常に子どもたちの質問に正直に答えてください。子どもの年齢や理解度に気を付けて。あなたの答えが「わからない」でもいいのです。これを子どもと一緒に何か新しいことを学ぶ機会にしてください!
子どもに寄り添って
あなたの子どもは怖がったり、混乱しているかもしれません。子どもたちが気持ちを分かち合う場を設け、あなたが彼らのためにそこにいることを伝えてください。
ヒーローは、誰かをいじめたりしない
COVID-19の感染には、人の見た目や出身地、言語などは関係がないと説明してください。私たちは病気の人々や彼らの世話をしている人たちに思いやりを持つことができるのだと伝えてください。感染拡大を止めるために働き、病気の人々の世話をしている人々に目を向けてください。
たくさんの話が広がっています
真実ではない情報もあります。信頼のおける最新情報は、厚生労働省サイト(日本語)、またはWHOサイト(英語)・WHO神戸センターサイト(日本語)をご確認ください。
楽しい気持ちで終えましょう
あなたの子どもが元気かどうかを確認してください。あなたが気にかけていること、そしていつでもあなたと話すことができることを伝えてください。そして、何か楽しいことを一緒にしてください!