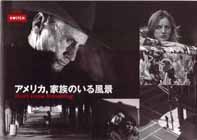5月12日午前6時からCSテレビのザ・シネマで観た。
概要
ヴィム・ヴェンダース監督が『パリ、テキサス』以来20年ぶりにサム・シェパードとコンビを組んだ人生ドラマ。
主人公ハワード・スペンスを演じるのは脚本も担当したサム・シェパード。
共演にサム・シェパードの私生活のパートナーでもあるジェシカ・ラング、その他にサラ・ポーリー、ティム・ロス、エヴァ・マリー・セイントなど。
ストーリー
西部劇スターからすっかり落ちぶれてしまったハワード・スペンス。
今の自分に嫌気が刺し撮影現場から逃げ、30年ぶりに母のもとを訪れると、かつてハワードが自分の子を身籠らせた女性から連絡があったと聞かされる。
驚きの事実を知らされたハワードはまだ知らない我が子に会うため若い頃に過ごしたモンタナ州ビュートへ向かい、かつて関係をもった女性のもとを訪れる。
そこでハワードはバーのステージでロックを歌っている青年が自分の息子だと知らされる。そしてさらに、母の骨壺を抱えた若い女性もハワードのもとを訪ねてくる。
キャスト
女性たちと子供たちの映画である。主人公は年老いた西部劇俳優で、彼の過去と現在とを巡る物語なのだから、どう見たって「男の映画」であるはずなのに、そうではない。
主人公はどこか弱々しくだらしない。「どうして死ななかったのか」なんて冒頭から呟いているのだ。
もちろんそんな主人公が登場する「男の映画」だっていっぱいある。
ではなぜこれが「女性たちと子供たちの映画」なのかといえば、この映画の女たち、そして子供たちだけが彼らの現在と未来に足を踏み出しているからだ。「死ななかった」主人公の生きる場所は、そこにはない。
撮影現場を逃げ出して、本当の「現実」に足を踏み入れても、今更どうなるわけでもない。
そんな現実を主人公が受け入れるまでを、この映画は描く。
それは男の人生の終わりかもしれないが、そのことによって世界の姿が変わる。光の中にある女たち、子供たちの傍らに、男のシルエットがある。そんな構図。
男の時代はお終い。男がシルエットになることによって、女たちや子供たちの人生により深みが増すのである。つまり、女たち、子供たちも変わる。そこではきっと、誰もが生まれ直すことになるのだ。
9・11以降の世界の混乱の中、覇権争いをする男たちの世界に背を向ける監督ベンダースの姿が、そこにはっきりと見えてくる。
(樋口泰人)
アメリカ、家族のいる風景の画像(2/4)
アメリカの砂漠地帯を舞台に、失った家族の絆を取り戻そうとする、家族再生の物語をサム・シェパードと組んで作った、ということになれば、当然「パリ、テキサス」以来という言葉を使わざるを得ないだろう。そういう宣伝文句があちらこちらに飛んでいる。久しぶりに広告も力が入っているようだ。
私が見たかったのは、美しい映像と胸を打つ物語を一緒に味わえる映画。それが「パリ、テキサス」だったし、ほかにも何本かはいいなと思える作品がある。「Don't come Knockin」はおそらく、その中の一本に加えられるだろう。ヴェンダースを長い間見続けて良かったと、いろいろな想いがあふれて来て、胸が詰まった。
砂漠は相変わらず美しいが、モンタナ州ビューイという街もヴェンダースが長年あたためてあった街だけのことはあって、驚くような美しさがある。このチラシのカットなど、まるっきり絵のようだ。家を多く描いたホッパーのような、という表現はどうしてもしてしまうが、なんだかそれだけとも言い難い。観客が映画を見終わった後、美しい映像が印象にばかり残って、物語が残らないのは本末転倒というような発言をヴェンダースはしているが、この映画についてはその両者のバランスはうまくとれているようだ。美しい映像と物語が、心に残っている。
この映画、徹底的なダメ男を3人の女性が救う物語ではないだろうか。一人目はハワードの母親。30年もほったらかしにしておいた息子が帰ってくる。暖かく迎え入れるが、ベタベタと面倒をみたりはしない。「好きにしなさい」といった放り投げ方で自分のペースを守るのだ。ゆっくり話をするでもなく、カジノに行くという息子に「楽しみなさい」と行って送り出してしまう。「地下に部屋を用意した」と事前に電話があったので、それから部屋を作ったように言っているが、実際は息子がいた当時そのままの部屋を引っ越した家にも作っていたのだ。その上俳優である息子の良い話悪い話、全部をスクラップにしているという濃密な愛情を見せつける。でもまたちゃんと送り出す姿は、本当に凛々しい。自分の人生を無駄にして来た気がして、人生をやり直したいと考える瞬間、母親のところに行くのはしごく真っ当だと思わせる。
二人目は昔の恋人ドリーン。子供が出来た当初男の母親に連絡はしておくが、その後は自分から一度も男を捜そうとしない。有名な俳優なのだから、まったくわからないというわけでもないだろうに、放っておく。自分で選んだ人生だと言わんばかりに、子供を産み、育てあげた。息子は決して真っ当な職業とは言えないだろうが、ぐれているわけではない。経済的にもウェイトレスをやっていた店を任され、自立している。まるで強いアメリカン・シングルマザーの見本のようだ。
三人目は彼の娘スカイ。彼女がダメ男を一番恋しがっていたようだが、別に探しているわけではなく、母親のお骨を収めにきた街で偶然出会っただけだった。アールとドリーンに拒絶され、落ち込んでいた父親に対して、ただ一人ストレートに愛情を表現する。アールとスカイの違いは父親が誰かを聞かされていたかどうか。アールの方が知らなかったためにショックが大きく、受け止めきれていない状態なのを、スカイが救い出すような、そんな印象を受けた。そしてラスト近く、スカイが長年の穴を埋めるかのように語り出すシーン。「パリ、テキサス」のジェーンの独白ほど長くはないが、胸を打つものがあった。
冒頭の砂漠のシーン、車で移動するシーン、そしてビュートの街並み、全部が美しいのだが、なかでも重要なんだなと思えたシーンがアールが投げ捨てたソファーにハワードが力なく座り込むシーンである。ここだけ異常に長い間一カ所にカメラが据えられ、動かない。動かないのではなく、動けないのだとすぐにわかった。人間が本当にどうしたらよいかわからなくなったとき、動けなくなるものだなと、それはすごくよくわかった。
ただ一つ、ちょっと解せないのが、スカイの存在を周囲がどういう過程で受け止めていくかなのだ。アールは「血のつながりがある」と言われ、ハワードの方は「私の母を知っている筈」と言われるだけなのである。それだけで偶然にも息子と娘が現れたというような状況、父親と姉(妹?)が現れたという状況を納得できるものなのか。ハワードの方はヤケになっている感じで受け止めていた様子だが、せめてホテルの部屋で「私の母親は20数年前この街の○○で働いていた××よ」くらいの具体的な台詞があってもよかったのではないか。また最初のドリーンとスカイの会話で、具体的にスカイが母親が何者であるか言って、それでひょっとして…とドリーンが思ってアールに話す、というようなちょっとした過程があってもいいのではないかと思う。スペンサーの車の前に居座るインディアンのシーンは何故作られたのかはわかったが、作者の遊びのようなもので、その分少しぐらいは説明調のカットがあってもよかったのではないだろうか。
もちろん、いきなり息子と昔の恋人を探しに行って、いきなり見つかるというところからして、リアリズムに乗っ取る必要性はまるでなく、物語がいわば童話(Má:rchen)なのはよくわかっているが、それでも、多少は物語に説得力をもたせても良いのではないかと思った。
希望のもてるラストで本当に良かったと、今なら思える。彼の子供たちは年齢のわりにとてもピュアに見えるのが不思議だ。
















![アメリカ 家族のいる風景 [レンタル落ち]](https://m.media-amazon.com/images/I/51aUXZmWKUL._AC_SY445_.jpg)