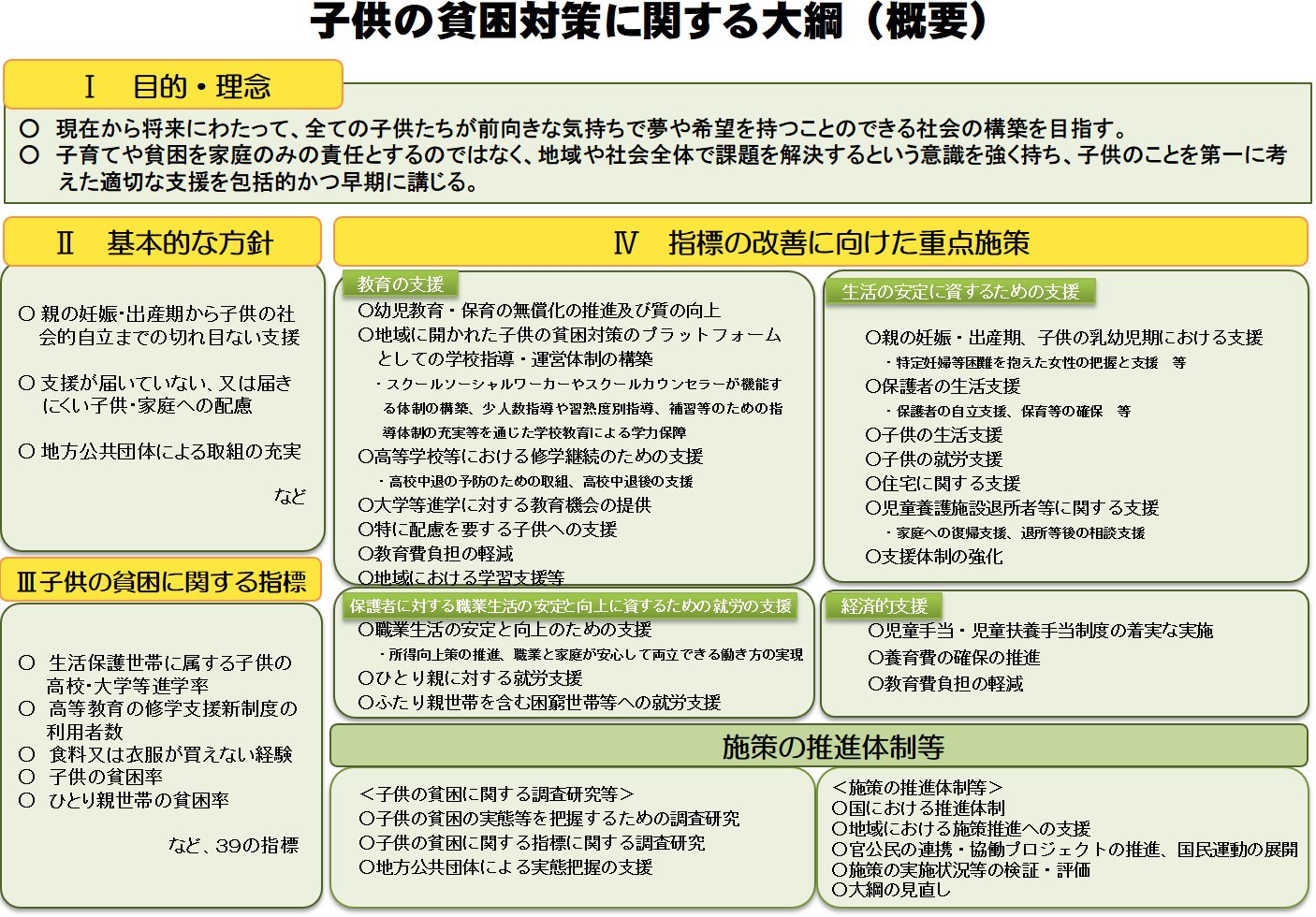解説
「ヴェノム」「ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー」のリズ・アーメッドが主演を務め、聴覚を失ったドラマーの青年の葛藤を描いたドラマ。ドラマーのルーベンは恋人ルーとロックバンドを組み、トレーラーハウスでアメリカ各地を巡りながらライブに明け暮れる日々を送っていた。
しかしある日、ルーベンの耳がほとんど聞こえなくなってしまう。
医師から回復の見込みはないと告げられた彼は自暴自棄に陥るが、ルーに勧められ、ろう者の支援コミュニティへの参加を決意する。
共演に「レディ・プレイヤー1」のオリビア・クック、テレビシリーズ「ウォーキング・デッド」のローレン・リドロフ、「007 慰めの報酬」のマチュー・アマルリック。監督・脚本は「プレイス・ビヨンド・ザ・パインズ 宿命」の脚本家ダリウス・マーダー。
Prime Videoで2020年12月4日から配信。第93回アカデミー賞で作品、主演男優、助演男優など6部門にノミネート。
編集賞と音響賞の2部門を受賞。日本では2021年10月に劇場公開。
2019年製作/120分/G/アメリカ
原題:Sound of Metal
配給:カルチャヴィル
劇場公開日:2021年10月1日
スタッフ・キャスト
- 監督
- ダリウス・マーダー
- 製作
- ベルト・ハーメリンク
- サシャ・ベン・アローシュ
- キャシー・ベンツ
- ビル・ベンツ
- 製作総指揮
- リズ・アーメッド
- マイケル・サゴル
- ダニエル・スブレガ
- ディッキー・アビドン
- デレク・シアンフランス
- カート・ガン
- フレデリック・キング
- 原案
- ダリウス・マーダー
- デレク・シアンフランス
- 脚本
- ダリウス・マーダー
- エイブラハム・マーダー
- 撮影
- ダニエル・バウケット
- 美術
- ジェレミー・ウッドワード
- 衣装
- メーガン・スターク・エバンズ
- 編集
- ミッケル・E・G・ニルソン
- 音楽
- エイブラハム・マーダー
- ニコラス・ベッカー
メタルバンドの話で、ものすごく騒がしい作品なのかと思っていたら、むしろ聴覚を失ってゆくミュージシャンの物語だった。
まあ、メタルバンドのドラマーが主人公なので、最初の印象が間違っているわけではないのだが。
タイトルの「サウンド・オブ・メタル」はダブルミーニングだった。
メタルバンドの主人公が音を失っていくという点でメタルの音の物語でもあるが、もう一つは、聴力を取り戻すためのインプラント手術後の音を指している。
インプラント手術は簡単に言うと金属を耳に埋め込むようなもので、疑似的に聴力を回復させるためのもの。この音が大変に不快な金属音なのだ。
映画は主人公が手術を受けた後の音を観客にも体感させる。
世界の音の何もかもが金属の反響音として聞こえてくる。
本作は、そんな描写も含めて、「ろう」とは治すべき病気や障害ではなく一つの生き方の実践であると描いている。
ある日突然、耳がほとんど聞こえなくなる。それも、恋人と一緒にトレーラーハウスに住まい、行く先々のライブハウスでドラマを叩き続けるドラマーがである。当然、彼の絶望感は半端ない。唯一の治療は脳に音を音として感知するチップを埋め込むことなのだが、如何せん治療代が高額だ。
そんな八方塞がりのドラマーが、友達の紹介で入所するろう者の支援コミュニティで、仲間たちと手話を介して対話し始める。
だが果たして、そこは主人公にとって終の住処たり得るのかどうか?ことはそう簡単ではないことを本人も観客も知っている。
しかし、明確な手がかりがある。焦り、もがき苦しむドラマーに対して、コミュニティの創設者がこう語りかけるのだ。
「耳が聞こえないことはハンデではない。治すものではないのだ」と。そして、「静寂こそ平穏が得られる場所なのだ」と。
音のある世界からない世界へ、豊かさから貧しさへ、勝者から敗者へ。
人生は様々な試練(騒音)と無縁ではいられないけれど、もしもそれを肯定できたなら、人は救済されるに違いない。
激しいドラムプレーで始まる物語が、無音の世界へとシフトしていく意外性のある構成、主人公の聴力と第三者(観客も)の聴力を区別した録音演出、主演のリズ・アーメッドの痛々しいほどの肉体表現と追い詰められた演技。見所はふんだんにあるが、白眉はコミュニティの創設者を演じるポール・レイシーの、まるで神のような佇まいだ。
レイシー自身も役柄と同じくベトナム帰還兵で、ろう者の両親を持つ身であることを考えると、さらにその演技は説得力を持つ。アーメッドとレイシーは共に来年のオスカー候補入りが確実視されている。
ろう者のコミュニティが牧歌的な心地よいコミュニティとして描かれているのもその表れだ。
音が非常に重要な作品なので、本当は映画館で観たい作品である。
ドラマーであるルーベンが聴覚を失い、路頭に迷うなか、ハンデを抱えながら自分の聴かせたい音楽をどうやって、人に伝えていくか
と言うストーリーでした。
日々の暮らしのなか、路頭に迷うルーベンが
恋人のルーの勧めもあり、聴覚障がい者の
コミュニティーに参加する場面は、
手話を通して自分と人とのコミュニケーション
を、少しずつしていき、自分の音楽と共鳴し合う!
自分の音楽を表現することが出来る!
ほとんど音が聞こえないなか、静寂から
音を振動で感じる、ルーベンが新しく一歩
踏み出す姿を見守っていきたい気持ちで
見ていました。
突然降りかかる障害に向き合うのはほんとに難しい、と、言葉で言うのは簡単。
主人公の苦悩は計り知れないだろう。
その中で、耳が聴こえない事をハンディと捉えないという施設が出てきて、手術をして恋人に再会もして、主人公が迎えるラストシーンが秀逸。
どのようにも解釈できるラストシーン。ただ一つ言えるのは、人生は続いていく、っていう真理。徐々に食らうラストでした。
教会の鐘、街のざわめき、無音のなか
父親と再会できた喜びは人生の再出発を
嬉しく思うシーンでした。
補足、耳のインプラントの手術を初めて知りました。
失ってようやくその恩恵に気付く 職業的な突発性難聴のお話だと思っていたのですが、もう治らないんですね そう人間(?だけじゃないだろうけど)の聴覚はスグレモノなのだ。 大音量の中で人と会話しててもちゃんと会話だけ聴き取れるし(カクテルパーティー効果)、何も聞いていないようでも、気になる言葉が耳に入れば注意を向ける。
無意識の内に選択的に聞けるにようなっているのだ ルーベンが人工内耳の手術を受けてからのくだりは、祖母の補聴器の話を思い出しました すぐに落ちたり、音が全部が全部大きくなってどうにも不愉快だったらしいです。
聾のコミュニティの教えを受入出来なかったのが残念でしたが、最後は哀しいけど、悟ったようですね。
しかし難聴になる人とならない人の差が? アルコールとドラッグ関係あり?
アカデミー賞音響賞を受賞しただけあって、音の表現は圧巻です。主人公そのものを生きることができる作品はそう多くはありませんが、この映画はそれに成功した作品の一つでしょう。
ただし、この映画が社会に何らかの問題意識を共有したい作品である(監督自身もそれを目指している)ことを考慮すれば、主人公ルーベンやその他の聴覚障害者の苦しみが描ききれていなかったように感じます。もちろん、個人的な苦しみ(ドラマーとして聾者になること、療養中に彼女が前へと進み始めていたこと、手術を受けても生活は元通りには戻らないことなど)は繊細で洗練されたものとして多くの人の記憶に残ったでしょう。
ですが、社会的な苦しみはあまり描かれることはありませんでした。
それはこの社会がいかに聴覚障害者にとって生きづらい世界かという、社会のデザイン側を問う視点です。
障害学には、障害の「医学モデル」と「社会モデル」という概念が存在します。
医学モデルは、障害は本人にあり、医療によってそれを治療しようとする考え方です。
一方で、社会モデルは障害を社会の側に帰属させる、すなわち、様々な身体的制約のある人々の生活を拒むような障害が社会の側にあるとすると考え方です(「バリアフリー」という言葉の「バリア」はこの意味で使われています)。
障害学は、医学モデルを批判し、社会モデルをその立場としています。
この映画では、「障害は治すものではない」という医学モデルの否定まではありました。ところが、「結局は当人の考え方次第」というところへ帰着してしまい、社会の側を問う描写はほとんどありませんでした。
もちろん障害者に対するセラピーはとても重要ですが、そればかりにフォーカスすると障害というものを個人に背負わせてしまいます。障害者理解を広げるためならば、社会モデルもきっちりと扱うべきだったと感じます。
とはいえ以上のことが、音響のダイナミクスや役者の素晴らしい演技を否定してしまうわけではありません。鑑賞後は劇場で、騒がしいほどの静寂を楽しみました。