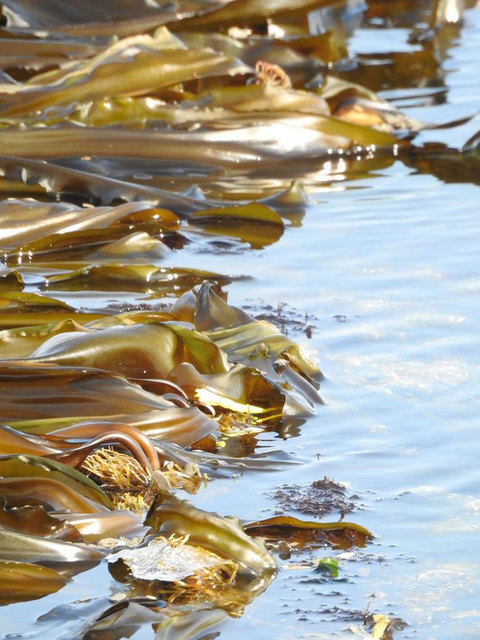「カレーハウスCoCo壱番屋」。ココイチの愛称でも知られる黄色い看板が印象的で、文字どおり、カレーライスを中心とするメニューを取りそろえたカレー専門の外食チェーンだ。日本全国に展開する約1260店のネットワークは、国内で2番手とみられる「ゴーゴーカレー」の約70店を圧倒的に引き離す。直営・FC(フランチャイズチェーン)でココイチを運営する壱番屋は、同業態で唯一の株式公開を果たしている。
そのココイチが、ハウス食品グループ本社の傘下に入る。言わずと知れた「バーモントカレー」「ジャワカレー」「こくまろカレー」などのカレー用ルウで首位の食品メーカーだ。壱番屋はハウス食品からすでに19.5%の出資を受けているが、ハウス食品のTOB(株式公開買い付け)を経て連結子会社となる。TOBが完了する見通しの12月1日にはハウス食品の出資比率は過半の51%まで高まる見込みで、一連の買収額は約300億円に上る。
ココイチカレーの原材料はハウス食品から
もともとの資本関係があったことからも2社の関係は一朝一夕ではない。ココイチで使われるカレーの原材料は原則としてハウス食品から供給を受けており、ココイチが今の地位を確立する過程では、ハウス食品からさまざまな協力を得たと言われている。中国では合弁会社も設けていたり、海外でハウス食品がココイチのブランドでカレーショップを運営していたりなどの協力関係もある。
国内のカレー市場は家庭用、外食ともに成熟しており、人口減を考えれば今後も大きな成長は見込みにくい。加えてココイチは今年春に一部のトッピング具材を値上げするなど、原材料の高騰に悩まされてきた。ココイチから見て売上高で5倍以上、総資産で7倍以上の大手企業であるハウス食品の傘下に入ったほうが、今後、市場拡大が見込まれる中国をはじめとする海外展開の加速や原材料の調達コスト低減などを今まで以上に有利に進められるという側面はある。
壱番屋の子会社化を発表した10月30日の記者会見でハウス食品の浦上博史社長は、「外食のプロの壱番屋のほうが展開のスピードが速い」と話した。海外展開においてココイチの力を一層借りたいというのがハウス食品側の思惑だろう。
ただ、ココイチが直ちに大手食品メーカーの傘下に入らなければならないほどの切迫感は見えてこない。直近本決算である2015年5月期は売上高440億円に対し、本業の儲けを示す営業利益は約46億円と営業利益率は10%を超える。外食チェーンとして見ると収益力はかなり高いほうだ。自己資本比率は73%台、有利子負債もゼロと財務体質も極めて健全な超優良企業である。しばらく単独で運営する道を選んでいても、まったく不思議はない。
にもかかわらず、あえて悪く表現すると「ココイチがハウス食品に身売りした」という解釈もできるのが、今回の話である。これにはどのような背景があるのだろうか。謎を解くカギは創業者の宗次徳二さん本人と、その妻である直美さんが代表を務める有限会社ベストライフが併せて約22%の壱番屋株を保有する「創業家」にある。今回のTOBを経て、宗次家はその保有株をすべてハウス食品に売却することが決まっている。
ビジネスモデルをつくりあげた創業家
宗次徳二さんは2002年に経営の一線を退いてからは、名古屋・栄に私財を投じて「宗次ホール」を開設。クラシック音楽の普及などのボランティア活動を進めており、株の売却資金はボランティア活動の原資に充てるそうだ。もともと壱番屋にハウス食品が資本参加するきっかけとなったのも、同じ事情だという。
創業家が経営に重大な発言権を持つ大株主でなくなってしまう。つまり、ココイチのビジネスモデルをつくりあげた創業家がいっさい身を引く、というのが重大なポイントである。
ココイチはスタンダードな日本の定番カレーを提供し続けてきた。そして定番をベースに、量や味、辛さなどをお客一人ひとりの嗜好に合わせて提供する、いわばマスカスタマイゼーションの先駆者でもある。宗次家は、そんなココイチをどのようにつくりあげてきたのか、歴史的に重大な局面を迎えている今、ルーツをたどってみよう。
壱番屋は「ニコ、キビ、ハキ」をキャッチフレーズに店舗を運営してきた。いつもニコニコして、キビキビ動き、ハキハキ対応する。奇抜ではないものの、この「当たり前」の徹底にこそ壱番屋の強みがある。ココイチのファンを着実に増やしていった要因だ。
1号店が名古屋市郊外にオープンしたのは1978年1月。宗次徳二さんと直美さんの夫婦は当時、喫茶店を営んでいた。店舗に立つなり天職だと知った徳二さんは、そこからすべてを捧げていく。もともと出前サービスの客単価を上げるためにカレーを考案したのち、すべての市販カレーを試食し、自前カレーの提供を決意し、そこからカレー専門店のココイチ屋につながっていく。
家庭の定番メニューであるカレーを主力商品に据えたり、のちにチェーン化していったりすることは、ある種の発明であった。もちろん後付けの解説ではあるものの、定番カレーを提供し続けてきたことにココイチの成功があった。
立地が悪くても客数を伸ばすために日々考え続け、そして、土日もすべて働いてきた。直美さんも子どもを保育園に預けて、迎えにいって寝かしつけたのち、夜な夜な働く日々を送った。
店舗が全日本に広がってからも、2人のハードワークぶりに変化はなく、店舗を見回っては掃除が完璧ではないと、清掃具をもって掃除を始めることもあったそうだ(もちろん社員にとめられた)。バブル期にも堅実すぎる経営を続け、なんら無駄な経費を使わなかった。直美さんは雑誌のインタビューに「うちは飲み屋さんの領収書が1枚もない会社ですから、国税局が入ったときには、2回とも1円の修正もなかったのよ」と答えている(雑誌「2020AIM」2000年12月号)。
年間5000時間以上も仕事に費やす
宗次徳二さんは、早朝に出社し1日に約1000通も届くお客様アンケートにすべて目を通し、コメントつきで店長にFAXしていた。時間があれば自社店舗をつぶさに見て回り、現場の改善にすべてを捧げた。仕事とは無関係ゆえに、趣味がなく、また友人をつくることを自らに禁じていた。
年間5000時間以上を働き、元旦には休むとはいえ、大晦日から元旦にかけて経営目標を立てたのち、であった。その働きぶりの極端さは、ある意味、感動的なほどだ。今回、この記事を書くにあたって宗次徳二さんの資料をまとめて再読していたとき、私は胸が熱くなった。
宗次さんはもちろん、単なるハードワークだけではなく、経営上の発明も行った。「ブルームシステム」と呼ぶ独特のフランチャイズシステムだ。ブルームとは「開花する」意味を持つ。ブルームシステムとは、いわゆる「のれん分け」制度で、壱番屋に入社後2年で独立できる仕組みで、全国に急拡大してきた。
2009年からは「ストアレベルマーケティング」という手法も展開する。これは、いわば地域戦略であり、それぞれの店舗が商品を開発し、それを全国展開する仕組みだ。現在、コンビニエンスストアであっても、たとえばセブン-イレブンは全国均一展開するプライベートブランドの品質向上とともに、地域限定商品を将来的には50%以上に引き上げようとしている。
飲食店とはコンビニエンスストア以上に地域に根付かなければならない。フランチャイズシステムを有しつつ、全国一律の店作りを志向しない”面白さ”がそこにはある。今のココイチの土台は、こうやって作り出された。宗次さんはカレー専門外食チェーンで圧倒的な地位を築いたカリスマ経営者といっていい。

10月30日の会見で壱番屋の浜島俊哉社長は、「単独でやっていくのが難しいのか」という質問に対して、「もう少し長いレンジでモノをみている。創業者が亡くなったときのことも考えて、株を安定的にしっかり持ってくれるハウス食品に任せるのがいいだろう」と答えた。
カリスマ経営者が大きくした企業には後継者問題の難しさがある。創業者であればなおさらだ。そして創業者自身が「自分のつくった会社は竈(かまど)の下の灰まで、すべて自分のモノ」という意識を持って、仮に一線を退いても名誉職で残ったり、大株主であり続けたりして影響力を発揮することがある。血縁関係だけで才覚もない身内に継がせて、経営がおかしくなる企業も枚挙にいとまがない。
一方で、会社側も創業者やカリスマ経営者だからこそ、その手腕にいつまでも頼ってしまうケースもある。ただ、それでは大きく時代が変わっていく中で新しい発想を採り入れられずに、商機を逃してしまうような場面もありうる。
ココイチは創業家が経営の重要事項に今後は原則としてかかわらない方向で、一線を引いた。会社も創業家も覚悟したうえでの決別なのだろう。後々振り返ったときに、この決断が「鮮やかな引き際だった」と賞賛される日が来るかもしれない。