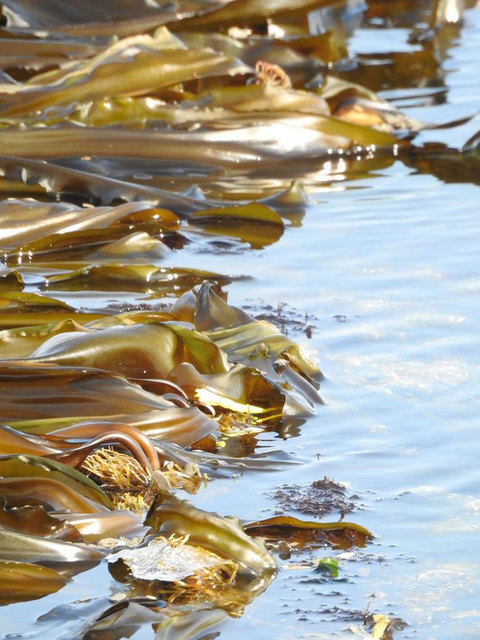季節の食材とその由来や歴史、食にまつわるお話をご紹介します。
プーアル茶・発酵茶・黒茶・ダイエット

熟成年数が上がるほどに、深みや旨味が増すプーアール茶。
後発酵製法で作られ、発酵度が高くなるほどより美味しく健康維持に適切なお茶になるそう。
麹菌で発酵させるビンテージはお値段もナカナカですが、自身で煮出して持って歩くと、効能もひとしおです。
ウーロン茶と並んだダイエット茶として有名なプーアル茶は、緑茶を発酵させた発酵黒茶。
この発酵途中で生成される重合型カテキンが、脂肪のつきにくいスッキリボディーへと導いてくれます。
プーアール茶は脂肪を溶かす作用があり、お皿の油汚れも落とすほどです。
プーアル茶を野菜スープにしたり、豚の煮込み料理に加えて煮るとさっぱりした煮豚になりヘルシー。
ですが、何でも摂取しすぎはいけません、胃腸が弱い方はほどほどにします。
ひじき・ひじきの梅煮
いつものひじき煮のお味をほんの少し薄めにし、酢に浸して戻したぷっくりした梅干しを入れて炊いてみてください。
肝機能が低下しがちなこの季節は、梅が心地よいアクセントになって疲れをとります。
酢が梅干しの塩気を和らげ、ひじきに含まれるカルシュウムの吸収をよくする。
ひじきは血を補うので、血行をよくして乾燥肌や抜け毛などにも・・・
豊富なカルシュウムやマグネシュウム、鉄分は貧血や骨粗症予防によく、繊維は便通を促します。
干しシイタケのビタミンDもカルシュウムの吸収を助けるので加えてもよいですね。
発酵食・鰹節(かつおぶし)・おかか焼き飯
鰹節にはグレードがあり、4回以上良質のカビ付け工程を繰り返して天日干ししたものが本枯鰹節になります。
お出汁は澄んでいても旨みが深い。
鰹節は生鰹の水分を徹底的にぬいて乾燥させ、栄養分を凝縮させて保存性を高めたもの。
ビタミン類、カリウム、ミネラルなどと、体内では合成できない必須アミノさん9種類の全てと、ストレスに良い物質のトリプトファンを含む。
ギャバ(脳をリラックスさせる)が豊富な、ぬか付けと合わせれば、リラックスする効果がより高くなります。
昔から食されている当たり前の日本の食卓風景ですね。おかか焼き飯美味しいですよ。
炒めたごはんにすりごま、ミツバ、おかかをたっぷり加え炒め、塩、ナンプラー、醤油で味付けする。
八丁味噌・豆味噌
大豆と塩のみで作られる豆味噌。
長期熟成させるので硬めで赤黒い色をしており、愛知県岡崎市が有名です。
江戸時代に徳川家康発祥の地である岡崎城から西へ八丁離れた味噌蔵で作られていたので、八丁味噌と呼ばれています。
戦国時代には小さく丸めたものを、陣中食として腰袋に入れて携帯していたそう。
三河地方では沿岸の吉良の塩と、矢作大豆が手に入りやすかったので豆味噌になりました。
味噌煮込料理などは三河味醂と調理されますね。
コクがあるので鯖の味噌煮などにも適しています。
栄養価が高く皮膚の再生力も期待できる豆味噌。
油焼きしたなすの赤だし味噌汁は我が家の夏の鉄板です。
杏(あんず)

ほんのり甘い香りに気づいて見上げると、杏の実がたわわ。
杏のやわらかな色合いを目にすると幸福感が生まれます。
完熟杏は香りよく果肉も食べやすい、旬が短いので見かけるたびに堪能します。
杏酒にしてもドライフルーツにしてもいいもの。
半分に割って種を取り、低温のオーブンか果物乾燥機でセミドライにした杏を作ります。
黄色いパプリカとオリーブオイルで蒸し焼きにして冷ませば、お互いの良いところがきわだった鮮やかな冷製サラダになります。
杏はカロチンが非常に豊富で、粘膜をうるおす効能があり、種の中身(仁)は漢方薬の原料の杏仁です。
杏仁豆腐でも有名ですね(生では食べられません)。
白きくらげは肺を潤す食材と言われていますが、氷砂糖と1時間半ほどゆっくり煮てトロトロにし、そこへ杏仁の粉を加えると咳にもよい美味しいデザートになります。
冷たくても温かくてもおすすめです。
生クリームなどお好みで加えてください。
茄子(なす)

茄子に含まれるナスニンの色素はポリフェノールの一種で抗がん作用や、体の余分な熱をとる効果が期待できます。
真っ黒になるまで炭焼きにしたものは歯茎の腫れに良いとされ、ペーストになって市販もされていますね。
丸々使える野菜です。
お料理としては、炒め茄子は多めの油で焼くと美味しいですが、カロリーが気になります。
塩もみしてから調理すると少ない油でも火の通りがよくなります。
焼きなすは香ばしい香りと、ふんわりした口当たりが身上、生姜じょうゆとおかかで美味しいですね。
人数が多い時の焼きなすの作り方です。
皮をむいて1本ずつラップでくるみレンジに2分ほどかけます。
後は熱した魚焼きグリルで、全体に焦げ目がつくまでゆっくり焼けば、とろりと美味しい焼きなすを皆さん揃っていただけます。
ヨーグルト・冷製スープ・発酵食
ヨーグルトの本場、ブルガリアの冷たいヨーグルトスープ・タラトル。
風邪をひいたり、体調が悪い時にもヨーグルトを食べる風習のあるブルガリア。
手作りも当たり前で、日常的にたっぷり料理に使います。
きゅうり1本分の皮をところどころ剥いて粗みじん切りにし、オイル大さじ1、おろしにんにく、クミン、レモン果汁各少々とヨーグルト2カップを加え混ぜ、牛乳や水1カップくらいで飲みやすく伸ばし、塩、胡椒で味を整えます。
冷蔵庫で冷やして器によそい、オイルをさらにひと垂らし。
柔らかいディルを添えるとより本場風になります。
ヨーグルトは発酵食ですが、グッと腸に効かすには野菜の食物繊維、ビタミン、良質のオイルと共に摂取することが大切です。
お腹に効くスープ、旬の野菜や好みのスパイスを加えてもいいですね。
梅(うめ)ビネガーシロップ

南高梅です。
洗ってザルに置くのですが、甘酸っぱい香りが部屋中に充満します。
梅のビネガーシロップ=梅1kgは傷があるものは除き、3時間ほど水につけてアク抜きをし、ヘタを竹串などで取って水気をしっかり拭いて下処理。
消毒した保存瓶に氷砂糖500gの半量を入れ、梅を入れてりんご酢をかぶるくらいに注ぎ、残りの氷砂糖を散らす。
酢から梅が出ないようにラップをかぶせる。甘みはお好みで足す。
1週間位は1日に1回やさしくふる、完熟梅なので1,2週間位い寝かせると出来上がりです。
ソーダやミルク割り、香りのよい酢の物やお料理に最適、素麵つゆに少し加えても。
疲れがパッと消えます。