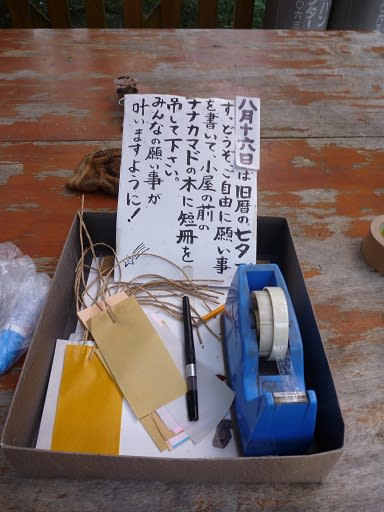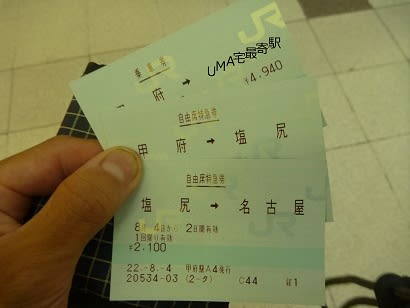山行日:2010年8月23日(月)~26日(木)
山行者:UMA単独
コースタイム:
1日目 自宅4:30=新穂高P7:42/7:50…わさび平9:04~9:10…
鏡平山荘12:10~12:25…弓折岳13:34…双六山荘14:41(テン泊)
2日目 双六山荘3:00(起床)/4:40…双六岳5:11~5:20…三俣蓮華岳6:18~6:25…
三俣山荘6:59~7:05…鷲羽岳8:21~8:31…ワリモ岳8:59…ワリモ分岐9:17~9:25…
水晶小屋10:53…水晶岳10:28…水晶岳11:00~11:20…祖父(じい)岳12:24~12:34…
雲ノ平山荘13:10~13:30…雲ノ平CP場13:50(テン泊)
3日目 雲ノ平CP場4:00(起床)/5:00…アルプス庭園5:29…奥日本庭園5:42…
アラスカ庭園6:02…雲ノ平分岐6:31…奥スイス庭園6:59…高天原峠7:31…
高天原山荘8:11…夢ノ平8:34~8:45…高天原温泉8:58~9:30…高天原山荘9:45…
高天原峠10:20~10:30…(休憩)11:21~11:31…雲ノ平山荘11:44~12:09…
雲ノ平CP場12:15~12:47…スイス庭園13:00~13:20…雲ノ平CP場13:30(テン泊)
4日目 雲ノ平CP場3:00(起床)/5:26…(休憩)6:24~6:35…渡渉点6:55…
三俣山荘7:24~7:40…(休憩)8:45~9:00…双六山荘9:37~9:50…
鏡平山荘11:05~12:03…(休憩)12:49~13:00…わさび平小屋14:05~14:30…
新穂高P15:33=温泉(中崎山荘 奥飛騨の湯)15:40~16:30=自宅20:00
日本最後の秘境といわれる雲ノ平、秘湯中の秘湯といわれる高天原温泉へ新穂高からピストンした。
天気は四日とも晴れで大きく崩れることはなくとてもいい山行となった。
≪一日目≫晴れ時々くも一時雨
月曜出発としたのは混雑を避けるため、
新穂高まではマイカーでのアプローチとなるが
駐車場は市営の無料駐車場にしたいと考えていた。
盆休明けの月曜からなら駐車場は空いているだろう
という考えでいたが、到着してみて考えが甘いことに気付かされた。
無料駐車場はほぼ満車状態。数台の空きしかなく、

(150台停めることができるそうですが…)
何とか停めることはできたが平日でありながら登山者と観光客の多さに驚かされた。
ちなみにロープウエイ駅近くの有料駐車場はガラガラ、
やはり皆さんちょっとでも節約しようとのことなのですね。
僕も4日間停めることとなるので有料だと駐車料がばかになりません。
新穂高バス停横のトイレで用を済ませ、歩きだします。
晴れ渡った空、視界に入る高い山は笠ヶ岳でしょうか、

左岸から右岸へ、そして右岸から左岸へ橋を二つ渡ると間もなくゲート、

ゲートの横をすり抜け登りらしい登りとなる小池新道登山口までは緩やかな林道歩きとなります。
盆休明けの平日ともあろうに老若男女登山者が多いことに驚かされます。
ゲートから50分ほどでわさび平小屋、わさびと関係があるのかな?と思いつつ休憩をします。

小屋脇には木の水槽?のなかにキュウリやトマトといった野菜、
りんごにオレンジ、大きなスイカまで浮かべ冷やされています。

とても美味しそうですが帰りに頂くことにします。
トイレと給水を済ませ再び林道歩き、20分強で小池新道登山口に到着です。


ここからは弓折乗越までずーっと登り、道は沢伝いに登っていき
途中からトラバースしP2303と弓折岳の間へ入っていくように見えます。
実際はその先に鏡平山荘があり、そこまでは一頑張りです。
小池新道登山口から40分程で秩父沢に掛けられた橋を渡ります。
秩父沢は真っ白な石で埋め尽くされており、冷たくてきれいな水が流れています。

秩父沢は上部で左手へ曲がっていきますが、
そのまままっすぐ上に目をやると大ノマ岳が目に入ります。

秩父沢から30分弱でチボ岩、大きな黒い石で埋め尽くされた沢?を横切っていきます。

チボ岩を過ぎ20分弱でイタドリヶ原、さらに40分弱でベンチもあるシシウドガ原


どちらも一息つくにはいい場所ですが、
日の光を遮るものがないので木陰のある場所などを捜して休憩を入れることとします。
シシウドガ原からは道は沢伝いからトラバース気味の道へ、少し楽になります。
20分強で熊のおどり場、さらに20分程で鏡平山荘です。

(平日は熊の踊りショーはやってないそうです(嘘))
鏡平山荘の前後には比較的大きな池があり、眺めているとホッとさせてくれます。

(山荘手前にある池、お弁当広げたくなります)

(山荘です)

(山荘を越えたところにある池です)
登山口から3時間弱の登りでヒートアップしてしまった身体に
ベストフード?鏡平山荘名物かき氷です。

かき氷、久しく食べてない様な気がします。
こんなところでかき氷が食べられるなんてほんとありがたいです。
夢中で食べていると、頭がキーンときました。
かき氷でクールダウンしたらあと1時間程の登りで弓折乗越、
弓折岳へはちょいちょいなのでザックをデポして向かいます。
山頂特に何もないようなところでした。

(通過点っぽい感じ)
弓折乗越まで戻り再びザックを背負い双六小屋へ向かいます。
双六小屋までは1時間程、小ピークを幾つか越えて行きます。
一つ目のピークにさしかかった時とんでもないことが。
右斜面からハアハアという鳴き声?を発しながら黒いモノが斜面を上がってきます。
え?ナニナニ??とドキドキしながら立ち止まっていたら黒いモノが登山道に出ました。
その黒いモノとは熊!!僕との距離は10mくらいしかありません。
もう完全に体が固まってしまいましたね、まさかこんな所でお会いするとは…。
で、熊さんこちらの存在に気付いたらしくチラッとこっちを見ました。
その時が一番怖かったかな、時間が止まってしまったような気がしました。
熊さん、僕の方をチラッと見たら僕が向かっている方へ登山道をダダダダッと走っていきまして、
左斜面のハイマツを掻き分けながら下りて行ってしまいました。
暫く斜面を下っていく熊さんを見ていましたが、
ハッと我に帰り大分下まで行ってしまった熊さんという脅威が
去って安全であろうことを祈って先を進みました。
体長は1mくらいあったでしょうか。
もうね、ホント怖かったね、
再び歩き出した後も熊がまた斜面を登ってきて
後ろから襲ってきたらどうしようとか考えてしまいました。
途中で出会った登山者に話したらかなりびっくりしてましたね、そりゃそうか。
登山道は双六小屋の手前で右に山を見ながらトラバース気味に下っていきます。
やがて木道となり左手に池、奥に双六小屋の屋根が見えてきました。
双六小屋はちょうどコルに建っていて双六岳と樅沢岳に挟まれている感じ。

(奥に見えるは双六岳東の肩)
受付を済ませ缶ビールを買ってテント場へ。
風がひっきりなしに吹いて設営しづらいなかなんとかテントを張って中に潜る。
北アルプスは南アルプスより人気があるのだろう、
平日だというのにテントの数が多かった。小屋泊まりの人も結構多いみたいだ。

多いといえば山ガールも多い、南アルプスより圧倒的に多い、里山と比べたら…。
夏休みなのでどこかの大学の山岳部かワンゲルが2・3グループいた。
元気がいいというかやけに騒がしかった。
夕方からゴロゴロっときてパラパラッとしたが大して降ることはなく星空を見ることが出来た。
満月に近い月が出ていて明るすぎて天の川までは見ることが出来きなかった。


(小屋とカシオペア)
≪二日目≫晴れ時々くも一時雨
夜が明けきらない四時頃、お隣の大学山岳グループは
早々にテントを撤収し出発の準備をしていた。
僕も今日は行程が長いので三時には起きて夜明け前には出発。
東の空はオリオン座を見ることはできた。
まだまだ下界は残暑の中、
山の上でも徐々に秋に近付いているというのに星空はもう冬支度をしているようだ。
双六小屋から双六岳へは急登から始まる、朝一番にこれはかなり応える。
振り向くと東の地平線あたりが赤く燃え始めている、そろそろ日の出か。
急登を登り詰めつと、緩やかな弧をかいてはいるが、
ほぼ平らな場所を道がまっすぐ双六岳山頂に延びている。山の上にしては珍しい地形だ。

山頂直下のちょっとした岩場をひょいひょいと上がっていくと双六岳山頂。
今日初めての登頂を喜んでいると山頂に居た人から“日が出るよ”との声。
振り向いて見るとちょうど地平線から太陽が昇ってくるところだった。

山で見る日の出は去年の富士山以来か、
あの時は八合目小屋前からだったから山頂からの御来光は初めてかもしれない。
なんて綺麗なのだろうと思った。
やや寒かったが日の出に見とれて暫くそのままじっとしていた。
双六岳山頂からは360°よく見渡せる。
朝早いからまだ雲が湧きおこってこず山と山の間でおとなしくしているようだから眺望がよい。

(双六岳の頂から見た槍ヶ岳)
こうやってみると北アルプスの山もずいぶん大きいように見える。
南アルプスの山は一個一個大きいのだが、
ここから見た北アルプスでも黒部源流の山々は大きく見えた。
槍ヶ岳から西穂高に続く山はピークが乱立して
何かごちゃごちゃしている感じがするのだが、
北アルプスの山々がすべてそうではないのであると思い知った。
といってもこれも食わず嫌いみたいなものなので
登ってしまえば心底惚れ込んでしまうかもしれないからなんとも言えないのだが。
双六岳からは三俣蓮華岳へ向かう、間に丸山という山がある。
標高でいえば三俣蓮華岳よりわずかに高い、しかし山頂には標柱も何もなくちょっと寂しい。
少し下ってまた少し登り返せば、三俣蓮華岳山頂。
ここは三方向に稜線が伸びているから三俣なのだろうか、
蓮華岳というのは北アルプスにもう一つあるが
蓮華という名になんとなく惹かれる。岐阜県の花だから?
頂から北東に目をやると鷲羽岳、
なんとなく南アルプスの駒津峰から見た甲斐駒を思い出させる山容だ。
尾根道を登っていくようだが上の方はずいぶん険しいように見える。
一旦、三俣山荘まで下る。ハイマツの中に埋もれているような小屋だ。

(三俣山荘と鷲羽岳)

(鷲羽岳寄りから見た三俣山荘、ハイマツに埋もれる!?奥は三俣蓮華岳)
名物がサイフォン式コーヒーで、飲んでみたかったが
四日目の復路でまた寄るのでその時にしようとこの時は思っていたのだが、
後からそれは間違った判断だと気付いた。
三俣山荘からハイマツ生える道をやや下ってから鷲羽岳へ登り返す。

(かっこいいです)
中腹まではやや緩やかであるが、中腹から上は岩場の連続だ。
CT一時間半だが時間通り辿り着けるだろうか?
実際登ってみると下から見上げた時程険しい感じでもなく
三点支持の必要もないくらいで振り返るとちょっとスリルがあるかな?という感じだ。
ほとんどCT通りに山頂に立つことができた。
頂から南側を覗くと鷲羽池が見える、

周りを外輪山で囲まれていたからここは火山で池は火口湖なのだろうか?
そういえば三俣山荘付近で硫黄臭を感じた。
鷲羽岳から急な坂道を下って登り返すとワリモ岳、ここは山頂直下が結構急だ。
三点支持というかクライミングに近い感じで登った。
実をいうと山頂直下で道を見失って強引に登った。
山頂には足跡はあったが標柱とかそれらしいものはなかった。

(ワリモ岳の頂です)
後から聞いたらこの山は巻くらしい。
ということはかなり強引に登頂したということか、
しかし山頂の砂地には踏み跡はあったので結構登られていると思うのだが。
ワリモ岳から下っていくと分岐に出る、まんまワリモ分岐。
祖父(じい)岳への道と水晶岳・野口五郎岳への道へとに別れている。
今日の目的地は祖父岳を越えた雲ノ平だが
分岐から水晶岳へピストンしたいのでザックをデポして
サブザックに貴重品と水とカメラを入れ水晶岳へ向かうことにする。
よく見たらザックが幾つかデポしてある。
分岐で休憩している人に聞いたら、水晶岳や野口五郎岳をピストンする人だという。
みんな考えていることは同じか。
サブザックは当然だが大して入ってないので相当軽い、
軽過ぎてしばらくはバランスがとれずに前後へフラフラした。
軽さに慣れたらなんだか嬉しくなってきた。空をも飛べてしまえそうだ。
水晶小屋を過ぎると前方には波打ったよう岩の小ピークが水晶岳頂までつづく、

道はピークの左手に付いており道に左側は所々切れ落ちておりまともに見ると足がすくみそうだ。
ちょっとしたハシゴやロープが掛かっているところもあり、慎重に進む。
山頂は狭くやや細長い。高度感は素晴らしいがあまり長居したい感じではない。

(水晶岳から南の方向を望む)

(真ん中の台地が雲ノ平)
一人っきりの山頂で自分撮りして証拠写真を撮ったらさっさと下山を開始した。
水晶小屋へ寄って昼飯、カップヌードルと三ツ矢サイダーを頂く。

まだ先はあるからビールという炭酸飲料は我慢、三ツ矢サイダーで我慢する。
といっても三ツ矢サイダー大好きなので全然我慢でも何でもないですが。
カップヌードルを食い終わった頃、小屋のオネーサンに土間に避難してくださいと言われる。
何事かと思ったら荷揚げのヘリがやってくるということだ。
ザックも何も吹き飛ばされるということなので、
周りの人間は食べているものやら何やら持って小屋の中の土間に一時避難。
小屋のドアもそうだが窓もきっちり閉める程の備えよう、
小屋のオネーサンはヘルメットとゴーグルをして外でヘリが来るのを待機していた。
すぐに荷を吊るしたヘリがやってきた。
ものすごいスピードで飛んでくる。

小屋前のわずかなスペースに荷を下ろすとのことだが、
ホントに狭いスペースでそんなこと出来るのかと自分も含め周りは興味津々。
目と同じ高さにあるヘリから吊るされた荷が迫ってくる。

(ズーム写真じゃないです)
この勢いだと小屋にぶつかる!!
そう思っていたがすぐさま減速、
ホントうまい具合で小屋の前に荷がポトッと落とされた(置かれた?)。
その一部始終を見て感動したが、
ヘリによる巻き上げの風も凄かった、
まるで外は砂嵐のようである。

(この写真からあの凄さはわかりませんが…)
小屋のドアや窓の隙間から砂埃が入ってくる。
そとで荷揚げに対応している小屋のオネーサンは
慣れた手つきで小屋から下界へ下ろす荷をヘリに付け、
ヘリはあっという間に下界へと飛び去っていった。

(あっという間に行ってしまいました)
もう大丈夫ですよと小屋のオネーサン、
なんかかっこよかったですね
見た感じ痩せていてそれ程頼りがいがありそうではないように見えましたが
(失礼!!女の子に頼りがい求める男なんてダメダメ!?)
凄いですね、女の子だからって小屋で働くのは逞しくないとだめなようです。
ただ山が好きなだけでは小屋で働くのは厳しいかもしれませんね。
水晶小屋からワリモ分岐へ戻ります。ザックの方は無事でした。
水晶小屋でカップヌードル食べていたときに喋っていた
山ガールの子がワリモ分岐に先に着いていました。
いろいろ話を伺うと、単独テント泊縦走で烏帽子から入って新穂高へ抜けるそうで、
相当行動力あるような感じの子でした。
荷の方は軽量化に気を使っているそうで、
どれだけ長期でも15kgは超えないと語っていました。
これには驚きです。
僕は余計なものを持ってきているので重いですが水抜きでも19kgあります。
この子は僕とルートは違いますが、
3泊4日でテント・水・食糧他もろもろで最大15kgくらいにしかならないと言っていましたから、
僕がいかに余計なものを持ってきていて、軽量化に力を入れてないか丸分かりでした。
今回も?地図に“夏遅くまで登山道上に雪渓あり”
というところが書いてあったのでアイゼンを用意、12本爪なので1kg近くあります。
この子に聞いたら“出発前にルート上の小屋に電話してアイゼン必要か聞いたから持ってきてない”と言われてしまいました。
うーん、確かに…納得。
それが常識なのかも!?ちょっと僕はそこら辺が至らずといった感じでしょうかね。
可愛い子でしたが凄くしっかりしていて逞しく見えました。
それでですね、サブザックからザックに背負い変えた時によろめいて転んでしまったんですが、
ばっちり見られてしまいまして“大丈夫ですか?”と言われてしまいました(涙)
この時“嗚呼、僕はこの子と一緒になれるかもしれない権利!?を完全に失ったな”と思いましたね。
恥ずかしかったです。
その前に“私はイケメンじゃないと嫌なの”って言われるかもしれませんが(笑)
ちょっと寂しかったけどその可愛い子と別れて祖父岳へ向かいます。
祖父岳と書いて“じいだけ”と読みます。

(ジイだけぇ~)
ちなみに雲ノ平の近くには祖母岳がありますが、こちらは“ばあだけ”と読みます。
祖父岳の頂は平らで人丈ほどに高く積まれたケルンがいっぱい。ちょっと異様です。

雲ノ平への下りは大きな黒い石がゴロゴロなところを歩きます。
途中でハイマツの中から出てきたライチョウと出会いました。

(食べるところがいっぱいありそうです)
近くまで寄って撮ろう(捕ろうではなく)と思ったのですがハイマツの中に逃げられてしまいました。(チッ)
分岐まで下りるとあとはほとんど木道歩き。
雲ノ平周辺は植生保護のためか木道が整備されています。

(木土。あれ!?金は?)
乾いていると歩きやすいですが濡れているとトラップとなりそうです。
雲ノ平山荘と雲ノ平キャンプ場は歩いて20分程離れています。
キャンプ場受付には山荘まで行かなければなりませんので
分岐にザックをデポして空身で山荘へ向かいます。
雲ノ平山荘は建て替えたばかりで真新しいく木の匂いがぷんぷんします。
話によるとまだ完全には完成してないそうで、
2階のテラスと壁の断熱材を入れて来年完成だそうです。
雲ノ平まではそうそう来ることはないと思いますがまた立ち寄ってみたいですね。
分岐まで戻ってザックを回収しキャンプ場へ向かいます。
キャンプ場は緩いカール状の地形で眺めが大変良いです。
雲ノ平山荘に水場はありませんがこちらには冷たくておいしい水場があり、トイレもあります。
これほど良いテント場はなかなかないのではないでしょうか。
まあ難点といったら、アブ等の虫が多いのと、
大雨になるとキャンプ場内のあちこちに小さな川が出来てしまいそうなところでしょうか。
水場から流れた水はキャンプ場内を川となって流れていますが、
キャンプサイトのあちこちに水が流れたような跡がいっぱいありましたので
大雨の時とかは大変なことになると予想されます。
この日からだったでしょうか、富山県警のヘリがひっきりなしに飛んでいました。
遭難者が出たか、それとも頻繁にけが人が出ているのかどちらかだろうと思ってましたが、
下山日になって他の登山者から聞いた話では前者でした。
笠ヶ岳から双六辺りまでは目撃されていたのですがその先消息不明とのことでした。
どういう経緯で遭難したかわかりませんが、自分も気を付けなければなりませんね。
山行者:UMA単独
コースタイム:
1日目 自宅4:30=新穂高P7:42/7:50…わさび平9:04~9:10…
鏡平山荘12:10~12:25…弓折岳13:34…双六山荘14:41(テン泊)
2日目 双六山荘3:00(起床)/4:40…双六岳5:11~5:20…三俣蓮華岳6:18~6:25…
三俣山荘6:59~7:05…鷲羽岳8:21~8:31…ワリモ岳8:59…ワリモ分岐9:17~9:25…
水晶小屋10:53…水晶岳10:28…水晶岳11:00~11:20…祖父(じい)岳12:24~12:34…
雲ノ平山荘13:10~13:30…雲ノ平CP場13:50(テン泊)
3日目 雲ノ平CP場4:00(起床)/5:00…アルプス庭園5:29…奥日本庭園5:42…
アラスカ庭園6:02…雲ノ平分岐6:31…奥スイス庭園6:59…高天原峠7:31…
高天原山荘8:11…夢ノ平8:34~8:45…高天原温泉8:58~9:30…高天原山荘9:45…
高天原峠10:20~10:30…(休憩)11:21~11:31…雲ノ平山荘11:44~12:09…
雲ノ平CP場12:15~12:47…スイス庭園13:00~13:20…雲ノ平CP場13:30(テン泊)
4日目 雲ノ平CP場3:00(起床)/5:26…(休憩)6:24~6:35…渡渉点6:55…
三俣山荘7:24~7:40…(休憩)8:45~9:00…双六山荘9:37~9:50…
鏡平山荘11:05~12:03…(休憩)12:49~13:00…わさび平小屋14:05~14:30…
新穂高P15:33=温泉(中崎山荘 奥飛騨の湯)15:40~16:30=自宅20:00
日本最後の秘境といわれる雲ノ平、秘湯中の秘湯といわれる高天原温泉へ新穂高からピストンした。
天気は四日とも晴れで大きく崩れることはなくとてもいい山行となった。
≪一日目≫晴れ時々くも一時雨
月曜出発としたのは混雑を避けるため、
新穂高まではマイカーでのアプローチとなるが
駐車場は市営の無料駐車場にしたいと考えていた。
盆休明けの月曜からなら駐車場は空いているだろう
という考えでいたが、到着してみて考えが甘いことに気付かされた。
無料駐車場はほぼ満車状態。数台の空きしかなく、

(150台停めることができるそうですが…)
何とか停めることはできたが平日でありながら登山者と観光客の多さに驚かされた。
ちなみにロープウエイ駅近くの有料駐車場はガラガラ、
やはり皆さんちょっとでも節約しようとのことなのですね。
僕も4日間停めることとなるので有料だと駐車料がばかになりません。
新穂高バス停横のトイレで用を済ませ、歩きだします。
晴れ渡った空、視界に入る高い山は笠ヶ岳でしょうか、

左岸から右岸へ、そして右岸から左岸へ橋を二つ渡ると間もなくゲート、

ゲートの横をすり抜け登りらしい登りとなる小池新道登山口までは緩やかな林道歩きとなります。
盆休明けの平日ともあろうに老若男女登山者が多いことに驚かされます。
ゲートから50分ほどでわさび平小屋、わさびと関係があるのかな?と思いつつ休憩をします。

小屋脇には木の水槽?のなかにキュウリやトマトといった野菜、
りんごにオレンジ、大きなスイカまで浮かべ冷やされています。

とても美味しそうですが帰りに頂くことにします。
トイレと給水を済ませ再び林道歩き、20分強で小池新道登山口に到着です。


ここからは弓折乗越までずーっと登り、道は沢伝いに登っていき
途中からトラバースしP2303と弓折岳の間へ入っていくように見えます。
実際はその先に鏡平山荘があり、そこまでは一頑張りです。
小池新道登山口から40分程で秩父沢に掛けられた橋を渡ります。
秩父沢は真っ白な石で埋め尽くされており、冷たくてきれいな水が流れています。

秩父沢は上部で左手へ曲がっていきますが、
そのまままっすぐ上に目をやると大ノマ岳が目に入ります。

秩父沢から30分弱でチボ岩、大きな黒い石で埋め尽くされた沢?を横切っていきます。

チボ岩を過ぎ20分弱でイタドリヶ原、さらに40分弱でベンチもあるシシウドガ原


どちらも一息つくにはいい場所ですが、
日の光を遮るものがないので木陰のある場所などを捜して休憩を入れることとします。
シシウドガ原からは道は沢伝いからトラバース気味の道へ、少し楽になります。
20分強で熊のおどり場、さらに20分程で鏡平山荘です。

(平日は熊の踊りショーはやってないそうです(嘘))
鏡平山荘の前後には比較的大きな池があり、眺めているとホッとさせてくれます。

(山荘手前にある池、お弁当広げたくなります)

(山荘です)

(山荘を越えたところにある池です)
登山口から3時間弱の登りでヒートアップしてしまった身体に
ベストフード?鏡平山荘名物かき氷です。

かき氷、久しく食べてない様な気がします。
こんなところでかき氷が食べられるなんてほんとありがたいです。
夢中で食べていると、頭がキーンときました。
かき氷でクールダウンしたらあと1時間程の登りで弓折乗越、
弓折岳へはちょいちょいなのでザックをデポして向かいます。
山頂特に何もないようなところでした。

(通過点っぽい感じ)
弓折乗越まで戻り再びザックを背負い双六小屋へ向かいます。
双六小屋までは1時間程、小ピークを幾つか越えて行きます。
一つ目のピークにさしかかった時とんでもないことが。
右斜面からハアハアという鳴き声?を発しながら黒いモノが斜面を上がってきます。
え?ナニナニ??とドキドキしながら立ち止まっていたら黒いモノが登山道に出ました。
その黒いモノとは熊!!僕との距離は10mくらいしかありません。
もう完全に体が固まってしまいましたね、まさかこんな所でお会いするとは…。
で、熊さんこちらの存在に気付いたらしくチラッとこっちを見ました。
その時が一番怖かったかな、時間が止まってしまったような気がしました。
熊さん、僕の方をチラッと見たら僕が向かっている方へ登山道をダダダダッと走っていきまして、
左斜面のハイマツを掻き分けながら下りて行ってしまいました。
暫く斜面を下っていく熊さんを見ていましたが、
ハッと我に帰り大分下まで行ってしまった熊さんという脅威が
去って安全であろうことを祈って先を進みました。
体長は1mくらいあったでしょうか。
もうね、ホント怖かったね、
再び歩き出した後も熊がまた斜面を登ってきて
後ろから襲ってきたらどうしようとか考えてしまいました。
途中で出会った登山者に話したらかなりびっくりしてましたね、そりゃそうか。
登山道は双六小屋の手前で右に山を見ながらトラバース気味に下っていきます。
やがて木道となり左手に池、奥に双六小屋の屋根が見えてきました。
双六小屋はちょうどコルに建っていて双六岳と樅沢岳に挟まれている感じ。

(奥に見えるは双六岳東の肩)
受付を済ませ缶ビールを買ってテント場へ。
風がひっきりなしに吹いて設営しづらいなかなんとかテントを張って中に潜る。
北アルプスは南アルプスより人気があるのだろう、
平日だというのにテントの数が多かった。小屋泊まりの人も結構多いみたいだ。

多いといえば山ガールも多い、南アルプスより圧倒的に多い、里山と比べたら…。
夏休みなのでどこかの大学の山岳部かワンゲルが2・3グループいた。
元気がいいというかやけに騒がしかった。
夕方からゴロゴロっときてパラパラッとしたが大して降ることはなく星空を見ることが出来た。
満月に近い月が出ていて明るすぎて天の川までは見ることが出来きなかった。


(小屋とカシオペア)
≪二日目≫晴れ時々くも一時雨
夜が明けきらない四時頃、お隣の大学山岳グループは
早々にテントを撤収し出発の準備をしていた。
僕も今日は行程が長いので三時には起きて夜明け前には出発。
東の空はオリオン座を見ることはできた。
まだまだ下界は残暑の中、
山の上でも徐々に秋に近付いているというのに星空はもう冬支度をしているようだ。
双六小屋から双六岳へは急登から始まる、朝一番にこれはかなり応える。
振り向くと東の地平線あたりが赤く燃え始めている、そろそろ日の出か。
急登を登り詰めつと、緩やかな弧をかいてはいるが、
ほぼ平らな場所を道がまっすぐ双六岳山頂に延びている。山の上にしては珍しい地形だ。

山頂直下のちょっとした岩場をひょいひょいと上がっていくと双六岳山頂。
今日初めての登頂を喜んでいると山頂に居た人から“日が出るよ”との声。
振り向いて見るとちょうど地平線から太陽が昇ってくるところだった。

山で見る日の出は去年の富士山以来か、
あの時は八合目小屋前からだったから山頂からの御来光は初めてかもしれない。
なんて綺麗なのだろうと思った。
やや寒かったが日の出に見とれて暫くそのままじっとしていた。
双六岳山頂からは360°よく見渡せる。
朝早いからまだ雲が湧きおこってこず山と山の間でおとなしくしているようだから眺望がよい。

(双六岳の頂から見た槍ヶ岳)
こうやってみると北アルプスの山もずいぶん大きいように見える。
南アルプスの山は一個一個大きいのだが、
ここから見た北アルプスでも黒部源流の山々は大きく見えた。
槍ヶ岳から西穂高に続く山はピークが乱立して
何かごちゃごちゃしている感じがするのだが、
北アルプスの山々がすべてそうではないのであると思い知った。
といってもこれも食わず嫌いみたいなものなので
登ってしまえば心底惚れ込んでしまうかもしれないからなんとも言えないのだが。
双六岳からは三俣蓮華岳へ向かう、間に丸山という山がある。
標高でいえば三俣蓮華岳よりわずかに高い、しかし山頂には標柱も何もなくちょっと寂しい。
少し下ってまた少し登り返せば、三俣蓮華岳山頂。
ここは三方向に稜線が伸びているから三俣なのだろうか、
蓮華岳というのは北アルプスにもう一つあるが
蓮華という名になんとなく惹かれる。岐阜県の花だから?
頂から北東に目をやると鷲羽岳、
なんとなく南アルプスの駒津峰から見た甲斐駒を思い出させる山容だ。
尾根道を登っていくようだが上の方はずいぶん険しいように見える。
一旦、三俣山荘まで下る。ハイマツの中に埋もれているような小屋だ。

(三俣山荘と鷲羽岳)

(鷲羽岳寄りから見た三俣山荘、ハイマツに埋もれる!?奥は三俣蓮華岳)
名物がサイフォン式コーヒーで、飲んでみたかったが
四日目の復路でまた寄るのでその時にしようとこの時は思っていたのだが、
後からそれは間違った判断だと気付いた。
三俣山荘からハイマツ生える道をやや下ってから鷲羽岳へ登り返す。

(かっこいいです)
中腹まではやや緩やかであるが、中腹から上は岩場の連続だ。
CT一時間半だが時間通り辿り着けるだろうか?
実際登ってみると下から見上げた時程険しい感じでもなく
三点支持の必要もないくらいで振り返るとちょっとスリルがあるかな?という感じだ。
ほとんどCT通りに山頂に立つことができた。
頂から南側を覗くと鷲羽池が見える、

周りを外輪山で囲まれていたからここは火山で池は火口湖なのだろうか?
そういえば三俣山荘付近で硫黄臭を感じた。
鷲羽岳から急な坂道を下って登り返すとワリモ岳、ここは山頂直下が結構急だ。
三点支持というかクライミングに近い感じで登った。
実をいうと山頂直下で道を見失って強引に登った。
山頂には足跡はあったが標柱とかそれらしいものはなかった。

(ワリモ岳の頂です)
後から聞いたらこの山は巻くらしい。
ということはかなり強引に登頂したということか、
しかし山頂の砂地には踏み跡はあったので結構登られていると思うのだが。
ワリモ岳から下っていくと分岐に出る、まんまワリモ分岐。
祖父(じい)岳への道と水晶岳・野口五郎岳への道へとに別れている。
今日の目的地は祖父岳を越えた雲ノ平だが
分岐から水晶岳へピストンしたいのでザックをデポして
サブザックに貴重品と水とカメラを入れ水晶岳へ向かうことにする。
よく見たらザックが幾つかデポしてある。
分岐で休憩している人に聞いたら、水晶岳や野口五郎岳をピストンする人だという。
みんな考えていることは同じか。
サブザックは当然だが大して入ってないので相当軽い、
軽過ぎてしばらくはバランスがとれずに前後へフラフラした。
軽さに慣れたらなんだか嬉しくなってきた。空をも飛べてしまえそうだ。
水晶小屋を過ぎると前方には波打ったよう岩の小ピークが水晶岳頂までつづく、

道はピークの左手に付いており道に左側は所々切れ落ちておりまともに見ると足がすくみそうだ。
ちょっとしたハシゴやロープが掛かっているところもあり、慎重に進む。
山頂は狭くやや細長い。高度感は素晴らしいがあまり長居したい感じではない。

(水晶岳から南の方向を望む)

(真ん中の台地が雲ノ平)
一人っきりの山頂で自分撮りして証拠写真を撮ったらさっさと下山を開始した。
水晶小屋へ寄って昼飯、カップヌードルと三ツ矢サイダーを頂く。

まだ先はあるからビールという炭酸飲料は我慢、三ツ矢サイダーで我慢する。
といっても三ツ矢サイダー大好きなので全然我慢でも何でもないですが。
カップヌードルを食い終わった頃、小屋のオネーサンに土間に避難してくださいと言われる。
何事かと思ったら荷揚げのヘリがやってくるということだ。
ザックも何も吹き飛ばされるということなので、
周りの人間は食べているものやら何やら持って小屋の中の土間に一時避難。
小屋のドアもそうだが窓もきっちり閉める程の備えよう、
小屋のオネーサンはヘルメットとゴーグルをして外でヘリが来るのを待機していた。
すぐに荷を吊るしたヘリがやってきた。
ものすごいスピードで飛んでくる。

小屋前のわずかなスペースに荷を下ろすとのことだが、
ホントに狭いスペースでそんなこと出来るのかと自分も含め周りは興味津々。
目と同じ高さにあるヘリから吊るされた荷が迫ってくる。

(ズーム写真じゃないです)
この勢いだと小屋にぶつかる!!
そう思っていたがすぐさま減速、
ホントうまい具合で小屋の前に荷がポトッと落とされた(置かれた?)。
その一部始終を見て感動したが、
ヘリによる巻き上げの風も凄かった、
まるで外は砂嵐のようである。

(この写真からあの凄さはわかりませんが…)
小屋のドアや窓の隙間から砂埃が入ってくる。
そとで荷揚げに対応している小屋のオネーサンは
慣れた手つきで小屋から下界へ下ろす荷をヘリに付け、
ヘリはあっという間に下界へと飛び去っていった。

(あっという間に行ってしまいました)
もう大丈夫ですよと小屋のオネーサン、
なんかかっこよかったですね
見た感じ痩せていてそれ程頼りがいがありそうではないように見えましたが
(失礼!!女の子に頼りがい求める男なんてダメダメ!?)
凄いですね、女の子だからって小屋で働くのは逞しくないとだめなようです。
ただ山が好きなだけでは小屋で働くのは厳しいかもしれませんね。
水晶小屋からワリモ分岐へ戻ります。ザックの方は無事でした。
水晶小屋でカップヌードル食べていたときに喋っていた
山ガールの子がワリモ分岐に先に着いていました。
いろいろ話を伺うと、単独テント泊縦走で烏帽子から入って新穂高へ抜けるそうで、
相当行動力あるような感じの子でした。
荷の方は軽量化に気を使っているそうで、
どれだけ長期でも15kgは超えないと語っていました。
これには驚きです。
僕は余計なものを持ってきているので重いですが水抜きでも19kgあります。
この子は僕とルートは違いますが、
3泊4日でテント・水・食糧他もろもろで最大15kgくらいにしかならないと言っていましたから、
僕がいかに余計なものを持ってきていて、軽量化に力を入れてないか丸分かりでした。
今回も?地図に“夏遅くまで登山道上に雪渓あり”
というところが書いてあったのでアイゼンを用意、12本爪なので1kg近くあります。
この子に聞いたら“出発前にルート上の小屋に電話してアイゼン必要か聞いたから持ってきてない”と言われてしまいました。
うーん、確かに…納得。
それが常識なのかも!?ちょっと僕はそこら辺が至らずといった感じでしょうかね。
可愛い子でしたが凄くしっかりしていて逞しく見えました。
それでですね、サブザックからザックに背負い変えた時によろめいて転んでしまったんですが、
ばっちり見られてしまいまして“大丈夫ですか?”と言われてしまいました(涙)
この時“嗚呼、僕はこの子と一緒になれるかもしれない権利!?を完全に失ったな”と思いましたね。
恥ずかしかったです。
その前に“私はイケメンじゃないと嫌なの”って言われるかもしれませんが(笑)
ちょっと寂しかったけどその可愛い子と別れて祖父岳へ向かいます。
祖父岳と書いて“じいだけ”と読みます。

(ジイだけぇ~)
ちなみに雲ノ平の近くには祖母岳がありますが、こちらは“ばあだけ”と読みます。
祖父岳の頂は平らで人丈ほどに高く積まれたケルンがいっぱい。ちょっと異様です。

雲ノ平への下りは大きな黒い石がゴロゴロなところを歩きます。
途中でハイマツの中から出てきたライチョウと出会いました。

(食べるところがいっぱいありそうです)
近くまで寄って撮ろう(捕ろうではなく)と思ったのですがハイマツの中に逃げられてしまいました。(チッ)
分岐まで下りるとあとはほとんど木道歩き。
雲ノ平周辺は植生保護のためか木道が整備されています。

(木土。あれ!?金は?)
乾いていると歩きやすいですが濡れているとトラップとなりそうです。
雲ノ平山荘と雲ノ平キャンプ場は歩いて20分程離れています。
キャンプ場受付には山荘まで行かなければなりませんので
分岐にザックをデポして空身で山荘へ向かいます。
雲ノ平山荘は建て替えたばかりで真新しいく木の匂いがぷんぷんします。
話によるとまだ完全には完成してないそうで、
2階のテラスと壁の断熱材を入れて来年完成だそうです。
雲ノ平まではそうそう来ることはないと思いますがまた立ち寄ってみたいですね。
分岐まで戻ってザックを回収しキャンプ場へ向かいます。
キャンプ場は緩いカール状の地形で眺めが大変良いです。
雲ノ平山荘に水場はありませんがこちらには冷たくておいしい水場があり、トイレもあります。
これほど良いテント場はなかなかないのではないでしょうか。
まあ難点といったら、アブ等の虫が多いのと、
大雨になるとキャンプ場内のあちこちに小さな川が出来てしまいそうなところでしょうか。
水場から流れた水はキャンプ場内を川となって流れていますが、
キャンプサイトのあちこちに水が流れたような跡がいっぱいありましたので
大雨の時とかは大変なことになると予想されます。
この日からだったでしょうか、富山県警のヘリがひっきりなしに飛んでいました。
遭難者が出たか、それとも頻繁にけが人が出ているのかどちらかだろうと思ってましたが、
下山日になって他の登山者から聞いた話では前者でした。
笠ヶ岳から双六辺りまでは目撃されていたのですがその先消息不明とのことでした。
どういう経緯で遭難したかわかりませんが、自分も気を付けなければなりませんね。