現状、「子供の情景」でヤバそうな曲といったら
第2曲 不思議なお話 (Kuriose Geschichte)
第3曲 鬼ごっこ (Hasche-Mann)
第5曲 十分に幸せ (Gluckes genug)
第7曲 トロイメライ(夢) (Traumerei)
第8曲 暖炉のそばで (Am Kamin)
第9曲 木馬の騎士 (Ritter vom Steckenpferd)
…えっ、多い(o_o;;
 ←急がば回れ。木馬がなかなか走り出さない
←急がば回れ。木馬がなかなか走り出さない
とゆうわけでちょっとは工夫をして練習しないと(汗)
何度漫然と弾いてもちっとも整ってこない(成功率の上がらない)曲の練習方法というとやはり
ゆっくり練習
かなと思うのですが、
「シャンドールピアノ教本 身体・音・表現」で昨日読んだ個所にあったのが
「テンポにムラのある練習こそ効率的だ」
というもの。
ゆっくり練習が非常に役に立つものであることは論をまたないとして…
どんなパッセージにも、どんな音にも、十分な時間をかけつつ進むことを考えると、
もし、ある一番難しい個所に対してそこにふさわしいテンポで弾き、
かつその一定のテンポで通すということにすると全体ではめっちゃ時間がかかるわけで、
それぞれの個所について
「自分の欲する動作を完全にコントロールできる限りにおいて」
最も速いテンポで練習せよ、
つまりテンポはムラだらけになるのだけど
「個々の音にそれぞれ必要とされるテンポを正しく見て取ることは絶えざる注意力の産物であり、これこそ知的な練習をしている歓迎すべき兆候」
一方、
「哀れな犠牲者に何から何まで機械的に同じテンポで弾かせる機械的練習」
は時間の無駄遣いだというわけ。
んーーー
でもそういえば、前にバイオリンの初心者アンサンブルとかやってたときに、
なんでだかどうしてもズレちゃう問題
というのがあって、その原因を追究してみたらば、
この融通無碍な練習法が間違いの元だというのがあったんですよ。
たとえば「1、2、3、4」と四拍分が一小節だったとして、自分のパートは「1、2」と伸ばして「3、4」と休みだったとするでしょ。それで、ひとりでれんしゅうするときに「3、4」とだまって数えてるのは時間の無駄だというわけでいつも「1、2 (すっと次の小節にジャンプ) 1、2、…」てなことをやってたらしいの。
したら、みんなと合わせるときにもそうやって弾く習慣になっちゃって(o_o)
ずれるってばそれは…
(休符だけじゃなくて長い音符を縮めることまでしてた模様)
まぁそこまで極端な人は少ないだろうけれども、人前演奏のときにも微妙にテンポキープできてない(お指の都合で速くなったり遅くなったりするとか、長い音符を十分伸ばしていないとか)人はけっこういるしね。案外、普段の習慣って怖いものだと思う。
まぁたぶん、シャンドール先生の周囲は音大生とかちゃんとした人ばっかりであまりそんな心配はしたことないのかもしれないけど。artomr先生は逆に、ゆっくり練習するときもきーっちり行くように強く勧める派ですね。
私はやっぱり、ゆっくり練習するなら一定テンポでやるのが安全かなと思うんです。長い曲をゆっくりで通したらたいへんだけど、「子供の情景」の一曲分とかスグだしね。長い曲でも部分に分ければいいわね。
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)
←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
第2曲 不思議なお話 (Kuriose Geschichte)
第3曲 鬼ごっこ (Hasche-Mann)
第5曲 十分に幸せ (Gluckes genug)
第7曲 トロイメライ(夢) (Traumerei)
第8曲 暖炉のそばで (Am Kamin)
第9曲 木馬の騎士 (Ritter vom Steckenpferd)
…えっ、多い(o_o;;
とゆうわけでちょっとは工夫をして練習しないと(汗)
何度漫然と弾いてもちっとも整ってこない(成功率の上がらない)曲の練習方法というとやはり
ゆっくり練習
かなと思うのですが、
「シャンドールピアノ教本 身体・音・表現」で昨日読んだ個所にあったのが
「テンポにムラのある練習こそ効率的だ」
というもの。
ゆっくり練習が非常に役に立つものであることは論をまたないとして…
どんなパッセージにも、どんな音にも、十分な時間をかけつつ進むことを考えると、
もし、ある一番難しい個所に対してそこにふさわしいテンポで弾き、
かつその一定のテンポで通すということにすると全体ではめっちゃ時間がかかるわけで、
それぞれの個所について
「自分の欲する動作を完全にコントロールできる限りにおいて」
最も速いテンポで練習せよ、
つまりテンポはムラだらけになるのだけど
「個々の音にそれぞれ必要とされるテンポを正しく見て取ることは絶えざる注意力の産物であり、これこそ知的な練習をしている歓迎すべき兆候」
一方、
「哀れな犠牲者に何から何まで機械的に同じテンポで弾かせる機械的練習」
は時間の無駄遣いだというわけ。
んーーー
でもそういえば、前にバイオリンの初心者アンサンブルとかやってたときに、
なんでだかどうしてもズレちゃう問題
というのがあって、その原因を追究してみたらば、
この融通無碍な練習法が間違いの元だというのがあったんですよ。
たとえば「1、2、3、4」と四拍分が一小節だったとして、自分のパートは「1、2」と伸ばして「3、4」と休みだったとするでしょ。それで、ひとりでれんしゅうするときに「3、4」とだまって数えてるのは時間の無駄だというわけでいつも「1、2 (すっと次の小節にジャンプ) 1、2、…」てなことをやってたらしいの。
したら、みんなと合わせるときにもそうやって弾く習慣になっちゃって(o_o)
ずれるってばそれは…
(休符だけじゃなくて長い音符を縮めることまでしてた模様)
まぁそこまで極端な人は少ないだろうけれども、人前演奏のときにも微妙にテンポキープできてない(お指の都合で速くなったり遅くなったりするとか、長い音符を十分伸ばしていないとか)人はけっこういるしね。案外、普段の習慣って怖いものだと思う。
まぁたぶん、シャンドール先生の周囲は音大生とかちゃんとした人ばっかりであまりそんな心配はしたことないのかもしれないけど。artomr先生は逆に、ゆっくり練習するときもきーっちり行くように強く勧める派ですね。
私はやっぱり、ゆっくり練習するなら一定テンポでやるのが安全かなと思うんです。長い曲をゆっくりで通したらたいへんだけど、「子供の情景」の一曲分とかスグだしね。長い曲でも部分に分ければいいわね。
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社










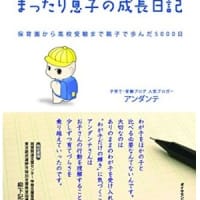



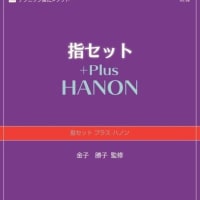







>まぁそこまで極端な人は少ないだろうけれども、
いえ、実はこれ、少なくないどころか、大ありなんです。
休符を端折るまではしなくても、(^^;)
次の音は3倍伸ばすべきところを2.5倍くらいで次へ行っちゃったり、音楽が変わるといちいちテンポが変わるとかね。
シャンドール先生の周囲はよほど時間感覚の優秀な方ばかりなのでしょうけれど、
私も昔、不安定テンポ練習でテンポ感が変になった苦い経験があるので、
シャンドール先生よりアンダンテさん式が正解です。というか、安全です。
つまらないゆっくり練習にならないためにテンポ感を弾んで感じられるといいですよね。
大時計の振り子のように・・(^^)
> 大時計の振り子のように・・(^^)
つまり、ゆっくりでも、時間が止まるのではなくて
あくまで物理法則に従って時を刻んでいるんですね。