沙汰よしメイト秋の田を。
(佐竹義和(さたけよしまさ)(秋田・明徳館)
[ポイント]
1.佐竹義和は、藩校明徳館を設立した。
[解説]
1.佐竹義和(1775~1815)は、18世紀末頃から秋田藩の寛政の改革を実施し、荒廃する農村と財政難を克服した。また藩校明徳館や郷校を設立するなどの教育の振興による人材の育成をおこなった
〈2016早大・人間科学
問5 下線部c(18世紀後半の農村)の村内の階層分化に関連する記述として、正しいものはどれか、1つ選べ。
ア 困窮した百姓に金を貸し、質にとった土地を集めた町人は蔵元と呼ばれ、商品作物の生産流通の中心を担った。
イ 自分の土地や家を失った百姓は、小作人になるか、年季奉公・日傭稼ぎのために村を離れていった。
ウ 18世紀後半、幕府は質流れのかたちで田畑が売買されるのを禁じたため、各地で質地騒動が起こった。
エ 天災や飢饉で疲弊した農村の立て直しを図るため、松江藩の佐竹義和は徹底した勧農抑商策をとった。
オ 享保の改革では、江戸に流入していた没落農民の帰村・帰農を奨励する旧里帰農令が出された。」
(答:イ ※ア×蔵元→質地地主、ウ×「田畑の質入れは認めるが質流れは認めない」という趣旨の質流地禁止令を農民が質地取り返しができる徳政令と解釈したためおきた騒動、エ佐竹義和は秋田藩主、オ×旧里帰農令は寛政の改革)〉
〈2012中大・法
諸藩では幕府にくらべ財政が不安定であったという・こともあり,藩政の見直しをせまられるという事態が早くからみられた。土佐藩では江戸時代前期に儒学を学んだ野中兼山が積極的に新田開発や殖産興業につとめた。なお,大名のなかには木下順庵などの儒学者を侍講・顧問などとして積極的に用いる例がみられた。
藩政改革において成果をあげた大名は名君とよばれた。秋田藩[ 5 ]はそのひとりである。彼は職制を整備し,農業・林業・鉱業をさかんにした。また人材育成をめざして4藩校を設立した。
問6 下線部4藩校に関連する説明文として正しいものにはイ、誤っているものにはロをマークしなさい。
a この藩校の名称は日新館である。
b この藩校の設立は水戸藩の藩校である弘道館の設立より早かった。
c 小田野直武はこの藩校開校にあたり招かれた儒者である。
(答:5佐竹義和、問6aロ×明徳館、bイ、cロ×小田野直武は秋田蘭画という一派を形成した画家。明徳館にはそれほど著名な儒者は招かれていない)〉

















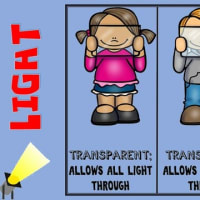








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます