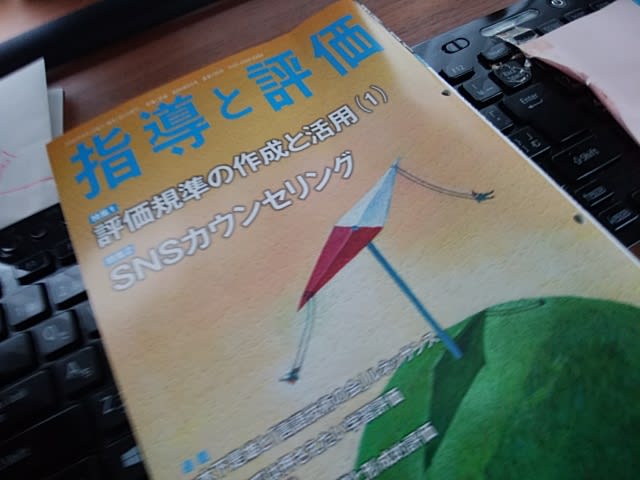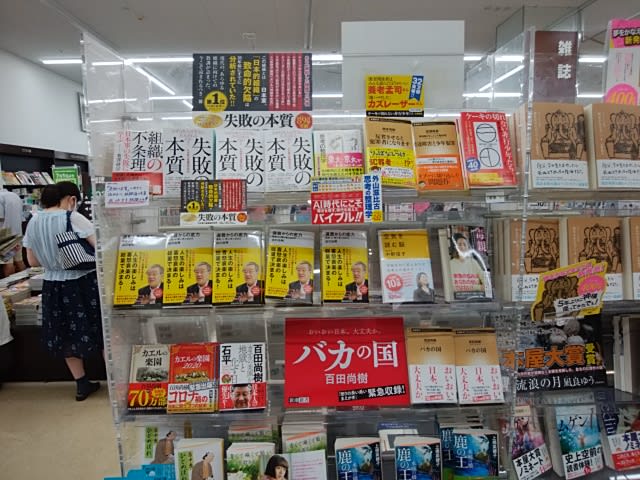「マニュアルとともに、20年」
●研究だよりでお許しを
平成18年三月末日で筑波大学を定年になります。
「定年まで5年を切った教官は大学院生をもたない」という専攻内の申し合わせのため、次第に院生が減りつつあり、現在は、日本学術振興会のPD1名と2名の院生、卒論生1名になりました。否が応にも、研究室の店仕舞いの態勢に入りつつあります。こんなときに研究「室」だよりはないでしょうというわけで、自分の研究だよりでお許しいただくことになります。
そうはいっても、ちょっとだけ、研究「室」だよりを。
これまでの研究室のポリシーとして、認知心理学という大枠は掲げてはいるものの、指導できる範囲内であれば、基本的に、「来る者こばまず、去る者大歓迎」「研究テーマはやりたいものをやってよい」ことにしてありましたので、今いる5名の院生の研究デーマは、次のようにかなりバラエティに富んでいます。
・人工物を介した対話の特性と最適化
・心的演算をめぐる諸現象とその認知メカニズム
・ワーキングメモり(作業記憶)の個人差と言語情報処理
・記憶検索における抑制と促進
・読書時のオンライン自動的情報処理
このうちのいくつかのテーマは、それなりに指導はできると思ってはいるものの、「そんなテーマで研究して何がおもしろいの?どんな役に立つの?」と思ってしまうようなものも実はあります。でも「やめたら」とまでは(できるだけ)言わないようにはしています。自分も30代終わりまではそんな研究をしてきましたし、もしかすると、彼らの中から第2の田中さんがでてくるかもしれないからです。研究評価は本当に難しいですね。
●マニュアルとともに、20余年
さてでは、「研究だより」それも「回顧(自慢話?)編」です。
次の2冊の本の出版が、それまでのほぼ20年にわたる基礎的・実験室的研究から応用研究のほうに軸足を移すきっかけになりました。これは、自分の研究生活の上で、劇的な変化でした。
・1987年「ユーザ読み手の心をつか むマニュアルの書き方」(共立出版)
・1988年「こうすればわかりやすい 表現になる---認知表現学への招待」 (福村出版;絶版)
いずれも、ユーザ、読み手、聞き手の頭の働きのくせにあった表現とはどのようなものであるべきかを考えてみたものでした。
この本の出る5年前頃から、ワープロが急速に普及してきました。それに比例するかのように、そのマニュアル(取扱説明書)がわかりにくくて困るという苦情がメーカーに殺到してしまい、弱り抜いていたようでした。
そんな時でした。日本IBM(株)の大和研究所の人間工学のセクションでマニュアル評価の仕事をしていた加藤隆氏(現在、関西大学教授/総合情報学部長)から、認知心理学の立場から、これを解決する方策がないかと相談されたのがきっかけで、マニュアルの世界に足を踏み入れることになりました。
どんなことをしたかというと、認知心理学をベースにして、「ユーザはマニュアルをこんな風に読んでいる」「マニュアルを読んでいるときにこんなことを頭の中でしている」だから「こんなふうにマニュアルを書いてくれるとわかりやすくなるはず」という提言をしてみたのです。