



↑三十八社神社(はっせんさんじんじゃ・

7月9・10日 夏季大祭
10月 10日 例 祭
第2日曜 神輿渡御祭(長浜曳山を思わせる芸屋台、祇園祭の山に通じる松を乗せた引き屋台が出ます。かつては、鉾に通じるものもでていました。)





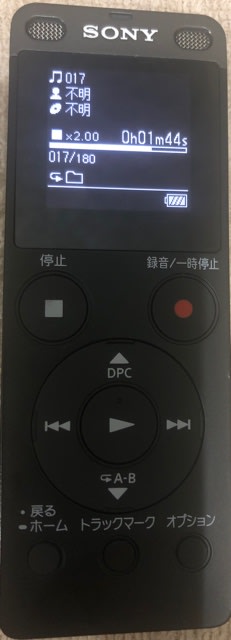
●淡路市野島平林貴舩神社のだんじり
少し高いところにある神社拝殿と本殿では、 宮座?の神事が行われていました。そして開いていたのは、だんじりの収蔵庫。しっかりと飾り付けがされていました。


淡路市平林貴舩神社(アクセス)
祭礼日 敬老の日の前の土日。
日曜日は野島八幡神社(アクセス)に集合していたそうですが、他の地域のだんじりが集まります(上田氏のご教示)。
●二代目黒田正勝の彫り物
目を引くのは彫り物です。黒檀彫の欄間(狭間)と井筒彫刻は播州でも活躍していた二代目黒田正勝だそうです。

↑だんじりでも活躍した黒田正勝ですが、布団だんじりの彫刻に適応するために、より人物が小さめに彫られています。
↑井筒も富士の巻狩りなど人物の彫刻が入っています。
↑井筒端は植物が複雑に入り組んだもので、向こう側が透けて見える籠彫が徹底されています。硬い黒檀をここまで彫れる技術の高さが伺えます。

↑さらに、金具は牡丹のまわりも一つ一つ点がうちこまれています。この打ち込みが光の反射によって微妙な濃淡がでます。

↑雀が斗組についています。
↑欄干の下にも、景色の彫り物があります。
●刺繍


↑そして、提灯です。題材は日清戦争。清の旗が見えます。
2代目黒田正勝の活躍した時代は、戦勝祝いの雰囲気に国内が満たされていた時代です。人物ものが縫われているのも珍しいですが、日清、日露戦争の題材が残っているのはさらに珍しいものです。管理人のようなマニアが訪れた時も一様に驚くとのことです。

↑浮き物刺繍というよりも山車の刺繍に近いものですが、顔の表情はちょび髭以外は伝統的で整った顔立ちで縫われています。馬のたてがみがリアルに表現されています。地面は違う色の糸が巻きあっており、微妙な色の違いを表現しています。馬の糸が細く首のあたりはたてがみに近いところとそうでないところの色が微妙に違います。違う色のいとをより合わせて一本の糸をつくる「糸より」の技法が使われていると思われます。
シンプルかつ繊細な屋台
屋台の形態としてはオーソドックスで、華やかなものとは言い切れません。しかし、よく見ると細かいところまで細工が凝らしてあることがわかります。
一見シンプルに見えるけど、実はよくできているだんじりは味わい深いものです。
謝辞
関係者の方々が忙しい中にもかかわらず、様々なことを教えてくださりました。この場を借りてお礼申し上げます。
屋台・だんじりも使えば傷みます。その際に必要なのが、修理や新調。現在の社会状況などから、どのようにしていけばいいのかを考えてみました。

昨年は台風で泉州地域にも大きな被害が出ました。そのような中でも奇跡はあったようです。














-祭ヘイトな人はどんな人?-
●神武帝の熊野〜橿原への平定行軍伝説(詳しくはウィkペディaへ)
古事記や日本書記の中で神武帝(神倭伊波礼毘古命)は熊野から橿原へ北上したと言われています。その間に数々の戦を経て、まつろわぬ者を平定します。まつろわぬ者とされた人の中には、先住民族がいたと考えられます。
神武帝の行軍伝承の故地にアイヌ語やアイヌ文化を思わせるものがありました。
●熊野
今や世界遺産となっている熊野街道。神武帝一行が熊野に差し掛かった時、大熊が現れ、一行は気を失います。太刀を受け取ることで、熊野の荒ぶる神達は倒され、気を失った一行は目をさまします。
熊はアイヌ語で「山の神」を意味する「 Kimun Kamui 」となります。アイヌ民族においては熊が最も重要な神の一つと位置づけられており、「Kamui(神)」だけで、熊を意味することもあるそうです。
その神が荒ぶる神の象徴ということから考えると、アイヌ文化が反映された記紀神話の記述なのかもしれません。さらに妄言を言うと、「kimun」 から 「Kumano熊野」に転化した??と考えるのは行きすぎでしょうか??
●兄宇迦斯(えうかし)弟宇迦斯(おとうかし)
神武帝の征戦中で宇陀に差し掛かった時、兄宇迦斯(えうかし)弟宇迦斯(おとうかし)が出てきます。兄宇迦斯(えうかし)は神武帝に恭順せず、弟宇迦斯(おとうかし)に自ら仕掛けた罠に入るように詰められ、討ち取られると言う話です。 兄と弟をとった「宇迦斯(うかし)」と言う言葉ですが、「エカシ」という言葉があります。長老の尊称を意味するので、一族の長としてはふさわしい意味になります。しかし、本当にウカシが長老となると、長老が前線にたって戦うことになってしまい、その点は不自然さを感じます。しかし、エカシ、ウカシの意味が当時は一族の頭領的な意味で使われていた可能性も否定できません。
最終的に兄宇迦斯(えうかし)は、死体を切り刻まればらまかれます。
●鷲家口
宇陀のすぐ隣の土地です。バスでは鷲家口を「ワッカグチ」と発音しているように聞こえました。この地は、川が二つに分かれる水別れの土地でした。wakkaは、水をアイヌ語で意味します。
ですが、実際は「ワシカ」と読むようです。他の地名は分かりませんし、管理人もはじめはアイヌ語が語源かなと思ったのですが、wakkaが語源ならば鷲ではなく、若など「ワカ」と読める漢字を使うと思われます。
子音と母音の組み合わせで構成されるハングルでも考えてみます。
오(オあるあはワ行子音)
ㅏ(ア段母音)
ㅅ(サ行子音、下にくる場合、促音・小さい「ッ」)
ㅣ(イ段母音)
ㅋ(カ段母音)
これを組み合わせて、ワシカとハングルで書くと
와시카 ワシカ
三文字中、母音の仲間はずれはㅣ・イ段があるシ・시です。口の形を変えずに楽に発音するためにㅣ・イ段が脱落します。
왓카 ワッカとなります。


●記紀神話にアイヌ語
記紀神話に書かれるなど古くから使われている言葉などには、アイヌ語や文化の名残があってもおかしくはないと思われます。しかし、それっぽく見えて実は違う、全く関係ないように見えて実はそうということも頻繁にありそうです。
祭が近づいてきたなあー
