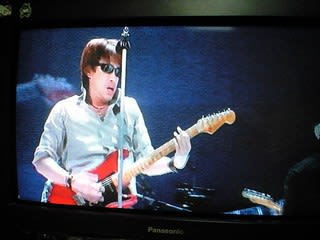明日18日(日)に、京都嵐山の渡月橋上流の大堰川で
平安時代の王朝絵巻さながらの舟遊びを優雅に
再現する「三船祭」が催されます。
三船祭は平安時代(898)に、宇多上皇が嵐山大堰川で
竜頭の船を浮かべ詩歌管弦を興じたことに由来する祭で、
和歌、漢詩、奏楽の達人を3隻の舟に乗せて舟遊びを
されたということから、「三船祭」と呼ばれています。
祭当日は渡月橋上流の川面に竜頭、鵜首など美しい飾りを
施した多数の船を浮かべ、平安時代の衣装に扮した人達が
船上で詩歌、管絃、舞楽などを興じるなど、当時の平安絵巻
の姿を今に再現した風雅な祭です。
祭には毎年、渡月橋周辺に約10万人の拝観者が訪れます。

また、三船祭は芸能の神様として芸能人の信仰が厚いことで
知られる車折神社が斎行している神事でもあり、正午に神社から
嵐山の大堰川までを衣装に扮した人達の神幸行列が進み
渡月橋を渡って飾り船に乗り込まれます。
昔、大堰川は時々の大洪水で毎年大きな被害が出ていました。
その都度、復旧工事に当たっていたのが車折神社・祭神の
清原頼業(よりなり)公の子孫一族であった事から
境内に水の神様を祭り治水を祈願したといいます。
平安時代の人々が水の恩恵への感謝と同時に
治水の祈りを込めて三船祭が今日まで続いて
きたといわれています。
今も昔も川の持つ真の姿を流域に住む人々は
敏感に感じていたのでしょう。
また、祭の奉納行事の一つに‘扇流し’があります。
昔、足利将軍が嵐山近くの天龍寺へ参詣の際、
お供の童子が扇を誤って川に落したところ、
扇が川面を流れる優美なさまを見て、将軍が
大層喜ばれたという逸話があり、以後、天龍寺参詣の
度毎にお供の人々が競って扇を川に流したという故事に
由来しているそうです。
この扇は嵐山通船さんの貸しボートに乗れば幾らでも
拾い上げることもできますよ~。
とても優美な模様が描かれた値打ちものの扇なので
私はっちんもよくいただいております。
明日は午前中に保津川下りをして、昼から
嵐山の三船祭をご覧になるというのが
祭りの日の通な遊び方です。
正午12時頃、保津川の船にお乗り頂くと
三船祭の華やかな風景が船の上でご覧に
なれるかもしれませんよ!
*嵐山渡月橋下を流れる大堰川は保津川の下流部です。
上流部の保津峡を流れる区間を保津川と呼び、
嵐山へ入ると大堰川と呼び名を変えるのです。
*三船祭スケジュール
正午 車折神社において「おでまし式」
午後1時 神幸行列神社御出門、三条通を西へ向い渡月橋を
渡って嵐山中の島公園剣先に到着。
午後1時40分 中の島公園剣先において神儀が御座船に御乗船。
午後2時頃 御座船を先頭に龍頭船、鵜首船以下各供奉船が
順次発船、この間御座船に対して龍頭船を先頭に
各供奉船は奉納行事を行いつつ、
大堰川(おおいかわ)を舟遊します。
午後4時頃 神儀が北のりば付近に御上陸の後、車折神社
嵐山頓宮に入御、祭事を了えます。
平安時代の王朝絵巻さながらの舟遊びを優雅に
再現する「三船祭」が催されます。
三船祭は平安時代(898)に、宇多上皇が嵐山大堰川で
竜頭の船を浮かべ詩歌管弦を興じたことに由来する祭で、
和歌、漢詩、奏楽の達人を3隻の舟に乗せて舟遊びを
されたということから、「三船祭」と呼ばれています。
祭当日は渡月橋上流の川面に竜頭、鵜首など美しい飾りを
施した多数の船を浮かべ、平安時代の衣装に扮した人達が
船上で詩歌、管絃、舞楽などを興じるなど、当時の平安絵巻
の姿を今に再現した風雅な祭です。
祭には毎年、渡月橋周辺に約10万人の拝観者が訪れます。

また、三船祭は芸能の神様として芸能人の信仰が厚いことで
知られる車折神社が斎行している神事でもあり、正午に神社から
嵐山の大堰川までを衣装に扮した人達の神幸行列が進み
渡月橋を渡って飾り船に乗り込まれます。
昔、大堰川は時々の大洪水で毎年大きな被害が出ていました。
その都度、復旧工事に当たっていたのが車折神社・祭神の
清原頼業(よりなり)公の子孫一族であった事から
境内に水の神様を祭り治水を祈願したといいます。
平安時代の人々が水の恩恵への感謝と同時に
治水の祈りを込めて三船祭が今日まで続いて
きたといわれています。
今も昔も川の持つ真の姿を流域に住む人々は
敏感に感じていたのでしょう。
また、祭の奉納行事の一つに‘扇流し’があります。
昔、足利将軍が嵐山近くの天龍寺へ参詣の際、
お供の童子が扇を誤って川に落したところ、
扇が川面を流れる優美なさまを見て、将軍が
大層喜ばれたという逸話があり、以後、天龍寺参詣の
度毎にお供の人々が競って扇を川に流したという故事に
由来しているそうです。
この扇は嵐山通船さんの貸しボートに乗れば幾らでも
拾い上げることもできますよ~。
とても優美な模様が描かれた値打ちものの扇なので
私はっちんもよくいただいております。
明日は午前中に保津川下りをして、昼から
嵐山の三船祭をご覧になるというのが
祭りの日の通な遊び方です。
正午12時頃、保津川の船にお乗り頂くと
三船祭の華やかな風景が船の上でご覧に
なれるかもしれませんよ!
*嵐山渡月橋下を流れる大堰川は保津川の下流部です。
上流部の保津峡を流れる区間を保津川と呼び、
嵐山へ入ると大堰川と呼び名を変えるのです。
*三船祭スケジュール
正午 車折神社において「おでまし式」
午後1時 神幸行列神社御出門、三条通を西へ向い渡月橋を
渡って嵐山中の島公園剣先に到着。
午後1時40分 中の島公園剣先において神儀が御座船に御乗船。
午後2時頃 御座船を先頭に龍頭船、鵜首船以下各供奉船が
順次発船、この間御座船に対して龍頭船を先頭に
各供奉船は奉納行事を行いつつ、
大堰川(おおいかわ)を舟遊します。
午後4時頃 神儀が北のりば付近に御上陸の後、車折神社
嵐山頓宮に入御、祭事を了えます。