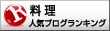単に生産地と消費地が近いだけで「地産地消」で良いのでしょうか。
確かに狭義的には、”地域で生産したものを地域で消費する”を”地産地消”でOKだと思います。
しかし本当に地産地消が確立されてしまえば、”お取り寄せ”はあり得ない。
まして産地のみですべてを消費するということは、現実的な話ではないですよね。
また地域で採れた食材を、学校給食に使うのも”地産地消”は当たっているかもしれないけど、
”食育”には必ずしもならないのでは?
どこか行政主導だったりするこの”地産地消”は、
どことなく経済的な枠組みを形成しつつあるように思います。
その良い例が、学校給食への納入。
内需拡大の縮小版みたいです。
地域に納入先ができたことは、経済的にはOK!
でも長期的には、生産者やこれに関わっている流通関係者の”競争力の低下”も
覚悟しておくべきではないでしょうか。
労せず得た繁栄は長続きしません。
生産者ではなく消費者としての自分の思いは、
「地産地消」とは、互いの顔が見えて”安心感や親近感”を共有すること。
店頭の顔写真には、少なくとも親近感は湧きません。
また”地産地消”を大々的に標榜しているようなスーパーで、
なぜ他地域の同一野菜を売っているのか?
小売店の取り組む”地産地消”は、あくまで売り上げ向上のためのツール。
もっともらしく顔写真を飾っている反面で、”契約栽培野菜”の方は写真がなかったり。
”地元産は新鮮で安い”これも、おかしな論理。
新鮮はともかく、安いとは限りません。
特に都市部に於いては、
作付けのスケールメリットは耕作面積が小さいためにほとんど期待はできません。
生産コストを考えれば、わかりそうなもんです。
私が申し上げるのも何ですが、
言葉(宣伝)とイメージに惑わされずしっかりとした自身の考えで行動してみませんか?


確かに狭義的には、”地域で生産したものを地域で消費する”を”地産地消”でOKだと思います。
しかし本当に地産地消が確立されてしまえば、”お取り寄せ”はあり得ない。
まして産地のみですべてを消費するということは、現実的な話ではないですよね。
また地域で採れた食材を、学校給食に使うのも”地産地消”は当たっているかもしれないけど、
”食育”には必ずしもならないのでは?
どこか行政主導だったりするこの”地産地消”は、
どことなく経済的な枠組みを形成しつつあるように思います。
その良い例が、学校給食への納入。
内需拡大の縮小版みたいです。
地域に納入先ができたことは、経済的にはOK!
でも長期的には、生産者やこれに関わっている流通関係者の”競争力の低下”も
覚悟しておくべきではないでしょうか。
労せず得た繁栄は長続きしません。
生産者ではなく消費者としての自分の思いは、
「地産地消」とは、互いの顔が見えて”安心感や親近感”を共有すること。
店頭の顔写真には、少なくとも親近感は湧きません。
また”地産地消”を大々的に標榜しているようなスーパーで、
なぜ他地域の同一野菜を売っているのか?
小売店の取り組む”地産地消”は、あくまで売り上げ向上のためのツール。
もっともらしく顔写真を飾っている反面で、”契約栽培野菜”の方は写真がなかったり。
”地元産は新鮮で安い”これも、おかしな論理。
新鮮はともかく、安いとは限りません。
特に都市部に於いては、
作付けのスケールメリットは耕作面積が小さいためにほとんど期待はできません。
生産コストを考えれば、わかりそうなもんです。
私が申し上げるのも何ですが、
言葉(宣伝)とイメージに惑わされずしっかりとした自身の考えで行動してみませんか?