2017年9月11日(月)
「パブリッシャーズ・ビュー/白水社の本棚」181号(2017年7月15日)、「愛書狂」欄に小気味よい記事あり。転記する。
***
三月八日付け『朝日新聞』の「声」欄に、21歳大学生からの「読書はしないといけないの?」なる投書があった。某君は高校生までまったく読書習慣がなく、大学へ入って、必要から専攻する教育や社会一般の本を読んだが、「読書が生きる上での糧になると感じたことはない」。それが問題視される方がおかしいという。
後日、これについてどう思うか、賛否の意見が寄せられ、議論はさらに再びくり返された。「大人は読書を押しつけないで」と同調する中学生、「人との出会いを求めるなら」と諭す中年など様々。私はこのやりとりを不毛に思い、冷たく見ていた。もちろん、投書した某君は、読書する必要などまったくなく、そのまま一生を終えればいいのである。ただ、気の毒な人だと思うが……
読軎体験に見返りや理屈は要らない。幼い頃に一度その喜びを知れば、頭より先に、身体が欲して止まないというだけのことだ。本は情報を盛る皿ではなく、読書は何より、深い感動が根底にある体験である。「声」欄の某君は、幼少時に絵本や児童書、青春期に文学の洗礼を受けていないようだった。痩せた土地に、いくら水や肥料をやっても、芽は出ず、花は咲かない。
先日地下鉄で、こんな光景に出くわした。男子小学生が、背が取れかかってボロボロの歴史漫画の本を、夢中になって読んでいたのだ。父親の本だろうか。降りる駅が来て、少年は起ちあがったが、本は手に開いたまま。彼なら大人になっても「読書しないといけないの?」と悩むことはないだろう。私は心の中で拍手を贈った。
(野)
***
「愛書狂」は一面下部のコラム、「天声人語」(朝日)、「編集手帳」(讀賣)、「余録」(毎日)に相当する。愛媛新聞なら「地軸」で、このネーミングはなかなか良い。「愛書狂」欄もこれらに劣らず軽快な切り口で毎回楽しみにしているが、今回面白いのは最終段落で紹介される小学生の読んでいたのが「歴史漫画」であることだ。「漫画か、嘆かわしい」ではないのである。
これは大いに嬉しいことで、僕も両親に買ってもらった科学漫画の12巻本を、「背がボロボロになるまで」愛読した。むろん活字本も劣らず濫読して今に至るけれど、『鉄腕アトム』やなぜか『のらくろ』はじめ漫画から受けた影響また否みがたく、どちらも大事というほかない。ただ、冒頭の21歳大学生氏がコラムを読んだら、「自分が言ったのは活字本のこと、漫画なら大いに生きる糧になる/なった」と言わないものか確信がなく、ひょっとしたら「愛書狂」子が的を外したのではないかとやや心配である。
ついでながら「狂」の字のこと。これを精神疾患/障害に使わないのは確立した約束事だが、こういう文脈では活躍の余地がある。似た境遇にあるのが欧米語の mania で、もともと古代ギリシア語で躁病ないしは精神の変調一般を指すものとして使われた。「躁病」の用法が今日に引き継がれているのに加え、「◯◯mania」という表現もまた生き残って、ちょうど「◯◯狂」という日本語に照応するものになっている。bibliomania がほぼ「愛書狂」に相当するが、どちらかというと稀覯(きこう)本をあさる猟書家を意味するらしく、愛書家を表すならむしろ bibliophilia かもしれない。
いずれにせよ、この語を敢えて使う編集者の思い入れは相当なもので、世の中には似たような御仁があるものだと微笑ましいのである。
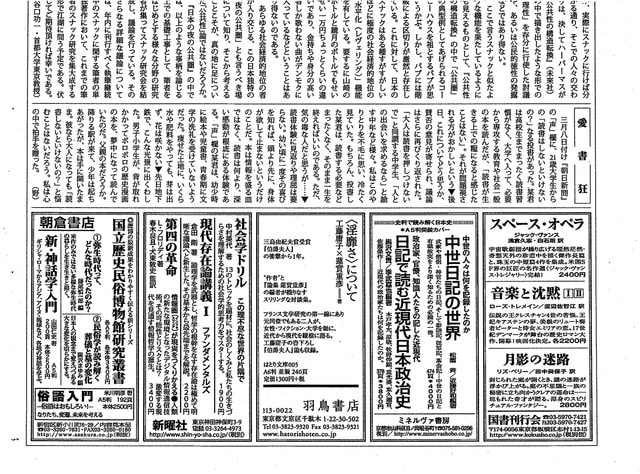
Ω









