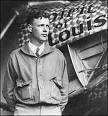昨夜は後半だけだが久しぶりに良い番組を見た。TBS系の「超地球ミステリー特別企画・1秒の世界2」。
中でも、1秒間に世界中で405万円のお金が戦争に使われているという事実。戦争を永久に放棄したはずの日本だけでも、いつの間にか年間4兆円以上が防衛予算という名の軍事費に使われるようになっている・・・毎秒13万円だよ・・・人間は(正しくは“国家”だが)いつまでこんなバカなことをしているんだろう・・・と再び思わずにはいられなかった。平和は戦争や戦争の準備をすることでは絶対にありえない。平和は平和の準備をすること、それ自体の中にあるのだ。
ともあれ、特に感動的だったのが、エチオピアのコンソ村の様子。電気も水道もガスもない、つまり私たちがライフラインなどと呼んで、生活するために必須のものとされている“もの”がことごとくない世界だ。

しかし、あの少女や子供たちの笑顔の美しいこと!一切を無駄にしない村人の生き方の見事なこと!かつてシャルル・フーリエやE・カーペンターが夢見た社会がまさにそこにあるように私には見えた。
マーク・トゥウェインは「文明とは不必要な必需品の限りない集積である」と見切ったが、現代の文明社会がいかに、石川三四郎の言う“幻影の”必需品によって支えられているか・・・よく分かるというものではないか。
無論、コンソ族が500年前に他の部族に草原を追われて、山岳地帯に逃げ込むように居住を始めたことの悲哀や、ほとんど全て自然に拠って日常生活を送ることの厳しさは、文明・強者の側に住む人間が容易に察する範囲を超えているかもしれない。
しかし、文明文明といっても、たかだかこの100年か良いとこ200年の話で、うちの田舎などのほんの50年前は、庭の井戸から水を上げ、米も風呂も裏山で取れた薪で焚いていたし、おかずの魚や海藻は目の前の海にいくらでもいた。山ではないが、このコンソの村のような自然と共に生きる匂いがあちこちに残っていたのである。
中でも、1秒間に世界中で405万円のお金が戦争に使われているという事実。戦争を永久に放棄したはずの日本だけでも、いつの間にか年間4兆円以上が防衛予算という名の軍事費に使われるようになっている・・・毎秒13万円だよ・・・人間は(正しくは“国家”だが)いつまでこんなバカなことをしているんだろう・・・と再び思わずにはいられなかった。平和は戦争や戦争の準備をすることでは絶対にありえない。平和は平和の準備をすること、それ自体の中にあるのだ。
ともあれ、特に感動的だったのが、エチオピアのコンソ村の様子。電気も水道もガスもない、つまり私たちがライフラインなどと呼んで、生活するために必須のものとされている“もの”がことごとくない世界だ。

しかし、あの少女や子供たちの笑顔の美しいこと!一切を無駄にしない村人の生き方の見事なこと!かつてシャルル・フーリエやE・カーペンターが夢見た社会がまさにそこにあるように私には見えた。
マーク・トゥウェインは「文明とは不必要な必需品の限りない集積である」と見切ったが、現代の文明社会がいかに、石川三四郎の言う“幻影の”必需品によって支えられているか・・・よく分かるというものではないか。
無論、コンソ族が500年前に他の部族に草原を追われて、山岳地帯に逃げ込むように居住を始めたことの悲哀や、ほとんど全て自然に拠って日常生活を送ることの厳しさは、文明・強者の側に住む人間が容易に察する範囲を超えているかもしれない。
しかし、文明文明といっても、たかだかこの100年か良いとこ200年の話で、うちの田舎などのほんの50年前は、庭の井戸から水を上げ、米も風呂も裏山で取れた薪で焚いていたし、おかずの魚や海藻は目の前の海にいくらでもいた。山ではないが、このコンソの村のような自然と共に生きる匂いがあちこちに残っていたのである。