
記憶とは言葉
三浦しをん『舟を編む』
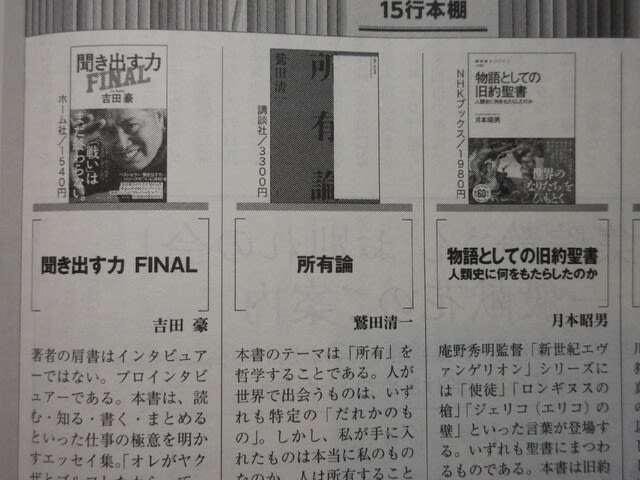
「週刊新潮」に寄稿した書評です。
吉田豪『聞き出す力 FINAL』
集英社 1540円
著者の肩書はインタビュアーではない。プロインタビュアーである。本書は、読む・知る・書く・まとめるといった仕事の極意を明かすエッセイ集だ。「オレがヤクザとゴルフしたからって、誰が困るってんだよ」と笑う小林旭。「高い服を着て美味い飯を食ってデカい家に住むために芸人になった」と本音を語る、かまいたち濱家。遺言を聞き出す覚悟と千変万化できる柔軟性こそ著者の真骨頂だ。
鷲田清一『所有論』
講談社 3300円
本書のテーマは「所有」を哲学することである。人が世界で出会うものは、いずれも特定の「だれかのもの」だ。しかし、私が手に入れたものは本当に私のものなのか。人は所有することで幸福になるのか。著者は個人や国家にとっての所有、帰属、譲渡などの概念を検証していく。やがて見えてくるのは「所有」から「受託」への流れであり、提示される「共(コモン)」という考え方が刺激的だ。
月本昭男
『物語としての旧約聖書~人類史に何をもたらしたのか』
NHK出版 1980円
庵野秀明監督『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズには「使徒」、「ロンギヌスの槍」、「ジェリコ(エリコ)の壁」といった言葉が登場する。いずれも原典は『旧約聖書』である。本書は聖書学の第一人者による入門書だ。キリスト教やユダヤ教にとっての『旧約聖書』とは何か。アダムとエバ、ノアの箱舟、バベルの塔などのエピソードは何を伝えているのか。その「複眼性」は現代にも繋がる。
(週刊新潮 2024.03.14号)

夜ドラ「ユーミンストーリーズ」NHK
異なる脚本家と演出家による
競作としても楽しめる
興味を引く企画だ。ユーミンこと松任谷由実の楽曲に触発されて書かれた短編小説をベースに、3本のオムニバスドラマが作られた。夜ドラ「ユーミンストーリーズ」(NHK)である。
先週放送された1本目は、綿矢りさが原作小説を書いた「青春のリグレット」だ。
結婚して4年の菓子(かこ、夏帆)は夫・浩介(中島歩)の浮気を知り、2人の関係を修復しようと旅行に誘う。行き先は八ヶ岳のコテージ。だが、そこで浩介から離婚を切り出され……。
菓子が八ヶ岳に来たのは2度目だ。以前つき合っていた陸(金子大地)と一緒だった。陸を物足りない相手と思っていた菓子は、旅行の後で別れてしまう。
これからどうするのかと陸に訊かれ、「次につき合う人と結婚するかな?」と菓子。陸はたったひと言、「無理だよ」と突き放す。
岨手(そで)由貴子の脚本は原作を大胆にアレンジしている。過去と現在、2つの旅が交差する構成が見事だ。
かつて誰かを傷つけ、惨めな思いをさせてきた自分。そして今、深く傷つき、惨めな思いをしている自分。
しかし、そこにあるのは「リグレット(後悔)」だけではない。人生の岐路に立つ30代女性を、夏帆が繊細に演じていく。
今週放送されているのは柚木麻子原作の「冬の終り」。来週は川上弘美の「春よ、来い」だ。異なる脚本家と演出家による競作としても楽しめる。
(日刊ゲンダイ「TV見るべきものは!!」2024.03.12)

気がつけば、今期ドラマの「おじさん」たちが元気です。それも、ただのおじさんではない。
昭和を生きてきたおじさん。アイデンティティーのベースに昭和があるおじさん。メンタルが昭和なおじさん。つまり「昭和のおじさん」です。
『不適切にもほどがある!』(TBS系)がそうですが、原田泰造主演『おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか!』(東海テレビ・フジテレビ系)もまた、出色の「昭和のおじさんドラマ」です。
主人公の沖田誠(原田)はリース会社の室長。「男が上を目指さないでどうする!」などと部下を叱咤激励(しったげきれい)してきました。
いや、それだけではありません。「お茶は女の人がいれたほうがおいしいだろ?」や「そんなんじゃ嫁に行きそびれるぞ」といった発言も日常的でした。
しかし、メンタルが昭和な本人には当然の言動も、部下たちにとってはパワハラやセクハラだったりします。
家庭内でも同様です。推し活を楽しんでいる妻の美香(富田靖子)を「こんな女みたいな男どこがいいんだか」とからかう。
また息子の翔(城桧吏)の友人で、ゲイの大学生・五十嵐大地(中島颯太)には、「君といて(息子に)ゲイがうつったら困る」などと暴言を吐いていました。
そんな誠ですが、大地と話をするうちに、自分の中で何かが変わり始めていく。そして、大地に勧められた、モラルの「アップデート」を試みようとするのです。
しかし、凝り固まった偏見をなくし、倫理観とマナーを更新するのは簡単なことではありません。
失敗を重ねる誠の姿に、見る側もつい自身を投影してしまう。昭和のおじさんの「成長物語」として秀逸なのです。
ある日、誠は気づきます。性別や性的指向は「おっさんのパンツ」みたいなものだと。何をはいても誰の迷惑にもならない。あくまでプライベートなことであり、公表する必要もない。
それに家族だって自分とは違う人間だ。他者が大事にしているものを自分の尺度で否定してはいけない。それは、このドラマの根幹にかかわる「発見」でした。
原作は練馬ジムさんの同名漫画。藤井清美さんの脚本が原作のメッセージをしっかりと伝えています。
人は誰も自身の人生の積み重ねを経て、今を生きています。
「おじさん」と呼ばれる年齢になれば、良くも悪くも自分の価値観は出来上がっており、それをベースにあらゆる判断を行っているのです。
しかし、その価値観や物事の判断基準は本当に正しいのか。自分が知らない、もしくは知ろうとしない新たな常識を棚上げにしてはいないだろうか。
このドラマを見ていると、ふと自分にも問いたくなります。
いつの間にか、世の中には十分理解しているとは言えない事象や言葉があふれています。誠もそうでした。
妻の「推し活」、息子と「LGBTQ」、娘(大原梓)の「二次元LOVE」、そして部下が愛用する「メンズブラ」等々。
誠は、「若いころは当たり前に分かった流行が分からなくなっている。いつ変わったのかも知らない。どう変わったのかも説明できない」と心の中でつぶやきます。
自分とは無関係だと切り捨てるのか、それとも知ろうと努力するのか。誠は、自分にとって一番大切な「家族」と共に生きていくためにも、「アップデート」を決意したのです。
とはいえ、昭和的なものを無条件に排除するのではありません。時代とズレてしまった部分の価値観を必要な分だけ更新していくのです。
それは昭和のおじさんに限った話ではないでしょう。世代や性別などにかかわらず、「なかなかアップデートできない」という人は少なくないはずです。
抱えている常識は古めで、偏見にも縛られている誠ですが、情は厚くて真っ直ぐなところがあります。
そんな男が「出来るところからやってみよう」とトライするドラマだからこそ、すべての人にとってのケーススタディになり得るのだと思います。
『不適切』も『おっさんのパンツ』も、昭和と令和のギャップが物語の基盤となっています。
前者はSF(サイエンス・フィクション)の要素を生かした「ツッコミ型」であり、後者はリアルな現在(いま)と向き合う「ヒューマン型」。
そのアプローチは違っても、「笑い」という武器は共通しています。
見る側は、昭和のおじさんたちが巻き起こす、「衝突」や「理解」や「受容」といった展開を笑いながら楽しめばいい。
その先に見えてくるのが、「令和」という時代の、世代を超えた歩き方なのではないでしょうか。
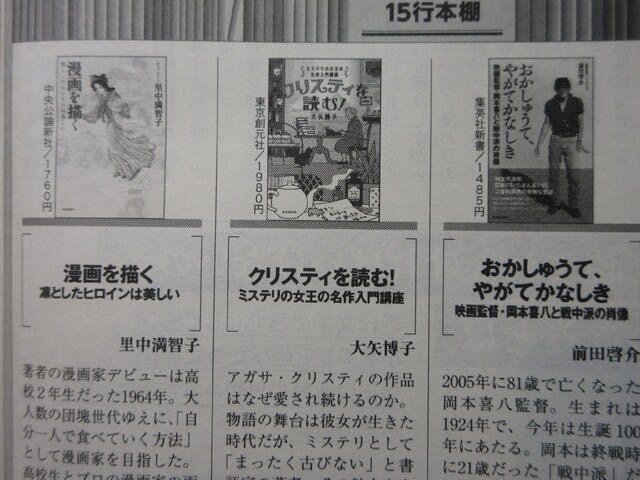
「週刊新潮」に寄稿した書評です。
里中満智子『漫画を描く~凛としたヒロインは美しい』
中央公論新社 1760円
著者の漫画家デビューは高校2年生だった1964年。大人数の団塊世代ゆえに、「自分1人で食べていく方法」として漫画家を目指した。高校生とプロの漫画家の両立を学校が禁じると自主退学。大阪から上京して漫画に専念する。本書は画業60年を記念する本格自伝だ。昭和の漫画家事情をはじめ、『アリエスの乙女たち』や『天上の虹』など、ヒット作の背景や作品に込めた思いが明かされる。
大矢博子
『クリスティを読む!~ミステリの女王の名作入門講座』
東京創元社 1980円
アガサ・クリスティの作品はなぜ愛され続けるのか。物語の背景は彼女が生きた時代だが、ミステリとして「まったく古びない」と書評家の著者。その魅力を多角的に解説している。ポアロが異邦人であることに注目して読む『スタイルズ荘の怪事件』。英国社会の目撃者、ミス・マープルが謎を解く『書斎の死体』。さらに「舞台と時代」や「人間関係」といった視点で作品世界へと導いていく。
前田啓介
『おかしゅうて、やがてかなしき
~映画監督・岡本喜八と戦中派の肖像』
集英社新書ノンフィクション 1485円
2005年に81歳で亡くなった岡本喜八監督。生まれは1924年で、今年は生誕100年にあたる。岡本は終戦時に21歳だった「戦中派」だ。著者は自ら発見した、大学時代から東宝入社にかけての岡本の日記も精査。『肉弾』や『日本のいちばん長い日』などの作品に投影された、戦中派の心情を丁寧に探っていく。「何を言いたいか、その熱気が人の心を打つ」と語った“全身監督”の実像が立ち現れる。
(週刊新潮 2024.03.07号)

テオ君の可愛らしさがハンパじゃない!
二階堂ふみ主演「Eye Love You」TBS系
二階堂ふみ主演「EyeLove You」(TBS系)には大きな特色が2つある。
まず、ヒロインの侑里(二階堂)が、他者の心の声が聞こえる「テレパス」の能力を持っていること。そして、恋の対象がテオ(チェ・ジョンヒョプ)という年下の韓国人青年であることだ。
見ていると、「マカロニ・ウエスタン」を思い出す。1960年代から70年代にかけて人気を博した、イタリア製の西部劇だ。クリント・イーストウッド主演「荒野の用心棒」などがあった。
このドラマ、いわば日本製の韓国恋愛ドラマのようなものだ。なまじ相手の本音が分かってしまうため、恋愛を遠ざけてきた侑里。しかし、テオは韓国語なので心の声は理解できない。
誤解や気持ちのすれ違いはあったが、ようやく自分も好きだと伝えることができた。やや現実離れしている侑里の純情ぶりも、「和製韓流ドラマ」だと思えば微笑ましい。
それにしても、「テオ君」の愛玩動物的可愛らしさが半端じゃない。キュートなキャラクターは韓国恋愛ドラマには必須。
日本人俳優がキラキラした目で「僕は侑里さんの特別になりたいです!」などと言ったら、テレくさくて見ていられないだろう。韓流、恐るべし。
人の心を読む能力が登場する韓国ドラマには「君の声が聞こえる」などがあるが、本作は三浦希紗と山下すばるによるオリジナル脚本だ。
(日刊ゲンダイ「TV見るべきものは!!」2024.03.05)

昭和のおじさんドラマ『不適切にもほどがある!』(TBS系)。
主人公の小川市郎(阿部サダヲ)が、娘の純子(河合優実)と暮らしている「1986年(昭和61年)」とは、一体どんな年だったのか。
5月、海外の純資産額で日本が世界一になったことが報じられます。また9月の国土庁発表では、東京23区内の商業地で40%も地価が上昇。「狂乱地価」といわれました。
10月に売り出されたNTT株も人気を集め、11月になるとサラリーマンの生涯賃金が大卒で2億円を超えていきます。
では、テレビの世界はどうだったのか。
前年に始まった『ニュースステーション』(テレビ朝日系)の成功で、民放各局がワイドニュースに参入。同時に、ニュース番組のキャスターに女性が相次いで起用されていきました。
『モーニングショー』(同)の美里美寿々(現・田丸美寿々)さん、『NNNライブオンネットワーク』(日本テレビ系)の井田由美さん、そして『ネットワーク』(TBS系)の三雲孝江さんなどです。
今年4月、三雲さんの娘である星真琴さんが、NHKの看板報道番組『ニュースウオッチ9』のメインキャスターに就任するのも不思議な符合です。
ドラマのヒット作には、市郎も話題にした『男女七人夏物語』(TBS系)がありました。ひょんなことで出会った、結婚適齢期の男性3人と女性4人の恋愛模様。複数の男女の誰と誰が結ばれるのかを予想させる展開は、後のトレンディドラマの原型です。
また、『な・ま・い・き盛り』(フジテレビ系)も話題となりました。ヒロインは中山美穂さん。人気アイドル主演の連続ドラマの先駆的作品でした。
バラエティーでは、今年3月に幕を閉じる『世界ふしぎ発見!』(TBS系)や、視聴者参加のゲーム番組『風雲!たけし城』(同)がスタート。
さらに、過去のドラマやアニメなどの名場面をネタに盛り上がる『テレビ探偵団』(同)もこの年に登場しています。
市郎と純子、世代の異なる2人が生きている86年。今では、どこか揶揄するような口調で語られてしまう「バブルの時代」です。
しかし、好景気にわく社会も、高視聴率番組が林立するテレビ界も、そこに生きる人たちも、今より元気だったことは確かなのです。
宮藤官九郎さんが、過去の舞台を1986年(昭和61年)にしたのはなぜでしょう。
この年、70年(昭和45年)生まれの宮藤さんは、16歳の高校1年生でした。
ドラマの中の市郎の娘・純子は高校2年生で17歳。宮藤少年の同世代として、同じ時代の空気を吸っていることになります。純子には、当時の宮藤さん自身が投影されていると言えるでしょう。
また、市郎は1935年(昭和10年)生まれと設定されています。86年には51歳。そして宮藤さんは今年53歳です。市郎が、現在の宮藤さん自身とリンクする。50代は立派な「昭和のおじさん」なのです。
さらに、市郎が2024年(令和6年)にも生きていたなら、御年89歳になっているはずでした。残念ながら、1995年の阪神淡路大震災に巻き込まれたことが明かされています。
昭和10年生まれで思い浮かぶのが、宮藤さんにとっては脚本家の大先輩である、倉本聰さんです。
86年に51歳だった倉本さんは、ドラマ『ライスカレー』(フジテレビ系)を手がけています。若者たちがカナダでカレー屋をはじめる物語でした。時任三郎さん、陣内孝則さん、そして中井貴一さんなどが出演した作品です。
ちなみに、今年2月に亡くなった小澤征爾さんも昭和10年生まれでした。市郎の「生年設定」は、敬愛する先達(せんだつ)たちへのオマージュかもしれません。

「週刊新潮」に寄稿した書評です。
北野圭介『情報哲学入門』
講談社選書メチエ 1980円
かつて近未来として語られ、今や完全に実現した「情報社会」。しかし、そもそも「情報」とは何なのか。そこにはどんな哲学的課題があるのか。メディア研究者である著者が解説していく。情報の概念や技術、そして知能の再定義。情報がもたらす政治や経済の未来像。さらに、社会だけでなく、「人間」も情報によってデザインされ得る時代にどう対応するのか。未知の「生存戦略」も提示される。
中央公論新社:編『50歳からの読書案内』
中央公論新社 1650円
50歳以降に読んだ印象深い本、あるいは今も読み返す大切な本は? その問いに50人の著名人が答えている。関川夏央が「大人を超えて老いに至ると、しみてくる」という森鷗外『じいさんばあさん』。永井荷風を繰り返し読む川本三郎が、同じく再読する野口富士男『わが荷風』。酒井順子を古典の世界へと導いたのは橋本治『桃尻語訳 枕草子』だ。本は常に「冒険」であり、また「途上」でもある。
神保喜利彦『東京漫才全史』
筑摩書房 2310円
江戸時代から関西で発展してきた「上方漫才」。大正時代に出現したのが「東京漫才」だ。本書はその歴史をまとめた労作である。戦前の東京漫才黄金時代。戦後のラジオと東京漫才の復興。やがてテレビの登場で漫才師のあり方も変化する。獅子てんや・わんや、晴乃チック・タックといった懐かしい名前から、現在も活躍する「ニュータイプ」まで、時代の縦軸と横軸で語られる東京漫才の正史だ。
(週刊新潮 2024.02.29号)