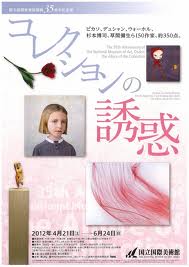最近とみにシュタイナー教育が気になる。
小中連携という言葉もちまたには飛び交う。
中学校の先生が小学校に行って教える?って
これが小中連携?
英語教育が小学生にとって本当に必要とは
思えない。
本当に小学生にとって必要な教育を私たち
無免許の者ができるとしたら、、、、。
よっぽど勉強して納得してからでないと
実践なんてできない。
というわけで昔から気になって本まで
買ったシュタイナー教育
私が手に入れたのは
筑摩書房 シュタイナー コレクション1
子どもの教育
高橋 巌 訳
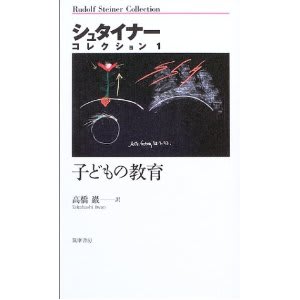
一度2~3年前に読みかけたけれど
私の中での興味が盛り上がって
いない時だとどうにも読んでいて
眠くなるのです。お恥ずかしい話
でも今回なんだか私の中で警鐘がなる。
「シュタイナーに行け」と
関係ないですけれど
昨日NHKで未解決事件 オーム真理教という
番組をやっていて元信者に「なんで入信したんですか。」
というのを聞いていた。
その問いに元信者は「いつもこれは現実、これは空想
って日常生活の中で現実と空想が入りみだれる。」と
いう答えを言っていた。
うーんそれってわかるような気がする。
あくまでも私にはそいういう日常はないけど
突然神がお告げみたいにピーンと来る瞬間はある。
そういう出会いなんですね。シュタイナーとは。
という話をするとシュタイナーの人智学って
そういうオカルト的な部分に踏み込んでいくので
本当はオカルトではないのですけれど
ってえらそうに言いながら私まだその核心は
定かではありません。
でもこのコレクション1の「子どもの教育」には
いくつかのすごい内容が含まれているのは事実だと
思います。私は。
この内容をシュタイナーが書いたのは
19世紀終わりから20世紀初めなんですよね。
その中で
子どもの教育で大切なことは
7歳までは子どもは大人の事を模倣する。
7歳~思春期までの子どもに
とって一番大切なのはおのずから
生まれた権威に従うことと。
記憶力を育ててやること。
知性は思春期を過ぎた頃から
現れるという。
これってすごい事じゃないですか!?
よって小学校お受験なんて具に骨頂だということ。
早期教育があかんという事。
小学生~中学校1年生にとって総合的学習はやってはいけないこと。
なんですよね!
もっと言えば幼児期に虐待を受けた子は
自分の子どもにも虐待をするという可能性が高いという事ですよね。
もう一つ言えば小学校でクラス崩壊にあった子どもは
権威に対して素直に敬虔な気持ちで頭を下げるということが難しい
ということですよね。
主にこのシュタイナーコレクション1に
収められるいる文章は1920年までに書かれた物が
中心なんでしよね。
私シュタイナーに自分の子どもが生まれる前に出会いたかった。
(でも早期教育なんてしてないけど、、、。)
小学生にとって
大切な事は直観を育ててやる教育
体を動かす事や音楽を楽しむことや
美しい色や形に直観で触れることなんですよね。
ということで小学校の先生
一緒にシュタイナー学んでみません?
ってお誘いの連携だったらできるかな?
小中連携という言葉もちまたには飛び交う。
中学校の先生が小学校に行って教える?って
これが小中連携?
英語教育が小学生にとって本当に必要とは
思えない。
本当に小学生にとって必要な教育を私たち
無免許の者ができるとしたら、、、、。
よっぽど勉強して納得してからでないと
実践なんてできない。
というわけで昔から気になって本まで
買ったシュタイナー教育
私が手に入れたのは
筑摩書房 シュタイナー コレクション1
子どもの教育
高橋 巌 訳
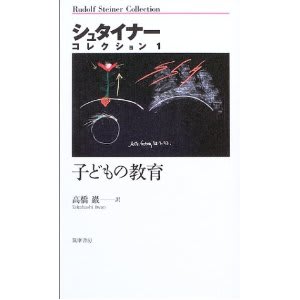
一度2~3年前に読みかけたけれど
私の中での興味が盛り上がって
いない時だとどうにも読んでいて
眠くなるのです。お恥ずかしい話
でも今回なんだか私の中で警鐘がなる。
「シュタイナーに行け」と
関係ないですけれど
昨日NHKで未解決事件 オーム真理教という
番組をやっていて元信者に「なんで入信したんですか。」
というのを聞いていた。
その問いに元信者は「いつもこれは現実、これは空想
って日常生活の中で現実と空想が入りみだれる。」と
いう答えを言っていた。
うーんそれってわかるような気がする。
あくまでも私にはそいういう日常はないけど
突然神がお告げみたいにピーンと来る瞬間はある。
そういう出会いなんですね。シュタイナーとは。
という話をするとシュタイナーの人智学って
そういうオカルト的な部分に踏み込んでいくので
本当はオカルトではないのですけれど
ってえらそうに言いながら私まだその核心は
定かではありません。
でもこのコレクション1の「子どもの教育」には
いくつかのすごい内容が含まれているのは事実だと
思います。私は。
この内容をシュタイナーが書いたのは
19世紀終わりから20世紀初めなんですよね。
その中で
子どもの教育で大切なことは
7歳までは子どもは大人の事を模倣する。
7歳~思春期までの子どもに
とって一番大切なのはおのずから
生まれた権威に従うことと。
記憶力を育ててやること。
知性は思春期を過ぎた頃から
現れるという。
これってすごい事じゃないですか!?
よって小学校お受験なんて具に骨頂だということ。
早期教育があかんという事。
小学生~中学校1年生にとって総合的学習はやってはいけないこと。
なんですよね!
もっと言えば幼児期に虐待を受けた子は
自分の子どもにも虐待をするという可能性が高いという事ですよね。
もう一つ言えば小学校でクラス崩壊にあった子どもは
権威に対して素直に敬虔な気持ちで頭を下げるということが難しい
ということですよね。
主にこのシュタイナーコレクション1に
収められるいる文章は1920年までに書かれた物が
中心なんでしよね。
私シュタイナーに自分の子どもが生まれる前に出会いたかった。
(でも早期教育なんてしてないけど、、、。)
小学生にとって
大切な事は直観を育ててやる教育
体を動かす事や音楽を楽しむことや
美しい色や形に直観で触れることなんですよね。
ということで小学校の先生
一緒にシュタイナー学んでみません?
ってお誘いの連携だったらできるかな?